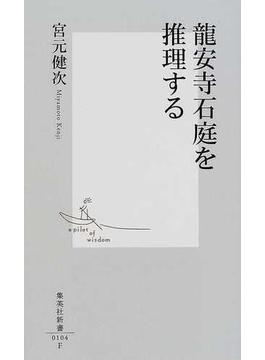「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
関連キーワード
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
謎が謎を呼ぶ
2001/12/11 10:21
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:小田中直樹 - この投稿者のレビュー一覧を見る
数年前に仕事で訪れたフランスで、ある家庭に招かれたことがある。そこのご主人は(いかにもフランスのインテリらしく)禅宗に関心を持ってて、「白砂と石だけで出来てて、石が一五個あるんだけどどこから見ても一四個しかみえない寺庭」とやらについて、それが意味するところについて質問してきた。それが龍安寺石庭だったわけだけど、僕は教養がなかったので、質問に答えられないばかりか、そんな庭があるさえ知らなかった。さいわい同席してた同僚が(盆栽好きだったため)この庭のことを知ってて、それは禅宗でいう「空」を表現してるとか何とかって答えて、相手を納得させたのだった。この本の著者の宮元さんによると、この庭は「日本文化のわび・さびを代表する存在」(三ページ)だそうだから、我ながら情けない話だ。
ところが、宮元さんによると、この庭については、本当に美しいのかも、どんな意図が込められてるかも、そもそも誰がいつどんな意図で作ったかもわかってない。つまり謎だらけなのだ。だから魅力的なのかもしれないけど、宮元さんは、この本で、龍安寺石庭の抱える謎のうちでもっとも基本的なもの、つまり造庭はいつか、造庭の意図は何か、作者は誰か、この三点について、様々な資料を利用しながら推測を試みた。
この本のメリットは次の二点にある。第一、三つの謎について、とても説得的な答を出したこと。造庭の時期については、たしかに禅宗寺院の南庭が儀式に使われてたのであれば、白砂や石は置けなかっただろう。龍安寺石庭の様式と、戦国時代以前の枯山水様式は、僕みたいな素人が見てもかなり違うから、室町時代にできたっていう通説はちょっと怪しいだろう。意図についても、借景を利用してたのが、樹木が茂って景色がみえなくなれば、解釈は難しくなるだろう。黄金分割や遠近法っていう、当時のヨーロッパで流行ってた手法が用いられてるということであれば、南蛮文化の影響は無視できないだろう。作者についても、造園のエキスパートで実力者で南蛮文化に造詣が深い人物がそんなに沢山いたとは思えないから、小掘遠州の可能性はきっと高いのだろう。
第二、「日本文化のわび・さびを代表する存在」が、じつは南蛮文化の手法を存分に用い、しかもたかだか四百年の歴史しかないものだってことを明らかにしたこと。僕らは、ともすれば日本文化は独自だとか、長い歴史があるとかっていう思い込みに陥りやすいけど、少なくとも安土桃山時代以降の日本文化は、ヨーロッパとの接触と相互浸透を抜きにしては語れない。さらに、考えてみれば、平安時代以降の日本文化だって、遣唐使や遣隋使を通じた中国文化との接触と相互浸透を抜きにしては語れないだろう。ついでに、この庭が脚光を浴びたのはイギリスのエリザベス二世が絶賛したからだけど、南蛮文化の手法を使ってるからこそ欧米人にはわかりやすいって推測することも可能だろう。
というわけで、僕はこの本を面白く読んだし、宮元さんの目的は達成されたと思うけど、読み終わったあとに色々と「無いものねだり」をしたくなった。とりあえず三つだけ挙げておこう。第一、借景がなくなったので造庭の意図がわからなくなったっていうけど、どんな意図があったのか、借景の消滅とともに、その意図がどのようにわからなくなったのか、説明がない。第二、南蛮文化を応用した庭を、欧米人が日本文化の粋とみなしてるのはなぜか、説明がない。第三、さらに根本的な疑問として、なぜ僕らはこの庭に惹かれるのか、説明がない。一素人としては、この本の成果をもとにして、誰かがこういった問題に取り組んでほしい。そうすれば日本人の心性の特徴に接近できるかもしれないし。[小田中直樹]
紙の本
魅惑の石庭の謎が解明された
2001/10/28 17:57
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:神楽坂 - この投稿者のレビュー一覧を見る
龍安寺の石庭は、日本で最も美しい庭の一つといっていい。欧米人にも評判が高く、日本的な美と賞賛されている。だが、配石が黄金分割になっているなど、西欧の庭園を思わせる要素が多い。何とも皮肉である。そして、この石庭には謎が多い。いつ、誰が造ったかが分からない。なぜ、西欧的な庭園成形になったのかも分からない。著者によると、寛永年間に小堀遠州とその配下のものたちによって造られたというのが正解らしい。決定打に欠ける気もするが、資料からするとそうなのだろう。明らかになったとされる写楽の正体のごとく、結論自体にそれほど感銘は受けないが、本の内容は面白い。
紙の本
石庭とキリシタン
2005/11/06 14:08
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:GTO - この投稿者のレビュー一覧を見る
第1章は、退屈である。決定的な史料はないため、他説を否定し自説を認めてもらおうと、史料の我田引水的な引用や推論が見られる。
第2章「造形意図の解明」からは、著者の得意分野となるため、図も増え文も生き生きしてくる。ただ、意図の解明(私はこれに一番興味があったのだが)に関しては、何も述べられてはいない。造形手法について述べられているだけである。知りたいのは、その手法によって、作者が何を意図したかである。これは、美学や建築学の分野ではなく、哲学の問題なので、この著者に答えを求めるのは酷だろう。
学生時代から現在に至るまで、何度も通った私としては、「いつ」「誰が」というような背景など関係なく、庭と対峙したその時、何かを考えさせてくれるから、よい庭であり何度訪れても新鮮なのだと思っている。当時の最新手法を駆使したことも確かであろうが、そうした庭の中でこの庭では、石があのように並んでしまった。並んでしまった石を見て何を考えるかに、たった一つの正解があるわけではない。禅の公案同様、答えはひとり一人、その時その時で異なる。だからこそ何度も訪れる価値があるのである。
第3章「作者の解明」の最終結論は「今後の研究成果を待ちたい」というつまらないものであるが、禅寺−石庭−茶道−キリスト教−西欧式庭園のつながりを知ることができ、私には新たなる発見であった。「大徳寺とキリシタン」(p.160)以降がこの本の価値ある部分である。