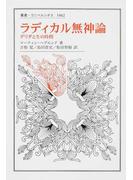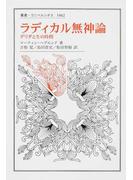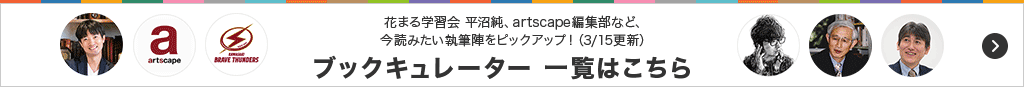映画論で見る表象の権力と対抗文化
- お気に入り
- 27
- 閲覧数
- 4853
現代世界史を通じて映画やテレビ番組などの映像メディアは、大衆文化・国民文化・対抗文化として、圧倒的な影響力をもってきた。その人種/ジェンダー/階級の表象は資本主義を広め強化してきた一方で、被支配者・マイノリティの側もまた映像メディアを用いて別様の表象を試みてきた。【選者:早尾貴紀(はやお・たかのり:1973-:社会思想史)】




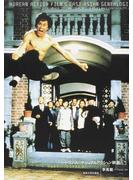

なぜ、いま、アクターネットワーク理論なのか
- お気に入り
- 121
- 閲覧数
- 25906
いま、アクターネットワーク理論(ANT)が多くの人をひきつけている。社会学や人類学はもちろんのこと、経営学、地理学、会計学、組織論など社会科学全般へとその波紋は広がり、哲学や建築学、アートなどでも広く参照されるようになっている。ここでは、社会学的関心から、なぜ、いま、アクターネットワーク理論なのかを考えるための5冊を紹介する。【選者:伊藤嘉高(いとう・ひろたか:1980-:新潟医療福祉大学講師)】






資本主義史研究の新たなジンテーゼ?
- お気に入り
- 89
- 閲覧数
- 5548
J・コッカ『資本主義の歴史』を翻訳し終え、彼の議論の特質について考えています。もしかすると、資本主義史研究の新たなジンテーゼがここから生まれるかもしれない。すでに決着済みのように思われていたものも含め、考えないといけない問題がこんなにもあるのか、と驚いています。【選者:山井敏章(やまい・としあき:1954- :立命館大学教授)】
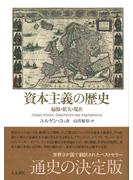
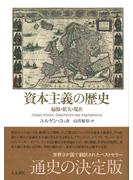


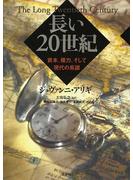
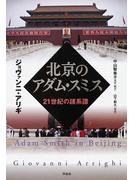
記憶と歴史──過去とのつながりを考えるための5冊
- お気に入り
- 105
- 閲覧数
- 7831
私たちは過去を振り返り、思い出を呼び起こしながら生きています。それは、個人の心理体験であるように見えます。しかし、人は常に他者とのつながりのなかで想起し、それを互いに伝えあっています。記憶と歴史、想起と忘却の形は、この営みを支える社会の形によって変わります。その可能性の広がりを考える手がかりに満ちた本をご紹介します。【選者:鈴木智之(すずき・ともゆき:1962-:法政大学社会学部教授)】




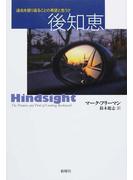

書架(もしくは頭蓋)の暗闇に巣食うものたち
- お気に入り
- 32
- 閲覧数
- 3753
「死とは空虚な名である。人が死に、魂と肉体が分離する時、なにものも滅することはないし、無に帰すこともない」(アグリッパ『隠秘哲学』第3巻36章)。死の気配が濃密さを増す暗い時代に不死性を統覚することは可能か。死の表象が反復する、狂おしい生のはざまに目を凝らしてみる。【選者:小林浩(こばやし・ひろし:1968-:月曜社取締役)】



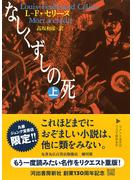


『nyx』5号をより楽しく読むための5冊
- お気に入り
- 16
- 閲覧数
- 2861
人文学に造詣の深い方々にはご好評頂いております雑誌『nyx』ですが、「難しいですね」といわれることもしばしばです。内容に通じておられる方には、本書内各論考の註や参考文献が役に立つと思いますので、今回はこれから「読んでみようかな」と思われる方々へ向けて本誌を「楽しむための」書籍をご紹介します。【選者:小林えみ(こばやし・えみ:1978-:堀之内出版編集担当)】
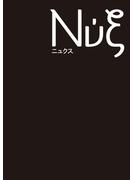
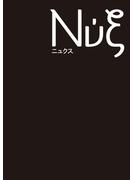
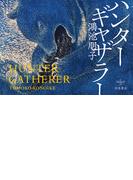
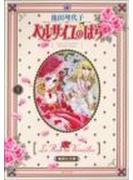


マルクス生誕200年:ソ連、中国の呪縛から離れたマルクスを読む。
- お気に入り
- 72
- 閲覧数
- 4811
マルクス生誕200年の今年(2018年)、マルクスの地元トリーアではマルクスが観光の目玉となった。だが 中国が贈ったマルクス像だけは不人気であった。トリーアの人々は中国のマルクス独占に批判的であった。マルクスは中国や、旧ソ連などの独占物ではない。もっと自由にマルクスを読もう。【選者:的場昭弘(まとば・あきひろ:1952-:マルクス研究者)】
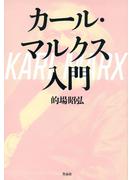
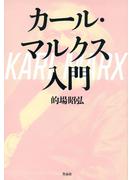




AIの危うさと不可能性について考察する5冊
- お気に入り
- 90
- 閲覧数
- 4215
AIの進展は、暮らしや社会の利便性を高める一方で、私たちを選別・管理し、支配するリスクも広げている。AIはけっして無謬ではなく、客観的でも公平でもない。また、AIは人間ならではの知とは何か?という問いを深めていくきっかけになる。「人間を支配するAI」から「人間と共生するAI」へ――そんな未来へのヒントを与えてくれる5冊。【選者:真柴隆弘(ましば・たかひろ:1963-:出版プロデューサー)】
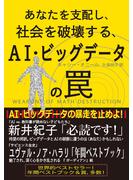
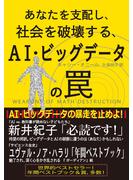

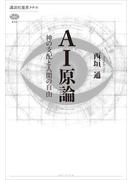

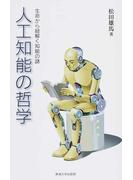
眼は拘束された光である──ドゥルーズ『シネマ』に反射する5冊
- お気に入り
- 91
- 閲覧数
- 9014
哲学と映画の正面衝突が生み出した書物、ドゥルーズの『シネマ』2巻は、その奇妙な性格ゆえに、ドゥルーズ哲学の「応用編」として、あるいは映画を論じるための便利な「道具箱」として、言ってしまえば読まれずに済まされてきた。しかし本書は同時に、「見て、書く」というきわめてシンプルな、芸術学にも批評にも詩作にも欠くことのできない営為に基づき、それを突き詰めたものでもある。私たちが新たに「見て、書く」ために、『シネマ』が反射する5冊を──うち1冊が拙著で恐縮だが──選んだ。【選者:福尾匠(ふくお・たくみ:1992-:横浜国立大学博士後期課程)】


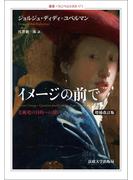

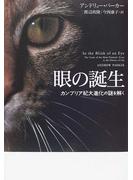

『ドローンの哲学』からさらに思考を広げるために
- お気に入り
- 32
- 閲覧数
- 3280
『ドローンの哲学』は単に軍用ドローンについての考察には尽きない。AI、ビッグ・データ、自律型ロボット等のホットなテーマばかりか、「身体」と「技術」の関わりをめぐる新たな生権力論の可能性ももつだろう。そこから思考を広げるためのいくつかの道筋を。【選者:渡名喜庸哲(となき・ようてつ:1980-:慶應義塾大学准教授)】



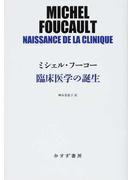


大文字の「生」ではなく、「人生」の哲学のための五冊
- お気に入り
- 94
- 閲覧数
- 7398
「言うまでもなく人生全体は崩壊の過程である」(F. S. Fitzgerald)。これは文字どおりに捉えるべき言葉です。始まりもなく終わりもなく、希望もなく絶望もないと言う「ない」づくしの生の哲学ではなく、始まりも、終わりも、絶望も、望みも「ある」、人生の哲学のための五冊を選びました。【選者:小倉拓也(おぐら・たくや:1985-:大阪大学特任助教)】
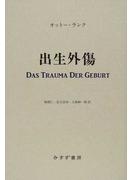
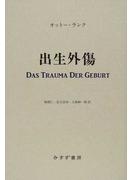
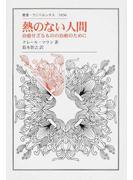

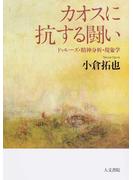

壊れた脳が歪んだ身体を哲学する
- お気に入り
- 175
- 閲覧数
- 8079
私も制作過程に立ち会った、友人の著した衝撃的な書物を中心に、互いに響きあって一つの星座をなす小品たちを選んでみました。半ば壊れた脳に、哲学すること、それを作品にすることはできるのかという問いのこだまが、哲学の可能的「かたち」を再考させてくれます。【選者:市田良彦(いちだ・よしひこ : 1957-:神戸大学教授)】




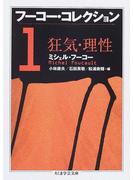

精神分析の辺域への旅:トラウマ・解離・生命・身体
- お気に入り
- 80
- 閲覧数
- 3987
精神分析は、医学、哲学、自然科学、宗教、催眠、そして心霊学などの土壌から19世紀後半に生まれて以来、排斥と包摂の運動を繰り返してきた。その歴史は、何が内部で何が外部かをめぐる議論に満ちている。その周辺と境界に目を注ぐことで生命体としての精神分析が見えてくる。【森茂起(もり・しげゆき:1955-:甲南大学文学部人間科学科教授)】
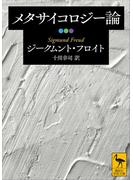
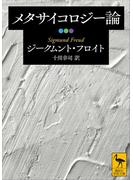



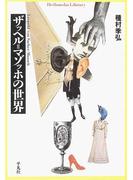
「偶然」にかけられた魔術を解く
- お気に入り
- 106
- 閲覧数
- 5815
「偶然」という言葉は、とかくマジック・ワードになりやすい。流行語をこしらえて、なにかを語った気になる不毛から抜け出したいのならば、まずはその言葉の使用に伴いやすい文法のパターンや隣接するテーマを学ぶことにしよう。言葉の魔法使いは魔術の解き方も知っておくべきだ。【選者:荒木優太(あらき・ゆうた:1987-:在野研究者)】






友情という承認の形――アリストテレスと21世紀が出会う
- お気に入り
- 60
- 閲覧数
- 5995
家族制度の動揺、社会の高齢化、セクシュアリティ感覚やジェンダー意識の変容、SNSの普及――21世紀の現実が、友情について新たに考えることを求めているように思われます。驚くべきことに、その際最も頼もしい対話者の一人は、紀元前4世紀の人アリストテレスなのです。【選者:藤野寛(ふじの・ひろし:1956 -:国学院大学教授)】


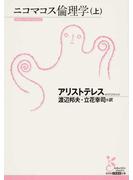


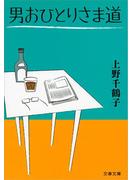
批判・暴力・臨床:ドゥルーズから「古典」への漂流
- お気に入り
- 90
- 閲覧数
- 5932
「古典」に新たな息を吹き込むという意味で、ルネサンスの人であるドゥルーズを出発点に、古典やその(再)読解を行う著作を選びました。様々なる意匠から遠く離れて、マルクスやカントを、一言一句、丁寧に(かつ野蛮に)読み直すことは、今日でも依然として、きわめて重要だと思っています。【選者:堀千晶(ほり・ちあき:1981-:仏文学)】




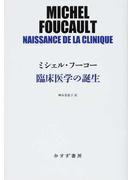

フランスの哲学教育から教養の今と未来を考える
- お気に入り
- 86
- 閲覧数
- 8255
フランスの大学入学資格試験(バカロレア)では哲学が必修科目です。哲学は教養ある人間を育てる学問であると考えられているのです。しかし、教養の概念自体が現在問い直されています。この時代に哲学することの意味を、フランスの哲学教育を出発点に学べる5冊を選びました。【選者:坂本尚志(さかもと・たかし:1976-:京都薬科大学准教授)】



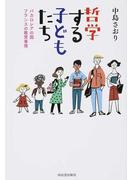


文化相対主義を考え直すために多自然主義を知る
- お気に入り
- 85
- 閲覧数
- 12025
文化相対主義の考えって、問題はないのでしょうか?文化相対主義は言い換えると「自然は唯一で、文化がたくさんある」とする「多文化主義」です。人類学では近年、「文化は一つで、自然が複数ある」とする「多自然主義」の議論が盛んにおこなわれています。【奥野克巳(おくの・かつみ:1962-:立教大学異文化コミュニケーション学部教授)】
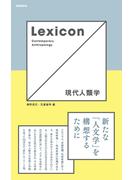
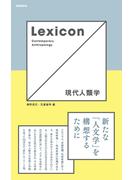




哲学書の修辞学のために
- お気に入り
- 116
- 閲覧数
- 6711
ジャンルとスタイル──『広辞苑』によれば「詩・小説・戯曲など文芸作品の様式上の種類・種別」と「文章の様式」のこと。じつは《哲学書》にも多彩な様式がある。人は哲学書を読むとき、何が書かれているかに傾注しがちだ。しかし、それでは片手落ち。どう書かれているかにも注目しよう。【選者:津崎良典(つざき・よしのり:1977-:筑波大学准教授)】
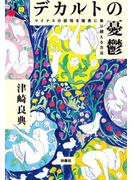
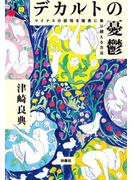



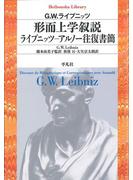
アーレントとマルクスから「労働と全体主義」を考える
- お気に入り
- 91
- 閲覧数
- 8729
近年、アーレントが各方面から注目を浴びているのは、現代社会が再び「全体主義」化しつつあるからであろう。「労働と資本主義」(マルクス)のみならず「労働と全体主義」(アーレント)の結びつきを解き明かすことこそが、混迷する現代の政治経済を読み解く鍵である。【選者:百木漠(ももき・ばく:1982-:日本学術振興会特別研究員)】
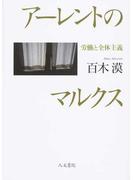
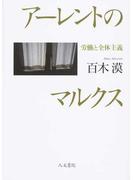




そしてもう一度、公共(性)を考える!
- お気に入り
- 78
- 閲覧数
- 4494
某政党が「新しい公共」宣言をしたのが2010年。それをピークに盛り上がった公共性論ですが、その宣言も忘れられつつある??そんな中、高校の社会科で「公共」という科目ができるようです。今だからこそ、改めて公共(性)を考えるための5冊を選びました。【選者:権安理(ごん・あんり:1971-:立教大学助教)】



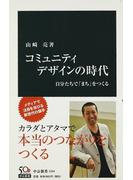
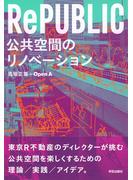
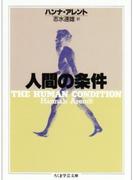
反時代的〈人文学〉のススメ
- お気に入り
- 100
- 閲覧数
- 7657
「21世紀」はテロと分断の時代をひたすらこじらせていくのか。それに対抗する知的資源はあえて反時代的な人文学のなかに見つけ出すしかないだろう。分断と越境のはざまに置かれた知識人が紡ぎ出した稀有な批評的書物を紹介する。【選者:早尾貴紀(はやお・たかのり:1973-:社会思想史)、洪貴義(ほん・きうい:1965-:政治学・思想史)】




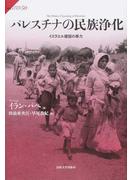

現代イギリスの文化と不平等を明視する
- お気に入り
- 32
- 閲覧数
- 3819
先進諸国が多文化社会へと変容していくなか、文化と不平等の関係を扱う文化研究への関心は高まる一方です。イギリスの21世紀の研究動向を中心に、最新の文化研究から見える社会のいまをご紹介いたします。【選者:相澤真一(あいざわ・しんいち:1979-:中京大学現代社会学部准教授)、磯直樹(いそ・なおき:1979-:日本学術振興会特別研究員)】



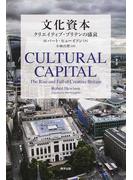
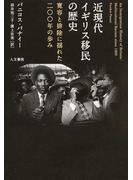

今を生きのびるための読書
- お気に入り
- 176
- 閲覧数
- 11982
年間8万点を超える新刊書籍の中から、私たちは、どのような本を選び、講読していけばいいのか。本を読むことは、自ら「思考」する力を鍛える行為でもある。そして思考することによって初めて、「表現力」が培われる。先の見えない時代の今だからこそ、紐解くべき5冊。【選者:明石健五(あかし・けんご:1965-:「週刊読書人」編集長)】





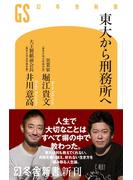
お金に人生を明け渡したくない人へ
- お気に入り
- 157
- 閲覧数
- 9716
お金がない(少ない)から好きな生きかたを選べない、とあきらめていませんか?問題は、「お金がない」ことではなく、「お金がないと生きられない」と思わせ、実際にそんな状況に私たちを追いこんでいる社会のしくみにあるのかも。お金の呪縛から自由になるための五冊を。【選者:吉田奈緒子(よしだ・なおこ:1968-:半農半翻訳者)】
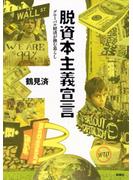
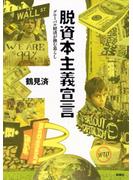
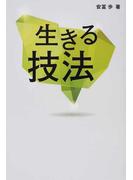


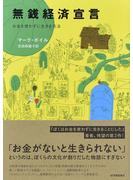
「実在」とは何か:21世紀哲学の諸潮流
- お気に入り
- 176
- 閲覧数
- 10730
実在論の復興として特徴づけられる現在の哲学の状況について、ここ数年の翻訳・紹介ラッシュによってようやく日本語でもその概要を把握することができるようになりました。『四方対象』の翻訳を機に、主に大陸的伝統から主要著作を紹介します。【選者:岡嶋隆佑(おかじま・りゅうすけ:1987-:慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程/非常勤助教)】



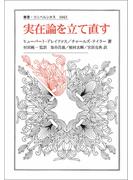


労働のいまと〈戦闘美少女〉の現在
- お気に入り
- 79
- 閲覧数
- 6534
いまや当たり前のものとなった、ポピュラーカルチャーにおける戦う女性の表象。それは、私たちの生きる現代社会のいかなる側面を、そしていかなる願望を反映したものでしょうか。この疑問を探究するための五冊です。【選者:河野真太郎(こうの・しんたろう:1974-:一橋大学准教授)】
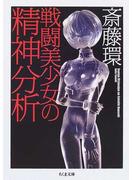
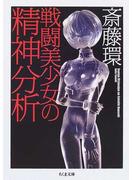
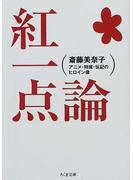
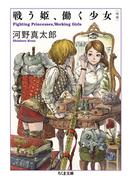


運命論から『ジョジョの奇妙な冒険』を読む
- お気に入り
- 35
- 閲覧数
- 10537
人間には自由意志があるのか?全ては神や環境によって決定されているのか?それは哲学や宗教のテーマでもありますが、近年のウェブ社会化や脳科学・神経科学・行動経済学などの発達によってあらためて身近な問いにもなってきました。『ジョジョ』の運命論を読み解くために役立つ著作を紹介します。【選者:杉田俊介(すぎた・しゅんすけ:1975-:批評家)】



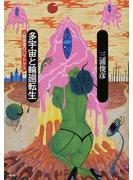

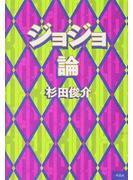
死刑を考えなおす、何度でも
- お気に入り
- 62
- 閲覧数
- 5310
正直に言って、日本では死刑存廃論は盛り上がっていません。大多数の人が、被害者遺族の応報感情への共感から、存置の立場を選んでいるからです。しかし、それ以外の論点を看過してよいわけではありません。何度でも、死刑制度を考えなおしてみませんか。【選者:高桑和巳(たかくわ・かずみ:1972-:慶應義塾大学准教授)】
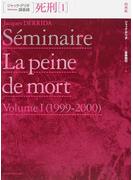
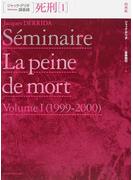
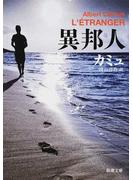

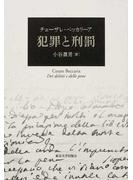

ラディカル無神論をめぐる思想的布置
- お気に入り
- 70
- 閲覧数
- 7635
「神の記憶を持つラディカルな無神論」という言葉を基本線にデリダを読解したヘグルンドの『ラディカル無神論』の翻訳が出版されました。それにあたり、同書といくつかの本を紹介することで、「ラディカル無神論」を巡る布置の概形を描くことを試みました。【選者:吉松覚(よしまつ・さとる:1987-:パリ西大学博士課程)】