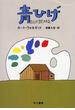映画より映像的な文章
2002/06/20 16:31
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:すまいる - この投稿者のレビュー一覧を見る
大邸宅に孤独に暮らす元抽象表現派の画家であり、前大戦において多くの勲章を得たアルメニア人の老人ラボー・カラベキアンの回想録。そんな彼の元をおとずれた謎の女性は何者なのか? カラベキアンがひた隠しにする納屋の中にはいったいどんな秘密が隠されているのだろうか?
ヴォネガットの作品にしばしば見られる回想録の形をとっているこの作品。過去と現在が交互に語られているのにもかかわらず、読者に少しも読み辛さを感じさせないところがすごい。うっかりしていると、読者はいつのまにか著者の紡ぎ出した映像的な文章の世界の真っ只中に!
著者の文章とあなたのイマジネーションは、一体どんな情景を生み出すのか!?
投稿元:
レビューを見る
やっと読了。思っていたより大作だった。
「猫のゆりかご」を読んだあと、heidiに「青ひげ」を薦められた。「猫のゆりかご」でヴォネガットに一定のイメージができちゃったので、「泣けるよー」と言われてもピンとこなかった。
でも確かに”泣ける”話。泣きゃしなかったけどね。
架空の画家ラボー・カラベキアンの一代記。この名前、あんまり大仰なもんだから、半分くらい読むまで主人公の名前だとうまく認識できなかった。
おとぎ話だと思うんだけど、何とも変わってる。皮肉と怒り?悲哀?。しつこいくらい、自分と世界をシニカルにこき下ろす。熱さを感じるくらい真剣な皮肉。
作中に出てくる女性、サーシ・バーマンにはほんと我慢ならなかったけど、この人物をはじめ極端にデフォルメされた人物がうまい。「猫のゆりかご」と同じ人が書いてんのかあ、と思ったけど、ムダがないなあと感じるあたりは確かに同じ。時期が後だから当然ながら、よりこなれた感じもするし。
面白く、ずっとわかりやすい話だった。「猫のゆりかご」がダメな人にも薦められるかも。
でも最後はちょっと……クサイかなあ。それがいいんだけど。
投稿元:
レビューを見る
ラボー・カラベキアンというアルメニア移民の老人が、自伝を書きながら、執筆中の現在についても日記のような感じで語っていくのが、エピソードごとに過去と現在が入り組んで語られます。なんでタイトルが『青ひげ』なのかは、じゃがいも納屋に隠して決して誰にも見せないでいたモノ(最後にはなんだったかわかります)があるので、そのことをペローの書いた原典『青ひげ』に重ねたのでしょうか??この主人公は別にイイモノでもワルモノでもなかったです。
投稿元:
レビューを見る
久しぶりに即2回目を読んだ本。
面白かった。
とくになにが、というわけでもないのだけど面白かったと思う。
近代美術について知りたくなりました。
2008,april
投稿元:
レビューを見る
「こうした偶然の一致をいちいち真剣にとっていたら、
だれでも気が狂ってしまう。この宇宙には、
自分にかいもく理解のできないことがわんさと進行中らしい、
と疑いを抱くようになる」(本文より)
1987年のヴォネガットの長編です。
戦争体験をベースに、しっちゃかめっちゃかになった
人生の回顧録である点においては、いつものヴォネガット。
「青ひげ」にはラストにオチが用意されているので、
いつもよりもちょっとわかりやすいヴォネガットかなと思います。
わたしがヴォネガットを好きな理由は、
奇跡的な出来事が、それが幸運であれ、その真逆であれ
いつ起きても、「ひとつの事実」として受け止める姿勢が
貫かれているからです。
登場人物がどんなに自分勝手でも自己中心的でも、
どんなにはた迷惑な存在でも、「存在」として尊重しているところかな。
投稿元:
レビューを見る
よくこれ書いちゃうよなぁ。
まあ、ヴォネガットの中では一番入りやすい作品かな。
わりとすらすら進む。
投稿元:
レビューを見る
「ある一瞬がほかの一瞬にくらべてべつだん重要ではなく、
すべての瞬間があっというまに過ぎ去ってしまうことを
表現するだけの勇気、知恵、それともたんなる才能が、
彼には欠けていた。」
投稿元:
レビューを見る
あるアルメニア人の絵描きが、老後カリフォルニアの孤独な邸宅で綴った自伝。最後の結実を迎えるための、数々のエピソード、彼がいかにして、ジャガイモ納屋に隠した真実を披露するかがこの小説の鍵。
絵を人間が、時代に翻弄され、一介のつまらない老人となる。そんな彼が最後に仕組んだ、巧妙なフィナーレを大いに楽しんで欲しい。
ヴォネガットの、悲哀とアイロニーの入り交じった文章は、小説が有益か、無益か以外のところで語られるための、よいサンプルとなるだろう。
投稿元:
レビューを見る
今度は画家の話
楽しみにしている作家の(けっこう)最新作。1987年である。戦争体験を持つ画家が自らの人生を振り返るというスタイルで書かれる。細切れに小さなセンテンスが区切られていて、あっちこっちへと時間がいったり来たりするものの、絶妙のタッチで読者が混乱することがない。多少冗長とも思える350ページの長編もスムーズに読むことができた。
本来自分の死後にのみ公開する予定だったジャガイモ小屋に残した最後の作品とはどんなものなのか? このテーマを最後まで引っ張りながら、ラストで一気にその作品を見せる。主人公である画家がそれを公開する気になる部分といい、公開したときにとかれる自らに課した呪縛みたいなものがラストを締めくくる。なかなかいい本だった。
投稿元:
レビューを見る
人間讃歌。に、辿り着くまでの人生劇場。結局どんなにブサイクな生き方をしていても自分だけには正直でいればなんとか形になるさ、とヴオネガットは言ってくれているような気がした。沢山の登場人物が自殺したり、戦争で死ぬが一様にいえぬそのいきさつの描き方に優しさを感じた。根底に流れる戦争体験からの思想に今現在生きる僕は学ばなければならない。
投稿元:
レビューを見る
初めて読む作家だったので知らなかったが、どうも有名なSF作家らしい。ただ、この作品は現代を舞台にした一般小説。
タイトルが「青ひげ」だし、粗筋に「鍵のかかったジャガイモの納屋」の存在がかかれているし、最初はもっとじっとりした、退廃的な話かと躊躇していた。が、実際のところはまるで違った。
軽妙な乾いた文章で綴られる内容は、私が想像した陰鬱な雰囲気は全くなかった。扱っているテーマや作中で語られる歴史はなかなか重いのだが、その辺をさらりと読ませる。
私は昔から、芸術というものがまるで分からない。
絵画や音楽は授業レベルの通りいっぺんの知識しかないし、実物を前にしても、ぞくぞくするような「美」を感じることはあまりない。元々凡庸な感性しか持っていないうえに、それら強く興味を惹かれることがないからだろう。
だから、作中に繰り返し出てくる「魂のない絵」というのがどういうものなのか、うまく想像できなかった。「魂がない」としてもとても精密に描かれているなら、私はそれだけで賞賛してしまいそうだ。この言葉も意味が経験的に分かる人が読むと、受ける印象も強いのだろう。そう思うと残念。
芸術論を理解できるかどうかを抜きにしても、過去と現在が交互に描かれる物語はとても面白かった。こういう老人の回想ものを読むと、生きていくのもそんなに悪くないと思えるな。
投稿元:
レビューを見る
SFを読んだ気はしないがヴォネガットマニアには感動作
表紙 7点和田 誠
展開 7点1987年著作
文章 7点
内容 731点
合計 752点
投稿元:
レビューを見る
老年の画家ラボー・カラベキアンのもとにサーシ・バーマンという女性作家が転がり込む。カラベキアンは彼女のすすめで自伝を書き始める。自伝そのものの部分と、自伝を書いている過程でのバーマンとのやりとりなどが交互に記されている。
ヴォネガットのいつもの人をばかにしたような文章は影を潜め、比較的淡々と綴られている。物語に抑揚がなく、どこに行き着くのか分からない自伝を読み進めるのは意外ときつい。しかし、最後のシーン。ジャガイモ貯蔵庫に隠しておいたものをバーマンに公開するところに至って、話は感動的な方向に大きく舵を切る。最後まで読んで、読んでよかったと思える。
投稿元:
レビューを見る
読み終わっての印象が薄いのだが、それはこちらの読み方が悪いせいなのかもしれない。
ヴォネガットの小説はこんなものだという先入観があって、期待通りにならないので、アレレという状態のまま最後までいってしまった。
こちらの読み方が雑で急ぎすぎということもあるけれど、それだけ前期の作品群のインパクトが強かったのだ。