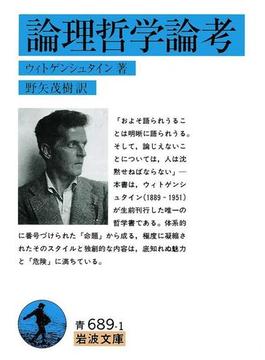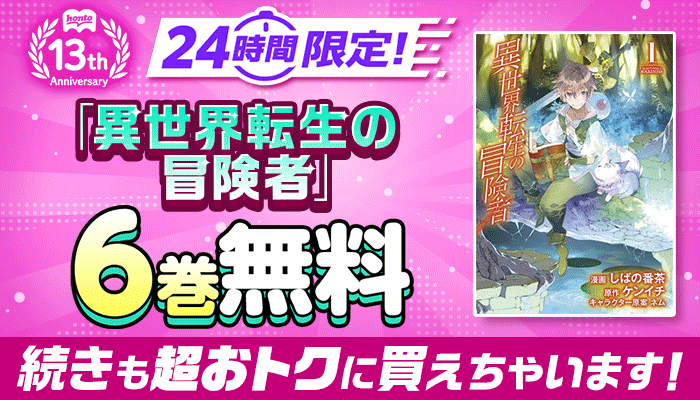- みんなの評価
 4件
4件
論理哲学論考
著者 ウィトゲンシュタイン著 , 野矢茂樹訳
「語りえぬものについては,沈黙せねばならない」という衝撃的な言葉で終わる本書は,ウィトゲンシュタイン(1889-1951)が生前に刊行した唯一の哲学書である.体系的に番号づけられた短い命題の集積から成る,極限にまで凝縮された独自な構成,そして天才的な内容.まさに底知れぬ魅力と危険をはらんだ著作と言えよう.
論理哲学論考
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
論理哲学論考
2005/03/04 19:02
ゾクゾクする文章
12人中、11人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:死せる詩人 - この投稿者のレビュー一覧を見る
20世紀が誇る偉大な哲学者ウィトゲンシュタインによる生前唯一の著書『Tractatus Logico-Philosophicus』の全訳です。
全ての文に項番が振られ「1.世界は成立していることがらの総体である/The world is everything that is the case.」から始まる論考は、全編を通じて不思議な魅力に満ちています。ウィトゲンシュタインの語る事は難解で、専門家ならざらる僕には半分も理解できません。しかし、余りにもアッサリと「世界」を叙述してしまう、その切れある文章には何故かゾクゾクと興奮させられ、次々とページを捲ってしまうのです。
最終的に「7.語りえぬものについては、沈黙せねばならない/Whereof one cannot speak, thereof one must be silent.」で終わる論考。哲学が分からなくても詩として読む事ができます。それ程までにウィトゲンシュタインの文章は切れ味が鋭いのです。
論理哲学論考
2020/05/02 09:55
第一次世界大戦の頃のオーストリアの哲学者ウィトゲンシュタインによる哲学書です!
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、オーストリアの哲学者(のち、イギリスの国籍を取得)で、言語哲学、分析哲学に大きな影響を与えたルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインによって、1918年に執筆され、ドイツで1921年に出版された哲学書です。当時は、ちょうど第一世界大戦の最中であると同時に、学問の世界では、論理哲学が勃興しつつあった時代でした。そのような状況において、彼は、同書によって哲学が扱うべき領域を明確に定義し、その領域内において完全に明晰な論理哲学体系を構築しようと志した一冊です。実は、この『論理哲学論考』は、彼が生前に出版したただ一つの哲学書であり、かつ前期ウィトゲンシュタインを代表する著作なのです。
論理哲学論考
2003/11/13 13:45
素人には素人の読みがある。読みたいように読めば、「論理哲学論考」は映画の科白にも使える名言集ってことで…
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:pipi姫 - この投稿者のレビュー一覧を見る
友人が訳したからというだけの理由で数年前に読んだのが、『ウィトゲンシュタイン』(講談社選書メチエ)だった。これがウィトゲンシュタインとの出会いだったが、とてもわかりやすい概説書だったおかげで、次は原典(もちろん翻訳で)を読んでみたいという気持ちに駆られたものだ。
文庫本が出たのはやっと今年になってからというのは意外だったが、さっそく
飛びついて読んでみた。
29歳の若者だからこそ書けた、まったく新しい哲学書。それは何かの論を叙述
しているというよりは、独り言のようにウィトゲンシュタインがつぶやく言葉の連なりなのだ。しかも一文ずつは曖昧さがどこにもなく、明解な論旨から成り立ち、隙がない。
論理学についてはまったく素養のないわたしが読んで内容を理解できたとは思われないのだが、数学の解説のような部分には反応しないわたしのような人間でも、本書をアフォリズムの書として読めば、実に味わい深く感じることができる。
かの有名な「語りえぬものについては、沈黙せねばならない」という言葉で終
わるこの哲学書は、そういう意味で、何度も繰り返し読んでこそじわじわと心に染みてくる。
「私の言語の限界が私の世界の限界を意味する」
「死は人生のできごとではない。ひとは死を体験しない」
「神秘とは、世界がいかにあるかではなく、世界があるというそのことである」
それにしても、ウィトゲンシュタインの師バートランド・ラッセルの序文はまったく興ざめである。ウィトゲンシュタインの含蓄ある書を、論理学の等式記号だけに押し縮めてしまうような解説のしかたは許しがたい。全然文学的じゃない。
その上、訳者野矢氏によれば、ラッセルは本書を誤読しているという。ウィトゲンシュタインの師にして論理学の大家が間違うんだから、素人はどう読んでも許されるんじゃないか、と思えてくる…。
ウィトゲンシュタインは、論理学をつきつめれば哲学の難問のすべてを解ける
と、ほんとうに信じていたんだろうか。『論理哲学論考』は読めば読むほど、謎が深まるばかりだとわたしは思うのだが……。
さて次は『ウィトゲンシュタインはこう考えた』を読まなくちゃ。