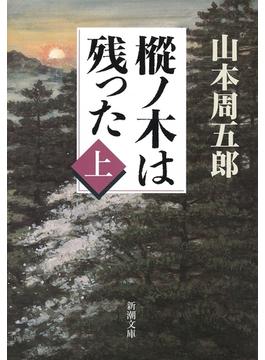紙の本
樅ノ木は残った 上
2022/05/13 19:40
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:雄ヤギ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本作は三巻を通じて三つあるとされる伊達騒動の最初と二つ目を取り扱っている。冒頭、藩主綱宗の隠居と上意討ちを称する殺人が描かれる。宿老の原田甲斐がこの遺族を引き取り保護するが、原田甲斐の立ち居地や意図がぼかされているので、物語がどう進むのかわからない。また同じ上意討ちで殺された遺族にも人によって差が出てくるのが面白い。
紙の本
なんという面白さだろう
2019/02/23 09:05
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る
山本周五郎の代表作のひとつで、NHKの大河ドラマにもなった名作である。
1954年7月から翌年の1955年4月まで日本経済新聞に連載、その後時間をおいて1956年3月から9月まで同紙に後半を書き続け、さらに書下ろしで加えたのち完成。
平成30年に改版として出た新潮文庫版では上中下の3巻仕立てになっている。
この作品は江戸時代前期に起こった仙台伊達家のお家騒動である「伊達騒動」を扱った歴史小説である。
従来は藩の乗っ取りを企んだ男として原田甲斐は評価されていたようだが、この作品で山本周五郎はその原田甲斐を主人公にして、むしろ藩のために一身を捧げた男として描いたとして有名になった。
作品が出来て半世紀以上も経つと、作品の評価も固まり、ましてや「伊達騒動」なるものも知らない人が増え、私もその一人であるが、この作品を読んだ人からすれば原田甲斐という男はヒーローに見えてくるにちがいない。
歴史上の正邪は措くとして、まずはじっくり長編小説を楽しみたいところである。
この上巻では、お家騒動の始まりとなる伊達家三代めにあたる綱宗(いうまでもないが、初代は伊達政宗である)が放蕩により幕府から逼塞を命じられ、それをそそのかしたとして藩士四名は惨殺されるところから始まる。
原田甲斐は家老職につける家柄ながら、まだここではそこまでの地位になっていない。
ただ政変の嵐に巻き込まれる気配に満ちていく。
妻との関係、その兄でもある友人と関係、あるいは謎の浪人とエンターテインメントの要素も高く、まず何よりもこれはめっぽう面白い。
電子書籍
おもしろく読みやすい
2016/10/22 10:39
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ME - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者の小説を初めて読んだが、非常に読みやすい文章だと思った。敵味方が分かりにくく、おもしろい。名前で呼ぶところと地名で呼ぶところがあり気をつけていないと誰のことを言っているのかわからなくなる。
投稿元:
レビューを見る
江戸時代の伊達騒動を舞台に、御家のために苦闘する家臣たちを描く山本周五郎の名作。
教科書的な歴史でいえば原田甲斐は大悪人になるのでしょうが、ここでは御家の存続のために「下馬将軍」ともいわれた老中「酒井雅楽頭」と伊達家の実力者「伊達兵部」の懐に飛び込んで自分を信じる人々をも欺いて苦闘する忠臣「原田甲斐」が描かれています。
伊達騒動には発生当時から様々な解釈が行われ現代でも続いていますが、登場人物たちが本当は何を考えていたのかなんて言うのはわかるはずも無く、状況証拠から積み上げてこう言う事だったのではないかと解釈をおこなっていくしかありません。
歴史とはそうやって様々な状況証拠を積み上げていって解釈していく学問です。
例えば、私が学生時代の教科書には縄文時代は戦争が無く平和な時代だったとか、古代栄えた4大文明という事も、現在では様々な証拠が積み上げられて違うんじゃないかという方向に向かっています。
そうやって、絶対的な正解がない歴史という学問が私は大好きですね、何と言っても自分の想像力を働かせる楽しみがありますからね。
投稿元:
レビューを見る
上・中・下巻。歴史小説です。とはいえ、私はこの話を、歴史小説の形をとった一種のファンタジー(あるいはSF)のようにも思います。作り事と言う意味ではなく、史実と創作(この辺にちょっとファンタジー(SF)的要素のようなものが)を上手く混ぜ合わせてある作品でなのではないでしょうか。
内容は、仙台藩の御家騒動、いわゆる伊達騒動を扱った作品です。
それまで逆臣とされ、極悪人とされていた大老 原田甲斐の解釈をみなおし、伊達家を守るために1人罪を被ることで藩を取りつぶそうとする幕府の陰謀を阻止した男として描いています。
テレビドラマにもなったそうです。私は見ていないですが。
陰謀に立ち向かう原田のおじさまが渋くて格好いいんです。
力を込めて主張したい名作です。
何より好きなのは、原田のおじさまと宇乃という娘の関係です。なんというか、言葉が必要ないくらい魂の深いところで結びついている様が、わたし的にすごく好みなのです。そして、この年齢差がまたいいんですよ。個人的な趣味ですね。
全然関係ないですが、私が買ったときは上下巻だったのに、何時のかにか上中下巻になったんですね。
投稿元:
レビューを見る
本当に5つ星では足りないぐらいの感動を与えてもらった。でも最初のこの1冊を理解するのが本当に難儀だった。同じ人物に与えられるさまざまな呼び名。慣れない武士社会の階級。でもここを乗り越えれば,これほど心を揺さぶられる作品はない。
投稿元:
レビューを見る
戦国時代は既に終わり、家光の代までのような武断政治も転換していこうとしている泰平の世の中で生きる一人の侍の話である。彼は独りで悩み、苦しみ、抗っていた。人間として組織人としての二面性を描いた秀作。時代小説ではあるもののギャング小説のような展開、人を騙すこと及び人から愛されることというのはどういうことなのかを感ぜずにはいられない作品だった。
投稿元:
レビューを見る
原田甲斐が本当にこのような人物だったかは定かではない。
むしろ嫌われ者だったという一説もあるという。
だが、樅の木は残ったで描かれる原田甲斐ほど魅力的な人物はいない。
最後、私は泣いたけど、それは感動だったのか悔し涙だったのかまだわからない。
大切な一冊。
投稿元:
レビューを見る
買ったけどまだよめてない!!でも傑作といわれてるし、山周だから☆5なハズ!!w
これを読むにはもう少し日本史の用語や歴史を勉強しないとあまり理解できないと思うから、そんなんで中途半端に読むにはもったいなさすぎる!時間+知識がもう少し増えてきたらゆっくりよみたいと思います☆
投稿元:
レビューを見る
先輩に薦められて、読み始めましたが、田村正和主演でドラマ化され、それを見てしまったので、途中で挫折しました。
投稿元:
レビューを見る
「侍というのは三つの場合しか刀を抜かないものだ」(中略)「主君の辱められたとき、誅奸のとき、おのれの武名の立たぬとき、―こんなくだらぬ喧嘩に刀を抜くほど、おれは腰ぬけではない」(七十郎)「―意地や面目を立てとおすことはいさましい、人の眼にも壮烈にみえるだろう、しかし、侍の本分というものは堪忍や辛抱の中にある、生きられる限り生きて御奉公をすることだ(中略)人の眼につかず名もあらわれないところに動いている力なのだ」(甲斐)「この闇夜には灯が一つあればいい、だがわれわれにはその一つの灯さえもない」(周防)
投稿元:
レビューを見る
そのむかし伊達騒動の常識をくつがえした本書に感銘を受け、一人で樅ノ木ツアーを敢行。
登場人物が領地名で呼ばれたりと紛らわしいので、宮城県の地図を片手に読むのがオススメ。
投稿元:
レビューを見る
物語、前半部。
登場人物が多く、ちょっと戸惑いました。
でも、テンポがよくてするすると読めました。
投稿元:
レビューを見る
義理・人情・正義・根性ですっぱり気持ちのいい周五郎作品の中で
珍しく正義だけでは生きていけない苦悩がにじみ出る本。
私の中の、暫定1位(2000〜2009年時点継続中)
歴史的に、悪役名高い
伊達騒動の原田甲斐のイメージをひっくり返す作品。
とにかく、感じたことは
「自分の正義が、すべてではない」ということ。
原田甲斐は伊達藩を守るため、
酒井大老は徳川幕府を守るため、
どちらにも正義がある。
どちらも正義の場合は、どちらが正しいのだろうか。
これは遠い江戸時代の話ではなくて
私たちの身近な物語として読んでほしい。
時々人間は大切なものを守る自分を正しいって思うけど、
それって自分にとって正しいだけ。
そのために傷つけられる相手にとってみれば
たとえどんな理由でも正しくなんかないと思う。
自分が生きていくために
結果として相手を害してしまう場合も
自分を正しいと信じてやるより、
侵害した自覚をもって行いたい。
投稿元:
レビューを見る
舞台は1600年代後半の仙台藩(伊達家)。世に言われる伊達騒動の渦中の人物であった原田甲斐が主人公です。
藩3代藩主の伊達綱宗が放蕩をやめずに若干21歳で隠居を命じられ、そのあとを2歳の亀千代(後の伊達綱村)が継いだことから騒動の火種がくすぶり始めます。
果たして伊達綱宗の放蕩は隠居に相当する出来事だったのか、それともそこに何か別の思惑が蠢いているのか...
【開催案内や作品のあらすじ等はこちら↓】
http://www.prosecute.jp/keikan/018.htm
【読後の感想や読書会当日の様子などはこちら↓】
http://prosecute.way-nifty.com/blog/2006/09/post_c5ac.html