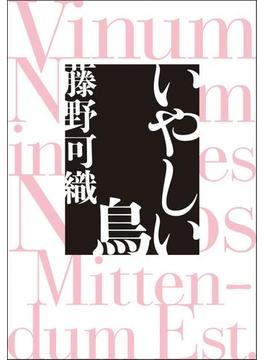投稿元:
レビューを見る
表題、「溶けない」「胡蝶蘭」の3篇。これらのジャンルはなんだろう。ホラー小説か。それとも。独特な世界で、次の作品も読んでみたくなった。カフカ「変身」を思い出させる表題、完全口語調の文体でよみやすいようなよみにくいような。2編目はもう一回読んでみないとわからないかな、恐竜ってなんだろう、お母さんはやはり本物ではなかったのかな。3編目は、シュールだけれど一番読みやすかったです」。
投稿元:
レビューを見る
これはひどい
家にかえってきて人死んでたらどうする
おどろく
逃げる
戦う
人間って選択肢あんだよ
ねーとか言うな
あほ
投稿元:
レビューを見る
「いやしい鳥」
鳥を飼う男。その隣人たる主婦。この二人の視点が交錯しながら、鳥とそれを食した青年の惨劇が紡がれる。
「溶けない」
幼い頃、母を恐竜に食われてしまった女性、その記憶と、その後の人生、そして再びの遭遇を描く。
「胡蝶蘭」
物喰らう胡蝶蘭。それを引き取った女性。その、奇妙に、愛しい日々。
3作ともに完成度が高く、なかなか満足だった短編集。個人的には「溶けない」が好きですかね。
現実と幻想がぐるぐると静かに渦巻いて、奇妙で、不気味で、どこか惹かれる世界を形づくる。読者はとにかくその流れに身を任せてしまえば良し。
文章もかなり好み。感覚をここまで適切に書ける人も珍しいのではないかと思います。過不足ない言葉で描かれているがゆえに、かえってその描写が浮き立って見えるとでもいいましょうか。人が何気なく感じていることを言葉にして提示する、という小説ならではの仕事を見せてくれました。
投稿元:
レビューを見る
先日読んだ「パトロネ」が良かったので、デビュー作が読みたくなり読んでみた。意外と「パトロネ」よりもストレートだった。以下若干ネタバレのため*を置く。
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
表題作「いやしい鳥」は可愛がっていたオカメインコが、成り行きで家に泊めた男トリウチに食べられてしまう。すると、トリウチはインコに変貌していき…、といった内容だが、心理描写が巧みなうえ、怖いけど軽妙な語り口なため、さらりと読める。
しかも、これは文学界新人賞を受作というから驚きだ。
今後、どんな作品を書いていくか楽しみな作家が一人増えた。
投稿元:
レビューを見る
不知道点儿。歩くときの靴の擦れる音とか、マットに浸みついた仕舞い忘れの魚のにおいとか、日常の隙間に巨大な恐竜が現れるとか。UFS,"Unknown Flying Story"
投稿元:
レビューを見る
「いやしい鳥」
「溶けない」
「胡蝶蘭」
文芸誌で短編一本読んだときから何となく気になっていた作家さん。
やはり好みな作風だった。
いずれの話も非日常・非現実な事柄が登場するのだけれど、それがもしかしたら語り手だけの体験なのではないかと不安を抱かせる。
この非日常との距離感がとても自分にしっくりくるもので、もっと他の作品も読みたいと思った。
「いやしい鳥」
即座に結びつく証拠は、この表題作でも消されている。最初に詮索好きで勝手に妄想を膨らます主婦の視点から、この物語の主要な語り手を外から描写。そして男の語りも最初は支離滅裂。とても疑わしい。
鳥になった男の不気味さは秀逸。同じ人間とは思えないところから、本当に人外へとなってしまう。
「溶けない」
三編の中では一番好き。
幼いころ「恐竜」に飲み込まれた母親は、姿形も記憶もまったく同じ別の母親になって戻ってきた。
同じくカメレオンを見たという同じ大学の女性や、「恐竜」じゃなくコモドオオトカゲだと言う大家。
飲まれるって何なのか?
母親との関係性や主人公自身の変化などが、人を飲み込もうとする何かとつながりを感じられて、このつながってるぽい距離感もいい感じ。
明白じゃないけど、意味を感じる。
「胡蝶蘭」
スッキリとまとまった一編。
最後がおしゃれ。
投稿元:
レビューを見る
言ってしまえば世にも奇妙な物語。
現実世界なの起こり得ない方向へすすんていく。
飽きない程度の長さのお話になっているのて矛盾とか詳しい説明が必要がない。
「溶けない」は妄想なのか仮想世界なのか最後までわからなかったけどこちらの想像が膨らむ話だった。ちょっと説明不足だったけど。
ちょっと怖いお話を読みたい時にびったりだと思う。
投稿元:
レビューを見る
「爪と目」「パトロネ」に続いて3冊目、相変わらず不思議ちゃん全開の藤野ワールド。
飲み会帰りにひょんなことから転がり込んで来た学生がペットのオカメインコを食ってしまったあげく自らがそのものになってしまい飼い主を攻撃するという荒唐無稽なストーリーなのだがやはり構成が冴えている。
読み手はオポチュニズム然とした隣人の主婦の目線で事件を俯瞰するという設定が面白い。そしてもっと面白いのは藤野さんが書きながらクスクス笑っているのだろうなと思わせる小技の数々。
若いのに曲者、なかなかやるな!が感想でした。
PS…ベリーショートながら「胡蝶蘭」が秀逸!新進気鋭の作家藤野可織そのもののシュールな仕上がりでした
投稿元:
レビューを見る
このデビュー作は、ガーリーは抑えられ。
寓話でもない象徴でもない、とうとつなグロテスクが冴える。
「いやしい鳥」
何がどうなるかと思いきや、バトル!!
「溶けない」
集中もっともぼんやり。
「胡蝶蘭」
猫の首というイメージでぐいっと惹きつけられ。
投稿元:
レビューを見る
「いやしい鳥」「溶けない」とショートショートの「胡蝶蘭」の3篇は、いずれも不可解な怪物に出くわす話。不条理な状況に翻弄されつつも、それに抗い立ち向かうラジカルさが更に事態を悪化させるのは、初期筒井作品を彷彿とさせる。
「いやしい鳥」は、お隣に住む主婦を一方の視点に加えたことにより物語に客観性を与えスラップスティックコメディ色が薄れ、筋立ての面白さが増しているように思う。ただ、次々に登場する不快なアイテムがあまりにありふれていてややしらける。三者それぞれの切迫感は感じるのだけど精神的に追いつめられていく様子があまり見られないため全体としてエッジが立っていないように思う。読んでいる間中セサミストリートの曲が頭の中を渦巻いた。
「溶けない」は、著者得意の母娘もの。女性特有のしぐさの描写は素晴らしく、全体として映像的なイメージの作品となっている。「溶けたりしないくせに。どうせ老いて死ぬくせに」というインパクトのあるひと言が本作の全てだろう。
「胡蝶蘭」は、わずか15ページほどの短い作品だが、視覚的描写が際立っているので、3篇中最も強い印象を残す作品となっている。「胡蝶蘭はなにも言わなかった。当然だ」というフレーズに、オチを付けねば落ち着かないという著者の上方気質を感じる。こういうの大好き。
投稿元:
レビューを見る
表題作は、どうも世界に入り込めなかったので、特に感想は書かず、併録されている「溶けない」について。
<溶けない>
子ども(小学校低学年)のころ、夜眠っているときに足を引っ張られるような感覚があり目が覚めてしまうことがたびたびあった。あの頃はオバケの仕業かとびくびくしていたのを覚えている。この小説で幼い「わたし」が恐竜に遭遇するシーンを読んだ時の印象が、ちょうどこれに似ていた気がする。
私の「足を引っ張られるような感覚」はもうなくなった。幼少時代の不思議な体験など、大人になるにしたがってそれが何か分かるあるいは気のせいだと思い、雲散霧消していくものだ。
しかし、この小説では終わらない。じわじわと日常に忍び寄ってきて、あろうことか大学生にまでなった「わたし」まで飲み込んでしまう。
周囲の人間の反応からすれば、その体験は「わたし」のもうそうだろうとは思うのだけど、「わたし」の視点が妄想を見ているそれとは到底思えないほどにくっきりしている。
こうしたズレはどうして生まれたのだろうか、この幻想は何かの隠喩なのか・・・そういった疑問は解けないままで心残りだけど、もっと同著者のほかの小説も読んでみたいと思うものではあった。独特の気持ち悪さこそが物語の醍醐味なのだろうか?
投稿元:
レビューを見る
「いやしい鳥」ピッピが食いしん坊なのか、トリウチが卑しいのか。
「溶けない」食べられても、大丈夫。恐竜は絶滅したんだから。
「胡蝶蘭」ここまでの「鳥」や「恐竜」に比べると、この胡蝶蘭はかわいい。
投稿元:
レビューを見る
胡蝶蘭はなにも言わなかった。当然だ。
けれど、そのとおりになった。私の言ったことに従って、胡蝶蘭はしんしんと真面目に咲き、花びらに受けた茶色い傷を数日のうちに治してみせたのだ。曲がった茎まで元通りになった。私は大した手入れはしていない。
(P.177)
投稿元:
レビューを見る
ここまでわけのわからない小説を読んだのは初めてかもしれない。
奇をてらったかのような擬音もしっくりこない。
感情的にも感覚的にも文章的にも、まったく反りが合わなかった。
投稿元:
レビューを見る
え、、、どうゆうことー!!?
怖かった。。。
話が三つあるうちの
話の順番が、
いやしい鳥→
溶けない→胡蝶蘭
でよかった。。。
いやしい鳥が怖すぎて、、、
いやしい鳥、、、なぜ色んな人の証言なのか、
入りづらかった。。。理解するのに時間かかる。けどなんとか読んだ。そして、怖くなった。
なんた。これは!作戦なのか。。。
どれにも共通してるのが食われるって感覚なんだけど、夕方、グエムルって怪物出てくる映画見たせいで、余計に想像された。
三つの話の中では、
溶けないが、面白いと感じるところが多々あった。
日常感が所々あったからだろうか。
胡蝶蘭は可愛らしくも思えた。
おんなじ人が三つ書いた感じがしなかった。
いやしい鳥は、妙にグロテスクな映像が頭に想像されて、、、だから、凄いのか。
うん。妙に、怖かった。文の感じも全体的に荒い空気が漂っていた。妙に雑な感じが、息継ぎもないような主人公の語りが続く所が、綺麗に作られた作り物というより。本当にあるものを羅列して。錯乱して、切れっぱなしの布みたいに、だから。怖かったのかも知れない。どこかそこが街頭インタビューかニュース番組でも見てるような、ドキュメンタリーのコメントのような、あーそう思ったら、面白い作品かも知れない。怖くて拒否反応がすごかったけど、後になって、そう思わせてきた、構成?というか、書き方というか
、、なんで三つの中で『いやしい鳥』がメインになってるんだと思ったけれど、こう考えていくと、なんだか、腑に落ちた。
怖かった。。。最初、星2にしようと思ったけど、
あの書き方は、似たような題材を使いながら、
それぞれにあった、文の書き方で書いてるのかも知れない!?と思ったら、星4つになった。
恐怖のち、不穏のち、謎の達成感と汗をかいた後の爽快感?がある本だった。