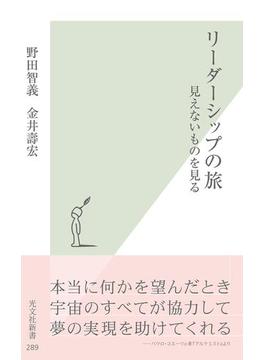紙の本
リーダーという名の幻想
2007/06/27 02:25
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:濱本 昇 - この投稿者のレビュー一覧を見る
リーダーシップと言えば、世間一般には、「英雄、自分とは縁遠いもの」と考えがちで有り、自分には成れないものと思っている人が多いと本書は書き始める。まず著者は、この「リーダーの幻想」の間違いを指摘する。リーダーとは、誰もが成り得るものであると著者は説く。リーダーは、見えないものを見て、まず自分が荒野に向かって第一歩を歩み出す(リード・ザ・セルフ)、そうする事に拠って、ファロワーが現れる(リード・ザ・ピープル)、そして最終段階において社会を動かす(リード・ザ・ソサァティ)、この段階を踏む事に拠って、リーダーは輩出されるのである。世間一般では、まず、このリード・ザ・セルフの段階が踏み出せない。何故ならば、そこに世間体や常識が障害になるのである。自らに信念、情熱、理想を持つ事が出来れば、これらの障害は、障害にならないのであるが、自らが傷つくのを恐れて、まず、常識の域を出る事をしようとしない。私には、信念も情熱も理想も持っている。リード・ザ・セルフの段階には達していると思うが、中々フォロアーが現れない。フォロアーが現れないのである。従って、私はリーダーとは呼べない。
リーダー待望論が唱えられて久しいが、会社に求められるのは、リーダーであるか?マネージャーであろうか?我が国の大企業の創始者は全てリーダーであろう。日立の小平波平氏しかり、ホンダの本田宗一郎しかりである。しかし、企業が発展した段階では、マネージャーが求められる。既存の価値を守る人材である。世間では、このリーダーとマネージャーの区分も良く理解出来ていない。リーダーは、「見えないものを見る」のに対し、マネージャーは、「見えるものを解析する」のである。私は、部長に「貴方は、自分をリーダーだと思うか?マネージャーだと思うか?」と聞いてみた。彼は、「どちらも失格だな。」と私との議論を避けた。自分の考えを議論出来ないだけで、彼は、リーダーでは無い事は明確で有る。
リーダーには、暗黒面が有る。それは、ヒトラーを見れば分かる。彼は、本書で述べるリーダーの側面を全て有している。従って、本書の定義で言えば、彼はリーダーなのである。しかし、歴史上に名を残す人類に対する大犯罪者である。ここで、本書は、リーダーには、高い倫理観を求めている。リード・ザ・ソサイアティの段階を踏むものには、この高い倫理観を求められるのである。日本における松本智津夫もそうである。信者の間だけであるが、信者のソサイアティに対しては、リード・ザ・ソサイアティに達していて、この意味ではリーダーであるが、日本犯罪史上に残る大犯罪を犯している。
歴史に名を残すリーダー、ガンジー、キング牧師、ケネディ等々数えられない程居るが、彼らは、本書で述べるリーダーの要素を全て備えている。
私の周辺にリーダーと呼べる人材は、居ない。私は、自らがリーダーに成るよりは、フォロアーに成りたい人物である。しかし、リーダーは見当たらない。自らは、リード・ザ・セルフの段階でリーダーの要素は、持っている。ここが寂しい。
紙の本
実践的ではないが、本質的
2008/12/29 01:48
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:テレキャットスター - この投稿者のレビュー一覧を見る
「この本は、手っ取り早くリーダーシップを身につけたい、手っ取り早くリーダーを育てたいと思っている読者の方々には、あまり参考にならないかもしれない」と著者自身が認めている。確かに、明日からリーダーとしていかに振る舞うべきか、本書は教えてくれない。ただただリーダーシップについて、深く考えさせられる。いや、悩まされると言った方が、正解かもしれない。
その原因は、本書の論じるリーダーシップが「エマージェント・リーダー(自然発生的なリーダー)」を前提としているところにある。ところが、企業における多くのリーダーは、「エマージェント・リーダー」ではなく、あらかじめ役職や部下を与えられた「任命されたリーダー」である。そのギャップに悩まされるのだ。
とは言え、この本が無価値なわけではない。むしろ、純度の高い、本質的なリーダーシップについて考えを巡らせる、貴重な機会を与えてくれる。
リーダーは「結果として」なるものだ、と本書は主張する。タイトルにもなっている「リーダーシップの旅」とは、この「結果として」リーダーになるプロセスを指している。それは、「リード・ザ・セルフ(自らをリードする)」「リード・ザ・ピープル(人々をリードする)」「リード・ザ・ソサエティ(社会をリードする)」という段階を経るという。
「リード・ザ・セルフ」とあるように、この旅の起点は、自分の中にある。他の人には「見えないもの」を見ようとする、実現させようとすることが、初めの一歩だ。その原動力となるのは「何のために行動するのか、何のために生きるのかについての自分なりの納得感のある答え」だという。
その答えを見つけるヒントとして、本書には「ナメクジが這った後に残る白い線」「馬車が去っていったあとの轍」といった表現が登場する。つまり、これまでに自分がやってきたことを振り返り、「キャリア・アンカー(自分が一番自分らしいと感じられるキャリアのよりどころ)」を見つけることが重要なのだ。「中年が見る夢は現実性とのすり合わせができていて意味がある」という一文には説得力がある。
本書では、他にも、リーダーシップとマネジメントの違いや、リーダーに求められる資質(構想力、実現力、意志力、基軸力、そして人間力)についても論じられている。
この本を読んでも、明日からすぐに役立つ知識やテクニックが身に付くわけではない。ただ、繰り返しになるが、リーダーシップの本質を深く考えさせられる。本書に言わせれば、それは「生き様を問う」ことに他ならない。
リーダーとして行きづまりを感じている人には、ぜひ一読をおすすめしたい。そして、悩んでほしい。準備ができたら、旅に出よう。
紙の本
自分への問いかけを怠れば、リーダーシップは理解できない
2007/08/16 14:38
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:六等星 - この投稿者のレビュー一覧を見る
リーダーシップ研究と実践の第一人者二人が、リーダーシップをコンピタンシーではなく、「見えないもの」を探し求めるプロセスととらえ、リーダーはなろうとしてなるのではなく、「結果として」なるのだと、説いている。理論書というよりはエッセイ的な、対談形式だが、それがゆえに、自然な発想と切り口で、リーダーシップ論を深堀りしている。
だがあえて注文したい。両氏ともマネージャーとリーダーを区別することに力が入っているが、この区別を実際のシーンに適用することに、現実的な効用はあまりないだろう。ある人物がマネージャーなのかリーダーなのかを区別しても、その人は一人なのだから、結局両方の要素を持っているとしか言いようがない。リーダー率何パーセント、マネージャー率何パーセントなどと測定できるわけないし、たとえある時点での傾向が説明できても、彼(彼女)が次にとるべき行動を決めてくれるわけでもない。マネージャー、リーダーと表現するから区別をしたくなってしまうのであって、単純に例えばボスと表現してリーダーとマネージャーの両方の性質をもつ人物として捉えることに、実用的な不都合はないはずだ。
とはいえ、本書全体としては最高ランクの評価をつけたい。エピローグで野田氏は「いつ旅が続けられなくなっても、自分に納得できるよう一歩を歩みつづける。旅の結果よりも、そのこと自体が一番重要ではないか」という。そもそもリーダーシップの旅はどこへ行くのか、行き先がわからない旅もある。だからこそ「旅人としての自分の今を問い続ける」ことが大事なのだ。自分への問いかけを怠れば、リーダーシップは決して理解できない。その主張に素直に賛同したい。
投稿元:
レビューを見る
リーダーシップについての理念、思想、ひとつの理想型を説いている。所属する組織社会はどうにも理不尽だ。あんな上司、社長がのさばっている会社はいずれ立ちゆかなくなるに違いない・・・そうは思って(願って?)いても、存外どこ吹く風の様相を呈しているもの。『究極の利己とは利他である』と引用するが、結果はあくまで結果であり、ある言説が正しいことを決して証明するものではない。よい子は理解しやすい、もしくは理解可能なきれいごとにすぐに飛びつかないこと。そんな私はひねくれ者かしらん。けれど、エピローグで紹介のスティーブ・ジョブズSEO復帰スピーチは感動的。この文章に出会えただけで私には十分過ぎる。
投稿元:
レビューを見る
評価も高そうで、日経ビジネスでも紹介されていたので読んでみました。
リーダーシップ論としてはとても変わったアプローチの本です。まず、その構成として2人の著者が対等な立場で交互に前の論旨を受けて話を展開していく形式になっています。この構成自体、非常に成功しにくい形式だと思うのですが、本書は2人で語ることによって流れを壊すことなく話題を発展させ、説得力を加えている稀なケースだと思います。著者2人の論者としての力量に加えて編集者の手腕の確かさが感じられます(あとがきでも当然のごとく謝意を表されていますが)。
また内容としても、「リーダーになろうと思ってリーダーになった人はいない」という最初のところからして普通のリーダーシップ論から距離を置いています。よって会社で部下を持ったからこういうのを読んでみようかな、という即効性を求める人には全く不向きです。そもそも、リーダーシップ論が会社の組織論と合わせて議論されてしまっているところがリーダーシップ論の不幸だとも言っています。もう少し大きな観点からのリーダーシップ論(論というべきではないのかもしれません)として、読まれるべきものだと思います。それが役に立つのか立たないのかはあなた次第というところで。
良書だと思います。
投稿元:
レビューを見る
リーダーとは何か。伸ばすがリーダー。維持するのがマネージャー。今求められるのはリーダー。大きな絵が描けないから日々が忙殺される。リーダーは課題解決ではない。後ろを振り返ると皆がついてきている。誰も見ていない絵を見る。
投稿元:
レビューを見る
2008/3
リーダシップって一体何?
そこから始まり、リーダーシップというものがどうしたら見についていくのか、まさに旅のようなものだと著者の2人が解説している。読んでいてうなづける部分も多く、なかなかいい一冊。
投稿元:
レビューを見る
リーダーシップという言葉を聞いて、大抵の人が思いつくイメージ(先頭をきって周りを引っ張っていく、率先してまとめ役になる、など)を一掃した上で、人間一人一人に宿る果てしない可能性と、生きていることの幸せを、分かりやすい言葉で記した人生論にも似た書籍です。この種の本で涙を流すとは思いませんでした(最近の私が涙もろくなっているのは差し引いたとしても…)。実際、終章で著者二人から読者になげかけられる言葉の強さは誰の心にも響くはずです。
この本がテーマとして掲げるリーダーシップに関する議論(偉大な人=リーダーシップという定義)と、リーダーシップ待望論とのギャップを折り合わせることができないことはなぜなのか?時代の急速な変化からリーダーを待望する声が高まっているのはあきらかなのですが、その言葉から想起されるリーダーといえば歴史に名前を残すような偉大な人しか思い浮かべられない…。それはリーダーという言葉への理解や、その理解から想起されるものへの縛りがあるからだと思うのです。著者の二人は、さまざまな事例を引き合いに出しながら、この縛りをほどいていってくれます。
こうした二人の言葉に、自分の心が共鳴していると感じられるのであれば、既に読者はリーダーであるため(リーダーになるため、ではないことに注意)の旅を始められる準備が済んだといって良いと思うのです。天性、学歴、略歴などがリーダーの素質を形成するのではないことを、できるだけ多くの人に気付いて欲しいと思います、この本を読んで。私の心に響いた文章は数が多すぎるので、解釈をまとめたものを記します。
●リーダーはある条件を満たしたり、目指して「なれる」ものではなく、周囲の認知があっていつの間にか自然状態として「ある」ものだ。
●「Lead the Self」、「Lead the People」、「Lead the Society」へと進むより広い範囲とかかわりあうようになること。
●組織の安定性と持続性を維持するためにはマネジメントが必要であり、組織の変化を生み出すためにリーダーシップは機能する。
●事前の不確実性と事後の確実性という異質な2つを、リーダーシップは飛び越える。
●リーダーには魅力としての人間性がある。それを要素分解すると、「構想力」「実現力」「意志力」「基軸力」の4つに大別できる。
●「カリスマ」に全てを頼り、任せるのは危険だ。ダースベイダーやヒトラーはそうして生まれた。
●人についてきてもらったという経験が、自身の原動力を利己から利他にする。自分の夢が皆の夢になる。
●社会を構成する個人は、等しく社会に責任を負う。他者とのつながりから生まれる喜びを、その人へではなく別の人や社会に還元することを実践する。Noblesse Oblige(高貴なる責任)の体現。
●徳とは、自己の最善を他者に尽くすことである。
●人はいつ死ぬかわからない。死生観を内包した人生設計が生きることの喜びと活力の源になる。
私は、既に両親、祖父母、家族・親類、恋人、恩師、友人、同僚、自然、日本、世界から数え切れない物的・心的ギフトを数多くいただいてきました。そのギフトをいただけた喜びが���の私を大部分を形成している。そのギフトへの返礼も何かしらの形で示したつもりだけど、本当は同じような喜びを他の人に感じてもらう精神、映画『Pay Forward(ペイ・フォワード)』で示されたような、感情の伝播・同期化(シンクロ)の一部になれるように生きていきたいと思います。
だから、私も「旅」に出ることにします。その「旅」から生還できるように都度努力し、その折にはこの星、この世の中、この社会のどこかにポジティブな形で貢献できていて、リーダーやエリートにいつの日かなれているような、そんな「旅」に出ようと思います。次の質問に、一つ一つ答えを見つけ出しながら…。
自分は何がしたい人間なのだろうか。
自分にとって現状を打破する仕事や挑戦はどのぐらいの意味をもっているだろうか。
それを実現できたらどういう気持ちになるだろうか。
逆にチャンスを見過ごし、着手さえしなかったら、後でどう感じるだろうか。
悔やむだろうか。悔やむとしたら、どのぐらい悔やむだろうか。
では、着手するとしたら、待ち受けている困難はどれほどのものだろうか。
自分にはその困難を乗り越えるだけの心の準備と気構えがあるだろうか。
それほどまでしてやり遂げたい仕事や挑戦なのだろうか。
(196ページより引用)
現在、著者の一人である野田さんは、経営者や有識者200人以上を巻き込みながら活動しているNPO法人「Institute for Strategic Leadership」を主宰されて活動しています。アカデミックな人間としては、王道というかこれ以上ないキャリアを歩んだ彼が、学校という場所ではなくて、NPOという組織形態を選択して、経営や市場の現場で活躍する人々とダイレクトにやりとりすることを選択したこと。教職というものに可能性を感じている、もしくは実現させたい目標として考えている私には、生き方として学べることの多い方だと思いました。この転身には、多分に彼の親友であるスマントラ・ゴシャール氏の影響を感ぜずにはいられません。
理念だけでは乗り切れないと喝破する人もいるでしょう。でも、現実を前に立ちすくんでいるよりはよほど良いと思います。理念や理想も形にしていくことで現実になりえるのですから。そんな私は、野田氏が翻訳をされたゴシャール最後の著書・『意志力革命』を読み始めました。こちらの感想文も後日書ければ…。
投稿元:
レビューを見る
大好きな金井先生の本ということで、読みましたが、金井先生以上に、野田さんの文章および熱い思いに感銘を受けました。
リーダーシップというと、マネジメントに携わる人向けのようであるけど、
ビジネスマン&ビジネスウーマンだけでなく、多くの人に通じるものと感じた。
非常にすばらしい新書です。
投稿元:
レビューを見る
NPO法人ISL理事長の野田智義氏と神戸大の経営の金井壽宏先生との共著。金井先生の本を読みたいと思い、購入。リーダーシップに関する本。この本で語られているリーダーというのは、組織の管理者(マネジャー)的なリーダーではなく、「他の人が見えない何か」を求めて独り、旅に出て、気づいたら後ろに多くのフォロワーがついて来ていたというような坂本龍馬型のリーダーの話。旺盛な探究心、謙虚さ、無償の贈与、バランス感覚などがそのようなリーダーにとって重要な要素だと感じました。内容も濃く、すごくいい本でした。
投稿元:
レビューを見る
星が4つの理由は、自分が途中までしか読んでいないからです。
最初の2章の印象は、とても好感が持てます。
ほかのリーダーシップに関する本は、専門用語が多かったり、個人の経験談を述べたり、知識のない人間にはちょっとつまらない内容でした。ちゃんとさがせば面白いのもあるかもですが。
こちらの本は、私が今、実際に学んでいる「リーダーシップ論」の先生も推奨です。
投稿元:
レビューを見る
2008年7月終了。
一度は途中で放り投げてしまっていた本。再度トライしたら面白いこと!面白いこと!
リーダーとは・・・に悩んでいる人、次なるステップに進みたい人なんかにオススメ。
とりあえず私は一歩進めたと思います。
投稿元:
レビューを見る
「最初から結論を言わせていただくと、リーダーシップとは、私たち一人一人が自分の生き方、仰々しく言えば、生き様を問うことだ。」
リーダーにもリーダー論にも興味があるわけではないのですが。この本にあるのはリーダーシップ論というよりは人としての「行き方論」だったように思う。
リードザセルフ⇒リードザピープル⇒リードザソサイエティ なるほど。
投稿元:
レビューを見る
この上半期でベストの一冊。精読&この本から何冊もの本との出会いがあった。
リーダーシップは見えないものを見る旅だ。ある人が見えないもの、つまり現在、現実に存在せず、多くの人がビジョンとか理想とか呼ぶようなものを見る、もしくは見ようとする。そしてその人は現実にむけて行動を起こす。世の中ではよくリーダーはフォロワーを率いる、リーダーシップはフォロワーを前提とsるなどといわれるが私はそうは思わない。旅はたった一人で始まる。(21)
その人がなぜ結果としてすごいリーダと呼ばれるようになったのか?のプロセスに興味がある(19)
リーダシップを旅に例えながら進めていく。旅の隠喩はリーダーシップをプロセスの視点からとらえるのに有効(21)
皆さんはリーダーと聞いて、どんな人をイメージされますか? → 天安門広場で戦車をとめようとして一人で立ちはだかった、名も知れぬ若い中国人の男性。 すごいリーダじゃないふつうの人のリーダ(24)
ポイントは権力や権限で人を動かすのではないという点だ(33)
経営学者の理論。実務家の持論。実務家の内省から生まれる持論。それをかたるのは高度で良質な言語ゲーム。内省的実践家。36
リーダーシップについては最終的に自分なりの持論をもとうとすることが大切だ(37)
リーダーシップの旅はリードザセルフを起点とし、リードザピープル、さらにはリードザソサエティへと段階を踏んで変化していく。この流れをリーダーの成長プロセス、リーダが結果としてすごいリーダーんあるプロセス。(50)
私たちは深く暗い森の中にいる森の住民だ。村の外れに不気味な沼地。村には昔から言い伝えがあってこの沼をわたるな、わたって戻った者はいない。たまに好奇心のある人が足を踏み入れるが、気持ち悪さにすぐ引き返す。村で暮らすあなたは何か抑えきれない衝動がある。遠くめをこらすと、沼と森の果てに何か光が見える。ひょっとしたら豊かな森と草原があるのでは?そこのすめればすばらしいのでは?たのしいのでは?と心が弾む。青い空を自分でみたい、年老いた両親にみせてやりたい。沼に第一歩を踏み入れる。水は冷たく、泥はよどんでいて深さをましていく。恐怖が襲い、思わず身がすくむが、それでお沼をわたり抜け森を抜けたい、青い空を見たい、見せてやりたい、という気持ちがあなたに歩みをつづけさせる。これが自分をリードするといいうリード・ザ・セルフだ。(52)
旅にでたいかどうかをまず頭で考える。頭では考えていてもなかなか一歩を踏み出せない。ココロがのぞんでいないから。(53)
リーダーは内なる声(inner voice)を聴く(Wベニス)(53)
フォレストガンプの例(56)
張さんの例(中国の留学生)(57)
振り返ると人がついてきていた経験(59)
リーダーはダンスフロアで踊る事もあるしバルコニーにもたってフロア全体を長めなる事も必要(ハインツェフ)(65)
リーダーは成功するから旅を歩むのではない。成功しなくても見たい者があり実現できるはずと信じて旅に出る。天安門の前で戦車に立ちふさがった中国人青年もそうだ(67)
不安と不確実性の中を、��スクをおって前えと進んでいくのがリーダーシップの旅だ。(67)
トランザクショナルリーダー(取引的/交換関係のリーダー)。論考行賞で動かすタイプ。一方で見えないものを見て、志と目指す者の崇高さゆえに飴とムチを使わずに大変革を成し遂げた人をトランスフォーメーショナルリーダーと呼ぶ。組織や企業はトランザクショナルリーダーであふれかえっている。トランスフォーメーションというのはチェンジとは違い、根底からがらっとかわる大変革。実際のところ、そんなリーダは滅多にでてこない。トランザクショナルとトランスフォーメーショナルリーダーの隔たりを埋めるのが「ささやかだけどトランザクショナルではない」リーダー。トランスフォーメーショナルほどおおげさじゃないけど、餌ではつらない。69
自然発生的(エマージェント)なリーダ、選挙で選ばれたリーダー、任命されたリーダの3種類の分類(70)
組織で生きる私たちちはこの3つのうちの二つだったりすべてを同時に背負ったり使い分けたりする可能性がある(74)
リーダーは旅にでるまではリーダーではなかったということだ。リーダーとはフォロワーを導く人ではなく振り返ると人がついてくる人をいう(75)
リーダーシップをマネジメントはどう違うとおもいますか?78
なぜ部下は社長や上司についていくのか?一般的な会社や組織において、部下がトップについていくのは、トップがリーダーシップを発揮した結果ではなく、ヒエラルキーによってだ。(82)
リーダーシップとはフォロワーを束ね方向付けする、という回答にマネジメントとの混同を感じる。ヒエラルキーの中ではリーダーシップではなくマネジメントが日常的に機能する(83)
もちろんポジションや権威を用いて組織を動かす事も大事。でもそこだけに焦点があたると、人を巻き込んで自発的に動いてもらうというとても大事なリーダーシップの本質が抜け落ちる(84)
権限を伴うポジションにある人間がリーダーシップを語るとき、そこには危険な落とし穴があることだけは最低限認識しておこう(84)
リーダーシップはいったいどこにあるのか?リーダーの側か?フォロワーの側か?両者の間か?リーダーシップはフォロワーの頭の中にあるといいたい(88)
リーダーはポジションではない。リーダーたる人物があるポストを手に入れた場合、その人のリーダーシップに何グラムかの不純物がまじりはじめる(90)
企業内でリーダーシップを語るとき、「指揮系統下にいない応援団がどれだけいるか?」を試金石と考えている。後ろを振り返ったらいやいやではなく喜んでついてくるフォロワーがいますか?(91)
ガンジーの有名な塩の行進(91)
トップ自らがリーダーシップをマネジメントをはき違えてしまうと、自分のどんな部分にフォロワーが喜んでついてきてくれてるのか?がわからず落とし穴に陥っていることにトップ自らが気がつかないという事態が起きる危険性がある。リーダーシップとマネジメントの違いの第一は、見えるか見えないか。リーダーは見えない者をみて、マネジメントは見えるものを分析し漸進的に対応していく。SWOT分析は見える者を対象にする。第二点は人としての働きかけか地位に基づく働きかけか。第三点はシンクロ(���期化)するか、モチベートするか。リーダーシップはフォロワーとリーダーの間にそれぞれの夢がシンクロナイズドしていく。マネージャーは部下を動機づけて動かす(92)
リーダーは創造と変革を扱う(96)
驚きはいらないマネジャー、驚きだらけのリーダー。
マネジャーを複雑生への対処、リーダーを変革への対処とキーワードで対比した。できるマネージャーは不在でもまわる組織を作る。102
マネジメントによって複雑性を減少させることが組織化のプロセス。目標達成のために不意打ちをミニマイズする仕組みが組織。それゆえにマネジメントに驚きはいらない。そういうのが上手なのがいい子ちゃん的なエリート。組織は組織化を進めれば進めるほど、つまりマネジメント機能を充実させればさせるほど、自己破滅の危険にさらされる。なぜなら環境が安定してる間はいいが、変化したときに、組織は過去への過剰適応をしているため現在の変化した環境との乖離を生んでしまう(111)
組織はリーダーシップを育む豊かな土壌を提供しているだろうか?組織の中で働く人が、組織の中でリーダーシップを発揮することはたやすいことなのだろうか?(112)
リーダーシップは実際にリーダーシップをとった人にしか教えられない(113)
会社をかえたい、かえようと努力を繰り返し、結局、何もかわらなかった時、人は「学習性無力感」を抱く。変革志向のミドルほど無力感を抱く。リーダーシップをとろうとする人ほど疲れ果て、気められたやらされ仕事だけする人が元気になる。(115)
経験から持論を。リーダーシップの学校は経験だと考えているが、こうした経験を会社の中でぐるぐるまわしていく事は不可能ではない。肝心なのは経験を放置しないこと。上司がとったリーダーシップを観察したらみんなで議論して教訓を引き出せるような場が必要。経験の意味付け、蒸留、純化が起きれば会社内にリーダーシップがおきる可能性がある。イーラリリーはleadership begins with leadershipを社内兵庫にして役員以下全社員がリーダーシップを自分たちの問題としてとらえる試みをしている(121-122)
リーダーシップについてそれぞれの社員が現場レベルで話し合いをし、考える。シニアリーダーたちが社員の前で自身のリーダイーシップについて語るのだ。(122)
リーダーシップについての自分なりの経験や観察を通じて、人に教えようと思えば教えられる自分なりの考え、見解、持論を持つ(122)
信用蓄積と特異行動(150)
夢なんか実現しっこないという人もいるが、実は夢しか実現しない。CCC増田社長(159)
不毛な忙しさ。アクティブノンアクション。毎日を多忙にすごしてるのに、本当に必要で意義があるように思えない状況。アクティブにみえて実は何の行動もしていない状態(164)
忙しいから絵が描けないのではなく、絵が描けないから忙しいのだ(168)
怠惰な多忙(ちなみに怠「情」ではなく。タイダ)。人生が短いのではなく、その多くを浪費しているのだ(セネカ)169
自分探しと志しや夢をたてることの違いは?。自分探しが問題の先送りや言い訳。それは私たちをどこにもつれていってくれない。自分探しに明け暮れて先送りするのではなく、いま現実に踏みとどまって現実と向き合いハードルをひとつづつクリアしていくことが必要では。実績をあげ人の信頼を勝ち取り信用を蓄積していくことは、リーダーシップの旅を始める準備をしたり、旅をはじめ継続するためにも有効だ。でも信用蓄積には落とし穴がある。手段であるはずの信用蓄積がいつの間にか目的になってしまうと私たちは旅にでることができなくなる(178)
リーダーシップの旅をつづけるのに必要なことはなんだろうか?構想力、実現力、意思力、基軸力と考える(182)
構想力:構想力においては、最初から絵を描ける力よりも、見えない者をみようとしてもがき、感じる力。旅の途中で突然、描けるようになる。184
実現力:構想を現実にかえる実現力。コミュニケーションを通じて見えないものへの理解、共感をえて、周囲や組織の中で行動の輪を広げ構想を現実にかえていく力。IQよりEQ(191)
意思力:沼地への最初の一歩を踏み出す意思力。マネジメントの世界では、外部からモチベートされることで人を動かすが、それだけでは足りない。なぜなら外からあたえられたものは環境の変化で意味をなくすことがある。ココロの奥底から踏み出したい、踏み出すんだ、後戻りしたくない、前へ歩くんだという力が行動をうむ(193)
基軸力:最初から確信をもってやれる人なんかいない。でも歯をくいしばってただしいんだと思って進める。そしていつしか確信が生まれる。203
クロートンビルを毎年1万人の革命家を生み出す場所にしてくれ(197)
4つのE。エナジー、エナジャイズ、エッジ、エクスキュート。エッヂは、誰かがいやな意思決定をタフにできること(197)
やるといったら絶対やる、とことんやる。途中で逃げない。というのはリーダーシップの条件の一つ。ポイントオブノーリターン(201)
企業の戦略の有無を議論する試金石として、選んだという意図がはっきりと存在するかどうか、意図的に選んだときにトレードオフの存在がしっかり自覚されているか?を問いかける。選択した代償として何を放棄したか?があるのが戦略。206
自分はどんな時に燃えたか、どんなときにがっかりしたか、部下はどんな時にもえたか、がっかりしたか?その理由は何か?を5分間話し合う。(211)
ビフォアレポートとアフターレポート。リーダシップについてかいてもらって、すべてのセッションがおわったらもう一回かいてもらう仕組み(211)
ミンツバーグのマインドセット。経営幹部がもつべき基盤。各職能が横串で持つべきココロのありよう(212)
リーダーシップの旅を歩む上で必要な力を要素分解すると「構想力」「実現力」「意思力」「基軸力」。でも要素分解には常に木を見て森を見ずの危険が伴う。これらの総合的な力がリーダーが人として持つ魅力、人間力(229)
人間力のある人とはこの人についていきたい、一肌脱ぎたい、一緒に仕事をしてみたい、といってもらえる人である。戦略的思考とかコミュニケーションスキルを磨く前に、魅力的な人間であること、リーダーはそれにつきる(229)
あなたのベストジョブは何ですか?仕事で一皮向けた経験を3つ語ってください。そこから経験にどういう教訓がありますか?その教訓はあなたのリーダーシップの持論に対して持つ意味あいはありますか?(228)
意思力は頭とココロの一致���なり、アクティブノンアクションを乗り越える力になる(232)
一皮むけた経験を内省すること。それは旅のきっかけには有効だ(233)
旅のスタートは高邁な理想である必要はない。旅の途中で私たちはふと振り返ると誰もついてきていない、という経験を味わうときもある。その分かれ目にあるのは利己と利他のせめぎあい。(240)
企業経営とは自分の夢を実現することではなく、現在はもちろん将来にわたっても従業員やその家族の生活を守っていく事だと気がつく。とんでもないことをはじめてしまったと思い知らされたl(京セラ、稲森さん)(242)
リーダーシップの旅を歩む人は自分の内なる声を聴き、一歩を踏み出す。(244)
人が後押ししてくれるから自分は先頭に立てる。やていける。自分が他人を支えているのではなく他人が自分を支えてくれる。己とほかの境界線は消えて利己と利他は渾然一体となる(244)
リーダーが学ぶべき事。徳を身につけることだ。徳とは自己の最善を他者に尽くす事だ(258)
人とのふれあいこそが人を成長させる。ローソンの新浪社長はフランチャイズ店のおばさんの笑顔で成長する。世のため、人のためというきれいごとではない人のふれあいが人を成長させる。ITベンチャーや金融マーケとから骨太なリーダがうまれにくい遠因ではないか?(ボランティアにいくべきかな)262
リーダーシップがそこに存在するかどうかを見定める基準として、自立的な判断を失う事なく喜んでついてくるフォロワーがいるか?(266)
リーダーが強力すぎてメンバーが自律性を失ったり従順になりすぎたりするのは問題だ。ダークサイドに陥りリーダーのダースベイダー化が進む(266)
リーダーシップをパフォーマンスとメンテナンスからとらえる。PM理論。放置していくとどんどんパフォーマンスにいく。だからメンテナンスも必要。三隅先生。タフなだけでもやさしいだけでもやっていけないのだーフィリップ/マーロウ(270)
スパイダーマンのスピーチ。ギフトを返す旅。旅を続けた結果、リーダーになった人は結果としてたくさんのギフトをもらっている。周囲の人たちとかから。ギフトには世界共通の原則がある。ギフトは返さなければいけない。くれた相手ではなくほかの人や社会に対して返すという原則だ。275 これが選ばれしモノの責務であり健全なエリート意識(278)
リーダーシップの旅を歩む人はギフトを授かる。得た者は自分の努力への対価でもあるが、旅を歩んでいられる事、歩ませてもらった事自体がギフト。もらたものを人に、社会に返そう。苦しい事、つらいことがあってもそう素直に思える人であればリーダーシップの旅も貫徹できるだろう(279)
リーダーは「結果として」なるものだ。旅をはじめ、続けるうちに、いつ振り返っても人がついてくれる経験をし、自分の夢がみんなの夢になる経験をし、利他性や社会性に目覚め責務感を身につけていく。すごい人だから身に付くのではなく、身につけなければ旅を続けられないから自然に人間が磨かれていく(280)
リーダーシップとは生き様の問題なのだ(286)
リーダーシップ。それはたった一回の人生という旅であり、生の意味を問い続けるプロセスである。(291)
投稿元:
レビューを見る
(解説 アマゾン抜粋)
天的な環境がリーダーを育むと説き、「すごいリーダー幻想」に惑わされるなと指摘。類まれなるリーダーとして称えられる者たちは、自らなろうとしてそうなったのではないと断じ、彼らは信念を貫く「旅」を歩む中で、結果的にフォロワー(従事者・支援者)の共感を呼び起こしたのだと言う。
(個人所感)
リーダーシップは、「内なる声」に耳を傾け、「旅」を経ながら、見つけていくものだということ。
「社長はなろうと思ってなれるかもしれないが、リーダーになろうと思ってなった人はいない。リーダーは結果としてなるものである。」「リーダーとマネージャーは違う。」「リーダーは創造と変革を扱う。」「現在の競争だけにとらわれていないか。忙しいふりだけをして、大きな絵を描くことを忘れていはいないか。」
など、ガツンと頭をたたかれた気がしました。同時に目の前が開けた気がしました。
というの、自分自身がリーダとはなんだろうかと整理できずにいたし、自分流に解釈すると、「どきどきわくわく」すればいいんだ
それが自然とフォロワーの共感を呼び起こすのだと気づき、特別な理屈やスキルが必要な高尚なものだと思っていたリーダ像がとても身近に感じたからです。
一方で、現代の複雑な事業構造の中で、事業リーダとして「いくらかの」責任を持つ以上、フォロワーを率いる責務として、闇雲に走るだけではなく、説明責任やメンバーの居場所の確保、気持ちのフォロー、知的好奇心の充足の場所など、リーダーシップ以外の以外のスキルを再認識しました。
リーダーシップ、マネージャー、事業経営の整理が自分自身でついた一冊です。