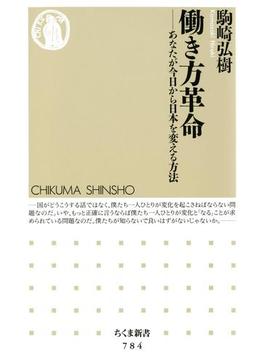紙の本
著者の自己啓発の記録
2009/11/21 22:12
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:marekuro - この投稿者のレビュー一覧を見る
前作がビジネス書的に良かったので
新書になった本書は、ビジネス書よりも
詳細に社会起業家に関する色々を学べるのでは?
と期待して購入しました。
結論からいうと、期待とは違いました。
なぜなら、本書は働き方革命と言ってはいますが
その内容はほとんど
著者の自己啓発記だからです。
「こんなに自己啓発しましたよ」的な記述のオンパレード。
もちろん自己啓発記が悪いと言う訳ではありません。
選書の段階で自分のニーズに合わない本を
選んだ評者のミスも大きいです。
ですが、本書の評価を3にしたのは
自己啓発書としては中途半端
そして、社会起業家についてを学ぶには
あまりに記述が散文的。
ワークライフバランスについての
詳細な提言があるわけでもなく、
あるいはワークシェアリングについて
述べられているわけでもなかったからです。
言い換えるなら、「働き方革命」と呼ぶには
少々タイトルが大げさなのです。そして副題も大げさ。
本書で述べられているようなノウハウは
類書にもっと優れた物がたくさんあります。
けど、読み物としては読みやすいと思います。
自己啓発書やビジネス書の著者にありがちな
鼻につく自慢話は少なく、どこかノリと勢いで書いたような
文章は読むのに労を要しません。本書から勢いをもらうことも出来るでしょう。
また、自己啓発記として読むのなら、参考になる箇所が無いとは
いえません。実際、いくつか参考になる箇所があったのも事実です。
しかしタイトルやサブタイトル。帯に偽りありといった印象は拭えません。
前作が参考になったと共に楽しめる内容だった事。
また著者の本業での活動が尊敬できるものである事から
次回作に期待したいです。
投稿元:
レビューを見る
2月1日、はっきりとした口調で駒崎さんが言ったこと。
「勉強しなさい。ついてこれないやつはついてこなくてよろしい。」
正直、学生を切り捨てるような怖さを感じた。
でもそうじゃないことがよくわかった。
挑発―
伝わらない人には伝わらない。
でも伝わった瞬それはとても大きな力になる。
駒崎さんのような、人間になりたいと心底思った。
投稿元:
レビューを見る
日本の多くの会社が似たような現象を起こしてる。就業時間が長過ぎる。友人と話しても、必ずどこかで忙しさ自慢になる。「今週全然寝てないよ」「土日も会社行かなきゃだよ」って。
え、でもこんなに働かなきゃ、日本ってまわらないのかな?こんなに頑張らなきゃ、食っていけない国なのかな?
この疑問はずっと、僕の中にあって。もしそうなんだとしたら、変えなきゃいけないと思う。「働き方」を。筆者が言うように「働く」の概念を拡張するんだ。傍を楽にさせること、それを全部「働く」ととらえて。
僕のライフビジョンは著者のものともう少し違うと思うけど、みながその実現に向けていけたらいい。
投稿元:
レビューを見る
働き方革命と題し、働く=他者に価値を与えることと広い意味で再定義。目標を掲げライフビジョンを描くことが大事。仕事のスマート化の為、スリムタイマーを活用とかいており、導入したいと考えた。育児、介護、様々な課題が山積する課題先進国日本が解決策を輸出出来る様、まずは帰る時間と寝る時間、休日の調整を図り、コミットメントを増やしていきたい。
投稿元:
レビューを見る
自己イメージが、私たちの行動を規定する(52頁)
アフォーメーション(54頁)
目標は必ず言語化し、繰り返し見て、自分自身に刷り込んでいきなさい。(69頁)
メール自動転送
「自分のやるべきことを把握し、それに沿って仕事を組み立てる」ということから逃げていないか。(87頁)
投稿元:
レビューを見る
【オススメ人】中村奈津
【読んでほしい人】就職活動生・働く父親、母親
【オススメポイント】
「働く」というのは会社に行って仕事をすることだけじゃない。
「傍(はた)を楽(らく)にすること」それが働くの語源。
ワークライフバランスというのは、なにか新しい価値観ではなく
当たり前に存在していた価値観だったと気付かされた本でした。
就職活動をする際、自分はどう働きたいのかという考えを
広げて考えようとするので精いっぱいで、
しかしそれ自体が視野が狭くなっていることと同じでした。
就活を終えてみて、多くの学生・社会人は
「あの頃は必死だった、懐かしい。」と振り返る。
しかし就職活動は一時の試験なのではなく、
将来を考える一番大切な時期だと思う。
この本を読むことで、本当に自分の人生を考えていくことができる気がする。
投稿元:
レビューを見る
「働く」ということは、「仕事をする」と言うこととはイコールではない。
働くとは、家族との時間を共有したり、地域の活動に貢献したり、自分磨きの時間にあてたり
といろいろなことをするためにあるものであると。
働くということについて、もっと多くの人が考え始めたら本当に変わるのではないだろうかと思う。
自分も含め、多くの人が「働く」ことに対して改革を起こす時期が来ているみたいです。
投稿元:
レビューを見る
一人一人が、自分の未来についてマジになる。
革命ほどではないけど、変化は一人一人がもたらす時代になっているんだ。
投稿元:
レビューを見る
一気に読んだ。働きマン、寝る時間も惜しんで働き、残業しない日はない、日々笑顔を忘れ、仕事のメールに追いまくられ、効率ばかり求めていた著者の「働き方革命」。一言で言うとワークライフバランスがうまくいった人の話になっちゃうけど。自分がどう生きたいか、考えていることを書き出してそれを実行していく。なぁんだ そんなこと と思うけど、思うだけなのと実際実行するのでは、10年経ったとき天と地ほどの差があるんだろうね。まず目標とするライフビジョンを描くことから始まる。・私は家族と仲良しである・両親が丈夫で楽しく暮らしている・仕事にやりがいを感じて充実している などなど。そうだね〜私も書いてみよう!これもマインドマップと同じで、こうしたいっていう思いを描くとそれに向かって行動も自然とそうなっていくんだろうと思う。それもただ描きっぱなしではなく、毎日毎日見ることが大事。お金持ちになるのではなく、時間持ちになったというところも「うらやましい」って思う。
投稿元:
レビューを見る
「しごと」に対する考え方とかやり方とかの本。
感想としては「できる人はできる。できない人はできない。」かな。
やり方としてはGTDに通じるところもあってわかりやすいけど、時間を時給で比較するところところとか違和感が。
投稿元:
レビューを見る
社会起業家として著名な彼が、これまでに経営者として生きてきた時間を振り返りながら、時にコミュニケーションや仕事の割り振りを考えるビジネススキルを磨き、時に自分の働き方の違和感から時間の使い方からひいては長い人生設計そのものにまでつなげるなど、おおむねマネジメント全般を体験的に叙述した本です。
なので、言ってしまえば問題点として著者自身が発見するものは身近なものであり、管理職たりえる人となるには基本的に必要となるであろう項目が書かれているだけなのです。その点では新鮮味というものはあまり感じられません。しかし、駒崎さんと私の年齢が近いこと、そして彼が取り組んでいる分野が私の仕事領域と完全に重なること、さらには彼自身のかなり口語的でぶっちゃけ気味な文体な醸し出す親近感に引き寄せられる感覚が、この本を2時間弱でサラッと読み終えてしまえた理由なのかも知れません。
なので文章を読みながら考えるという私が選ぶ書籍でよくありがちなパターンにははまらず、読み終えてみて振り返りながら自分の明日にどう役立てるかというプロセスがこれまでにないスピード感で爽快感さえ感じることができました。本来ならば新書はこの程度のスピードで読まれるべきものなのかもしれませんがいかんせん遅読の私にはなかなか体験できないものでした。
既に読み終えている他の書籍との関連性でいえば、人口減少社会のこの国にあって一億総中流社会や男性中心社会など、高度経済成長期を通じて暗黙のうちに作り上げられてしまったテーゼを何によって突き崩していけば良いのかを考えるために必要な考えにワーク・ライフ・バランスがある理由を、考えるきっかけになると思います。折からの不況でやることがたくさんあるのに何が定時退社、何がノー残業デーだと言われることもあるかもしれません。
でも、一方で個人的にはなかなか達成できていない中で、自ら帰宅が遅いときには次のように割り切ることもあります。限られた時間の中で仕事を処理しきれないのは、自分のキャパシティに合わないほど膨大な仕事が集中しているか、もしくは与えられた仕事を時間内に処理しきれない自分の能力の無さを責めるのか。大概にしてわたしが後者であることが多い分、著者の訴えを実現できるように自己研鑽を続けて1分1秒でも早く自宅の扉を開けられるようにしなくては、改めて思える書籍でした。
投稿元:
レビューを見る
著者のまっすぐな性格が伝わってくる書き口でとても読みやすい。納得することは多く、自分も忙しさにかまけていないで時間を作らないといけないなぁ、と反省。
投稿元:
レビューを見る
最近、ある同僚と私の間で、ライフハックツールがはやっている。
主にタスク管理に関するライフハック的なアプリだとか、Webサービスだとかを使っては、これいいよ、とか教え合う。
その同僚が、スリムタイマー(slimtmer.com)を紹介してくれて、「この本に載ってたんだよね。もう読まないから、この本、あげるよ」と、いとも簡単にこの本をくれた。
そんないきさつで偶然手にした本だったが、読み物として面白く、そしてとても共感できる内容で、あっという間に読んでしまった。
会社を軌道にのせた著者は、いつの間にか、無駄な時間を許せなくなりどこでもメールを見て、仕事をしながらランチを食べるようになり、他の人の生産性の低さが目について叱ることが多くなり、土日は寝るだけ・・・
仕事のスピードだけはあがって、どんどん多忙になるスパイラルに入っていった。
そんな著者が、あるきっかけから、自分のライフビジョンを描き、それを実践していった結果、「闇夜の泥道を這うような働き方」から「晴れたハイウェイに愛車を走らせるような働き方」に変わっていく。本著には、その過程が描かれている。
面白おかしく書かれていて、少し脚色が入っているのかも、と思う。
でも、具体的にどうやってワークライフバランスをとっていったのかが書かれていてとても参考になる。
著者の本を読んだ、とてもとても優秀な女性の何人かが、著者の会社に入社したというエピソードも書かれていたけど、すごく、よくわかる気がした。働く女性キラーですね、この本は。
あと、個人的には、著者の姉との会話にめちゃウケ。
外資系勤めの著者のお姉さんが、「身振りと手ぶり」を駆使しながら、「私がアグリ-なのはね・・」とかカタカナまじりで言っているシーン。
・・・私のまわりにいっぱいいる。っていうか、私もそのうちの一人だ~。
普段は出ないようにしてるけど、同類と話すと、100%出る。
よく観察してますね、駒崎さん。なはは。
【とくに印象深かった箇所:本書からの引用です】
・ ジェンセンおやじは、仕事を楽しみ、一所懸命やりながらも、将来の自分のために勉強をして、家族を愛し、家族のために時間や気持ちを使い、地域にも貢献していた。ジェンセンおやじという1人の個人の中に、いくつもの世界があった。いくつもの世界がジェンセンおやじの中で綾をなしてキラキラと輝いていた。
・ 「会議のルール」から:
- ひとつの会議は1時間半を越さない。
- 議題は前日までに出し、議題にないものはと議論しない。
・以前は、読書しても、100読んでも5しか参考にならないことを「95無駄にしてしまった」ととらえ、時間を無駄にしたくなかったから読む本を厳選し、結局なかなか読めずにいてしまった。
しかし、5が継続的に得られるということは偉大なことだ。1か月に1回5が得られるのと、3か月1回15が得られるのでは、前者のほうが得だ。なぜなら、最初の1か月5を得られれば、少なくとも残りの2か月は何も得られていない状態より、5だけすぐれた行動ができる。
この「��間差」が変化の速い時代には聞いてくる。経営者にとって、数か月が命取りになることもある。継続的に読書などのインプットの時間がある、というのは経営者やマネージャーにとって、命綱になりうるのだ。
・ 昔から「パートナーとなるような人と出会いたい」と思っていろんな女性と付き合ってきた。しかし致命的な間違いを犯していたことに「働き方革命」を始めた後に気がついた。パートナーというものがいて、それに出会うのではない。人はパートナーになっていくのだ。しかもそれを相手に期待するのではなく、自分が変わることで新しい関係性を創りだすことができるのだ。
・ マネージャーのマネジメントを管理する方法として、プロセスを管理するやり方がある。彼がどういう人材を仕事につけたのか、部下のキャパシティにどの程度タスクを詰めているのか、というチーム内経営資源の配分を見ていくことで、うまくマネジメントしているかどうかわかる。しっかり効率的にマネジメントできていれば、残業時間数はゼロになるはず。
・ 自分のために、自己中心的に仕事の手を抜いて、自分のことに時間を使おう、ということではない。人生そのものを「働く」としてとらえる。食いぶちを稼ぐことも、家族と生きることも、自分のために学ぶことも、全部ひっくるめて「働く」と考えたらどうか。「働く」を「他社と自分のために価値を生み出すこと」とする。
投稿元:
レビューを見る
前半がおもしろい。
優秀な女性が家に入ってしまうことを「監禁男」呼ばわりしていた著者が、もしかして自分も??と気づき、周りの人たちとコミュニケーションしていく様子がリアルに描かれている。こんなふうに気づいて変化していける、そしてそれを表明しても否定されなくなった社会になって嬉しい。さて、この男性の意識変化に本当の意味で女性がついていけるかですね。
後半は、最近のキーワードである「仕組み化」「効率化」を軸に展開。このあたりは多くのビジネス本と共通するところ。100111
投稿元:
レビューを見る
(2010/1/15読了)一言でまとめると「ライフワークバランスのすすめ」ということになりますが、単なる理念だったりノウハウだったりせず、ご本人の具体的な体験談がベースになってて、物語仕立てで読めるのが面白い!16時間労働の仕事中毒だった著者が、8時間労働に激変する様がすごい・・・。