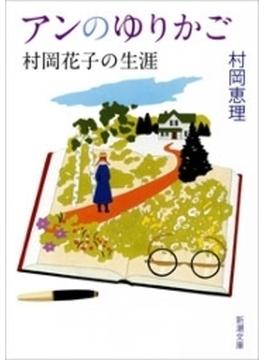読割 50
電子書籍
アンのゆりかご―村岡花子の生涯―(新潮文庫)
著者 村岡恵理 (著)
戦争へと向かう不穏な時勢に、翻訳家・村岡花子は、カナダ人宣教師から友情の証として一冊の本を贈られる。後年『赤毛のアン』のタイトルで世代を超えて愛されることになる名作と花子...
アンのゆりかご―村岡花子の生涯―(新潮文庫)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
アンのゆりかご 村岡花子の生涯 (新潮文庫)
商品説明
戦争へと向かう不穏な時勢に、翻訳家・村岡花子は、カナダ人宣教師から友情の証として一冊の本を贈られる。後年『赤毛のアン』のタイトルで世代を超えて愛されることになる名作と花子の運命的な出会いであった。多くの人に明日への希望がわく物語を届けたい──。その想いを胸に、空襲のときは風呂敷に原書と原稿を包んで逃げた。情熱に満ちた生涯を孫娘が描く、心温まる評伝。 ※文庫版掲載の写真は、電子版では一部掲載していません。ご了承ください。
関連キーワード
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
女性史
2017/12/06 18:12
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:七無齋 - この投稿者のレビュー一覧を見る
解説にも触れられているように身内のことの書籍だが客観性が濃くありがちな身びいきな著述がないことに感服する。村岡花子を通してのこの時代の女性史とも読めるこの本はよく調べられた本だ。アンを知らなくても読める。
紙の本
ドラマを見て再熱。
2017/02/03 12:51
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:honpochi - この投稿者のレビュー一覧を見る
学生の頃、夢中になって赤毛のアンをおそらく、全シリーズ読んだと
思っていたのですが、最後にアンのゆりかごは読んでいなかった事に
気がついて、ドラマを見ていて、なんとなく購入。
ドラマで描かれているのとは違った面や、細かい部分を知る事ができ、
とても読み応えありました。
村岡花子さんの訳した赤毛のアン大好きだったなぁ。
多分、違う人が訳したであろうアンを読んだ事があったけど、
なんか読み心地が悪かったのを思い出します。
紙の本
人も時代も読める
2015/09/19 21:41
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:山口ポン子 - この投稿者のレビュー一覧を見る
朝ドラが先でしたが、とてもおもしろく読みました。恋文のやりとりは、ドキドキしながらも微笑ましく感じました。私自身元々英語や国語が得意だった、はずなのに、普通の人になってしまっているので、花子さんの言葉に対する姿勢や言葉そのものが心にしみます。花子さんだけでなく、柳原白蓮や広岡浅子、市川房枝等、当時活躍した女性たちも多く登場し、あの時代についても知ることができます。
紙の本
感動しました。
2015/01/29 17:49
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:かおべえ - この投稿者のレビュー一覧を見る
村岡花子さんは朝ドラの主人公になるまで知りませんでした。
朝ドラを見て村岡花子さんのお孫さんが書いた本に興味を持って購入しました。
花子さんが単におとなしい女性でなくあの当時の女性としていろいろな運動に関わってこられたのだなと知りました。
花子さんたちの努力があって今の女性の生きやすさにつながっているのだと実感しました。
やはり息子さんを亡くす所は涙なしでは読めませんでした。息子を亡くした後、生き方を変えるところが感動でした。
紙の本
物足りない点もあるものの、興味深い事実を知るのに手頃
2014/08/18 23:26
4人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ががんぼ - この投稿者のレビュー一覧を見る
ドラマにはあまり関心がないのだが、
今、NHK朝ドラの『花子とアン』を楽しんでいる。
『赤毛のアン』を翻訳した村岡花子が主人公と知って見てみることにした次第。
てっきりどこかの教養ある裕福な家庭のお嬢さんぐらいに思っていたら、
これがなんと、貧しい小作農の家の出身だというではないか。
いうまでもなく相当な苦労と努力もあったはずである。
ドラマを見ていたら史実を知りたくなった。
なんといってもドラマは最終的にドラマで、フィクションの色彩が強いからだ。
ということで読んでみたのがこの本。
著者は、村岡花子の養女になった姪の娘さん。
つまり法的には孫娘、いずれにしても血筋である。
正直な話、伝記文学としての水準はそれほど高いようには思わなかった。
事実の扱い方にも、こちらの好みもあるのだろうが、ときどき違和感を覚えた。
たとえば花子とのその夫の結婚前のラブレターをここまで公開する必要があるのかどうか。
一方、同じ事柄を語るにしても、妙に美談めいていたり。
しかしなんといっても事実としての興味深さがあり、
それを数多く伝えてもらっただけでもありがたいことだろう。
何しろ日清戦争後から太平洋戦争の後までの日本である。
いかに激動の時代だったかがあらためてわかる。
ドラマでは仲間由紀恵が演じて、ドラマ性という点ではピカイチの柳原白蓮をはじめ、
数多くの文人・知識人とのつながりがあることにもあらためて驚く。
要するに歴史の面白さなのだった。
村岡花子自身の人生と、彼女が訳した『赤毛のアン』の主人公アン、
ひいては作者モンゴメリの人生とが、よく似ているのもびっくりだ。
その『赤毛のアン』は、花子とその周辺だけでなく、
いわば日本の国としての幾多の労苦を経て出版にこぎつけたように見えて、
それを描いた段は感動的である。
亡くなるまで『赤毛のアン』の舞台のプリンスエドワード島を訪れることはなかった、
というのも興味深い。
結局、彼女の言う「想像の翼」のままに生きたということだろうか。
児童文学の翻訳家としての村岡花子がいかに優れていたかという点については、
身内の筆ということもあるのか、具体的なことはよくわからない。
その辺については、たとえば菱田信彦『快読「赤毛のアン」』など、
ほかに優れた文献があるようなので、そちらに当たるのがいいのだろう。
紙の本
おもしろい
2016/12/12 11:46
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ひのえ - この投稿者のレビュー一覧を見る
花子さんはたくましいですね。彼女だからこそできた翻訳です。私も馴染みがあるからかもしれませんが、題名は「赤毛のアン」でよかったと思います。
紙の本
テレビで
2016/06/26 16:30
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:エピゴーネンキャット - この投稿者のレビュー一覧を見る
朝ドラのヒットで出したんでしょうか。
私には全く面白くなかったな・・・・