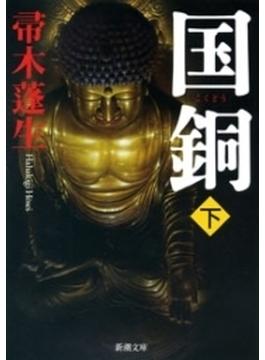紙の本
感激する本にであえた
2017/03/29 04:07
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:銀ちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
タイトルからすると、けんえんしそうな難しそうな本のイメージがありましたが、ちがいました。
読んだ後、色々と、考えさせられる本です。
現在でも知られた地名がでてき、お坊さんにも色々いるんだなって思わされた。
感動というよりこの本に出あえて感激です。
紙の本
主人公の造形がいまいちかな
2023/03/02 15:32
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Koukun - この投稿者のレビュー一覧を見る
大仏の製造工程や周辺の政治 社会 経済状況など、克明に描き出されている。天皇の勅にあったように「国の銅を尽くして」作り上げた大仏 というものが、しっかり存在感を持って描かれている。それに引き換え 主人公は感情の動きが表面にあまり出てこず、欠点が殆ど感じられないので、やや魅力に乏しい気がする。
紙の本
びっくりするくらい
2017/02/09 16:03
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:るう - この投稿者のレビュー一覧を見る
この作者さんの書かれる登場人物には個性が無いので困る。誰も彼も性格は同じというか。ストーリーは興味をひかれるがそのせいで頭に残らない。
投稿元:
レビューを見る
奈良時代の庶民を描くという、地味な物語ではあるが、なかなか爽快な読後感が味わえる傑作かも。
できれば若いうちに読むべき本。おじさんにはちょっと物足りないかな。
投稿元:
レビューを見る
実のところ、国人が都に行くことになった辺りから、結末はほとんど予測できていた。下手をすれば、国人だって奈良登りにはたどり着けない。でも、国人が待ち望んでいた再会はなかった。それが、悲しい。たくさん、話したいことがあっただろうに。
都で、国人の感覚は、詩や歌を覚えることで、ずいぶんと華やいでいたと思う。人足たちの中でも、文字が読め、仏の意味も深く考えていた。すごく雅て見える。でも、奈良登りへ帰る道々、仲間を失っていく中で、どんどん荒々しいものになっていったように見える。そして、奈良登りの石仏の碑を彫りつけようとする国人の姿は、荒々しさそのもの。
これは、仏作りに関わって、聖なる者になっていく話ではなく、仏と交わることによって、かえって俗に戻っていく話だったのだと思う。
投稿元:
レビューを見る
棹銅を作り、都へ行き大仏を作った国人を初めとする奈良時代の人足の物語。もうほとんど語り手・国人と同じ視線で、朝から晩まで働き、山草木を愛で、字を覚え宇宙の広がりを感じてることが出来た。聖武天皇ではなく人足何十万人の労働で大仏は出来た。この小説を読まなければそう思うこともできなかったでしょう。
投稿元:
レビューを見る
名作である。
銅がテーマかと思ったが、私は大仏の対比、仏のことから、生きることをテーマにした作品だと感じた。
2008年05月05日読了。
投稿元:
レビューを見る
華やかな奈良の都で、大仏造営に携わった国人が主人公の物語。
銅の産出から、大仏造営と奈良時代の社会、風俗良く描かれていて大変興味深く読めた。
大仏造営を底辺で支えた人々の営みが興味深かった。
投稿元:
レビューを見る
これほどに魅了された作品は久しくない。
想像をはるかに超える苦役に就きながらも、心は腐らず真っ直ぐに生きる主人公を応援し、全ての出会いに感謝しながら読んでるなんて。
何度となく大仏さんにお参りしているが、次回は別の見方で感慨一入になるだろう。
投稿元:
レビューを見る
読み終わる頃には涙を抑えるのに苦労しました。
なんという臨場感!!!
多分これから何度も読み返すことになるでしょう。。。
投稿元:
レビューを見る
国人は大仏の完成をみる。そして帰郷の許可が…。
だが、その過程で失ったものも。
大仏を造り、そして故郷に戻り、彼が得たもの、失ったものは?
最後は涙なしでは読めませんでした。
国人の歩みは、ちょっと歯がゆいところがあるのですが、それもまた彼の良さで、歯がゆく感じてしまう私の考え方が間違いなのかもしれません。
素直に聞き、学ぶ…それが大事なんですよね。
投稿元:
レビューを見る
国人は、大仏造営の傍ら詩を詠み、薬草を採り過ごし、遂に故郷へ帰ることを許されたが・・・
意外とあっさりだったかな。それでも、これだけの人々の労苦の上に成り立っていると思うと、大仏を見る目も変わってくるかもと思った。
投稿元:
レビューを見る
祈るような気持ちで読み終わった。 大仏を見に行って、こういう人たちが作ったのだということを思い出したい。
投稿元:
レビューを見る
私は先に「水神」の方を読んでしまったが、この「国銅」があって「水神」がある、そんなことが自ずと頓悟された。
非常によくできた二昔前ぐらいの連続テレビドラマを観ているかのようだ。
主人公の国人が絵に描いたような善人の模範で、周りの人々や環境にも異様なほど恵まれる、などといったフィクションならではの好都合も随所に見られるが、本作全体を貫き通す真っ直ぐな流れは揺らぐことなく、読者の真情に迫る。
物語の中には、謎もどんでん返しもトリックも出てはこないが、“生きる”とはどういうことなのか、そんな命題に真っ向から取り組み、そのプロセスを経て得られた著者なりの答えが示されている。
「水神」同様、作中に出てくるなんでもない食べ物の数々や、また医師ならではの見地から描かれた疾病の表現などが印象に残る。
大仏建立の具体的な方法についても、ここまでよく調べられたものだと感服する。
奈良登りの掘り口や釜屋、吹屋もそうだが、登場人物たちが働いている現場の暑さ寒さまで伝わってくるような臨場感だ。
投稿元:
レビューを見る
国人の目線と登場人物の生き様を通じて生きるとはというところを考えさせられる
それとやっぱり言葉の持つ力ってすごいなぁーって
国人が字や薬草の知識を学んでいくところがステキだった
何を学ぶかもとても重要なことなのだと
苦難の中に喜びや驚きが点在しまた突然抗い難い残酷な一面を見せ付ける人生とはかくも感慨深いものだ