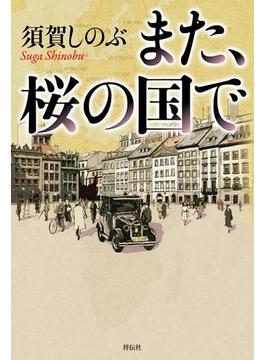紙の本
物語の力
2016/12/27 14:35
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:クロぽん - この投稿者のレビュー一覧を見る
最初のページを捲ってから最後まで止まらずに読んだ。読まずにはいられなかった。襟首を掴まれて、引き摺られて遠く、遠く放り投げられたようで、読後から3日間くらいは言葉にできない思いが溢れ、こっそりと涙ぐむほどの余韻があった。決して明るい話ではないが、私にとって幸せな読書体験だった。
主人公棚倉慎の人への信頼と人生への真摯な態度、それは時に揺らぐこともあるがその度に彼は顔をあげ前を向く。異国の友のために、日本人としてどう生きるかと問いかけながら。
ワルシャワ蜂起では二十万人の犠牲者が出たという。二十万人と括られる人達にはそれぞれの顔があり、人生があり、交わした約束も、夢見たこともあっただろう。その果たされなかった幾万の約束や夢は歴史書では語られないことであり、物語の独壇場であると言って差し支えないと思う。
今更ながらに気が付く。確かにそこには人がいたのだ、と。そしてそれは忘れてはいけないことなのだ。
物語の力、とでも言うべき作品だと思う。
作者の須賀しのぶさんと棚倉慎に心から敬意を表したい。
紙の本
熱い作品
2017/05/17 22:25
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:冬みかん - この投稿者のレビュー一覧を見る
ずっと以前はコバルトとかでライト目の小説を書く作家さんだと認識してましたが、認識を改めました。ポーランドが舞台で、正直読み通すことができるか不安でしたが、力のある作品でぐいぐい読めました。
紙の本
新たな名作の誕生
2017/04/11 12:32
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ブレーブス坊や - この投稿者のレビュー一覧を見る
苦難の歴史をたどってきたポーランドの第二次世界大戦の様子を丹念に描いた秀作です。
少し話がうまくつながり過ぎるところもありますが、全体の流れで考えると気になりません。
個人的にポーランドは何度も訪れたことがあるために、街の様子や食べ物などが目に浮かび、引き込まれるように一気に読んでしまいました。
読後の余韻が強く残る作品で、私の中では、大好きな佐々木譲さんの第二次世界大戦三部作、帚木蓬生さんの「ヒトラーの防具」、逢坂剛氏のイベリアシリーズに並ぶ作品で、佐々木・逢坂両氏のハードボイルド感と帚木氏の温かみを兼ね備えているように思いました。
多くの方に読んで頂きたいと思います。
紙の本
緻密ですね。
2017/06/20 18:46
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:飛行白秋男 - この投稿者のレビュー一覧を見る
友情 愛国心 勇気 愛 リーダーシップ 国籍 戦争 爆撃 死
涙 感動
ぜひ、読んでくださいませ。
497頁 長編ですが、一気に読めます。
投稿元:
レビューを見る
「神の棘」の衝撃から6年、なんて煽られたらもう……! と胸を熱くして購入した本書。覚悟はしていたがポーランドがいかに苛烈な道を歩まされてきたのかが容赦なく描かれており、胸が痛いを通り越して息苦しいほどだった。“じぶんは何者なのか”と葛藤する主人公の姿もさることながら、孤立を極めたあの国で何があったのかをほとんど知らずにいたじぶんに声をなくす。涙腺は緩いほうだとわかってはいたが、それでもなんども目の前が霞み、終章では嗚咽が漏れた。あの約束があったからいまがあるというのなら、歴史を学ぶ意味はあると断言できる。
投稿元:
レビューを見る
ぜひ広く読まれてほしい作品。第二次大戦時のワルシャワが舞台。ロシア人を父に持ちながら日本で生まれた主人公は、人種というものについて長らく複雑な思いを抱きながら育ち、やがて外務省の書記生としてポーランドに赴任、ドイツ軍による侵略とユダヤ人の迫害を目の当たりにする。ソ連とドイツに挟まれ、歴史上何度も蹂躙を受け、独立を奪われてきたポーランドの人々。ナショナリズム、アイデンティティについての物語であり、誰かの犠牲の上に生きることを恥じる人々の話。
投稿元:
レビューを見る
第二次世界大戦下、ロシア人の父をもつ外務書紀生、棚倉慎を視点に描かれたドイツに蹂躙されるワルシャワが舞台。
彼の父親が語った、強国によって呑み込まれた世界で、当事者となった彼が見た世界はイデオロギーや利害関係はなく本当に美しいものだった。
憎悪ではなく、信頼と尊敬で愛国心が培われていくものなら平和な世界を築く事が出来るのではないか。
国とは個人とは色々考えさせられ、涙なしには読めない作品だった。
最後に交わした3人の約束が切ない。
投稿元:
レビューを見る
凡そ500頁のハードカバー本。
重くて持ちにくくてとにかく扱い辛い・・・なんて愚痴をこぼしていたのも束の間、この分厚い本は読み始めたら止まらない、そんな力のある作品だった。
第二次世界大戦中の欧州の様子は、教科書で読んだくらいの知識しか持っていなかった。
ナチスによるユダヤ人の弾圧や、アウシュビッツの惨劇。
ドイツがとにかく酷い、狂気的。
そんなイメージが大きかった。
ポーランドが幾度も侵略を受け、奪い尽くされた真実も、蜂起して何度も戦った事実も、よく知らなかった。
人間の尊厳をかけて、自由を勝ち取ろうと立ち上がる人々の痛切な思いと生き様が凄まじい。
この熱い余韻をうまく言葉にできないのが、もどかしい。
多くの人に読まれるべき傑作だと思う。
投稿元:
レビューを見る
内容(「BOOK」データベースより)
ショパンの名曲『革命のエチュード』が、日本とポーランドを繋ぐ!それは、遠き国の友との約束。第二次世界大戦勃発。ナチス・ドイツに蹂躙される欧州で、“真実”を見た日本人外務書記生はいかなる“道”を選ぶのか?
投稿元:
レビューを見る
読み応えのある作品。
ノンフィクションかと思ってしまったが、史実に基づいているので、フィクションとも言い難いような?
杉原千畝さんの名前が出てきて、これは物語ではなく、事実なんだとハッとさせられる。
杉原さんが救ったユダヤ人はは6千人くらいだと伝えられている。
ものすごい数だけど、それでも一握りだったんだな、と。
満州引き揚げ、ナチス・ドイツのユダヤ人迫害などに関する本を最近も何冊か読んだが、この本に出てくることも無関係ではない。
むしろ、ポーランドや周辺各地の事実を知り、全てが繋がっていることに気づく。
こんなことは繰り返してはいけない。
遅ればせながら、もっともっと歴史を知らないといけないなという思いが強くなった。
投稿元:
レビューを見る
第二次大戦下のポーランドを舞台に日本人外交官が活躍する話。約500ページの長編だがノンフィクションかと思わせるようなリアリティで最後までワクワク読めた。「戦場のピアニスト」から取ったと思しきエピソードが出てくるのが面白い。(この映画では「革命のエチュード」はかからないのだが・・)
投稿元:
レビューを見る
年末年始を跨いで第156回直木賞候補となった5作品を読みました。
今回の候補作は全て長編で読み応えのある力作が並び、読書に浸る喜びを十二分に味わうことができました。
そんな中で、私の心に一番強く残ったのは本作でした。
本作の舞台であるポーランドは、恐らく多くの日本人にとって名前ぐらいしか耳にしたことがないのではないでしょうか。実際私もそうでした。しかし本作を読了して、ショパンに代表される優れた文化と誇り高き国民を有する国であること、そして近代史上あまりにも悲惨な扱いを受けてきた国であることを初めて知りました。
物語の中で印象に残った場面はいくつもあります。
例えばドイツと枢軸国の関係にある日本人外交員(書記生)という立場上、ナチスの残虐行為から目をそらさざるを得ないことに対する主人公の葛藤に、私はすごく共感できました。ちょっと場違いな感想かもしれませんが、自身の理想に対して妥協を重ねていかざるを得ない主人公の姿は、サラリーマンをやっているととても身にしみます。
そして終盤、一個人としてできることは何かを自問自答した結果、日本人外交員としてではなく、ポーランドのためにある道を選ぶことを主人公は決意するわけですが、その決死の思いに胸が熱くなりました。
そこからはラストまでノンストップで一気読みでした。
また、本作では登場人物から印象的な言葉がいくつも発せられます。
自身もハーフである主人公の慎、そしてナチスに迫害されるユダヤ人の血を引くヤンなどから、個人と国家、民族、人種、歴史、そして正義とは何か?についての問いかけが何度もなされ、読者はその都度自分自身を省みることになります。
それらはいつの間にか自らの誇りを失い、アメリカに代表される強者についていけばよいとしか考えられなくなり、ヘイトスピーチを例に挙げるまでもなく他者に対する寛容さを失った私たち日本人に対する、著者からの強烈なアンチテーゼであるように私には思えました。
こんな時代だからこそ読んでほしい一冊、という宣伝文句は決して大げさではありません。
素晴らしい作品に出会えたことを心から感謝します。
投稿元:
レビューを見る
ショパンの名曲『革命のエチュード』が、日本とポーランドを繋ぐ。
それは、遠き国の友との約束。
第二次世界大戦勃発。ナチス・ドイツに蹂躙される欧州で、〈真実〉を見た日本人外交書記生はいかなる〈道〉を選ぶのか?
1938年10月1日、ロシア人の父に日本人の母という彼の容貌は父の血を受け継ぎ、日本で生まれ育ちながらもアイデンティティに悩みを持ちつつ成長した棚倉慎はワルシャワの在ポーランド日本大使館に着任した。
ナチス・ドイツの侵攻、続くソ連の侵攻、ナチスの統治、ユダヤ人迫害、ゲットー蜂起、カチンの森、ワルシャワ蜂起・・・。
幼年時に日本に来たポーランド人孤児と交流があった慎は祖国に帰った孤児たちが作った極東青年会と協力し戦争回避に向け奔走する。
ワルシャワの青年イエジにヤン、アメリカ人記者レイや、ユダヤ人女性ハンナらの生き生きとした人物像を絡めながら、民族や国籍を越えた「信頼」そして人としての「自由と尊厳」を壮大で悲惨な歴史の中から、ほのかな希望の光として、そっと取り出したような小説だったな、読めてよかったな、と思った。
投稿元:
レビューを見る
ポーランドがこれほど虐げられていたとは。私にはショパンの国という認識しかなかったが、あまりに壮絶な第二次大戦。
本書を読んで、かなり以前に読んだプラハの春を思い出した。
投稿元:
レビューを見る
ポーランドでこんな事実があったとは!
最初は、カタカナ表記の人名と地名に悩まされるが
中盤以降は一気に読んだしまった(読みたくてしかたなかった)
「第2次世界対戦」と一括りで言ってしまいがちだが
日本がアメリカと戦った太平洋戦争と
大陸で繰り広げられた戦争とは
全く別のものである事が改めて認識できた。
旧ソ連の狡猾さと
ドイツの(全てをヒトラーとナチスドイツのセイにして責任を回避した)戦後処理のうまさ?
を感じずにはいられない。