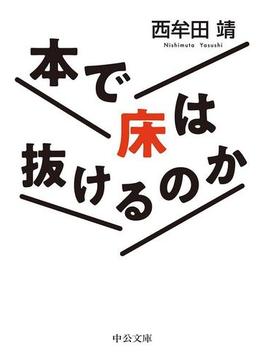紙の本
誰もが抱える問題
2018/11/18 00:50
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:つきたまご - この投稿者のレビュー一覧を見る
自分が、その辺の人よりは本を多く持っている気がして、かつ、かなり作りが不安なところに居住していることもあり、「床抜け」の不安は常につきまとっていました。そんな状況で、この本を書店で目にしたために、購入してしまいました。(そのせいで、また我が家に本が1冊増えたわけですが。。。)
最初は、床抜けの対策について色々と書かれているのですが、この本全体の中で印象的だったのは、持ち主が亡くなった後の本の行方について書かれた章でした。確かに、気になってはいたのです。ものすごく有名な賞を取った経歴のある方の蔵書ならともかく、ただ大量の本を持っていた一般人や、普通の研究者さんや作家さんの蔵書はどうなるのだろうと。。。
この本に、それらの何パターンかの事例が書かれていて、悲しくなる話もありましたが、死後もなお周りを巻き込みまくった方の話もあって、一番興味深かったです。
時折挟まっている書庫や本棚の写真が圧巻でした。
とりあえず、我が家の床は大丈夫そうです(笑)
紙の本
アナログ世代の吐息かも
2018/05/05 23:45
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ヤマキヨ - この投稿者のレビュー一覧を見る
捨てるに忍びない蔵書の重さで我が家の床が抜け得るかもしれない。この危機を回避するにはどうすればいいのか。以前井上ひさしさんの『本の運命』で、膨大な蔵書をいかに保管するかについては読んだことがあった。井上さんとこの筆者が異なるのは収入の多寡であった。お金をかけずに蔵書を守り、床を抜かない方策はあるのか?この疑問に端を発した取材は、次第に対象が広がり、蔵書の保全と向かい合う様々な人にその対象を広げていった。実態のある紙の本にこだわりがある人たちの思いにあふれた一冊である。その一人である筆者を待ち受けていた結末は、予想外のものであった。本って言うものは・・・。
手紙がe-mailになり、音楽も写真もなべてアナログから電子データに取って代わられた。本も紙にこだわる世代から、いずれ電子データで事足りると思う世代に移っていくのだろうか。「本が捨てられない」が死語になれば、こんなテーマの本も書かれなくなるのだろう。
紙の本
面白かったです
2022/04/10 12:31
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:iha - この投稿者のレビュー一覧を見る
本の虫にとって非常に気になるタイトルです。著者自身も含めて、本を集めすぎた人びとの末路が様々で非常に興味深いです。
紙の本
結構怖い話もあり
2021/12/22 17:11
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:きなこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
タイトルに惹かれて購入しました。本で床が抜ける、というのは文字で見ると笑ってしまいますが、実際に抜けた人、抜けそうな人の話が収録されていて意外と真面目なきもちになってきます。笑える本、という印象とは裏腹に本好きにとっては結構怖い話だな、という感想を持ちました。
投稿元:
レビューを見る
著作です。新しい情報を加えたり、「文庫版に寄せて」を加えたり。また角幡唯介さんによる解説も加えました。
投稿元:
レビューを見る
単純に面白かった。どれくらいの本だと床が抜けるのかを検証する過程はちょっと文章だとわかりにくい。試みは面白かった。ただ、家族が崩壊してしまったのは、残念な限りだ。
投稿元:
レビューを見る
ちょうどいま新居に書庫を作ろうとしているところ。
他人事ではない。(2階に3畳ぶん床から天井まで前後段違いの作りつけ。……これが正しいのかどうか、もはやわからない)
消費者としていずれ読みたい文芸書人文書芸術書漫画だけで、一室で足りず実家もいっぱいなのだから、生産者として資料本を資料収集し利用ことが仕事のノンフィクション作家・ルポライターは桁違いなのだろう。
桁違いの人が、自分とさして変わりない賃貸のマンションに住むとなれば……。推して知るべし。
一軒家にしても、薄給の人間が作れる家の広さから考えると、一階は生活スペース、二階が子供部屋や趣味の部屋となり、二階に書庫や本棚という間取りは「仕方ない」。
(井上やすし、立花隆、本書で言及はされないが荒俣宏やウンベルト・エーコといった、さらに桁違いの金持ちたちはちょっと別世界。)
kindleや電子本は数冊ぶん購入して、慣れないなーと面喰ってからは棚上げしている。
自炊はまだ踏み出せずにいる対策だ。
本来ならすべて自炊しOCRにかけ検索できる状態にして、書庫の本もそのまんまにしておくというのが理想的。が、無理。
またすべて捨てることを前提にして自炊することはできない。
本は思い出でもあるから。
その行き着くところが、著者の別れる妻が捨てたゴミ袋から透けて見えた「じゃあじゃあびりびり」。
愛想付かされて離婚、愛娘とも別れたのだ。(もちろん蔵書だけが原因ではないだろうけれど。)
いま我が家で、背表紙がなくもはや厚紙でしかないにもかかわらずフルに働いてくれているあの本が、ゴミ袋に入ることを想像するだけで、もう胸だか腹だかが落ち着かない。
わが妻にこの本は紹介できない。
蔵書とは甘苦しい罪悪感そのものでもあるのだ。
漫画を押し付けられた実家の母が、押し入れの板が歪んでいることやいつか床が抜けるのではと、愛息たる私に訴えるのを聞きつつ、自分とは異なる見方やリアリティを感じている、とは感じていた。
妻もそうなるやもしれぬ。子もまた。
他者と暮らすとはこういうことだ。
自分の趣味や仕事が家族という他者の場所を侵害すると……。互いに侵害し合うこと……。
また書痴の先輩たちの生き死にの事例を見ると、本を溜めること……読むこと……読んだ記憶……災害……そもそも人生は期間限定だった……死後の蔵書の行方……困難な遺品整理……作家や研究者でなければ散逸は不可避……本を読んでは置いておくという行為自体、いずれ読むために置いておくという行為自体……などなど考えてしまう。
こうした「考えてしまう」の「考え」は、「思いに耽る」「遠い目をする」といったグラデーションを経て、いずれ「死んでしまえばそれまでよ」となるのが、書痴の理想形なのだろう。
「宵越しの金は持たない」は死生観の極北なのだ。
連想……澁澤龍彦や三島由紀夫。中島らもの自宅庭プレハブ。中井英夫とかどうなんだろうか。
中原中也が2歳の息子を思いながら日記に
「文也も詩が好きになればいいが。二代がゝりなら可なりなこと���出来よう。俺の蔵書は、売らぬこと。それには、色々書込みがあるし、何かと便利だ。今から五十年あとだつて、俺の蔵書だけを十分読めば詩道修行には十分間に合ふ。迷はぬこと。仏国十九世紀をよく読むこと。迷ひは俺がさんざんやったんだ」
と書いている。
これなどは未だ思うように評価されずにいる中也の自意識が子に投影されているのであって、ナマグサイことこの上ない。
この数か月後に愛息は突然死し、中也自身も「生前は実質ワナビー止まり」のまま30歳にして脳膜炎で死んだ。
吉村萬壱さんは田舎の平屋に越した。
すべて背表紙が見える状態の書庫兼家に住んでいるとか。
1 本で床が埋まる
2 床が抜けてしまった人たちを探しにいく
3 本で埋め尽くされた書斎をどうするか
4 地震が起こると本は凶器になってしまうのか
5 持ち主を亡くした本はどこへ行くのか
6 自炊をめぐる逡巡
7 マンガの「館」を訪ねる[前編]
8 マンガの「館」で尋ねる[後編]
9 本を書くたびに増殖する資料の本をどうするか
10 電子化された本棚を訪ねて
11 なぜ人は書庫を作ってまで本を持ちたがるのか
12 床が抜けそうにない「自分だけの部屋」
投稿元:
レビューを見る
増えすぎた蔵書をどのように扱うかを考察したノンフィクション。
蔵書の管理は多くの読書家が悩む問題のようで、著者も数千冊の蔵書を抱えて様々な方法を検討する。著者の状況は、他人事とは思えず考えさせられる事が多かった。
本の中身だけ判れば良いというのであれば、データ化して保管するのがベストだと思うけれど、モノとしての本、手触り、紙質、装丁に拘る人には、著者と同じ悩みを抱えることになる。理想は書庫を持つこと。これがベスト。あとは身の丈(部屋)に合うように削減するしかない。
因みに、自分は図書館併用。高価な本、嵩張る本は図書館を利用し、それ以外は価格と大きさ厚さの限度を設けて購入している。2つの本棚に入らない分は、取捨選択して古本屋へ。古本屋(読めない、読まない本)は、ある意味もう一つの収納場所だ。
本好きにはとても面白く読めると思う。
投稿元:
レビューを見る
本をため込む習性のある人は必読のエッセイ。いやー、このタイトルだけでめちゃ怖いんですが(笑)。床抜けの実話にびくびくさせられたものの、でもそれ以上に本が好きな人の話にはわくわくしちゃうんだよなあ。とはいえ、この本に登場する人たちとはレベルが違うと思います。なのでまあそうそう抜けることはないのかな……と安心してしまったので、あまり教訓にはならないのかもしれません。
床抜け問題だけではなく、電子化についても言及されていて。一概にどちらがいいとも言えないのだけれど、個人的には断然紙派です。やっぱり質感的には紙の本がいいですよ……困るのははい、置き場所だけですよね。そしてそれが最大の問題だということは、充分理解していますとも。
しかしそれにしても。読み終えるととても切ない気持ちになってしまうのですよねえ……。本を持つってそれだけのことなのに。大変なんだなあ。
投稿元:
レビューを見る
同年の著者による、本まみれになった人や、蔵書管理、書庫建設に関する取材記。専用書庫を持つのは夢なので、参考になるかと読む。
著者の視点は面白いのだが、なんでそんな疑問を持つのか?またその程度の掘り下げか?と思う点が結構あった。中途半端感が結構あった。それでも最後まで読んだのは、本、というねたの良さ。
そして自分の蔵書管理や小さいながらもある書斎に関しての考察、設計指針も実に中途半端であることを認識させられた。
投稿元:
レビューを見る
「本で床が抜ける」不安に襲われた著者は、解決策を求めて取材を開始。「蔵書と生活」の両立は可能か。愛書家必読のノンフィクション。〈解説〉角幡唯介
投稿元:
レビューを見る
ノンフィクション・ライターである著者が、際限なく増えていく本の重みで床が抜けるのではないかという危機感をいだき、大量の蔵書を抱え込んだ人びとのもとを訪ねて取材をおこなった本です。
作家の井上ひさしや評論家の草森紳一、経済学者の松原隆一郎といったケースについて取材を進めていくのですが、その過程でも著者の本はいよいよ増えていったであろうことがうかがわれます。また、本を減らそうと業者に依頼して電子データ化を試してみた経緯やその結果わかったことなどが語られるとともに、出版業界の問題を垣間見たりと、さまざまな方向へ話がつながっていきます。さらに本書の執筆中に、大量の本が原因の一つになって、妻子と別れて暮らすことになるという思いもかけない出来事に見舞われることになり、その経緯についても綴られています。
みずからさまざまな苦悩を抱え込みつつ、増えつづける本への愛憎をバネに本書の執筆という仕事をつづけていく著者に共感をおぼえながら読みました。
投稿元:
レビューを見る
引っ越しの度に蔵書を処分しながら生きている為、タイトルに惹かれて手にした一冊。
本で床が抜けるのか…抜けるような…抜けないような。抜ける事を恐れたら何をすべきか、体験談からドキュメンタリーまで、多彩な内容でした。あちこち話題が飛び回る構成は読み難いなとも思いましたが、連載作品の為致し方無いかなとも。
自分の脳内の縮図と考えて部屋を作れ、という事を何かで読んだのですが、知の巨人と呼ばれるような巨匠クラスの文筆家であれば、広い自宅なり書庫なり作って大量の本を所有していても、その人の脳内であるなら流石ですとしか言いようが無いのですが、タダの愛書家である一般市民の雑多なコレクションなどタカが知れている、と思い切って毎度処分しています。その為、体験談として(著者の最後の悲しい顛末まで含め)読むなら面白い読み物でした。足で稼ぐと仰る通り、著者のフットワークの軽さは脱帽です。床抜けの不安を払拭できる要素はあまり書かれていないので注意です。
正直、もう少し図書館の可能性も探って欲しかったなとも。
投稿元:
レビューを見る
蔵書家たちが大量の蔵書にどのように対処しているか、を主に扱ったルポ。
登場人物それぞれの本に対するスタンスの違いを知れて面白い。
もっとも、著者自身の独白・経験談が多分に含まれているが、その箇所はどうも自分の肌に合わなかった。
投稿元:
レビューを見る
本を持つ身としては、気になる内容なので読んでみた。
著者が借りていた木造アパートが、本の重みで床が抜けるのでは....という不安な状態に陥ったのをきっかけに、本で床が抜けた人はいるのか、どんな状態で抜けたのか、どうすれば床を抜くことなく本を貯蔵できるのか、いろんな人に会い、いろんな可能性を検証し、最適な方法を探す為に書かれたのだろう。
だが残念なことに、この本では明確な答えは導き出されていないような気がする。
貯蔵本を自炊で電子化し鉄筋・鉄骨物件に越したという著者。
それが答えだとしたら、なんとも残念な内容である。