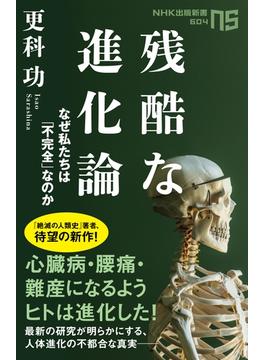紙の本
ヒトは進化の頂点ではない
2020/03/08 10:29
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:KazT - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書のタイトルの「残酷」とは、限られた地球の中で行われる生存闘争の結果が「進化」であることを伝えています。特に、様々な証拠からヒトは進化の頂点でもなく、特別な存在ではないことを著者は説明します。よく「ヒトはサルから進化した」と言われ、チンパンジーやゴリラは人より劣っていると考えがちですが、そのような誤解は本書を読めば、彼らはそれぞれの環境下において進化の頂点にいて、現存するすべての生物がそれぞれ進化の頂点にいるのだと気づかされます。
そして、なぜ、我々は死ななければならないのか、この重要な疑問にも自然淘汰の宿命であることを教えてくれます。
非常に専門的な内容も分かりやすく解説してくれて、前作「絶滅の人類史」同様、進化や自然淘汰について理解を深めさせてくれる良書だと思います。
電子書籍
進化について
2021/07/31 10:30
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:福原京だるま - この投稿者のレビュー一覧を見る
哺乳類よりも鳥類の方が陸上生活に適した構造をしていたり現生人類よりアウストラロピテクスの方が(骨盤だけ見れば)直立二足歩行に適していたりとさまざまな進化について知れてよかった
電子書籍
残酷、不完全
2021/04/07 08:14
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
そういわれたら、つい、手に取りたくなるタイトルです……しかも、NHK出版。要するに、進化、とは、人間が、そのトップにはいない、ということなんですね……。
紙の本
残酷な進化論
2021/09/22 16:07
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:渡り鳥 - この投稿者のレビュー一覧を見る
人類が誕生したのが700万年前。勿論、直立歩行で。滅茶苦茶に長い歳月を経ながら現在の人類に落ち着いているが、その過程で、人類は、心臓病や腰痛や難産になるように進化したことを他の生物をベンチマークに解説。あまりこの種の本を読まないので書かれている内容は、結構新鮮。百万年単位で物事を見ていると、今、悩んでいる事が随分とチッポケな事のように感じる。
投稿元:
レビューを見る
地球が有限だから、生き残れるものの数は限られる。
そのため、自然淘汰か働く。
自然淘汰、つまり、進化は、
計画的ではなく、今この瞬間に役立っているか、
のみ問題となる。
役立つ機能を生み出すモノは、
1つの機能だけを生み出すわけではなく、
いろんなことに役立っている。
従い、あちらたてれば、こちら立たずになる。
進化においては、新しいものを
ゼロから作ることはなく、いまあるモノを
使わざるを得ない。
そのため、このようなあちらたてればこちら立たずになる。
こらが、残酷さを生み出す、と。
投稿元:
レビューを見る
これまたおもしろかった。特に前半。後半はわりと知ってる内容が多かった。前半に新しい話題をよせたのか。それとも、私が知らないだけか。だいたい高校生物の知識などはほとんどないので。いくつかおもしろい話題を。これまたツイートをあつめて。何もできなくったって、恥じることはない。そんな生物は、たくさんいる。左心室より右心室の方が弱い筋肉でできているのは肺の毛細血管から血液が漏れだしてはいけないから。心臓自体に血液を送るのは冠状動脈。確かに右心房、右心室に流れるのは静脈血だ。それだけでは酸素が不足する。魚では心臓から送り出した血液はまずえらで酸素を受け取り、全身に酸素を渡した後の血液が心臓にもどってくる。だから心臓は酸素不足となる。それを補うために消化管を利用した肺ができたらしい。それで、ときどき水面で口を開けて空気を取り入れるのだとか。なるほど。鳥類の肺につながる道は入り口と出口と2本ある。哺乳類より効率がいいわけだ。窒素を尿素で捨てる哺乳類より、尿酸として捨てる爬虫類、鳥類の方が陸上生活にはより適している。そうか、私はラクターゼ活性持続症だったのか。だから牛乳飲んでも大丈夫なんだ。意外と進化は速いということ。考えを改めないと。
ウマとヒトのマラソン大会。短距離は負けるけど、長距離になるとヒトが勝てる。普通哺乳類は毛でおおわれていて汗もかかないから、長距離走ろうとしても、体温が上がって走れない。ところがウマは汗をかくので長距離走れる。人類は直立二足歩行を始めると同時に犬歯が小さくなった。一夫一妻になり、オスどうしが争う必要がなくなったから。そして、オスは子育てに参加し、空いた手で食料を運べるようになり、生存競争に勝ち、直立二足歩行をする個体の遺伝子が広まった。死ななくては自然淘汰が働かない。自然淘汰が働かなければ生物は生まれない。つまり、死ななければ生物はうまれなかった。生物は「死」と縁を切ることはできない。進化は残酷なのだ。
投稿元:
レビューを見る
学校でどこまで習ったのかを、既に覚えていないので、ヒトの体って、こんな構造になっているのだと、知る喜びがありました。最も興味深かったのは、ヒトと腸内細菌の駆け引きしつつの助け合いです。こんな事が自分の体で毎日起きているのかと思うと、新鮮な気分になります。そして、本題の「不完全」さについてですが、その時々の環境において、その時点での子孫を残すために最も適した方法として進化するのですが、それが部分的で万能ではないので、代わりに劣る点が出てしまう。要は、子孫さえ残せれば、あとはどうでもいいわけです。それが不完全で残酷といってしまえばそうかもしれませんが、それと向き合って少しでも上手くやっていくことの必要性も大事だと感じました。また、ヒトが他の生物よりも優れているわけではないということ。視点を変えるだけで、立場はたちまち変わってしまう。完璧なものは、この世にはないということに改めて気付かされました。それゆえに、気楽に物事を考えるのもありかなとは思いました。
投稿元:
レビューを見る
残酷な進化論:なぜ私たちは「不完全」なのか(NHK出版新書)
著作者:更科功
タイムライン
https://booklog.jp/timeline/users/collabo39698
投稿元:
レビューを見る
学校で習ったことの記憶を辿ると、多くの生き物がいる中で哺乳類はそのピラミッドの頂点にあり、さらに「ヒト」はその上を極めています。確かに我々「ヒト」は他の生物を利用したり食べることで生きています。
頂点に至る過程で私達は様々な進化を遂げてきたのですが、この本によると、その進化は「不完全」であるということが解説されています。不完全なので、私達の身体にある臓器は今も進化しているらしいです。環境に応じて進化というか対応していくのでしょう。私達は完全ではない、だからまだ変われる、というのは希望が持てた感じがしました。
以下は気になったポイントです。
・宇宙空間を移動する宇宙船は、細長い形がよい。宇宙空間は完全な真空ではないので、ガスや塵・小石があり、そういうものにぶつかりにくくするには細長い形をしているほうがよい(p22)
・がん細胞といえども酸素や栄養なしに増えられない、がん細胞には血管をつくる能力がなければならない。がん細胞が増えるのは、増えながら新しく血管をつくっているから(p27)
・心臓はたくさんの筋肉でできている、筋肉は縮むことはできても伸びることができないので、例えば腕を曲げるときには、腕の内側の筋肉が収縮する。心臓の場合は、心房と心室をつくって、心室が収縮したおきには心室が拡張、心室が収縮したときに心房が拡張するようにしている(p33)
・進化は、前からあった構造を修正することしかできない、切ってつなげるとか、分解してから組み立てるとか、そういうことは無理である。常に変化しつづけていて、役割も変化し続けて、過去から未来につながっていくのが進化である、進化をやめるのはその種が絶滅したとき(p45、54)
・硬骨魚類の肺からでた血液は心臓に戻る前に、全身の細胞から戻ってきた血液(酸素が少ない)と合流する。なので酸欠状態となる(p47)
・鳥類は優れた呼吸器を持っているので他の動物が生きられないような空気の薄いところでも生きていける。鳥類は恐竜の子孫なので、恐竜もこの優れた呼吸器を持っていた可能性がある(p55)
・タンパク質に含まれる窒素の処理が大変、魚類は周囲から水を取り込んでアンモニア(毒性強い)を大量の水に溶かして、鰓から排出すれば良い。しかし陸上動物は、窒素をアンモニアではなく尿素にして捨てている、両生類より哺乳類は陸上生活に適しているが、哺乳類よりも爬虫類・鳥類はさらに陸上生活に適応している(p60、68)
・ニワトリの卵の中では、窒素を捨てるのにアンモニアも尿素も使えないので、尿酸に変えて排出している。尿酸は尿素よりも毒性が低く、尿素よりもさらに水に溶けにくい(p64)
・生物はそのときどきの環境に適応するように進化するけれど、何等かの絶対的な高みに向かって進歩していくわけではない。進化は進歩ではない(p70)
・腸内細菌の数はおよそ1000兆個、私達のヒトの体は約40兆の細胞でできているが、はるかに多い。腸内細菌はほとんどが大腸にいるが、小腸の中にもいる。もしも管腔内消化でグルコースやアミノ酸まで分解してしまったら、それらを腸壁あら吸収する前に腸内細菌に食べられてしまう、なので吸収する直前にグルコースやアミノ酸をつくる(p75、80)
・塩辛さは、塩の量ではなく、塩の粒子数による、塩がたくさんあっても、大きな塊になっていればそれほど塩辛くない(p81)
・ダーウィンが言ったことで重要な部分が間違っていた、進化というものは、必ず長い時間をかけてゆっくりと進むということ(p83)
・大人がミルクを飲むと、ラクトースは分解も吸収もされない、それを分解する酵素(ラクターゼ)がないから、すると腸内細菌によってラクトースが違う方法で分解されて、メタンと水素ができる。その結果、腹部の張りや下痢に悩まされる、しかしラクターゼ活性持続症の人は飲める(p85)
・か状眼(明暗→方向→形がわかる眼)で見える像はピントを合わせると暗くなり、明るくするとぼける、ピントを合わせながら明るくする方法として、レンズを入れると良い。これが私達のもつ「カメラ眼」である(p104)
・昆虫が繁栄している理由の一つとして、飛翔能力があるが、脊椎動物にもその能力を持つものがいる。飛翔はなかなか難しく、長い動物の歴史の中で4回しか進化していない。そのうち1回が昆虫、残り3回は脊椎動物(翼竜、鳥、コウモリ)である(p120)
・カルシウムはどても重要な働きをしている、神経細胞が情報を伝えたり、筋肉が収縮したらい、怪我をしたときに血液を固めたりする。私達の骨が貯蔵庫となっている(p123)
・ヒトはチンパンジーよりも腰椎が自由に動かせるので問題も起きてしまった、オモチャの人形で腕が動かせるものはそこが壊れやすい、動くところが弱い。腰椎には体の重みがかかってくるので腰痛が起きやすくなる(p131)
・直立二足歩行をしているために、私達の内臓は下向きに重力を受ける、なにもなければ骨盤の穴をくぐり抜けて落ちてしまうので落ちないように筋肉が発達している。しかしこの筋肉が出産のときには邪魔になる(p170)
・直立二足歩行の利点の1つは、「両手があくので食料を運べる」しかし欠点として、走るのが遅いという重大な欠点があるから。この欠点が他の利点を上回っていたから直立二足歩行は進化しなかった。これが犬歯が小さくなったこととも関係している可能性がある(p188)
・シンギュラリティは「技術的特異点」と訳されることが多いが、「いままでと同じルールが使えなくなる時点」のこと。具体的には、「人工知能が自分の能力を超える人工知能を、自分でつくれるようになる時点」のことである(p210)
2020年3月31月日作成
投稿元:
レビューを見る
ヒトはなぜヒトになったのか。進化とは、
「そうなった方が生存に有利」「進化した側の繁殖力がそうでない側の繁殖力を上回ることでその種が広がる」。
なのでヒトが今の姿になったのは「たまたま」。ヒトはまだまだ進化(退化)を続ける。従ってヒトが地球上最高の生物という事ではない。
ヒトの目は精巧にできている、きっと誰かがデザインしたのだ、という俗説があるがそれも進化で説明がつく、と。
ヌタウナギなどは無顎類といって顎がなく、口が丸い。口に関しては一番原始的な形態をとっている。しかし、目にはちゃんとガラス体があり人間の目に近い構造になっている。
進化は案外早く起こる。ある鳥のくちばしの形が35年で変わった、という例がある。数百年、数千年あれば生物は変われる。
尿素の排出について一番合理的な器官をもっているのは鳥。尿素から尿酸をつくり、ほとんど水を加えない状態のものを輩出する。そのため膀胱を持たない鳥も多い。それに対しヒトは尿酸を合成するところまではできるが水に溶けない尿酸を無理やり尿に混ぜ込んで排出するというやり方を取っている。
これらの例からもヒトが最高の存在ではない、ということがわかる。
投稿元:
レビューを見る
「人類が生まれるための12の偶然」を読んだので一層興味深く読むことが出来ました。進化というのがどういうことなのか、人間が一番優れて進化して他の生き物は進化しなかったみたいなイメージしかなかった私には、人間が進化していない部分もいっぱいあることが新鮮でした。地球という枠組みの中で生きていくためには、死ななければ子孫を残せない運命になるのも事実なんだろう。学術的にどうなのかはわからないですが、こうした想像をめぐらして進化を考えるのも楽しいものです。
投稿元:
レビューを見る
人類は進化の終着点にいる、という自負なる認識に、様々な論拠を通して挑んでいる。へぇーと感心させられたり、そうなんだと新たな知見が得られたりで、読み進めることができる。ヒトは赤ん坊から大人になるに従い、能力の向上というプラス方向の成長しかないと思っていたが、そうではない事例が紹介されている。脳に関しては、他の書籍でも、赤ん坊から大人になるにつれ、不要な(
使われない)能細胞は消えていくという話を目にしたが、それが酵素レベルでも起きていることを教えられた。大人の中で、ミルクを飲むと、腹の調子が悪くなる人は、その答えを見つけられる。最近、新型のコロナウィルスが発生し、その解明に全力が注がれているが、人類と細菌の生存闘争には終わりがないのだろう。
投稿元:
レビューを見る
なぜ読もうと思って図書館に予約を入れていたのか忘れたが、いずれにせよ進化論の話は面白い。
本書はそれに「残酷な」と形容詞を冠して、生物の進化について論じる。総じて「ヒト」の進化が、なにも特異ではなく、また最先端を行く進化の優等生ではないということを、いくつかの身体機能を例に語っているもの。
酸素を取り込む呼吸の機能については、ひとつの気管(左右枝分かれはするが)で吸うも呼くもこなすヒト(や脊椎動物他も)に対し、鳥類は後気嚢、前気嚢を使い気体の流れは一方通行である。ゆえに、酸素の薄い高度を飛行できる。
食べ物に含まれる窒素の排出方法にしても、水に囲まれて暮らす魚は窒素の単純な化合物であるアンモニアを大量の水に溶かして排出、爬虫類や鳥類はあまり水分を必要としない尿酸にしてドロリとした尿を出す。我々ヒトは、毒性を下げるためにアンモニアを尿素に変えるが、水に溶けにくいので大量の水分摂取が必要にという。非効率極まりない。
我々は理にかなった他の生き物たちと較べて、いかに見劣りのする身体機能しか持ちあわせていないのかと思い知らされる。
また、この形態は、今だからこそ通用しているものであり、環境が変わればデメリットにも、あるいはよりメリットにも働く儚い姿でしかない。
こうして、ヒト(ホモ・サピエンス)という在り姿が、けっして進化の最終形態でもなんでもないといことが語られる。
進化は一方向ではないし、スピードも一定ではない(選択制選択か安定性選択か、時期による)。また、進化が我々の敵になることすらあるという(我々の心臓の冠状動脈は進化上の設計ミスだと言われることもあるそうな)。 医学知識や健康な生活習慣を武器に、進化と闘うことも時には必要か(自然淘汰に抗うのならね)。
いずれにせよ、人間は万物の霊長、などと奢り高ぶりを棄て去るにはよい内容。
【霊長】霊妙な力をそなえていて、他のかしらであること。
投稿元:
レビューを見る
数年前から人類史にハマっています。
先年、更科さんの「絶滅の人類史―なぜ『私たち』が生き延びたのか」(NHK出版新書)をおもしろく読みました。
更科さんの待望の新作とあって、早速アマゾンで注文した次第。
いや、知的好奇心を満たされました。
人類は「万物の霊長」などと言われますが、果たしてそうなのでしょうか?
本書を読めば、決してそんなことはないと分かります。
むしろ、我々人類は出来損ないなのでは? とさえ思います。
直立二足歩行のため高い圧力で血液を全身に送らなければならないヒトは、狭心症や心筋梗塞になりやすくなりました。
元々は水平だった脊椎を直立させ「不自然な姿勢」で生活するようになったため、多くの人が腰痛に悩まされています。
また、私たちヒトは、哺乳類の中では特に難産な種として知られています。
さらに、この眼だって、どうやら鳥類の方が優れているようなのです。
そう、私たちヒトは、実は大変に「不完全」な存在なのです(だから今も進化が人知れず起きているわけですが)。
本書によれば、陸上生活への適応という点から見ると、一番優れた種はトカゲとニワトリ。
ただ、水中生活への適応という点から見ると、順番は逆さまになります。
「何を『優れた』と考えるかによって、生物の順番は入れ替わる。どんなときでも優れた生物というものはいない。客観的に見て優れた生物というものはいないのだ。」
実に示唆に富む指摘です。
私たちヒトは、何かと言うと大きい脳を誇っていますが、脳は体重の2%しかないのに、身体全体で消費するエネルギーの20~25%も使ってしまいます。
「もしも飢饉が起きて農作物が取れなくなり、食べ物がなくなれば、脳が大きい人から死んでいくだろう。だから食糧事情が悪い場合は、脳が小さい方が『優れた』状態なのだ。」
本筋とは離れますが、私たちがミルクを飲めるようになったのは「自然淘汰」の結果というのも興味深いです。
私たちヒト(ホモ・サピエンス)が現れてからおよそ30万年が経ちますが、そのほとんどの期間、ヒトの大人はミルクが飲めなかったのです。
理由は、ミルクを消化する酵素「ラクターゼ」が成長するにつれ減るから。
しかし、大人になってからもラクターゼを出し続ける人の方が自然淘汰で有利になり、それで大人になってもミルクを飲めるようになったらしい。
ミルクを飲めるようになったのは、いわば突然変異。
こうした突然変異、つまり進化は、この1万年の間に何回も起きているというのだから驚きます。
私を含め多くの人は、「進化はゆっくり進むもの」と考えますが、そんなことは決してないのですね。
たとえば、ハワイ諸島に棲むコオロギは、非常に速い速度で進化が起きたことが知られています。
翅(ハネ)に突然変異が起きて、オスが鳴かなくなったというのです。
鳴かなければ寄生バエに見つからないので、生きていくうえで有利らしい。
この性質は、わずか5年でハワイ諸島のコオロギに広がったというからびっくりです。
つまり5年で進化したというのですね���
おお。
面白すぎて、あっという間に読了。
他の生き物に対して謙虚になること請け合いです。
投稿元:
レビューを見る
進化とはこんなものだという小話がいくつも続く感じ。結論があるというわけではないけど、読み物として読むのにはちょうど良い。この手のテーマは読んでてもあんまり食指が動かず読み進め難いことも多かったけど、この本はズンズン読めた。
200224