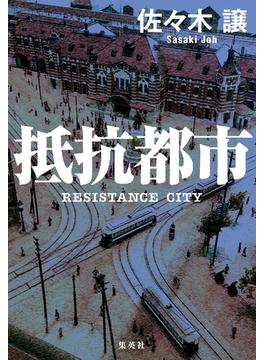紙の本
警察+歴史改編小説
2020/08/18 13:11
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:kapa - この投稿者のレビュー一覧を見る
物語の舞台は、第二次世界大戦後の荒廃した東京ではなく、日露戦争終結後11年後大正5年の東京。したがって、空襲を受けてもいないし、また、関東大震災もなかった頃のモダン都市、世界強国に仲間入りせんとする日本の帝都東京を舞台にした警察小説かと思ったら、表紙帯には「日露戦争に負けた日本」は、ロシア帝国に外交権と軍事権をロシアに委譲し統治されているといういわゆる歴史改編小説でもある。これまで読んだ歴史改編小説は、ナチス第三帝国が第二次世界大戦に勝利し、世界に君臨するという設定のなかで、極東では同じ枢軸国の日本が米国に勝利し、太平洋を支配している、というエピソード程度で触れられる程度。その中でもフィリップ・K・ディック 著「高い城の男」(早川書房)は、日本を中心に描いた数少ない歴史改編小説であったが、本書はまさに日本が舞台の歴史改編小説であり、しかも史実では勝っていた戦争に敗れたという設定。欧州の第一次世界大戦、また、ロシア革命を予感させるロシア国内(明石大佐が登場する)の情勢も視野に入れた意欲的な改編である。
作者の佐々木譲氏の著作は初めて読むが、その構成力と描写力に驚嘆した。ロシア統治機構の仕組み、日本政府との関係の説明、ロシア風に改名された東京の地名・通り名の設定(当然ロシアの文豪の名前)などいかにも敗戦国を感じさせる現実味を持つ。事件の舞台は、ほとんどが都心部、神保町、神田という狭いエリアであるが、その街並みの情景描写やロシア施設の配置等まるで作者が当時にタイムスリップして実際に歩いて見てきたような、緻密な情景描写である。独警察小説オッペンハイマー・シリーズは、当時の敗戦後の荒廃したベルリンが目に浮かぶような筆致力が魅力の一つ。そのシリーズも本書も読者の便宜を考えて地図が付いているが、それを見ながら読み進めなければならない物語なのである。
隅田川で発見された身元不明の変死体が事件の発端。警視庁刑事課の特務巡査・新堂と所轄の西神田署巡査部長・多和田が「相棒」となって捜査を開始。ところが警視総監直属の高等警察とロシア統監府保安課という日本国内における反ロシア活動の情報収集と摘発を任務とする上位の権力機構から別々に介入を受けるところは、この手の物語の必須のプロット。
二人は、地道に「地取り」を重ね、二つの権力機構と折り合いをつけながら、ありふれた事件の背後に、現在の統治体制の根幹を揺るがしかねない、第一次大戦への日本軍追加派兵を巡る親露派と反露派の対立など政治的な陰謀が潜んでいることを突き止める。書名「抵抗都市」はピンとこないが、英語の題名Resistance Cityの意味することも解ってくる。
スマホ、ネット検索、GPSなどのIT技術を駆使する捜査手法ではなく、移動手段は市電、当時のモダン女性の花型職業であった電話交換手を使った当時としては最先端の電話による情報連絡なども物語の説得力を増す仕掛けである。多和田の娘の身の危険を救うために奔走する新堂と二人の間にロマンスの展開が…と期待させるが、わずか2日間の怒涛の捜査の日々。展開する余裕もないし、硬派的な物語全体の構成からは期待はできないが。
表紙帯にあるように、知った事実が日本の利益にならなくとも犯人を逮捕するかという多和田の質問に、新堂は「当然です、わたしは警察官です。」と答える。歴史改編の構図は明らかに第二次大戦後一貫して親米路線を続ける戦後日本を過去に引き写したものであり、「今の日本への問題意識を示すために、この舞台を選んだ」という作者の思いは、主人公の警察官としての自負、いや日本人としての自負の発露の答えに込められている。
電子書籍
設定が秀逸すぎる
2019/12/23 20:40
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:眠眠ゼミ - この投稿者のレビュー一覧を見る
日露戦争に敗戦した第一次世界大戦中の日本。その設定がとにかく秀逸な作品でした。ストーリーの本筋は殺人事件捜査のいわゆるサスペンスものなのですが、それと同時に、少しずつ詳らかにされる日露戦争において敗戦した日本という不思議な平行世界。事件の謎と異世界の謎というふたつの謎が読者を惹きつけます。
また、敗戦国日本と戦勝国ロシアの微妙な政治的関係。変形した日本の統治機構。日露戦争で活躍したロシア人将軍たちの名に改名された地名。人々の細やかな生活の中に浸透しつつあるロシア文化。それらの些細な描写は、物語の深みになっていると同時に、歴史好きにはたまりませんでした。
電子書籍
著者による解説がほしかった
2020/01/24 08:50
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Masaru_F - この投稿者のレビュー一覧を見る
小説そのものは後半に向けて読み進むスピードが高まる面白さ。ただし、自分の知識の背景ではこの物語の設定された時代に関する知識が不足しており、現実の過去と本件の背景がどのように変化させているのかに関して理解不足。少しだけでも良いのでそのあたりに関する著者の開設があると、読後感が高まるのではないでしょうか。
投稿元:
レビューを見る
日露戦争で日本が事実上の敗戦となり、日本は露西亜帝国と同盟を締結。実質的には露の支配下に置かれている。海軍は廃止、陸軍は半減させられたうえ、現在は欧州の露西亜戦線(所謂第一次世界大戦)に、全陸軍の半数近くを派遣し、更に増派しようとしている。町には露軍が多数駐留し、行政・司法に深く介入。日本国民は親露と反露に分裂し、反露側への弾圧は強まっている。
そんな世の中で文具の外商(露側の内通者)が殺害され、警視庁と神田西署の刑事が捜査に乗り出す。そして警視庁官房室は露の統監府、日本陸軍の反露派らが暗躍する中での争いに引き込まれていき、非常に大きなヤマに発展する。
しかし、結末は余り納得できるものではなかった。事件の帰趨が、ではなく、ラストの中途半端さ加減と、「抵抗都市」というタイトルから、もっと壮大な話と想像していたからだ。
本筋とは余り関係はないのだが、日本の皇太子をロマノフ王朝の皇女と結婚させることにより、皇室を維持させるとか、コサック騎兵による反露運動への弾圧とか少し書かれていたのだが、この様な露西亜実行支配下における日本の様子をもう少し膨らませてあれば、この世界観をよりリアルに感じられて良かったのではないだろうか。
投稿元:
レビューを見る
虚実ごちゃ混ぜで境界線がよくわからないところが小説の面白さ。本作はその典型だ。中身からすると冗長すぎて3割ぐらいは削れそうな印象だが、大正の世界大戦勃発からシベリア出兵あたりの時代の空気や東京の雰囲気がよく描かれている。日露戦争講和後にロシアの半植民地化した日本でのレジスタンス、という設定がなかなか面白い。刑事二人が殺人事件から暗殺計画を暴いていくまでの筋は少し無理があると思う。
投稿元:
レビューを見る
2020年10月21日読了。
480ページほどの長編。
歴史改変小説。
日露戦争集結から11年後の東京、ロシアの統治下となっている。
巻初に東京駅周辺の地図が書いてあるが、ストーリーを追うにあたり欠かせない。
ロシア統治下なので、通りの名前や建物の名前などが現世と違うので、地理的関係が頭に入りづらい。
正直「面白い!」と思わせる内容ではないが、不思議とページが進む。
だが、なんとなく仕方なく読んだ感も残るのも事実。
投稿元:
レビューを見る
歴史改変警察小説とある。SFよりミステリー色が強い作品。日露戦争に敗れた日本は、「二帝同盟」の名の下にロシアに従属させられていた。折りしも、第二次世界大戦下の欧州に派兵中で、さらなる増派を求められていた。そんな中、ある殺人事件を追う二人の刑事を中心に話が進む。
この二帝同盟下の日露関係は、太平洋戦争後の安保体制下の日米関係を模していることに気づく。謎解きよりも、そちらに目が行ってしまった。作者が「今の日本への問題意識を示すために、この舞台を選んだ」と語っているとおり、今の日本を問うているのだ。
投稿元:
レビューを見る
最初、歴史小説と思い込んでいたので、しばし混乱。日露戦争で敗北し、ロシア統治下となった東京での反露運動めぐる殺人事件。今の日本への問題意識示すため執筆したと佐々木さん。ロシアを米と読み換えるとシュール!
投稿元:
レビューを見る
読み応えはあったが、いかんせん長い。思想や歴史背景の解説、地名の説明も本筋に関わる最低限で良かった気がする。そっちに集中力を持っていかれて犯人推測にエネルギーを使えなかった。
投稿元:
レビューを見る
日露戦争で敗北し、ロシア統監府が日本を統治。〝御大変〟と呼ばれる敗戦による大きな体制転換から約10年後、水道橋付近で死体が発見される。それは、国を揺るがすような陰謀へと繋がってゆく。捜査にあたるのは警視庁刑事課の特務巡査・新堂と西神田署の刑事・多和田。警視総監直属の高等警察とロシア統監府保安課の介入を受けつつも真相を追う。
改変歴史もの。
地名、反ロシア派、ロシア軍、親ロシア派の動き、ロシア統治の世界がしっかり描かれる。そういった土台だけでなく、新堂の過去のお話や、ロシア人大尉の人柄等、それがより一層物語を深いものにさせ、堅苦しくなく、暗くならず、一大エンターテインメント作品になっていると思います。
ただ、歴史やSFがどちらかというと好きでない私としては、長いなーと感じてしまった、正直なとこ。いや、予備知識なしに読んだら、そういう内容だったのかと。頑張って読みました。
投稿元:
レビューを見る
舞台設定がおもしろい。
現実はアメリカに支配されているが国民の思いはいろいろだろう。主権者としてよく考えたい。
投稿元:
レビューを見る
日露戦争に負けた東京で繰り広げられる陰謀をめぐるミステリー。ウクライナやポーランド、バルト三国で起きたことの焼き直しでは?と思う部分もあるが、歴史改変モノに珍しい「後ろ向き」な世界観のリアリティは秀逸。
東京特に千代田区周辺の土地勘があるとより楽しめます。
単に100年前のお話しと片付けられないのが深いところ。在日米軍を守るために日本の警察が日本人を傷つけたら、日本人は何を思う??
投稿元:
レビューを見る
フィクションなのに実際の場所がふんだんに出てきてリアルだった。が、長かった。ステイホームの時期でなければ、完読出来なかった。話は面白いし、破綻がない。
投稿元:
レビューを見る
「日本海海戦で負けたためにポーツマス講和条約で外交権と軍事権をロシアに委譲した1916年(大正5年)の東京」が舞台の警察小説。
ロシア統治下の東京の地名、道路計画、統治機構などに対する設定は緻密にセットされており、舞台となる都心部、神保町、神田エリアの街並みの情景描写や、市電を使った移動や交換手を介した電話コミュニケーションの展開はリアリティ(?)あり。
一方で、1914年に始まった第一次大戦に日本はロシア軍の一翼を担うかたちでドイツ戦線に2個師団を派兵しているという設定なのだが、この状況や、数年後のロシア革命の方向性についての言及はあまりない。また、米国が全く登場しないのも違和感。
「ロシア化された東京で犯罪捜査を行う刑事物」という目線で読めばよいけど、少し長かったかな。
コロナ篭りで終日在宅の昭和の日に、朝から深夜までかけて1日で読了。
投稿元:
レビューを見る
佐々木譲は基本的にミステリーの書き手ではなく、冒険小説作家だと思っている。スケールの大きい国際冒険小説、第二次大戦もの、幕末もの、どこをとっても骨のある男気の感じられる小説ばかりだ。とりわけ男性読者が多いのではないかと思われる。
最近は警察小説作家という印象が前面に出ているように思うが、それにしたって謎解きミステリーからは距離を置いて、現代、そして現実というところの素材を多く持ち出して、警官に血と体温を与えたような捜査の面を浮き彫りにしてゆくタイプの、いわば人間の生き様重視、それでいてスーパーではない庶民の、たった一つの生き様の重さを測っているようなところがある。
だから小説に血が通う。男女のロマンややわな描写をあまり得意とせず、どちらかと言えば無骨で真っ正直な庶民性のある主人公を持ってくるか、とことん英雄となるべき魂を持ってくるかのどちらかだろう。
本書は、その前者、無骨で真っ正直な帝都東京の巡査を主人公にして描いた、歴史改変捜査小説である。この作品世界では、なんと日本は日露戦争に負け、ロシアに統治権を委ねている。東京の通りの名前はロシアの有名人の名を冠され、天皇制は保たれているものの、警察権力にまで統治者であるロシアの監視を免れられない、これに逆らえば日本そのものが失われてしまうという極めて危うい亡国の状況の下に、たった一つの殺人事件が、国家を揺るがす陰謀の導火線に火を点けることになる。
新堂と多和田という二人の警察官が、大きなスケールの国際的謀略を、世界大戦の暗雲が押し寄せる時代の下で、日露戦争敗北後の帝都という舞台の上で活躍する物語なのである。こんな難路をなぜこの作家は歩むのだろう。著者自身が答えている。「今の日本への問題意識を示すために、この舞台を選んだ」と。
そう捉えると現代の日本が日露戦争ならぬ太平洋戦争という名の日米戦争に負けてアメリカの軍隊を受け入れ、準じているその姿をこの小説の背景に感じさせないわけではない。より過激なより古い時代に材を置きつつ、こうしたシミュレーション・ノヴェルのような状況下で血の通う刑事たちを生かす離れ業を、まずは考えてくれる作家、というだけで少し嬉しい。そして、その試みの意思を作品として結実させてくれることで、なお心強い。
前半は地道な捜査と時代状況の複雑さに圧倒されるが、刑事たちの有能さが国家的危機を救う鍵となり、彼ら自身も危険に身を曝す緊張状態の後半に入るにつれ、スリルとアクションとの連続、その中で読み解いてゆく真実への迷路、等々、古き時代の冒険小説を思い起こさせてくれそうだ。
現在のオートメーション感覚での面白さのサイドではなく、冒険小説の伝統を重んじた重厚かつリーズナブルな背景設定と、その暗さや重さにもめげぬ直球勝負の男たち、といった無骨で古臭いエンターテインメント。セピア色の懐かしさ。そして現代の冒険小説健在を感じさせてくれる作家の、この方向性こそがぼくには何より嬉しい一冊なのであった。