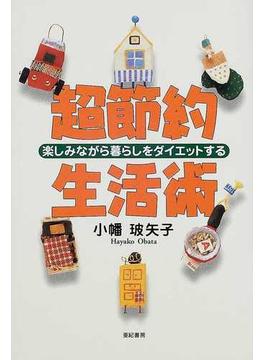「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
- カテゴリ:一般
- 発行年月:2000.11
- 出版社: 亜紀書房
- サイズ:19cm/237p
- 利用対象:一般
- ISBN:4-7505-0009-7
紙の本
超節約生活術 楽しみながら暮らしをダイエットする
著者 小幡 玻矢子 (著)
溜めた水で洗い物、野菜は皮をむかずに使用、箸袋で封筒・ポチ袋…。少しの工夫で無駄がなくなります。楽しみながら節約をする「始末に生きる」生活術を伝授。【「TRC MARC」...
超節約生活術 楽しみながら暮らしをダイエットする
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
溜めた水で洗い物、野菜は皮をむかずに使用、箸袋で封筒・ポチ袋…。少しの工夫で無駄がなくなります。楽しみながら節約をする「始末に生きる」生活術を伝授。【「TRC MARC」の商品解説】
著者紹介
小幡 玻矢子
- 略歴
- 〈小幡玻矢子〉1928年京都府生まれ。節約生活の重要さを訴え、自らも実践。クーラーなしの生活、手が荒れない糠洗剤、工夫料理など「始末のいい生活」をする。著書に「超節約クッキング」ほかがある。
関連キーワード
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
食べて遊んでまだ残る!が合い言葉
2001/08/22 01:14
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぱおっち - この投稿者のレビュー一覧を見る
「マコモ風呂」など、テレビなどでもお馴染みの節約おばさん小幡さんの節約指南本。この一冊を読むと、消費生活の何とも言えない味気なさが頭をかすめます。自分に関わるモノすべてに愛を込めて、自分の血肉のように最後まで使い切るその精神は、節約と言う言葉だけでは測りきれない、暖かな優しさを感じます。そんな生活をしているから、イヤでもお金が残ってしまう、その残ったお金で自分をリフレッシュさせるために遠い外国の地などに旅行に行くという潔さにも感服します。こんな時代、まやかしの物欲で自分を偽っている人間の何と多いことか。筆者はそんな風潮をするりとかわすように軽やかに今日も節約に励んでいることでしょう(笑)。
紙の本
そう。節約は心身にも良いというわけだ。
2001/01/26 15:23
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:瀧澤崇子 - この投稿者のレビュー一覧を見る
台所、衣類、掃除、水・電気・ガスなど基本料金、生活品、買い物と、暮らしの基本的な部分の節約ノウハウを紹介しているのがこの本。
「倹約」「節約」と、無駄を無くして賢く活用する言葉はいくつかあるけれど、本書では「始末」と言っている。これは著者が祖母から教わったものだ。もったいないことはしない、粗末にしないことをこう言っていたというのだ。考えてみれば、節約はいまに始まったことではなく、母の時代、祖母の時代、そのまた前の時代から当たり前のように脈々と受け継がれてきたこと。いまでこそ「節約」と言って、「ちょっとやってみようかな?」と遊び心あるゲーム感覚のものとなっているけれど、その根底にあることはちっとも変わっていないわけだ。
この本では、まず、節約の原則と効用が挙げられている。とりあえずこれだけは守ろう、知ろうというポイントだ。『物は「わが家の一員」にように遇する』などの7つの原則と、「気持ちいい節約は人の縁を広げていく」などの5つの効用。これらを基本にした生活全般のダイエット法を指南しているのだ。
おもしろいのは、節約の効用。なぜ節約するかと言うと、「お金を貯めたいから」「無駄遣いを減らしたいから」とお金にまつわることがほとんどだろう。節約の結果、貯金ができた、旅行に行けたなど物質的なプラスならすぐにでも思い浮かぶけれど、本書では、目に見えないところにも目を向けているのだ。とにもかくにも、節約するには、あれはどうすればいいか、これはどうするかと、頭を働かせる。ぼーっとして過ごすよりぐるぐる回転させていたほうが脳ミソにはいいはず。空気清浄機を使わなくても、硬く絞った雑巾を振り回しながら部屋のなかを踊りまわる節約法などでは、体を動かしている。そう。節約は心身にも良いというわけだ。お金も減らず欲しいものにも手が届きそうになりながら運動不足解消や頭のトレーニングになるとなれば「節約さまさま」というもんじゃないだろうか。また、なんでもかんでも安く済まそうという考えでもない。1点豪華主義を衣食住に取り入れると良いのだそうだ。たとえば「衣」に取り入れて、時計だけでも高価なものを身につけていたおかげで交渉ごとで信用を得られ、スムーズに処理できたなどの効用もあるものだというのだ。あなどれない、節約の心得……。結果や効用がわかれば、俄然やる気が出てくる。
節約の方法については、「ケチ」とも言えるほど慎ましやかなものが多い。実際、著者は「ケチ」と呼ばれ続け、著者に始末の心を芽生えさせた祖母自身もケチが悪いこと、怪しいことだとは思っていなかったのだから著者もそうであったのだろう。20年以上も前から節約の本を世に出し、ときには白い目で見られたこともあるだろうが、いまでこそケチも節約のひとつ。明るいケチ党が仲間を増やし、著者もケチの女王と扱かわれ方もかわっている。ケチの裏には代々受け継がれてきた”知恵”がある。そうそう、昔、おばあちゃんがやっていたなという懐かしさも蘇る。感心しながらしばし感傷にひたり、ちょっとわが身の堕落ぶりを反省するのであった。