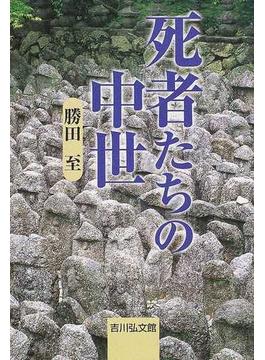「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
死体が路傍・河原・野にあることが日常茶飯事だった中世。死者はなぜ放置されたか。「死骸都市」平安京での死体遺棄・風葬など、謎に包まれた中世の死者のあつかいを解き明かす。巻末に中世京都死体遺棄年表を付載。【「TRC MARC」の商品解説】
著者紹介
勝田 至
- 略歴
- 〈勝田至〉1957年新潟県生まれ。京都大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。現在、芦屋大学非常勤講師。
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
埋葬の移り変わり
2021/07/30 02:10
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:藤和 - この投稿者のレビュー一覧を見る
中世日本の死者の弔い方の移り変わりを考察した本。
話の発端は五体不具穢という不吉な現象が起こった原因と、その現象が減っていった原因を考察するというもの。
中世の京都はおそろしいなと思いながらも、感覚の違いはなんとなく感じられるかも。
紙の本
死に触れることで
2017/06/13 08:42
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Todoslo - この投稿者のレビュー一覧を見る
死が現代よりも日常だった中世の世界観が伝わってくる。医学や科学の発達した後になって、死が忌み嫌われていくのは皮肉な結果だ。
紙の本
死者に囲まれた中世の日常が見える
2003/08/28 15:59
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:藤井正史 - この投稿者のレビュー一覧を見る
最近では伝統的な葬儀や墓の在り方に疑問を呈す風潮がある。本来の宗教的な意義を振り返ることなく、音楽葬、自然葬、散骨などを現代人の感性に合ったものとして持てはやす報道もある。宗教儀礼に意味を見出せない傾向は、人前結婚式なども同じ感性だろう。なぜ祈り、何に祈るのかという視点が欠けた歪み。それは、住宅地での墓地造成に反対運動が起きるなど、皆が健康で死者のない日常をつくり上げることに汲々としてきた日本人の感覚に通じるものだ。
このような感覚は今に始まったことではない。しかし、菩提寺での葬儀、墓地への納骨が行われるようになる前は、身近な死をどのように受け入れ、処置していたのだろうか。
中世の京都では空き地や河原、大内裏にさえ死体が放置されていたという。そのため、犬が人体の一部を咥えて敷地に入ってくるなど事態も日常的に起こりうる。これにより生じた穢れ=五体不具穢に関する記述を本書では丹念に追っている。当時、一般的だったのは風葬・放置等で、使用人や病人が死にそうになると、穢れが生じることを恐れ、亡くなる前に道路に遺棄することさえあった。自分の目の前さえ清浄であれば良いという公家社会の思想は、現在も生きているのではないだろうか。
当時の葬送儀礼の様子を追っていくと、現代ほど遺体・骨には執着していないことがわかる。穢れへの恐れこそが最も重要なのである。
やがて京中に放置される遺体は減少し、念仏講による臨終・葬儀の組織的互助の確立、蓮台野など共同墓地への移行、非人・河原者による葬送への関わりが始まり、戦国時代からは禅宗による豪華な葬儀や、華美な葬具の使用も見られるようになる。
この変化の理由を著者は探っていくが、現在の葬送儀礼の成り立ちを見つめることは、これからの葬儀の在り方を考えるにも重要なことだろう。葬儀を司る身としても非常に興味深く読んだ。(藤井正史/文筆家・僧侶 2003.08.28)
紙の本
死体
2019/05/18 20:28
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ハム - この投稿者のレビュー一覧を見る
中世の時代にはしたいが身近で、自分自身や家族や身近な人たちの死も身近なものだったんだなと思うと悲しい。
紙の本
目次
2003/08/28 16:03
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:bk1 - この投稿者のレビュー一覧を見る
第一章 死骸都市・平安京
死体放置の状況/死体の分布
第二章 死体放置の背景
葬送と血縁/遺棄の場/京中の死人
第三章 貴族の葬送儀礼(1)
臨終から出棺まで/臨終と遺体の安置/入棺/出棺
第四章 貴族の葬送儀礼(2)
葬送/葬列/火葬/葬式の後
第五章 貴族の葬法
玉殿と土葬/葬法と霊魂/墓の選定
第六章 共同墓地の形成
諸人幽霊の墓所/二十五三昧/蓮台野の形成/鳥辺野と清水坂
第七章 死体のゆくえ
可能性の検討/輿の力?/変わりゆく葬儀
系図/参考文献/中世京都死体遺棄年表