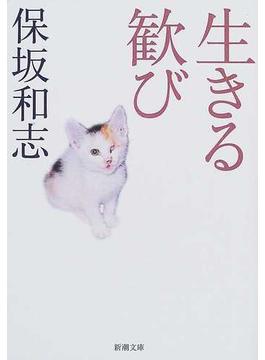「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
収録作品一覧
| 生きる歓び | 7-54 | |
|---|---|---|
| 小実昌さんのこと | 55-139 |
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
三つ目の小説?
2006/04/05 19:55
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:メル - この投稿者のレビュー一覧を見る
この本には、妻の母親のお墓参りに出かけたときに見つけた病気の子猫を、付きっきりで看病した模様を語る「生きる歓び」と、田中小実昌が亡くなったときに、その交流を振り返り、そのことを綴った「小実昌さんのこと」の二つの作品が収められている。
「あとがき」のなかで保坂は、この二つの作品にフィクションが紛れ込んでいるとしたら、小実昌さんから家までの道順を訊くところだけで、他にはウソはないという。そして、「「小説」と言っているんだったらウソのあるなしにこだわる必要もないだろうけれど、今回の私はこだわる」(p.141)と書いている。「だったら小説ではないんじゃないかという意見もあるかもしれないけれど、私は小説であることにもこだわる。この二つの話はあったことしか書いていないけれど、それでもやっぱり明快に小説なのだ」(p.141)と断言しているところが、なんだか気になる。なぜ「明快に小説」なのだろう? では、保坂にとって、「小説/非小説」の差異はどこにあるのか。これは、保坂の他作品を読むときにも感じることでもある。
この「あとがき」の言葉を読んでしまうと、「小説」というものが一体何なのか分からなくなるのだが、そんなとき、ふと感じたのはこの「あとがき」自身も実は「小説」と呼べるのではないかということだ。つまり、この本には、「生きる歓び」と「小実昌さんのこと」と「あとがき」という三つの小説が収められていると言ってもよいのではないだろうか。実際、「あとがき」にしてはやや長めの文章で、またここで語られているのは、「貢伯父さん」の思い出とその死についてなのだ。となると「あとがき」の文章と、たとえば「小実昌さんのこと」の文章の差異はどこにあるのだろう。
ひとつ補足しておくと、「生きる歓び」のなかにあった言葉すなわち「人間というのは、自分が立ち会って、現実に目で見たことを基盤にして思考するように出来ている」、「人間の思考はもともと「世界」というような抽象的でなくて目の前にある事態に対処するように発達したからで、純粋な思考の力なんてたかが知れていてすぐに限界につきあたる。人間の思考力を推し進めるのは、自分が立ち合っている現実の全体から受け止めた感情の力なのだ」(p.16)といったところが注目に値する。
「世界」ではなく、「自分が立ち合っている現実」に留まること。そして、それを受け止める「感情の力」。これらが、保坂の「小説」を創りあげるものであろう。「現実」ではなく「世界」のほうを語る言葉を「ご都合主義のフィクション」(p.16)すなわち嘘でしかないとする点が、保坂らしい。ご都合主義ではないフィクションこそが、保坂の小説だと言えそうだ。
紙の本
田中小実昌の自伝にはすっかり騙された
2004/06/20 14:28
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:pipi姫 - この投稿者のレビュー一覧を見る
この本には表題作以外に「小実昌さんのこと」という短編が収録されていて(「生きる歓び」よりそっちのほうがずっと長い)、今回は「生きる歓び」そのものについて興味のある方には、保坂の『世界を肯定する哲学』とセットでコメントしたわたしのblog「吟遊旅人のつれづれ」を読んでいただくことにして、今回は「小実昌さんのこと」について書きたい。
いやあ、まったく田中小実昌には騙された。『自伝』を読んですっかり田中小実昌は自堕落でええかげんでだらけた人間だという像ができあがってしまったのだが、保坂和志によれば、田中小実昌は非常に時間にきっちりした人物で、約束時刻の数分前に現れ、カルチャー講座も時間通りに始めて時間通りに終わり、電話での応対もきちんとしていて年賀状もこまめに書いていたというではないか。
これは自画像と肖像画の落差が激しい一例だが、よくよく考えて見れば、小実昌の自伝を読んでわたしが作り上げたイメージはわたし自身が捏造した人物像に過ぎなかったかもしれないのだ。確かに小実昌は「ぼくは時間にルーズだった」などとは書いていない。何をやっても不器用で時間がかかったとか、なまけ者だったかのように自分を描いてはいるが、「与えられた課題にはルーズだった」と彼は書いているだけなのだ。大学の講義には出席しないとか軍事教練には真面目に取り組まなかったが、彼は自分の楽しみには一生懸命取り組んだのだ。
この「小実昌さんのこと」という小説は、田中小実昌の実像の一つに迫り、実に生き生きと彼を描いている。田中小実昌への追悼文のはずなんだけれど、保坂自身は「これは小説だ」と「作者後書き」であくまでも言い張っている。エッセイでもなく、小説なのだそうな。
わたしには小説だろうがエッセイだろうがどうでもよくて、とにかくこの作品には田中小実昌の魅力が溢れ、どうしても小実昌の小説を読みたくさせるような優れた文芸評論でもあったわけだ。保坂が小実昌を見る目は大変細かく、小実昌とのつきあいの長さに沿うようにそのときどきの保坂自身の心理が小実昌を見る目に反映していて、筆致の変転が興味深い。
保坂と小実昌の出会いは、1979年の連作小説『ポロポロ』に始まる。これを読んで大きな感銘を受け、大笑いしてしまった保坂は、以後、田中小実昌という作家の名前を記憶にとどめることになる。保坂は『ポロポロ』からかなり長い文章を引用してその魅力を語る。一般には、『ポロポロ』以後、田中小実昌は哲学小説を書くようになったと言われているらしいが、保坂は小実昌の小説は哲学ではないという。
「小実昌さんの書いていたことは「哲学以前」だった。…「哲学」という括りに入らない何かを考えたくて書いていたわけで、それを「哲学」と言ってしまうことで別のものになってしまう」(p61)
これは保坂自身の小説にも当てはまることだろう。保坂が見た田中小実昌という図は、小実昌から保坂が多くの小説作風上の影響を受けていることをうかがわせ、この小説を文学史の系統図として読んでもおもしろい。
というわけで、以下、『田中小実昌 コミさんの不思議な旅』へ続く。
紙の本
多分僕は少年時代、コミさんと同じ風景を見た違いない。
2003/12/05 12:01
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:栗山光司 - この投稿者のレビュー一覧を見る
小島信夫との往復書簡『小説修業』(朝日新聞社)で保坂はリアリティについて夢の中で与えられた状況に対して、いくつになっても必死に逃げたり怖がったり途方に暮れたりして真剣に対処するが、目が覚めた時の現実の生活では年齢を重ねると共に状況を適当にいなしたり高を括ったりすることを覚えていくが夢の中では絶対にそのようなことにはならないと記す。
《もう先生には何度も申し上げたことですが、家で飼っていた猫が予想外の若さで死んだとき、私はいつまでたっても悲しくて、思い出すたびに喉が詰まって涙が溢れ出て、大人になっていても「悲しい」と感じる気持ちは子ども頃とじつは少しも変わっていないことを身にしみて知りました。大人になっても子どもと同じように笑うのですから、泣く方だけが成長とともに薄れるはずはないのです。「喜怒哀楽」という気持ちのエネルギーのようなものは年齢とともに変化することはたぶんなくて、それを社会生活や自分自身のバランスにとって必要だから、いなしたり弱まったかのように振舞うことは身につけていっても、エネルギー自体は本当はきっと子どものときのままなのです。それは夢の中でいくつになっても与えられた状況に真剣に対処することと深く関係しているはずです。同じことだと言っていいのかもしれません。》
人間の内面とか精神にとっては夢と現実では夢の方にこそリアリティがあるかも知れない。そのようなリアリティの切実さは愛猫の死を体験し、彼自身の生きることが書くことのストレートな同衾によって【身をやつす文体】の枠組みから意識して脱皮する事を心がけ、『猫に時間の流れる』から大きな文学的転換をはかったらしい。どうやら彼にとって猫との偶然の出会いは、一種の恋愛小説と同じ空間ではないか、『カンバセイション・ピース』(新潮社)でこんな風に書いている。恋をすると見るもの聞くものが楽しくなるとか、世界が生き生きしてくるとか言うのは本当で、バラバラに拡散しがちな視覚をひとつにまとめあげる力が恋する人の中で働き出して、風景は息を吹き込まれる。つまり恋愛小説とはそういう感覚を基盤にした人間と世界との関係の話で、保坂の猫もそういうことであろう。
収載の「生きる歓び」も「小実昌さんのこと」も異例の速さで脱稿し、猫が憑き、神憑り、カミが降臨したらしい。コミさんの父親は独立教会の牧師で瀬戸内を見下ろす人口密度は過剰な余り山の背まで人家で密集していた軍人と職工の街、呉の十字架のない教会でコミさん親子は住んでいた。その父が信じた、いや信でなく受(ウケ)という分らぬものだが、そんなアメン父が精神全体で感応するカミに似た何かが光臨したのであろう。作者が拾ってきた死に瀕した子猫の生命力が溢れ出てカミのカタチになったのかも知れない。
《猫は薬に馴れていないから本当によく効いて、どんどん治っていく。哺乳ビンの乳首も噛んで自分で飲み、赤身も小さい頭の小さい口からスルスルスルスルあまり見たことのない何か別のメカニズムで飲み込むようにして食べていった。》
確か二編とも小説らしい小説でないかもしれない。保坂文学の中身は窺い知れないが、小説とは「ああも書けるこうも書ける」という選択肢の中から書き手が主体的に選んだようなものはつまらないもので、「こうとしか書けなかった」というのが小説で、それは命を削るものであろう。
紙の本
保坂撮影のカバー写真は作中の子猫だろう
2003/09/04 16:26
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:king - この投稿者のレビュー一覧を見る
「生きる歓び」はある日母親の墓参りへ行ったときに、道でうずくまって寝ているようになっている猫を拾う話だ。その猫はとても弱っていて、死にそうなほどだったのを、語り手が拾って帰り、何とかエサを食べるまでに回復するまでの経緯が語られている。
胸をぐっと掴まれるような生々しさを感じた。この生々しさは何だろうか。猫が今にも死にそうだという、死の生々しさだろうか。確かに、つぶれてしまっている左目や、膿のたまっている右目からその膿を掻き出すシーンなどは、死に瀕している衰弱が、生々しく現れてくる。
ただ、私が感じたのは、そうではなくて、生きるということの生々しさだったのだと思う。そしてそれはまた、何かに直面すると言うこと、決定的な〈到来〉という生々しさでもあったと思う。
弱り切っていた子猫は、死や全盲になる危険を何とか乗り越えて、語り手の目に見えるほどの回復を示す。
「猫は薬に馴れていないから本当によく効いて、どんどん治っていく。哺乳ビンの乳首も噛んで自分で飲み、赤みも小さい頭の小さい口からスルスルスルスルあまり見たことのない何か別のメカニズムで飲み込むようにして食べていった」44〜45頁
〈生きることの歓び〉を発散しているようだと記述されるシーンのこの描写は、生々しい〈生〉を感じさせる部分だった。左目を失っても、死に瀕していても、そこから回復していく確かな変化。
「「生命」にとっては「生きる」ことはそのまま「歓び」であり「善」なのだ」45頁
猫との出会いは偶然だった。もしかしたら誰か他の人が連れて行ったかもしれないし、カラスに食われてしまっていたかもしれない。それでも、語り手がその猫を連れ帰り、回復にまで至ったのは出会いそのものによる。
「人間の思考力を推し進めるのは、自分が立ち会っている現実の全体から受け止めた感情の力なのだ」16頁
もうひとつの生々しさというのはこれのことで、直面するということ、出会うということの決定的な作用である。子猫の生に直面すること。それがおそらくこの小説の〈生々しさ〉なのだろうと思う。
「世界を肯定する哲学」の末尾の章と直接繋がっている小説であり、是非そちらも参照してほしい。
「小実昌さんのこと」は田中小実昌という小説家の訃報に接して描かれた作品で、保坂自身の田中小実昌との出会いやつきあいのことが書かれている。これを読んでみると田中小実昌の文体というのが保坂和志とかなり重なるようなものであることがわかり、保坂と田中という二人の作家の密接なつながりを見る思いがする。
〈見る〉というのもまた二人にとってとても重要な要素で、いくつもの作品を引用しながらいかに田中小実昌にとって見ると言うことが重要だったのかについて書いていく。保坂も「世界を肯定する哲学」のなかで、見ると言うことに終始こだわっていたのだが、〈私〉をめぐる視線の問題というのがこの二人に強く意識されていたのだと言うことがわかる。
作中に、「小島信夫っていうのは、田中小実昌とか後藤明生みたいな、ダラダラ書く作家の総本山みたいな作家なんだよ」という台詞があるように、小島信夫は途中から延々と長い饒舌によって突き進む奇妙な小説を書いている。保坂和志は小島信夫との往復書簡の本も出しているし、小島信夫についてはよく言及している。ここで、小島信夫、田中小実昌、保坂和志というラインが浮かび上がってくるというのが面白い(しかし、保坂和志が後藤明生に言及したのを見たことがないが、なぜなのかということがずっと疑問になっている)。
不思議な追悼小説の本作は「小実昌さんが死んだと聞いて意外な気がしなかった」と感じていることから、「小実昌さんが死んだことが変な感じがする。僕はこれを書いていたあいだ、外を歩いているときも、小実昌さんと一緒にいるようだったのだけれど」で終わる。