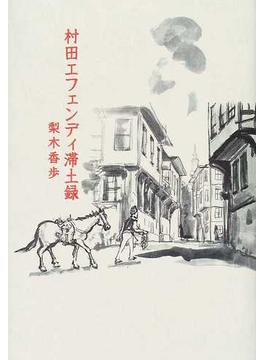「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
1890年末、トルコ文化研究のためスタンブールに出向いた村田君と、下宿屋の女主人や個性豊かな様々な国の下宿人たちとの熱い交流。いつしか芽生えた友情のようなものは…。『本の旅人』連載を単行本化。【「TRC MARC」の商品解説】
著者紹介
梨木 香歩
- 略歴
- 〈梨木香歩〉児童文学者のベティ・モーガン・ボーエンに師事。著書に「西の魔女が死んだ」(日本児童文学者協会新人賞等)、「裏庭」(児童文学ファンタジー大賞)など。
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
まるでラヴェルのボレロのよう
2011/04/18 14:48
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:BH惺 - この投稿者のレビュー一覧を見る
奇妙なタイトルからして興味を惹かれ、そして読了後すぐにラヴェルのボレロという曲を連想しました。 あの淡々と同じフレーズが繰り返されて、クライマックスに向けて盛り上がり劇的なラストで終わる、あの有名な曲。
まさにそんな感じのストーリーでした。初っ端から言い切りますが、名作です。
時代的には第一次世界大戦前。トルコ文化研究のために招聘された日本の学者・村田が主人公。舞台はエキゾチックなスタンブール(イスタンブール)。
その村田が下宿している屋敷の女主人はイギリス人。そして下宿人は彼の他、ドイツ人・オットー、ギリシア人・ディミィトリス。そして下働きのムハンマドと、その彼が拾ってきた鸚鵡の、国際色豊かな面々と一羽との静かで大切な心の交流。
最初はまるで実在の人物のトルコ滞在記かと見まごうばかりの、淡々とした村田の語り口で綴られていきます。スタンブールの風俗・風習、古代遺跡発掘の様子、村田と下宿人との交流……などなど、街や人々の的確で詳細な描写。情景が目に浮かぶようなリアルさに驚きも。
クライマックスには妖しげな女性霊媒師・美しい女革命家が登場し、そして今まで同じ下宿人と思っていたディミィトリスも密かに来るべきトルコ革命に一役買っていたという事実の判明。さらに、村田本人の日本への帰国……と、怒涛の急展開。戒律厳しいトルコ女性が実は急進的な革命分子であったり、世界は第一次大戦に突入していったり、そして戦後、トルコ革命の成功などなど。それまでのゆったりと流れるような日常から、真逆の事態の急変に目が離せず。
そしていよいよラスト、スタンブールでの下宿先の女主人から送られた村田宛の手紙が心打ちます。
共に生活し、青春時代の一時を分かち合った、それぞれ国籍の違うオットー・ディミィトリス・ムハンマド。その彼等は無残にも戦争の犠牲となってしまい、皆を偲ぶその手紙が涙を誘う劇的な内容。
何故作者は登場人物の国籍をこう設定したのか。ラストまで読んでやっとその理由がわかります。最初から張り巡らされた巧妙な伏線。秀逸なのは、なんといっても鸚鵡でしょう。 最後に村田に届けられたその鸚鵡こそ、村田の青春時代の証であり、亡き友たちの魂の化身でもあるのだなと。
「およそ人間に関わることで、私に無縁なことは一つもない」
特に印象的な作中のディミィトリスの言葉なんですが、これが今作のテーマでもあるのかなと。そして、村田の平坦な語り口の裏に隠された反戦への想いも併せて感じ取ったのですが。
エフェンディとは、おもに学問を修めた人物に対する一種の敬称とのこと。その村田の大切な青春時代とかけがえのない友情へのノスタルジーを描いた秀作。
読了後、静かな感動でしばし呆然としてしまいました。もちろん、涙腺が崩壊したことは言うまでもないです。
BIBLIO HOLICより
紙の本
淡々飄々と語られる百年前のトルコ留学記。このまま淡々飄々と終わるのかと思ったら、最後の最後にきゅーっと情感を引き絞るようなラスト、思わず涙してしまった。満足の一冊。
2004/05/19 00:09
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:うおざ - この投稿者のレビュー一覧を見る
100年前のトルコ、もとい本書の表記に従うなら「土耳古」というべきか。時代的にも地理的にもエキゾチックな舞台。そこへ考古学を学ぶために赴いた、真面目な村田青年。
彼の目を通して下宿の人々、スタンブールの情景・風物、考古学のエピソード、異国の地で育まれる友情などが、淡々と語られる。その合間に、人知の及ばぬ不可思議な体験をしたり、西欧のアジア支配の現状を憂いたり、近代化の道を歩み始めたばかりの祖国日本に思いを馳せたりしながら、けれども語り口はあくまで淡々と、やがて村田は帰国する。
落ち着いた色の糸でゆったりと織り上げた、という感じの短編が、ことさら奇をてらわず(中には十分玄妙な話もあるが)、声高に主張せず、端正に佇む風情だ。
てっきりこのまま、淡々と終わるのかと思った。つい先週読んだ「家守奇譚」がそうだったし、わたしはその独特の味わいを大変気に入ったので。ところが終盤、村田は物語の糸を一気に引き絞り、熱い情感を迸らせる。思わず涙してしまった。
思いがけないラスト。上々の読後感。大満足の星5つでした。
紙の本
百年と少し前の土耳古の街のざわめきが聞こえる
2004/05/30 02:02
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:風(kaze) - この投稿者のレビュー一覧を見る
淡々と綴っていく梨木さんの文章がとてもよかった。語り手の村田がそうであるように、まるで百年と少し前の土耳古(トルコ)の国に暮らしながら書いていったんじゃないかと、そんな錯覚すら覚えました。
本書は、1899年(明治32年)に専門の考古学研究のため、招かれて土耳古で生活した村田エフェンディ(註:エフェンディというのは、おもに学問を修めた人物に対する敬称で、先生というほどの意味)の滞在日記。私こと村田が、ディクソン夫人の下宿先で生活を共にし、語り合った国籍も色々な友人たちとの交友録を綴ったものです。
それぞれの国の文化や風土が違うように、彼ら友人たち、独逸(ドイツ)人のオットー、希臘(ギリシア)人のディミトリス、土耳古人のムハンマドの思想や神に対する考え方も実に様々です。それは、日本人である村田にしてもそう。多種多様、十人十色。しかし、国籍も色々な彼らが同じ住居で暮らし、その時を共有した思い出は、本当にかけがえのないもの。その尊く、何にも増して代え難い思い出が、はるか異国の地からの呼び声のように村田の心に響いてくるラストは感動的でした。泣いてしまいました。
そうそう。ディクソン夫人(土耳古での下宿先の女主人。英国人)の家で彼らと一緒に生活した鸚鵡(おうむ)が、キャラとしてすごくいい味を出していました。時折、絶妙な言葉をしゃべるんですよね、この鸚鵡。あんまり絶妙なんで、あちこちでくすりとさせられました。
村田の部屋の不思議な出来事とか、遺跡の発掘現場の場面など、歴史が立ち上ってくる雰囲気というのがよかったです。本書から一箇所、それを感じた文章を引用してみます。ちょっと長いので心苦しいのですが、考古学への村田の思いと、その場所の雰囲気が心に響いてきた文章です。ここを読んでいて、浦沢直樹さんの漫画『MASTERキートン』の主人公のことを思い浮かべました。
> 本書 p.56 より引用
中村 智さんによる表紙の装幀と、本の中の挿絵の数々。百年と少し前の土耳古、スタンブールの街のざわめきが聞こえてくるみたい。村田が綴る文章にしっくり溶け合っている風情が、実によいなあと思いました。
カバーを外すと、石が積み重なった写真が目に飛び込んできます。普段、カバーを外して読む私は、この石の風景を時折眺めながら、村田の書いた文章を読んでいきました。読み進めながら、石たちが語るつぶやきが聞こえてくるような気もしました。
今までに読んだ梨木さんの作品の中では、『西の魔女が死んだ』と双璧のお気に入りの一冊になりました。綿貫征四郎が書き付けた『家守綺譚』と繋がるところもありますね。本書か『家守綺譚』、どちらかお読みになった方は、もう一冊もどうぞとお薦めします。両方ともまだという方でしたら、できれば『家守綺譚』を読んだ後に本書を読んだほうが、本書の読み心地が一層増すかなと思います。
紙の本
遠い土耳古(トルコ)の地で育まれる友情
2004/05/04 15:03
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:スパンキィ - この投稿者のレビュー一覧を見る
中村智氏の装幀と水墨画のような挿絵が雰囲気をさらに盛り上げる。
場所は土耳古(トルコ)帝国、時はオスマン朝末期。主人公の村田は土耳古皇帝の直々の招きで歴史文化研究員として土耳古の君府・スタンブールへやってきた。下宿をしている屋敷には女主人で英国人のディクソン夫人がいて、料理や下働きの土耳古人・ムハンマドがいる。下宿人仲間には同じ学問を志す独逸人のオットーと希臘(ギリシア)人のディミィトリス。本書は彼等とムハンマドが道で拾った絶妙のタイミングで喋る鸚鵡を軸に、村田が体験した文化の違い、不思議な体験が綴られる連作である。
村田は前作『家守綺譚』の主人公・綿貫征四郎と大学の同窓なので、本書の最後のほうに出てくる。綿貫征四郎もそうだが、この村田という青年も土耳古で不思議な体験をしていくが、本書の主題はそういうことではなく、彼が異国の地で育んだ友垣との交遊であり、人間として分かりあえた青春の日々が国家という正体のわからぬものに振り回される日々へと変貌していったことへの寂しさであろうと思う。
そうした国家や民族を超えた交流の背景に描かれるのが、今から約100年前のトルコの風景である。まるで見て来たかの様に書かれていて、挿絵の美しさと凝った装幀と合わせてまだ見ぬトルコへと想いを馳せてしまった。まるで登場人物が実在であるかのようだ。
紙の本
なぜか懐かしさを感じる作品
2018/10/28 02:02
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:まな - この投稿者のレビュー一覧を見る
異国の、しかも遠い昔が舞台の話なのに、私には懐かしさを感じる作品でした。それは昭和を舞台にしたような作品で感じる懐かしさとは異なるもので。
人と人との間にある空気感、あいまいなものをあいまいに留め置く寛容さ。
神と人との関係、目に見えないがそこにあるということ。
ないものに目を向ける、そのまなざしに懐かしさを感じたのでしょうか。
漠然とですが、何年も後になって出版された同じ著者の「海うそ」という作品にも通ずるものがあると感じました。どちらも、喪失がテーマの一つになっているからなのだと思いますが、作品の醸し出す雰囲気は異なります。
本書は、著者が長年大切にされている「理解はできないけれど、受け入れる」ということ、そのことが強くあらわれている作品の一つだと思います。
紙の本
同じ時代に生きる幸せ
2004/07/10 23:09
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ナカムラマサル - この投稿者のレビュー一覧を見る
読んでいる最中は、あまりにも淡々としていて、もっと刺激を!と思う瞬間がたびたびあるのだが、読み終えると、なんかすごく偉大な本を読んでしまったのではないだろうか、と一週間ぐらい頭から離れない本、というものがあるとすれば、本作はまさにそれである。
明治時代、考古学研究員として土耳古に留学した、村田くんという日本人青年の物語。(「村田くん」などと呼んでしまうのは、彼があまりにもまっすぐで、純粋で、守ってあげたくなるような青年だから。)
発掘仲間の独逸人や希臘人、下宿先の英国夫人、下僕の土耳古人たちと接していく日々の中で彼が体得する、歴史・宗教・民族・文化に対する‘ものの考え方’には学び得る点が多い。それは作者が聡明で、思考にブレがないからだろう。
戦争や政変などは、歴史の表舞台。そうではなく、市井の人々の感情の発露に耳を傾けるのが、考古学者だ。彼らは、歴史というものそれ自体は、何かを目指しているものではなく、物にこもった気配や思いの集積なのだ、と思っている。発掘という作業を通して、この世には目には見えないあまりにも多くのものが蠢いているということも、身をもって知っている。
村田くんは、いつか自分の「思い」も何物かに宿り、目覚めた後の世でその思いを伝えてくれるだろうという確信にも似た考えに至る。この村田くんの成長ぶりに、読者は大いに勇気づけられる。励まされる。人類の長い歴史の中で、自分の小ささを嘆くのではなく、自分もこの悠久の歴史の一部を成しているのだ、そのことを誇りに思おう、と。
自分だけでなく、憎たらしいことばっかり言う自分の母親も、電車で思いっきり足を踏まれた見ず知らずのオヤジも、夢にでてくるほど愛しいあの人も、実は歴史を背負っているんだ、と思って、一人胸を熱くするのもいい。
時代を共有する私達がすべきことは、本文中の次の言葉に表れている。
「我々は自然の命ずる声に従って、助けの必要な物に手を差しだそうではないか。この一句を常に心に刻み、声に出そうではないか。『私は人間である。およそ人間に関わることで私に無縁なことは一つもない』と」。
読み終わった後、心の背丈がすこし伸びたような気持ちになる一冊だ。
紙の本
家守奇譚→本書へ
2015/08/25 19:27
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:夜メガネ - この投稿者のレビュー一覧を見る
この物語を読んでいると、行ったこともないのに恥ずかしいのですが、
トラン・アン・ユンのベトナムが舞台の映画を思い出しました。(舞台はトルコなのに。)
(映像美の映画監督。代表作は「青いパパイヤの香り」「シクロ」「夏至」「ノルウェイの森」。
この中でも「青いパパイヤの香り」「夏至」が本作を読んでいて思い出された。)
オウムや町並みの描写の見事さにモチーフが重なっているのだろうと思われます。
淡々とした中に、登場人物各々の時代的な事情が裏付けられていてとても写実的な描写力が見事。
家守奇譚よりは現実性が強まるが、気に入った人なら十分に楽しめる作品。