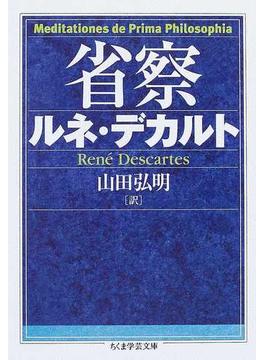紙の本
デカルトが『方法序説』の後に刊行した興味深い書です!
2019/01/25 14:58
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、近代哲学の父とも言われるルネ・デカルトが名著『方法序説』を刊行した後に出した興味深い一冊です。同書は、形而上学の関する思索をより精緻に描いたもので、6日間の省察という形をとって、徹底してすべてを疑いながら、その中から確実な事実のみを探り、神の存在と心身を区別しようとした画期的な内容となっています。ぜひ、デカルトを理解したい方々には読んでいただきたい一冊です。
紙の本
訳者山田弘明さんには五つ星進呈
2007/02/26 16:45
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:仙道秀雄 - この投稿者のレビュー一覧を見る
スタンダールが言っているそうだ。第二省察までは面白いが、第三省察からは坊主論議だと。この説になかば賛成する。なかばというのは言い切る自信がないからだが、一生懸命読んだが分らんことは間違いなく、いくら世間で良い書物だと言っていても、自分が分らなければやはりそれは自分には無縁だと判断せざるをえない。
メルロ・ポンティは第6省察を心身合一の立場から評価するそうなので、第6省察は再読するべきかもしれない。
第二省察からインスピレーションというと大層だが、「オモロイ」と思えた箇所があったので(英文ではあったが)牛王5号でのエッセイのタネにさせてもらった。
付録の「幾何学的仕方で配列された神の存在と精神と身体との区別を論証する諸根拠」はスピノザのエチカを思わせる。実体・共通概念という概念もある。
注解が解説ともども良くできていて、分りやすく大変参考になる。とくに自分らのような素人には。227頁から235頁には本文のパラグラフに対応した要約がついている。この要約をガイドにして本文にあたれる。本当に親切な本である。こういう仕事をした山田弘明さんには五つ星を進呈したい。
紙の本
解説がいい感じがする
2017/05/18 00:12
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ポージー - この投稿者のレビュー一覧を見る
省察を読むのはこれが初めてだから他と比較してるわけじゃないけど、解説とかが初心者に優しい感じがある。
僕は省察自体に興味があったわけじゃなくて、他の読みたい本があるからそれの準備みたいなことで読んだ。だから論理が込み入ってるところは適当にわかったことにしてとにかく早く終わらした。こういうスタンスでも解説でおさらいしとけばなんかいいんじゃないかって思わしてくれます。
投稿元:
レビューを見る
結局、神の存在に落ち着いてしまっているけれど、
どうもそれは、いわゆる「神」とは違うんじゃないかと
思い始めてしまったので、再読します。
文章構成天才。リズム感抜群。
投稿元:
レビューを見る
異様に面白かった。
ただ解釈を間違えば一瞬にして、下らない読み物と判断を下してしまうような繊細な著書。
神に依らない方法で世界観を建てる、ということが近代哲学の方法であり、デカルトがその始発点にいるのだが、
彼はこの書の中で神の存在証明を行っている。
神の存在が、私の正しい認識の前提になっていることを示す意図がある。
訳者自身この神は「哲学の神」だとは言うものの、神に依らないで建てる哲学に神が前提とされていることに十分理解が得られていないように思う。
認識に対する妥当性は何かとするデカルトの問題のためには、なにか基盤が必要であったのであり、そこに神が建てられている。それは別に「哲学の神」である必要はなく、認識を保証する神であればよい。むしろ、現代では神という名をつける必要はない。
この方法的懐疑と認識論、問題設定は、18世紀のカントへ受け継がれる。
投稿元:
レビューを見る
「方法序説」より格段わかりやすいと言われた意味がわかった。
原著はドイツ語だったから。それを知っていれば、こっちから読んだのに!と実に本を読むときには順番があると感じるこの頃(笑)
投稿元:
レビューを見る
[ 内容 ]
近代哲学の父にして偉大な数学・物理学者でもあったデカルトが、『方法序説』の刊行後、形而上学にかかわる思索のすべてを、より精密に本書で展開。
ここでは、一人称による六日間の省察という形式をとり、徹底した懐疑の積み重ねから、確実なる知識を探り、神の存在と心身の区別を証明しようとする。
この著作は、その後、今日まで連なる哲学と科学の流れの出発点となった。
初めて読むのに最適な哲学書として、かならず名前を挙げられる古典の新訳。
全デカルト・テキストとの関連を総覧できる註解と総索引を完備。
これ以上なく平明で精緻な解説を付した決定版。
[ 目次 ]
ソルボンヌ宛書簡
読者への序言
概要
第一省察
第二省察
第三省察
第四省察
第五省察
第六省察
諸根拠
[ 問題提起 ]
[ 結論 ]
[ コメント ]
[ 読了した日 ]
投稿元:
レビューを見る
デカルト(山田弘明訳)『省察』ちくま学芸文庫,2006年
1642年出版。6つの省察からなる。第一省察はすべてのものについて疑いうることを示す。有名な「最高の力と狡知をもった霊が、あらゆる努力を傾注して私を欺こうとしている」という「悪霊」の想定がある。第二省察は物より心のほうがよく知られることを論ずる。蜜蝋の例がでてくる。蜜蝋は温度によって変化し、味覚・嗅覚・視覚・触覚・聴覚のもとに感じられたものはみな変化する。第三省察は、私が考えているときは存在し、無ではないし、無にはできないことが指摘され、私には完全性の観念があることから、これは神から与えられなければありえないので、神は存在するとされる。表象的実在性とか形相的実在性とかの概念がやっかい。観念とは映像のごときものだという言い方もある。第四省察は人には知性と意志があり、知性は神が与えたものなので、これに従うかぎり誤らないが、自由意志を不正利用して知りもしないものに同意を与えると誤ってしまう。しかし、神が意志を与えたのは良き意図からだし、意志は不可分だから、神は誤謬の原因ではないことが指摘される。第五省察はすべての知識の確実性は神の存在に依存することが指摘されている。第六省察は精神は考えるもの、体は空間(延長)をもつものとして区分されることを述べる。
デカルトの『省察』は神の存在と魂の不滅を証明しているのであるが、これはマテオ・リッチが『天主実義』で証明するものと同じ対象である。リッチは中国人という本物の異教徒に説いたので、明快で分かりやすいが、デカルトはヨーロッパの知識人相手にやっているので、書き方が難しいし、よく分からんところがある。山田氏の訳注は細かくていい。とても敬服する努力であるが、関連するほかのテキストを注釈でつけるというのは、中国の古典学では「互注」という方法で珍しくないし、量が多くなるので、せいぜいノート程度である。これをまとめて、簡潔にシテ的確な注をつくってもらえたらと思う。
投稿元:
レビューを見る
総索引や解題、極めて充実した注釈、新しい時代の翻訳文で、極めて難解ではあるものの、だいぶ読みやすく、わかりやすい訳でした。三木先生の訳文は、読み解くのがすごく難しかったですが、こちらは、だいぶとっつきやすいです。といっても、取り上げているテーマ(形而上学。精神と身体の関係と神の存在)も、省察内容も難解なのですが。
投稿元:
レビューを見る
『方法序説』を読んでもよく解らなかったところ、一番知りたかったところが、デカルトの言葉で読むことができる。神の存在証明の詳細。デカルトにとって神とは。やはりデカルト的循環といわれても仕方がない気がしないでもない。また、論の大半はスコラ学の世界のもののような印象を受けた。
投稿元:
レビューを見る
方法序説よりは少し長いが、それでも130ページ程度だし、方法序説より厳密に書かれているのでかえって読みやすい。とはいえ、難しいのは難しい。
物事の真偽をいったん全て留保し、そこから疑いえない自分自信の精神を見出し、そして、自らの内にない観念の原因として神の存在を証明する。そこまではなんとかわからないなりにわかったんだけど、どのようにして物質的な実態を明晰に認識できるのかってところは正直ようわからんかった。
それから、デカルトが言及する神というのが、どうも非人格神ぽくて少し違和感があった。キリスト教(もう少し広くセム的一神教)は人格神が基本だけど、こういう非人格神的な取り扱いが当時のキリスト教社会の中でどう位置づけられてたのだろう。
哲学とか歴史とかの素養がないと、こういうの読むとき苦労するんだよな。
投稿元:
レビューを見る
デカルトの思考方法がよくみえる
でも、読んでてうんざりするタイプ
最終的に、方法序説でことたりる、もしくは、本書の解説がよくできてる
スコラ的な世界から新たな世界を立ち上げたのがデカルトなので、その方法論はやはりスコラ的な世界に思える
この一種のグダグダとも聞こえる論理の進め方とか
おぉ、と思うところもいっぱいある
省察でなんとなく背景を読みつつ、序説くらいに整理したもので十分なんじゃないかな
投稿元:
レビューを見る
ソシュールの言語学やメルロ=ポンティの理解を深めるため、近代哲学から学び直すという名目で読みました。結果良かったです。
特に第三省察の神の存在証明で使われた、観念の二義性である「表象的実在性/形相的実在性」は特に面白かったです。(この概念に詳細な言及はなされていなかったので、榮福真穂さんの口頭発表の文書を参考にしながら読みました。)
観念の「表象対象に依存した/表象対象とは無関係な」在り方、さらに観念の「多様性/画一性」というコインの裏表のような認識論ですが、これを批判的に発展させたものがソシュールの言語学や構造主義の哲学だと思いました。
デカルト哲学に通底している「精神と世界との接続」「知の確実性の獲得」という2つの根本的な動機において、この観念の二義性という概念は、重要な役割を担っていると思います。そしてそこから批判的に哲学や科学が発展していくと考えると、”近代哲学の祖”と呼ばれるのも納得できます。
古典ということもあり多少読みづらさはありましたが、プラトンの対話編のような文学性を感じることもでき、とても面白かったです。
投稿元:
レビューを見る
第三省察について。神の記載はキリスト教徒のデカルトだからこそ、実感があるのか。訳者である山田先生は「神」はキリスト教的ではないと解説されている。「神」とは考える自分に考えさせる者、システムなのか?
剣士でもあったデカルトならではの記載も多い。塚原卜伝の道歌「映るとも月も思はず映すとも水も思はぬ広沢の池」や、不動智神妙録「心こそ心迷わす心なれ 心にこころ 心許すな」を思わせる。
「神」についての第五省察を読んで、デカルトの言う「神」が、読者の思う「神」と同じとは限らないと分かった。読者を自分たらしめるために存在する者を、「神」とするなら、理解できる。
第六省察では、行き過ぎた懐疑を現実に戻す。
投稿元:
レビューを見る
悪意のある老獪な霊
【もし何か真なるものを認識することが私の力に及ばないにしても、断乎として偽なるものに同意しないように用心することは、私の力のうちにある。】
「そこで私は、真理の源泉たる最善の神ではなく、或る悪意のある、同時にこの上なく有力で老獪な霊が、私を欺くことに自己の全力を傾けたと仮定しよう。そして天、空気、地、色、形態、音、その他一切の外物は、この霊が私の信じ易い心に罠をかけた夢の幻影にほかならないと考えよう。また私自身は手も、眼も、肉も、血も、何等の感官も有しないもので、ただ間違って私はこのすべてを有すると思っているものと見よう。私は堅くこの省察に執着して踏み留まろう。そしてかようにして、もし何か真なるものを認識することが私の力に及ばないにしても、確かに次のことは私の力のうちにある。すなわち私は断乎として、偽なるものに同意しないように、またいかに有力で、いかに老獪であろうとも、この欺瞞者が何も私に押しつけ得ないように、用心するであろう。」