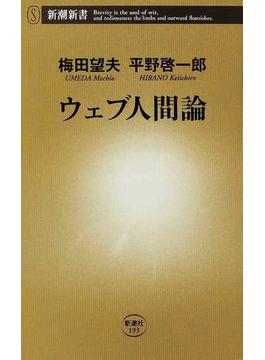「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
読割 50
紙の本
ウェブ人間論 (新潮新書)
「ウェブ進化」によって、世の中はどう変わりつつあるのか、そして人間そのものはどう変容していくのか。ビジネスとテクノロジーの世界に住む梅田望夫と、文学の世界に生きる平野啓一...
ウェブ人間論 (新潮新書)
ウェブ人間論
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
「ウェブ進化」によって、世の中はどう変わりつつあるのか、そして人間そのものはどう変容していくのか。ビジネスとテクノロジーの世界に住む梅田望夫と、文学の世界に生きる平野啓一郎が、その変化の本質と未来を徹底討論!【「TRC MARC」の商品解説】
著者紹介
梅田 望夫
- 略歴
- 〈梅田望夫〉1960年東京都生まれ。東京大学大学院情報科学科修士課程修了。(株)はてな取締役。
〈平野啓一郎〉1975年愛知県生まれ。京都大学法学部卒業。在学中に発表した「日蝕」で芥川賞を受賞。
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
ITの伝道師と芥川賞作家が出会った場所
2006/12/28 06:23
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:くにたち蟄居日記 - この投稿者のレビュー一覧を見る
まず 梅田望夫と平野啓一郎という二人が対談したという事実が興味深い。
シリコンバレーでITを主体とした実業家と 京都で中世欧州を舞台とした「日蝕」を書いた芥川賞作家の間の「距離」は いままでの常識で考えると 果てしないものがあるはずだ。つまり 出会うはずの無かったセグメントに属したお二人が 出会ってしまい かように刺激的な対談を行うようになったという点で 時代の変化を強く感じた。
二人の興味はネットという「新しい道具」を手にした「人間」にある。人間が道具を作ることは確かだが 作られた「道具」が逆に人間を変えていくことも歴史的な事実である。過去人間を変えてきた「道具」には色々あったと思う。「火」から始まり 「車」や「電話」など 人間の価値観自体を変えてきたような「道具」は 色々あった。
そんな「道具」の一つとして 「ネットがある」という点で 二人の意見は 一致している。それが この稀有な対談を可能にしたと思う。
一方ITを使った「実業家」が 「人間を考える」という点も興味深い。僕らが当初持っていたIT企業家といえば「ネットを使って さっと会社を設立、公開して巨額の個人試算を築く」という感じであった。それに対して 梅田氏の論点は そんな一種の拝金主義からはかけ離れた 極めて「思弁的」である。
これは梅田氏の個人的な資質と言ってしまえばそれまでだ。しかし ネットという人間を変える道具を使うに際して その「人間を見つめる」という視点が 実は 非常に重要なのだと強く感じた。
対談ゆえ 内容にはあっさりした印象はあるが 一方 きらめくようなヒントに彩られている本と言える。
紙の本
ウェブが人間を変えてしまうことはなさそうだ
2007/02/18 13:42
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:JOEL - この投稿者のレビュー一覧を見る
梅田望夫氏は『ウェブ進化論』(ちくま新書)で、ウェブ世界の本当の姿を分かりやすく描いて見せた。それは、シリコンバレーに長いあいだ在住し、なぜグーグルやアマゾンなどのウェブシステムが登場したのかを身をもって知っているいるからこそ著せた本であった。今回は、平野啓一郎氏という若き芥川賞作家との対談だというのだから、興味をそそられた。事前の予想は、ウェブ世界を手放しで信頼する梅田氏と、文学という伝統的世界から保守的な考えに立つ平野氏との火花を散らすような議論が展開されるだろうというものだった。
しなしながら、予想は良くも悪くも裏切られた。両氏の目線は相当程度共有されており、対立するような場面はなかった。むしろ、本の行く末についての議論に代表されるように、平野氏の方が、本はダウンロードして読むのが一般化するという変化を予感しているのに対し、梅田氏の方が紙の本の利点を強調し、本は変わりなく存続するという立場が逆転した場面さえあった。梅田氏は、ネット世界はもちろん、リアルな社会のことにも精通している。安直なネット社会礼賛ではない。これは、1960年生まれで、社会人としての基礎的トレーニングをリアルな社会で積んだ上で、シリコンバレーに移住したことによるものだろう。また、ブログなどによってネット世界でたくさん書き物をしつつ、新書で『ウェブ進化論』を出したことによる大きな反響が、リアルな社会の持つ力を感じ取ったことからも来るのだろう。
さて、本書の書名は『ウェブ人間論』とあり、簡単に言えばウェブ世界が人間のあり方も変えてしまうのかどうかを突き詰めて対談しようというものであろう。本書を総括すれば、それはどうやらなさそうだということだ。リアルな社会で、居心地のいい場所を見つけられない場合、ネット社会にそれを見つけ、島宇宙とでも言うべき空間に暮らすことを梅田氏は勧める。その主張からは、結局のところ生身の自分を保ったまま、もっと居心地のいい場所を逃避的に見つけることになり、社会はおろか自分自身さえ変えることがない。
対する平野氏は、ネット世界の島宇宙に暮らしてしまうと、リアルな社会での好ましくない動きを止められないのではないかという社会的な視点に立っている。この動きを止めるためにネットがどういう働きをなしうるのかという点にまで言及がないが、政治的・社会的な視座を失ってしまっては危ないという危機意識が見てとれる。
日本におけるインターネット元年は95年であるが、それから10年あまりが経過して何が起きただろうか。ネット上で簡単に買い物ができるようになったり、それまでは図書館に足を運んでかき集めていた情報がグーグルなどの検索エンジンで容易に集められるようになったという利便性の向上はあるが、それ以上のものはまだ生まれていないのではないか。本書にはイノベーションという言葉が何度も出てくるが、それはテクノロジーの領域に限定されており、レボリューションというような社会変革は何も起きていないというのが実際のところであろう。ましてや人間の認知の様式が変化したとまでは言えないだろうし、今後もないだろう。
人間は人に開示してみせることにできる表層的なレベルから、人には見せないが自分のなかにしまい込んである意識のレベル、自分でも把握できない無意識のレベルと、さまざまな層から構成されている。ウェブ世界の進化によって、影響を受けるのはせいぜい表層的なレベルにとどまり続けるだろうというのが、本書を読んだ感想だ。しかしながら、梅田氏はシリコンバレーに暮らす人間の息づかいを知らせてくれる。またオプティミズムに貫かれた姿勢が一服の清涼剤を与えてくれるのは間違いない。たとえ、表層的なレベルのイノベーションではあっても、ネット社会をよりよき方へ発展させてくれることを梅田氏に引き続き期待したいと思った。
紙の本
スケールの大きいウェブ論
2008/03/31 17:22
6人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:YOMUひと - この投稿者のレビュー一覧を見る
ポジティヴなウェブ論の旗手である梅田望夫と、京大在学中に芥川賞を獲った平野啓一郎という興味津々の対談である。
例によって梅田の発言は、ネットの世界の明るい面を牽引するものであるが、この対談で特に興味深かったのは、ネットによって社会の三層化が進展するという観測である。従来のエリート対大衆という社会の階層に加えて「クラスの上から五人、親戚という小さなコミュニティで一番敬意をもたれている人」といういわば中間層が浮上するというのである。確かに出版界やマスコミで発言できない一般人も、ネットでは自由に発信でき、内容によっては脚光を浴びることもありうるからであろう。このように私たちを力づけるのは梅田の面目躍如というところである。
また、グーグルを弁護して、「プログラムおたく的な性質と『スターウォーズ』に代表されるSFおたく的性質が結びつき、自分が何かすると世界が変わるという創造の喜びが基本」とこの人が言うと非常に説得力がある。しかし、現状はそうでもそれが永続する保証はなく、評者のグーグルへの警戒心は払拭されきれるものではないのであるが。
平野は、本来的な作家らしく、ウェブ世界の正負両面を正面から論じようという姿勢が感じられる。例えば、特に「公私の峻別」という言葉が「効率的な経済活動から、個人の思いとか思想だとかを排除」する理由づけとなっている現代日本において、ハンナ・アレントの所論を引用しながら、ウェブ社会が「人間が自分自身を表現するための新しい公的領域の出現」となる可能性を認める。
他方、「世界中のブログで使用されている言語の中で最も使用頻度が多いのは英語でなく日本語」という衝撃的な調査結果(紹介されたURLによって評者も確認)を披瀝する。その理由の一つとして、「日本では気楽な食事の場でも『場の空気を読む』という一種の抑圧が働くため、そこで言い残したことがブログにこぼれ落ちていってるんじゃないか」と分析する。これもさすがに鋭い指摘であろう。
残念ながら評者はまだ平野の作品を読んでいないが、この作家への関心をかきたてられた対談であった。
紙の本
紙上の異種格闘戦
2007/01/06 19:52
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:nanako17girls - この投稿者のレビュー一覧を見る
ITは単なるインフラである。そう、言い切ることがはっきり出来る。なぜなら、さまざまなひとが「IT論争」を繰り返しているのをみるとその感は強くなる。だれもがITが起こす変化について期待と不安を持っている。
この対談で平野はネットが人間のライフスタイル、価値観を劇的に変えると思っているようなふしがある。一方、梅田は「そんな心配はいりませんよ」となだめている(ように感じる)。そう、生活のあらゆることがネットで済ますことは出来ない。たとえば衛星放送によってリアルタイムで世界中の映像が流れたとしても、時差という根源的な問題があるかぎり、それは決定的な変化とはいえない。広大な金脈があったとしても、ひとりの人間が得られるものはすべてではない。自らの道を行ったりきたりするものだ。専門家は冷ややかともいえる視線を投げかける。「知の変化」がグーグルで行われていようとも、やはり、ひとりの人間が知ることが出来るのはごく限られたものだ。
この10年で、ネットは生活の必需品にまでなった。その使い方は「お好みで」というところなのかな?。個人的な本書の読みどころは2人のパーソナルなところである。あくまでオプティミズムな梅田と、真摯に物事を見極めようとする平野。とりあえず、内容よりもそちらが気になりました。