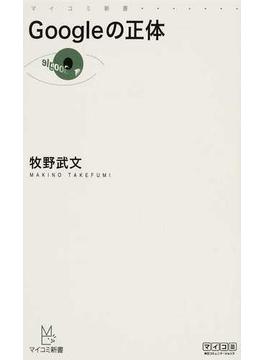「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
- カテゴリ:一般
- 発行年月:2010.1
- 出版社: 毎日コミュニケーションズ
- レーベル: マイコミ新書
- サイズ:18cm/212p
- 利用対象:一般
- ISBN:978-4-8399-3346-3
紙の本
Googleの正体 (マイコミ新書)
著者 牧野 武文 (著)
異例のスピードで企業規模を拡大させてきたGoogle。検索、ストリートビューなどを無料で提供し、その一挙手一投足に注目が集まっている。彼らは何がしたいのか。Googleの...
Googleの正体 (マイコミ新書)
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
異例のスピードで企業規模を拡大させてきたGoogle。検索、ストリートビューなどを無料で提供し、その一挙手一投足に注目が集まっている。彼らは何がしたいのか。Googleの正体を明かし、将来の姿を大胆に予測する。【「TRC MARC」の商品解説】
著者紹介
牧野 武文
- 略歴
- 〈牧野武文〉ITジャーナリスト。著書に「インターネット社会の幻想」「グラフはこう読む!悪魔の技法」「Macの知恵の実」など。
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
グーグルは何をしたいのか――これまでの企業とは大きく異なるグーグルの性格がよくわかる良書。ボリュームも値段もお手軽で、読みやすくわかりやすいが、内容は濃い。新書のお手本のような本。
2010/04/03 23:16
12人中、12人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:窓ぎわ猫 - この投稿者のレビュー一覧を見る
わたしがこの本を手にとったきっかけは、尊敬する、ある米国人作家が、グーグルブックを巡るグーグルと米作家組合との和解を批判して、同組合を脱退したというニュースに接したことだった。本と図書館をこよなく愛し、かつて「自由(liberty)とは図書館(library)のことだ」と書いた彼女が、インターネット上の無料図書館サービスのように見える「グーグルブック検索」を批判するのはなぜなのか、知りたくてたまらなかった。
本書『Googleの正体』は、わたしの疑問にしっかり答えてくれた。グーグルという企業の全貌――その特異性と重要性、そして潜在的な危険性が、ビジネスや経済にうといわたしにもよくわかるようにあざやかに描き出されていた。
まず、グーグルが、多くのサービスを無料で提供しつつ、急成長をとげているのはなぜなのか――その富が湧き出す仕組みが解き明かされる。グーグルの戦略が既存の企業の戦略とどのように異なり、グーグルがどのようにしてライバルを倒してきたかもわかる。
とくにグーグルとヤフーの比較は興味深い。「ヤフーはあくまでも、ポータルサイトであることを目指している。利用者が好みそうなコンテンツをできるだけ増やし、長時間ヤフーの内部にとどまってもらう。その間に広告を表示し、クリックしてもらおうという考え方だ。一方で、グーグルは検索をしたらさっさと外側にある別のサイトに飛んでいってもらってかまわない」「いわば、ヤフーは広告がちりばめられたディズニーランドで、グーグルはクーポン広告が置いてある街中のインフォメーションスタンドのようなものだ」(ともに93ページ)。
そういわれれば、この半年の間に、わたしのコンピュータのインターネット接続時に最初に出てくるサイトの設定は、にぎやかなヤフーのトップページから、そっけないグーグルの検索ページに変わっている。自分が無意識のうちにグーグルのビジネス戦略に沿った行動をとっていたことに気づいて、わたしは愕然とした。
後半の「第四章 成り立ちから読み解くグーグルの姿」では、グーグルの創始者たちの高い倫理性が評価されている。「悪事を働かなくてもお金は稼げる」というのが、グーグルのポリシーだそうだ。それは、徹底して利用者の側に立つことによって可能になる。「Google の使命は、世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにすることです」(本書161ページ。グーグルの会社概要の冒頭にある言葉だそうだ。)
一方、グーグルのあり方に危惧を抱く人々ももちろん多い。すでに多くの個人情報をためこみ、「当人以上に当人を知っている」存在になってしまっていることに対する本能的な恐怖。プライバシー、著作権など他者の権利を侵しているという問題。
グーグルは他者の権利について、事後承諾方式だ。「まずはサービスを始めてみて、問題点は後から考える」(183ページ)。権利を侵されたと思った側が文句を言わなくてはならない。
グーグルのこの強引なやり方に対する著者のまなざしは、割合好意的だ。「利益のためなら他人の権利さえ侵害することを厭わない」という20世紀型の邪悪さとは色合いの異なる、21世紀型の天真爛漫さを感じるという。
最終章である「第五章 グーグルと私たちの未来」では、すでに地球を覆うインフラになっているグーグルが「邪悪にならない」ままでいられる場合と「邪悪に変貌してしまう」場合の、ふたつのシナリオを考える。グーグルが高い理想に忠実なままであれば、世界は公平化に向かっていく(ただし、公平化は先進国にとっては貧困化である、という指摘があり、興味深い)。しかし、グーグルが「変節」すればどうなるか。「今のグーグルは、ビジネスと消費の間に立って互いの情報の流れを交通整理しているだけだが、情報の流れをグーグルが意図的に操作し始めたら、ビジネスも消費もグーグルを通してしか活動ができなくなる」(205ページ)
著者は、グーグルという独特な企業を分析し、評価した上で、その力の巨大さゆえに、監視し続けることが大切だと訴える。著者自身は、ややグーグルに好意的である感じはするが、その意見を読者に押しつけることはせず、公平な配慮のもとに、読者自身が考える材料を提供してくれる。
特筆すべきは文章のうまさだ。そのおかげで、読者は楽しみながら、学び、考えることができる。
現代に生きるすべての人におすすめしたい本だ。
紙の本
Googleが会社として成り立つ仕組みとは?明快な説明を通してインターネット社会を考えさせる。たとえが秀逸。
2010/06/17 17:15
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:銀の皿 - この投稿者のレビュー一覧を見る
検索でお世話にならない日はないかも、というぐらいのGoogle。でも、何の会社?といわれるとちょっと悩んでしまう。会社ならどうやって成り立っている?いろんな会社を買収しているけれどなにを目指している会社?中国でひともめしたりしてニュースにもなっているけれどなんで?普段気にしていないけれど考えたらよくわからない会社。
この本は、すっきりとこれらの「?」に答えてくれました。わりとざくざく読めてしまいましたが、インターネットを理解するためにも、よくまとまった良書になっていると思います。
「広告で儲けているんでしょ?」となんとなく思ってはいましたがその「アドワーズ広告」なるものの仕組みもわかりました。誰かが一回クリックしたときの報酬はほんの少しでも、世界中で「誰かが何かを」クリックする回数を集めたらすごい量になるわけなんですね。
だから、より多くクリックしてもらいたい。そのためにはインターネットをもっと普及させたい。だから・・・。
Googleの生い立ちや基本理念も書いてあり、Googleの仕組みが随分わかった気がします。
わかりやすいのは、著者が使うなかなかユニークな「たとえ」の力もあるでしょう。Yahooとの違いの説明で「Yahooはディズニーランド、Googleは割引クーポンがおいてあるスタンド」というのも、意図するものの違いを言い得ています。Googleはインフラ整備をして、道沿いの看板設置料はとるけれども自分でサービスエリアの店などは経営しない、というのも面白いたとえです。
話題となった「ストリートビュー」の問題の解決法についても著者の案ユニークでなかなか感心させられました。ああいう発想は日本人特有なのかもしれませんね。
ただし、Googleを「十字軍」に例えているのはどうでしょうか。まあ、自分たちが「良い」と思えばどんどん突き進む、という点は、確かにそうかもしれませんが。。。
普段気にしていないけれど考えたらよくわからない、でもないと困りそう。Googleに代表されるインターネットのシステムは、空気のような存在になりつつあるのかもしれません。電気や水道のように、インターネットは「ライフライン」になってしまうのでしょうか。だったらそれも少し怖い気がします。そんなことをいろいろと考えさせられました。
Googleから考え、これからのインターネット社会を捉えなおすことができるよい本に出会った気がします。
紙の本
私たちの問題としてGoogleを見つめる
2010/03/12 23:24
9人中、9人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:yukkiebeer - この投稿者のレビュー一覧を見る
新書という手ごろなサイズでありながら、Google設立の歴史やその狙い、無料サービスでありながら莫大な利益をあげるカラクリ、そしてGoogleが将来向かう先を最悪のシナリオと最善のシナリオを公平に併記していきます。
最善のシナリオは貧困国も含めてネットに廉価で誰でもアクセスできる社会の構築であり、最悪のシナリオはGoogleが個人情報を徹底把握することによって消費のすべてを独占するディストピアの現出。
Googleを手放しで持ち上げるでもなく、かといって不当に低く見積もることも著者はしません。それは一民間企業とはいえ、インターネットのあらゆる情報を確保したきらいのあるGoogle。生活インフラと化したGoogleを見つめるのは水道や道路といった旧来のインフラを見つめるのと同じことだと著者は考えるからです。Googleがどうなっていくかを考えるのは、まさに著者が訴えるように「私たちの未来を考えること」(209頁)でしょう。
10年前には考えらなかったネット行動が今後どういう変化を経て行くのか。他人事ではなく自分の課題として認識していくことを今一度教えられる気がする書です。