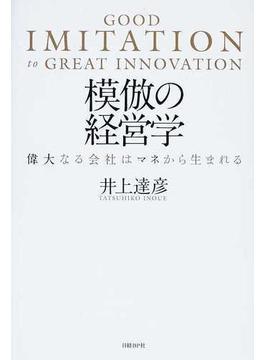紙の本
「学ぶとは真似ぶなり」とは、個人でも会社でも同じこと。模倣するための作法とは?
2012/04/04 15:49
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:サトケン - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、すぐれた会社はすぐれた模倣を行っていることについて書かれた一般向けの経営書である。クロネコヤマト、スターバックスとドトールコーヒー、J&J(ジョンソン&ジョンソン)、グラミン銀行などの具体的な事例をつかいながら、すぐれた会社が、何をどう模倣しているのか、あるいは反面教師として経営戦略をつくりあげたかを分析したものだ。
模倣というと上品な響きだが、英語でいえばイミテーション、本質的には真似(まね)と同じである。日本語では「学(まな)ぶとは真似(まね)ぶなり」という表現があるように、「模倣すなわち学習」のことである。子どもが大人を真似るように、何事もお手本となるモデルがなければ、独自性も創造性もあったものではない。いや、真似して自分のあったものを取捨選択して身につけることじたいが、じつはきわめてクリエイティブな行為なのだ。
模倣は基本的には個人レベルで行われるものであるが、会社レベルでも行われる。もちろん、会社を動かしているのは経営者や個々の従業員である以上、模倣のプロセスはそれほど簡単ではない。本書で行われているのは、基本的には経営戦略をつくって実行させる立場にある経営者レベルのものだ。著者は、本書において、経営者がみずから書いた本を材料にして事例分析を行っている。
本書は経営書ではあるが、経営者が書いたビジネス書などを読む際のガイドにもなっている。経営者が書いた回想録や経営書を読むことじたい、じつはビジネスパーソンにとっては、ある種のすぐれた模倣となるべきなのである。読者は、自分に必要なもの本から読み取って模倣するための手引としても活用すべきだろう。
マネジメント専門書を読むのはハードルが高いと、ためらっている若手ビジネスパーソンはぜひ手にとって通読してみるといいと思う。
投稿元:
レビューを見る
子供の頃よくマネするなと言われマネは悪と思われていた。本書では成功を模倣し、失敗から学ぶことについて述べられる。クロネコヤマト(吉野家が牛丼に絞ったように利益率の高い個人に絞る、JALのジャルパックのようなシステムのわかりやすいパッケージ化)、スターバックス(イタリアのカフェをアメリカで提供)などの企業は他企業(同じ分野とは限らない)の事例を模倣し、応用することで現在の事業を展開している。しかしながら、ただ単に模倣するだけでは第7章KUMONの事例でも明らかなように失敗に終わってしまう可能性もある。模倣には成功例から学ぶ・失敗から学ぶの2パターンあるが、失敗例から学ぶことのほうが効果が高いと証明されている。ゆえに、どんな事例からも学ぶ姿勢をもつことが重要である。今後に活かしたい。
投稿元:
レビューを見る
有名企業の経営戦略を「へーすごいね」で終わらせず、ちゃんと糧にするための考え方を説く本。余談だが、KUMONの公文公さんてすごい名前ですね。
投稿元:
レビューを見る
・業種を超えた共通性といのがイノベーションのきっかけになったりする。
・Position,Value,Activity,Resorce
*弊社の取材記事ものっているが、P-VARのValue部分がちょっと違う気もする。本来は、記載事項のその先の力を目指しているのでは?
投稿元:
レビューを見る
■模倣
1.模倣の方法は4つある。他社のビジネスモデルを真似る「単純模倣」、同業他社を悪い見本と見る「反面教師」、社内の既存ビジネスの模倣を考える「横展開」、事故の失敗と向き合い自信を反面教師とする「自己否定」
投稿元:
レビューを見る
【オリジナルを凌駕する模倣学の教科書】
すぐに真似されてしまう製品レベルでの模倣でなく、事業の「仕組みの模倣」を取り入れイノベーションを起こそうと言う趣旨
模倣の種類、ケーススタディ、具体的なフレームワークと活用方法など分かりやすくまとまっており、自社サービスで早速試したくなる展開
正転模倣(他から模倣する)
1.単純に持ち込み
海外や異業種から仕組み模倣するとしても、自社の領域で一番手となる事で新規性が生まれる
ex)サウスウエスト航空のLCCモデル
2.状況に合わせて作り替える
異なる世界に持ち込むときに生じる様々な問題を、自社に合うようにカスタムする事で新規性が生まれる
ex)日本市場に合わせた米国セブンイレブンとの違い
3.新しい発想を得る
成功している本質を自社に持ち込み、仕組みづくりを行なう事により、新規性を生み出す
ex)トヨタが得たスーパーマーケットからのヒント
※他にも模倣の種類が掲載されてます
P-VARと言うフレームワークでビジネスモデルを分析する
P:Position:競合・顧客
V:Value:提案価値
A:Activity:成長(投資)収益(改修)エンジン
R:Resource:経営資源
※複数企業のサンプルが掲載されてます
事業創造・変革の5ステップ(P-VARを用いて)
1.自社の現状分析
2.参照モデル選択
3.あるべき姿を描く
4.現状とのギャップを逆算
5.変革の実行
※ヤマト運輸を例に具体的に説明されてます
以上の様に、多くの成功企業が「仕組みの模倣」で成功してる要因分析と解説、具体的取り組み方についてまとめられた良書
P-VAR分析を日常の習慣として取り入れたと思う
投稿元:
レビューを見る
軽い気持ちで読んでみたけど、「模倣」は奥が深いことがよく分かった。
机上の空論ではなく、多くの実践及び成功体験について分かりやすく書かれていて、「創造的模倣」ができるような気になれた。
恐らく再読したくなるだろう。
投稿元:
レビューを見る
今日ご紹介する本は、今後の自分にとってのバイブルとなりそうな本です。
●ストーリーなきモデルは絵に描いた餅
今、日本で圧倒的な力を持っている偉大な企業の成り立ちなどを紐解きながら、なぜそのような競争優位を維持しているのかが、具体的に書かれています。
以前ベストセラーになった、楠木建氏著の「ストーリーとしての競争戦略」をかなり意識して書いているのではないかという点が多々あります。
本書のあとがきのところで井上氏は、はっきりとこう書いています。
「理想とするモデルが戦略立案に必要だという考え方は、ストーリーとしての競争戦略と対立するように見えるかもしれない。しかしその実は補完するものである。」
ストーリーとしての競争戦略は、戦略の立案におけるストーリーメイキングの重要性を示していますが、本書はモデルの重要性も強調しています。
「モデルなきストーリーは不安定であり、ストーリーなきモデルは絵に書いた餅になる。」
●仕組みを模倣する
実際に本書にも書かれているように日本を代表する企業も、必ずお手本にしたモデルがあり、その仕組みを模倣し、新しい価値を創造していきました。
本書の中では、トヨタ自動車、セブンイレブン、ヤマト運輸、スターバックスコーヒー、ドトールコーヒー、グラミン銀行、ライアンエア、KUMONなどを取り上げています。
本書では取り上げられていませんでしたが、かのアップルも模倣から新しいイノベーションを創造しました。
この本の中で一貫している著者の主張は、製品そのものを模倣するのではなく、仕組み(ビジネスモデル)を他業種、海外、過去、社内の他部署など、様々なところをお手本にして模倣し、新しい価値を創造するべきということです。
実際に製品レベルでの模倣は、インターネットの発達により、そのペースが早まったとされています。
模倣者がイノベーターを模倣するのに、19世紀だと、100年くらい、20世紀前半には10年くらいに、20世紀の最後には2年未満にまでに短縮されるようになったといいます。
ですから、技術的なイノベーションは、必ず追いつかれるということです。
本書にも書かれていますが、セブンイレブンが他社に追いつかれないのは、その流通の仕組みと季節や地域などの特性に合わせた各店舗からの発注の仕組みがなかなか真似ができないからなのです。
●創造のための模倣
井上氏は本書の最後をこう締めくくっています。
「ビジネスモデル発想における模倣は、単純な模倣にとどまるものではないし、競争戦略論における模倣戦略とも異なる。モデリングをベースにした学習戦略であり、創造のための模倣なのである。」
この一文に著者の伝えたいことが凝縮されています。
具体的にどのように模倣をしていけば良いのかというところを、ヤマト運輸の個人宅配事業の確立を例に上げながら、とてもわかりやく書かれています。
この��は、間違いなく私の今後のバイブルになりそうです。
会社を経営されている方、会社の中で新規事業を立ち上げようとされている方、これから起業しようとされている方には、必ず役に立つと思います。
ぜひ騙されたと思って読んでみてください。必ずどこかにヒントがあると思います。
投稿元:
レビューを見る
「学ぶことは真似ること」を解説した本ですが、
具体的な企業事例を多く掲載するなどの工夫で、
とても読みやすかったです。
・何故まねるのか?(WHY)
・何をまねるのか?(WHAT)
・どうやってまねるのか?(HOW)
など、模倣経営について、ポイントをついて
解説されています。
単純にモノマネするのではなく、概念的に理解
(モデリング)して、そこから学習したものを
自己の事業・業界に当てはめて再生成する。
この「創造のための模倣」という考え方には
共感します。
どのようなことであれ、少なからずヒトは他人
の振る舞いを参考にしながら生きています。
重要なのは、鵜呑みにせず、自分なりに解釈
して応用することですね。
この本の前半に、メタファー(隠喩)に関する
解説があります。語源はギリシャ語で、
メタ(Meta):〜を超えて
ファー(Phor):運ぶ、もって行く
という意味を含んでいるそうです。
うーん、深いなあ。。。
投稿元:
レビューを見る
競争戦略としての「模倣」の必要性について書かれた本。
社内と社外、成功と失敗とでマトリクスを作り、
それぞれの方向性について論理的に書かれており、
内容、著者の言わんとするとことは大変理解はしやすい。
しかし、事例として挙げられている企業が少なく、
その少ない事例から一般化しているが、汎用性にやや疑問を抱く。
どの企業も少なからずしているであろう模倣。
なかなか体系立てるのは難しいと感じた。
投稿元:
レビューを見る
早稲田大学社会人MBAの教授だけあって、大変面白い経営分析の本です。こういった本を教科書にしてMBAで議論したら本当に面白いと思います。
すべて私のアイデアですといえる経営者はいませんものね。
温故知新とはよくいったもので、他社のいいところを取り入れてよくしていく手法は昔からの常等です。VAR分析で自社を分析しながらの取り組みは、会社の幹部研修で使ってみようと思います。
投稿元:
レビューを見る
模倣のやり方にもいろいろあり、模範にするのか、反面教師にするのか、よく考えなければいけない。
第6章に「守破離モデリング」にあった、守破離という禅の考え方ベースに波及した学び方の作法・思想は常に頭に入れておきたいと思う。
守 → 師匠の教えを忠実に守る
破 → 次にあえてその教えを破る
離 → 最後に独自に発展させていく
投稿元:
レビューを見る
クリエイティブな発想や活動は模倣(イミテーション)から始まることがほんの根幹と感じました。筆者の言う「モデル」が本質的に何を指すのかが気になりました。
日本語の模倣が必ずしもimitationと同一ではないと感じました。まなぶはまねぶから来ているとも言われますが、真似ることがいいように思われていない実情がかなりあると思います。
投稿元:
レビューを見る
昨今、アナロジー思考やアイデアは既存の組み合わせという話しがよく書籍なりで話題に上がる事が多かったため、経営で具体的に模倣して成立している会社に興味があったので読んでみた。
模倣はクリエイティブであるというのが筆者の主張であり、具体的事例や模倣の要素まで取り上げられていたので興味深かった。
模倣の要素としては
・良い教師
・反面教師
という発想で、良い教師とは
・他業界で成功している企業
・海外で成功している企業
・過去の歴史や変遷
で、悪い教師というのは
・うまくいってない企業や業界、おかしな慣習
などである
良い教師の要素としては、アナロジー思考と同一の考えである。
また、模倣するレベル間でいうと、見た目や商品レベルではなく、仕組みを模倣する事が重要であると書かれてい。
これは、ストーリーとしての競争戦略と近しい内容であった。要は、見た目の模倣は簡単だが、うまくいっている企業は、模倣ができない何らかのストーリーがくまれているのでその本質が重要であり、そこを見抜けずに模倣するとほぼ失敗するという話しである。
ここは、公文の話しがおもしろかった。
ビジネスモデルの構築を考案する人は、アナロジー思考やストーリーとしての競争戦略と本書をセットで読むと理解が深まると思う。
投稿元:
レビューを見る
本質的に優れた経営は時代も業界も超えて伝承されて発展していくものである。Viva模倣!
経営学の本は過去の事例が沢山タイプか経営「学」のフレームワーク説明のようなものが多くてどれも同じ感じがするんですが、この本は良かった!
もー面白くて一気に読んでいしまいました。
ベストセラー?になった「ストーリーとしての競争戦略」も良かったですが匹敵する面白さです。
この本は優れた経営というのは業界を超えて模倣できるものであるとし、その模倣の事例や、模倣(モデリング)の手法について説明しています。
クロネコヤマトと吉野家、TSUTAYAと金融業界、トヨタとスーパーマーケット。異業種で一見なんの関連性もないような組み合わせですが、経営的に模倣、モデリングされている。うーん、なるほど。。。異業種から新しい発見をしてそれを自分の業界に組み込んでいってるんですねー。
成功の要因が何かを抽象化させて、モデル化して応用する、事例を通じてよくわかりました。
KUMONが模倣できそうでできない理由(仕組み)というのもなるほど。。
しかしこの仕組み自体は異業種では模倣できる可能性あり、ですね。
こういう模倣系は劇的なイノベーションはないかもしれないけれども、社内でも比較的取り入れやすいし、日本企業が取り入れやすい分野でもあると思うので、意識的に組み込んでいくと意外といけるかもしれないなー。希望がもててきたかも(笑)?
久々に面白い経営本でした、オススメ!