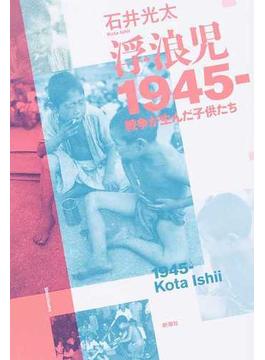紙の本
戦後の忘れもの
2016/05/12 22:51
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふさ - この投稿者のレビュー一覧を見る
昨年は戦後70年で、マスメディアでは「あの戦争」を振り返るニュースや企画があふれた。しかし、本書のテーマである浮浪児について、あまりにも語られないままで来たのはなぜだろうか。
あの戦争では、みんな大変な思いをしたのだ。肉親を失った奴も少なくない。だから、浮浪児がどうしたというのか。
昨年死亡した野坂昭如の代表作「火垂るの墓」の兄妹に涙しても、なぜか現実を生き抜いた浮浪児についてついぞ深い関心を寄せて来なかった私たち、いや私自身を本書はガツンと大きな一発を見舞ってくれた。
概要については本書の帯に任せたい。痛感したのは私たちはいまだに「戦後」を生きているということ。そして、強大な戦争の暴力を身をもって知る世代がいなくなる前に、誰でもいい、できるだけ身内の人に彼や彼女が経験した戦争と戦後の話に耳を傾けるべきだと思った。
投稿元:
レビューを見る
上野の地下道 浮浪児
朝鮮人ヤクザ 警察が手を出せない
東京露天商同業組合 警察がテキヤに組合を結成させ、闇市の治安維持の役割を担わせた
近藤マーケット
西武新宿線 都立家政駅 愛児の家 石綿さたよ
家庭の愛情でなくたっていいんです。友人や見ず知らずの大人からでもいいから、子供時代に多くの愛情をきちんと受けてきた記憶があるかということが大切なんですよ。そういう経験があるこそ、社員に愛情を注ぎながら引っ張ることができたりする。現在の虐待をうけた子どもだと、同じようにおおきくなってもなかなかそうはいきません。
子どもは家族から愛されたり、周りの人にめぐまれたいりすることによって初めてしっかりとした自我が生まれるものだ。人を愛し、自分を制御し、生きるということに向かって歩んで行ける
投稿元:
レビューを見る
<あの頃、上野の地下道にあふれかえっていた子どもたちはどこへ行ってしまったのか? >
1945年3月10日未明。東京大空襲が人々を襲った。家を焼かれ、家族とはぐれ、多くの子どもたちが街をさまよい歩いた。やがて敗戦。親を失い、浮浪児となった子どもたちは、上野駅に集まり、懸命に生き延びようとした。
これはそうした子どもたちの記録である。
著者は発展途上国のスラム街でストリートチルドレンを追っていたこともあり、戦後、浮浪児と呼ばれた子どもたちに関心を持っていた。
浮浪児たちはどういった経緯で例えば上野を住処とし、どのように生きる糧を得て、そしてどのようにその場を立ち去っていったのか。
伝手を辿り、100人近い証人から、5年の歳月を掛けて聞き取り、まとめたのが本書になる。雑誌『新潮45』の連載に加筆したものである。
太平洋戦争で生まれた戦争孤児は約12万人、浮浪児の数は推定3万5千人に上る。
浮浪児の実態についてはほとんど記録が残っておらず、まるで歴史から抹殺されたかのように、その暮らしぶりや行方については知られていなかった。
著者は丹念に証言を集めているが、戦後70年という歳月が経ったことを思えば、ほとんどぎりぎりの作業であっただろう。まずはその労力に敬意を表したい。
子どもたちが上野に集まったのにはいくつか理由がある。空襲直後に焼け残った主要駅は上野くらいしかなかったこと。地下道では雨風をよけることができ、たき火をする人もいて暖かかったこと。子どもに限らず、多くの人々が集まっていたため、何やかにやと食べ物や仕事にありつくことが可能であったこと。
不衛生ではあり、危険もあったが、子どもたちにとっては人の情けを受けることもあり、長じて「懐かしい」と感じるような場所ともなっていた。
上野駅の近くには、戦後、ヤミ市ができる。現在のアメ横の原型である。子どもたちはそうした店の手伝いをしたり、よそで仕入れた新聞を売ったり、靴磨きをしたりと、「したたか」に「がむしゃら」に生きていく。
もちろん、裏稼業に染まっていく子もいる。女の子(そもそも浮浪児の中で占める割合は低かったが)の場合は、手っ取り早く稼げる売春に手を染めた子も少なくない。
時には警察の「狩り込み」が行われ、浮浪児たちは根こそぎ連れて行かれて施設に送り込まれる。ところがこうした施設の多くは、虐待があったり、満足な食事もなく働かされたりと子どもたちにとっては決して暮らしやすい場所ではなかった。施設にうんざりして逃亡し、また上野に舞い戻った子も少なくない。
浮浪児たちの暮らしぶりに加え、アメ横成立の歴史や、当時の上野の森のいかがわしさ、また児童福祉法の施行、「篤志家」と言えるような善意の市民による養護施設の設立なども興味深い。
騒々しくて、不衛生で、猥雑で、しかしどこか懐かしい上野の喧噪。
戦後が遠くなるにつれ、上野から浮浪児たちの姿は消えてゆく。地下道から人々が追い出され、ヤミ市が取り締まられ、パンパンたちが検挙されるとともに、浮浪児たちは居場所を失った。
表の歴史にはほとんど���録も残されず、あるいは感化院に送られ、あるいは孤児院に入所し、あるいは個人的伝手で商店等に住み込みで働くようになる。
大人にとっても苛酷であっただろう終戦後の日々。親や家族の後ろ盾をなくした子どもたちは、懸命にがむしゃらに生きるしかなかった。ときには人の人情に助けられ、ときには人の汚さを直視し、ときには狡猾さも持ち、ときには仲間の子どもたちと助け合い。
努力して会社を興した者もいる。結婚して、配偶者にも過去を知らせぬままの者もいる。殺人犯となってしまった者もいる。闇に消え、どこにいったかわからぬ者もいる。
巻末の子どもたちの食事風景には胸を打たれる。
ひと言で総括できる本ではないが、こうした子どもたちがいたことを忘れてはならない、と思う。
投稿元:
レビューを見る
『新潮45』に2012年5月から13年6月まで連載されたノンフィクションで、当時リアルタイムで読んでいた。主に上野の地下通路を根城にして暮らしていた戦災孤児を扱っている。
3月10日の東京大空襲で親を亡くした孤児に加え、敗戦後疎開地から東京に戻ってきた学童年齢の子どもたちが、家族や親戚に引き取れた子と、不幸にも身寄りのない子に分けられ、すがる宛も住む家も失った子がたどり着いたのが上野を中心とした溜まり場だった。
当時、誰もが喰うや食わずの生活で、他人を思いやることなどできなかった。政府もマスコミも子供のことなどかまってはいられない。
子どもたちが自立しようにも、力もなければ宛もない。却ってパンパンと言われた女性たちが情けをかけて食べ物などを頒けてくれたという話もある。
寒さや飢えで死ぬものも多かった。そんな極限から生き延びて、施設に入ることができ、生き延びた人の体験も綴られている。
人生は誰にとっても過酷で、平等ではない。運命と言うにはあまりにも無惨である。
平和なときにこそ、このような最悪を想定して対策を立てておかねばならないが、誰もがオストリッチポリシーよろしく思考停止している。
「殷鑑遠からず」。げにウクライナ戦争の真っ最中である。
投稿元:
レビューを見る
私は大学生活時代、東京中野区の都立家政の街の共同住宅に下宿していたので、ひょっとするとここに掲載されている「愛児の家」の前を通り過ぎていたのかもしれない。戦災孤児の生活は、私たち戦後生まれの人々には想像を絶するものがあるでしょうが、私たちの親の世代も自身の戦争体験を多くを語ろうとしません。子供たちには聞かせたくない辛いものがあるのでしょう。いまの為政者こそ、戦争によって生み出された数々の悲劇に耳を傾けるべきでしょう。
投稿元:
レビューを見る
ノンフィクション作家の石井光太氏(1977年生)が、5年間の取材を通して、今迄ほとんど表沙汰にされていなかった戦後日本の闇を記しています。
本書は当時11歳で自ら命を絶った少年の遺書から始まります。
「死はただ一ツの人間らしい道を歩んだということのできる方法です〜(略)〜人間らしい心になることができて死ねるということを、幸福に思つて私は死んで行きます。」
東京大空襲から終戦を迎えた戦後の混乱の中、東京上野の地下道は親を亡くした、或いは生き別れになり浮浪児となってしまった子供たちでひしめき合っていた。
浮浪児たちは、テキヤ・ヤクザ・パンパンと呼ばれる人たちと関わり合いながら、人を信じ、人を頼り、時には人を欺きながらもたくましく生きていく。
「がむしゃら」に生きた彼(女)らは、その後どのような人生を送ったのか。当時の浮浪児たちの生き方を知ることで、今日の日本人に足りないであろう何かが見えてくる気がします。
投稿元:
レビューを見る
ぼくは、上野は比較的よく歩いている。この本に出てくる場所が現在のどのあたりのことなのか知りたくて、何度かGoogleMapを開いた。
上野駅周辺もずいぶんきれいになったのだと思うけど、地下道はやはりいまいちだし、上野広小路、松坂屋の地下あたりから京成上野までの地下道は、相変わらず浮浪者が多い。
このあたりの、ルノアールやベローチェでお茶を飲んでいると、いい年したおじいさんが2、3人で話しているのを見かけることが多い。ほかの町ではあまりない光景だ。
話している内容は、意外に仕事的なのことが多い。近くの中小企業の社長さん、またはご隠居さんなんだろう。
この本を読んで、そういうことが腑に落ちた気がする。
この本を読んで、その理由が少しわかったような気がした。
投稿元:
レビューを見る
子どものころ、浮浪児が上野動物園にゾウを呼んだ、という童話を愛読していた。「浮浪児」という表紙のワードにそれを思い出して購入。なかみはすごく現実的(といっても今では想像もできない世界だけど)
投稿元:
レビューを見る
終戦後、戦災孤児の数は12万人、うち3割近くが浮浪児、その多くが14歳以下の小中学生だったという調査があるそうだ(おそらく実数よりは少ないと思われる)。
中でも最も多く浮浪児が集まっていたとされる上野駅付近を調査の対象とし、5年ほどかけて丁寧に元浮浪児や施設関係者の取材を行い、『新潮45』に連載されたものを加筆修正してまとめたのが本書である。
前半は過酷な浮浪児たちの暮らしぶりが描かれている。終戦直後ということもあり、現代とはあまりに状況が違っていて今ひとつ現実の日本の話としてピンと来ず、そうだったんだな、という感じにしか思えなかったのだが、後半、現在の彼らや、実際に彼らを保護した孤児院の職員が登場すると、今この時代に実在する人物として一足飛びに過去と現在が結びつき、彼らの生き様が鮮やかに現実のものとして立ち現れて一気に引き込まれた。
戦争の悲惨さ云々といった当然の帰結よりもむしろ強く感じたのは、彼らの生き抜く強さ、人間としての強さだ。昭和の話とはおよそ信じられないほどの悲惨で過酷な状況を生きた子どもが、個々の事情こそ違えど、人として今も力強く生をつないでいる。
現在問題になっている被虐待児などは、生の安全が脅かされる環境で生きてきた。そういう意味で、当時の浮浪児たちと環境は似ていたはずだ。今の被虐待児が示す深刻な状況を思うと、なぜ浮浪児たちはそうならなかったのかと不思議でならなかった。
その思いに答えをくれたのが、当時私財をなげうって孤児たちを保護した石綿家の、現在80歳を超える三女、石綿裕さんだ。彼女がいみじくも語っていたのが、自分を支える人間の芯があった、ということだった。
親または周囲の大人などから愛情をかけられて幼少期を過ごしたうえでの浮浪だったから、彼らには自分を支える芯が出来上がっており、だからこそ極限の状態になりながらも、必死に命をつなぎ強く生きて行くことができたのだ、というものだ。
そう考えるとやはり、子どもを適切な時期に適切な環境で育てることがいかに大切かということに立ち戻っていく。
現代の児童福祉の面でも、非常に多くの示唆に富んでおり、反戦の思いのみならず、子どもの育ちというものを改めて考えさせられた著作であった。
投稿元:
レビューを見る
戦中戦後に荒野に投げ出された子供達はどこに行ったのか。
「がむしゃら」に生きていく子供達が描かれます。
石井氏はいつもストリートチルドレンであろうが
物乞いであろうが、憐れむ対象でなく、人格を持った対象として接する。今回は歴史という縦軸を描くので、多少の違和を覚えるものの、まなざしは一緒だ。
どんな状況だろうと人間は生きようとする。
それ自体は賞賛すべきものでも、唾棄すべきものでもないと思う。
ただ、戦中戦後だろうが自身の余裕の無さが他者への寛容を失わせる。
そのベーシックな部分に常に目を光らせたい。
投稿元:
レビューを見る
海外の貧困国を取り上げることが多かった著者。
その後テーマは東日本大震災に移行し、今回は浮浪時。
記録に残されていない70年前の日本のようすが、詳細な取材で明らかになっています。
戦争をしてはいけません。
投稿元:
レビューを見る
石井光太『浮浪児1945- 戦争が生んだ子供たち』新潮社、読了。起点の東京大空襲から平成までーー。先の戦争で家族を失い浮浪児となった子供たち。その実像を、記録記録やすでに高齢者となったかつての浮浪児百人以上の聞き取りから迫っていく力作 http://www.shinchosha.co.jp/book/305455/
「終戦から約七十年、日本の研究者やメディアは膨大な視点から戦争を取り上げてきたはずなのに、戦後間もない頃に闇市やパンパンとともに敗戦の象徴とされていた浮浪児に関する実態だけが、歴史から抹殺されたかのように空白のままだ」から本書は貴重なルポルタージュだ。
戦災孤児は約12万人、うち浮浪児は推定3万5千人(『朝日年鑑』1948)。上野駅の通路を住処にゴミをあさり闇市で盗んで食いついだ。警察の「刈り込み」による施設収容は、保護とは程遠い強制労働。幾重もの疎外の対象となった浮浪児こそ戦争最大の被害者といってよい。
45年年末までは、上野の浮浪児は戦災孤児中心で靴磨きや新聞売りが多数を占めたが、以後「ワル」が増加する。メディアの上野界隈に対する治安危惧の報道が、地方の不良少年たちを上野に吸い寄せたのだ。かくして“上野に行くも地獄、施設に行くも地獄”
46年、上野でパンパンが急増するが、RAA(特殊慰安施設協会)の廃止がその理由の1つという。RAAとは旧内務省が進駐軍のために作った慰安所のこと。エレノア・ルーズベルトの意向と性病率の高さからGHQは解散を要求。失職は上野へ誘うことになった。
「新日本女性に告ぐ!戦後処理の国家的緊急施設の一端として進駐軍慰安の大事業に参加する新日本女性の率先協力を求む!」
浮浪児と同じくパンパンも蔑まれたが、両者共に日本のご都合主義の「棄民」政策が作り出したもの。弱者は決して自己責任などではない。
極度の飢えと混乱。幼い子供がたった一人で生き抜いていくことは想像を絶する過酷さを伴う。本書は美化するでも蔑むでもなく淡々と描いていく。目の前で命を失う子供、あるいは自殺していく子供。誰もが浮浪児やパンパンを捨て駒としてあつかっていく。
浮浪児を取り巻く環境の変化は、46年に設立された孤児院「愛児の家」の登場だ。上野で見つけた浮浪児たちを連れ帰り、衣食住を提供し、就学や就労の世話をした。けんかやトラブルはつきないが、誰もが「ママさん」への信頼を今なお隠せない。
「僕自身が僕のことをわからない」--。
圧巻は、浮浪児たちの「六十余年の後」を追うくだり。バブルで大成功したあげくその崩壊を一人で引き受けた者、高度経済成長の陰と日向で苦闘した者。しかし、施設育ちは話せても、浮浪児だったことは話せない者が多い。
経済発展の連動でしばしば行われるのが町の「浄化作戦」。ひとはそのことで、ステージアップを夢想する。しかし社会構造が生み出した「浮浪児」を排除することが「浄化」なのだろうか。棄民で経済発展を錯覚する眼差しそのものを疑うほかない。
上野の地下道は、ペンキの塗り直しを重ねるが70年前のそのままだという。寝泊まりする人間は今もたえない。あの戦争は終わっ��いない、むしろその「余塵」と、みずから終わったのだと「ごまかそう」とする中で生きているのではないか、そう考えさせられた。
関連
【三省堂書店×WEBRONZA 神保町の匠】 『浮浪児1945――戦争が生んだ子供たち』 (石井光太 著)――忘れられた日本のストリートチルドレンからの貴重な証言
http://astand.asahi.com/magazine/wrculture/special/2014091900008.html
投稿元:
レビューを見る
戦後、親兄弟とはぐれたり死に別れたりした子供達。
浮浪児となり、がむしゃらに生きた姿を知る。
戦後の騒乱のなかで、健気に強かに生き抜く。
やはりまだまだ知らない事はたくさんある。
投稿元:
レビューを見る
今から65年前、浮浪児と呼ばれていた15歳の少年が、
路上で自殺を図った際に遺した遺書から、この本は始まる…
「母、母を求めて死んでいく。
現在の私には死よりほか、苦しみを救ってくれるものはございません。(中略)
悲しんで死んでいくのではありません。
母を求めて私の人間らしくなかった過去の生活と立派に縁を切って、
人間らしい心になる事が出来て死ねると言うことを、幸福におもって私は死んでいきます。
社会のみなさまどうか私の過去を許してください」
終戦直後、戦争孤児は約十二万人以上…
そのうち浮浪児の数は推定三万五千人、
多くが十四歳以下の小中学生を主とした子供とされている。
家を、家族を失い、一人になった子供たちは
這いつくばって生きなければならなかった。
スリ、物乞い、物売り、売春など…
それぞれのやり方で、彼らは生きた。
疲れ果て、心を病み、自ら死んでいく者もいれば、
垢まみれ、糞まみれになりながら生き続けた者もいた。
浮浪児だった者達の証言を通して、
壮絶な生と死の臭い、
差別や暴力の痛みが、
この本を閉じた後もなお、骨の中に沁みこんでくる。
今を生きる者として、
この事実を知るという意味と共に
再び歩きだしてゆきたいと思う。
必読。
投稿元:
レビューを見る
戦争の悲劇のまた新たな側面を知った。丁寧な取材と分かりやすい文章で、たくましくて哀しい浮浪児の実在が鮮やかに浮かび上がった。