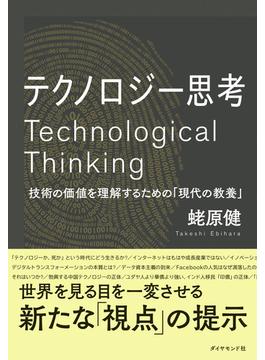投稿元:
レビューを見る
素晴らしい本だった!なにより基礎的な考え方から理論がまずあり、後半に向けてオンゴーイングな米中テック冷戦や、GDPRを巡る欧州 VS GAFAの今日的地政学のホットイシューに焦点がスライドしていく構成が気持ちよかった。
投稿元:
レビューを見る
圧倒的知識量
僕もテック系で働いているが知らなかったことだらけ
起業する前に読むべき本。
テクノロジー分野は寡占、飽和状態。オフラインが主戦場になるつつある。新たなイノベーションを生み出すのは参入障壁も増えさらに困難に
投稿元:
レビューを見る
素晴らしい良書。知識量、論理、現場感、どのアングルから見てもわかりやすい。
前半で言及されているアーバナイゼーション話
後半のインド、中国、米中の関係の話
物凄く重要かつ自分でも考察が必要
人にはあまり本は薦めないが、この本は確実に読む価値がある
投稿元:
レビューを見る
テクノロジーという切り口で、産業、政治、国際関係等の様々な分析を行っており、部分部分では理解もしくは感じていたことを一気通貫で纏めてあった読んでいて非常にすっきりした。すっきりすると同時に、自らも一つのストーリーをもって世界を理解し、行動することの重要性を再確認した。
・ソーシャルインパクトファンドとベンチャーキャピタルの交差点(P74)
・米国移民からインド人移民一世への歴史的パワーシフト(P139)
・フリップカートエフェクト(P157)
・「投資の目的地」から「世界の投資家」へ(P170)
・テクノロジー標準化戦争と国家安全保障(P200)
複数個所に、「そのような考えは非テクノロジー思考だ」との記述があったが、言い方にあまりいい気分がしなかった。
投稿元:
レビューを見る
テクノロジーで今の景況トレンドを捉えた一冊。難解な技術用語はないがIT系バスワードは満載なので、そのあたりの予備知識は必要。第6~7章の印中分析は非常に面白い。インド人CEOは多いが、IT極集中がさらに加速すると米国と伍する存在として中国とともにインドは並ぶかもしれない。そして今や核の代替としてITがポスト冷戦構造の武器として使われているのも興味深い。
冒頭は短絡的&断定的な見解が多く、それベースの三段論法が展開されるので無責任ブログにありがちな謂いっ放し感はやや強い。(例えばグーグルの数々のトライを長期視点を持たず「失敗例」として列挙したり)第3章の次のフロンティア分析(既にDX化した広告含め、医療、自動車)あたりから面白くなってくる。「テクノロジー思考」自体は本節とあまり関係ないのだが昨今のIT界隈のグローバルトレンドの変遷が分かる本である。
投稿元:
レビューを見る
現代を生きるにあたって知っておくべき内容が多い。
特に、米中インドのこれまでの発展とこれからについて。
残念なのは、著者の主張がなんなのかわからないこと。
一つの本につき一つくらいの大きな主張が強調されていないと読みづらい。
投稿元:
レビューを見る
## 感想
- テクノロジーそのものではなく、どのように世界や企業が動いているのかをテック面から考える、というアプローチの本。
- インドの話は印象的。数学に強い文化、ITならカーストを乗り越えられる、外に出ることに抵抗がない、みたいな色んな要素が今のインドを作っているという話。
## メモ
- テクノロジー思考=あらゆる事象にテクノロジーが関与している現代において、テクノロジーの影響度に焦点をおいた思考アプローチ。
- 2018年、スマホの出荷台数がゼロ成長に。インターネット産業は成長産業ではなくなった。次はインターネットの外がくる。
- 米国19年1月時点のスタートアップ時価総額はUber,Wework、Airbnb。どれも非インターネット。
- 外では、金融が真っ先に来たが、今はモビリティとヘルスケア。次いでバイオ・医療。
- 世界人口が地方から年経移動していることを都市化(アーバナイゼーション)という。
- 今は5割が都市にいる。7割にするまで40年かかる。しかしスマホは10年で40億人に行き渡る。つまり都市化をテクノロジーが抜く。
- GDPR、マルグレーテベスタエア。市場の独占、税金、個人データ保護、の3つを、GAFA等に突きつけているすごい人。
- インドめちゃめちゃ伸びてる。
- BPO先と思ってたらダメ。
投稿元:
レビューを見る
「テクノロジー思考」というタイトルだけど、どちらかというと「テクノロジーの世界地図と現代史」という印象でした。論旨がわからず途中から読み飛ばしてしまった。著者が投資家なのもあってか、投資や経済に関する教養がないとついていけない。あと全体的にサスペンス的な書き方なので、読んでいて不安になってくる。
とりあえず、テクノロジー(を持った企業や国家)がもたらす脅威と可能性をざっくり感じることはできたかな。じゃあ、明日からどうする?ということで言えば、最後にも書いてある通り「未来を予測する最善の方法は、それを発明することだ」というアランケイの言葉に集約されるだろう。
投稿元:
レビューを見る
基本的には資本が多ければ、研究費も多い。
都市に人が集まれば、市場は活発になり、資金の流動性も上がる。
インドと中国。
この二つの国は、今まさに資本が入り、都市に多くの人が流入している。
何も考えなくとも、普通に年月が流れれば、
成長しかない国だろうと感じた。
未来年表では2025年には東京の人口も減少していくという。
日本という国でも、地方というフロンティアに技術で橋がかけれれば、
もう一度世界と戦うことができると思った。
そしてもう一つの未来を考えてみる。
これまで地方から都市という移動だったかもしれない。
この事実を線形伸ばすだけで、
これからは国から国への移動がより活発になることが容易に想像できる。
さらに非線形で考えれば、
国の移動ではなく、
現実と仮想の空間を行き来するのも十分あるなと思った。
(以下抜粋)
○いまからたった60年前には、世界の人の7割が地方に住んでいた。
それが徐々に都市に流れて行き、2007年には都市人口と地方人口が均衡した。そして今後たかだが40年で、中国やインドやアフリカなども含めて全地球上の人の7割が都市に住む世界になる。(P.65)
○フェイスブックが解決している問題とは何か、それは端的に言うならば、豊かになった現代人類が世界共通にさいなまれる二大プロブレム、すなわち「暇」と「孤独」である。(P.228)
投稿元:
レビューを見る
社会や国際関係、歴史をテクノロジーという切り口から覗く本。新刊のため、直近のテクノロジー動向も把握できる。なぜ欧州がデータ保守主義に走っているか、なぜインドや中国がテクノロジー大国と化したがよく分かった。テクノロジーを学んでいるからこそ活きる。
ただ、タイトルから想像してたフワッとした概念的な話ではなく、具体的な話であり、真面目に読むには辛かった。
投稿元:
レビューを見る
スタートアップを含むテック業界を巡る現況、米中欧のパワーバランス、インドや中国などスタープレーヤーの環境について、と網羅的に幅広く記述されており、勉強になった。
スタートアップブームが生じている理由として、イノベーション至上主義(社会変化のスピード・インパクトよりも自らの変化が小さい場合は負けるというドグマ)と過剰流動性(金あまりにより機体収益が低いアセットクラスへ落ちてきたこと)が挙げられている。
リーマンショック後の10年間でスタートアップの企業評価額の中央値が5倍になっているという話は面白い。
一方で、本書は2019年8月に第1刷が出ているが、既に状況は変わり始めているように感じることが、この業界の展開の速さを如実に表しているように思う。
WeWorkに見られるようなスタートアップ企業への疑念、コロナウイルスを経て表面化してきたGDPRにおける個人情報の扱いに対する議論、など...。
ただし、本書は業界の地図を示しているだけではなく、こういった思考を持つことの必要性を説いている。
データに関する企業・国家の戦略、IoTプロダクツを利用した現実世界のIT化等、今後より一層重要性を増してくるのは間違いないので、引き続き勉強していきたい。
投稿元:
レビューを見る
テクノロジーの視点で世界の変化を考察した本
DXとは何か?なぜリアルやローカルに向かうのか?よく分かった。
加えて、中国やインドの成長の理由と今後のチャレンジも。
Written about transformation of the world from technology view.
I deeply understood what DX means and the reason why tech companies are targeting the real operation, local market.
In addtion, the reason why China and India acheived exponential growth and their next challenge too.
投稿元:
レビューを見る
「テクノロジー思考」とは、テクノロジーが支配的な立場として世界に強い影響力を与えている事実に焦点を当てた思考アプローチのこと。この本は筆者が普段実践しているテクノロジー思考を持って世界を眺めるプロセスをまとめたもの。
テクノロジーが世界に与えてきた影響、米国・欧州でのデータ資本主義に対する議論、インド・中国のテクノロジー革命とスタートアップ育成の動向がきれいにまとまっている。
・「イノベーションか、死か」、「テクノロジーか、死か」そういう時代を今、我々は否応なしに生きている
・イノベーション至上主義と過剰流動性によってスタートアップブーム、ユニコーンブームが生じた
・地方の都市化よりも早く、テクノロジーが地方に行き渡る。世界のテクノロジーリーダー達は、地方が都市化されるよりも前に、自ら地方に出向いて行ってその経済圏を獲得する競争(テクノロジーの地方革命)をしている。
・世界の優良企業はテック/ノンテックに関わらず、軒並みインドでR&Dとイノベーション探求に着手している。
・世界がグローバリズムとテクノロジーの二輪駆動で成り立つ現代社会において、マネジメントで最適化された人種はインド人。これは、インド移民の人的ネットワークとインドのテクノロジー教育によるもの。
・地理的意味において、米中印はその他の国とは別格。大国かつプライメイトシティを持たない国家というのは地球上でこの三大国の他にない。
・目的を持たないものを人はテクノロジーとは呼ばない。目的という抽象と、法則性と再現性を獲得した物質や物理現象という具体の融合こそがテクノロジー。
投稿元:
レビューを見る
目に見えないウイルスとの長い戦いに、近視眼的になっていた頭を冷やしてくれた感じ。外国はもちろん、自分の町からも、家からも出れず、とにかく内向きになってた視野が、少し広くなりました。
ブログ「新型コロナ自粛期間の読書一覧」
https://hana-87.jp/2020/06/02/jishuku/
投稿元:
レビューを見る
イノベーションの取り組むものは失敗を量産すべきである
失敗のコストが極小化している
ケンブリッジ・アナリティカ マイクロターゲティング
ヤンフィリップアルブレヒト GDPR 起案者
マルグレーテベスタエアー デンマーク デジタル規制分野
セブンシスターズ
元はギリシャ神話のプリアデスという7人姉妹
国際石油資本 ロイヤル・ダッチ・シェル、テキサコ、BP、シェブロン(ガルフ石油)、そしてスタンダードオイル
新セブンシスターズ GAFA microsoft アリババ テンセント
スタンダード・オイル 34に分割 そのごエクソン(NJ)とモービル(NY)となる
インドの印僑、中国の客家、ユダヤ人、アルメニア人をして四大移民
世界最大の電気自動車メーカはテスラでない、中国のBYDである
ドローン 深センのDJI
深セン ファーウェイ、ZTE OnePlus
アリババの城下町 杭州の猛攻
人間は具体と抽象により成り立つ
ビルゲイツ
我々はいつも、この先2年間に起きるであろう変化を過大評価しすぎる。そしてこの先10年間に起きる変化を過小評価しすぎる
ハイブサイクル理論
新しい技術が世に注目を浴びてから、社会に浸透するまでには、バブル的な過度な期待と、その後の失望を経てから、消えてなくなるものもあれば、着実な評価を得て社会に広く適応されていくものだ