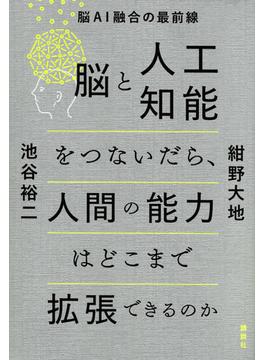紙の本
気軽に読み進めています
2022/04/23 14:40
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:tkm - この投稿者のレビュー一覧を見る
高名な池谷先生が著者の一人として名を連ねていらっしゃいます。先生の研究分野が脳とAIの融合だそうですが、本書は専門知識が必要な内容ではなさそうで、気軽に読んでいます。
紙の本
AIと最新の脳科学のコラボで実現できる世界に驚愕させられる!
2023/12/06 17:48
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:YK - この投稿者のレビュー一覧を見る
脳の研究で有名な池谷裕二氏による「池谷脳AI融合プロジェクト」に携わる池谷氏と紺野大地氏による著書で、テーマは脳とAIをリンクさせると、脳の機能がどこまで発展できる(可能性がある)か、というテーマについて述べた本。
会話中の脳の活動部位をMRIなどで調べ、その画像をAIに学習させると、MRI画像とAIをリンクすればリアルタイムにその人の話す内容が分かるようになったり、さらに発展して(口に出さずとも)頭の中で考えたことが、そのまま翻訳されて出力できるようになる可能性があるとの事。
一方、人工内耳、人工網膜と組み合わせて音や映像の電気信号を脳の聴覚や視覚をつかさどる部位に適切に入力できるようになれば、目や耳が不自由であっても”耳を介さずに脳で聞く”、”目を介さずに脳で見る”事の実現(いくつかの技術的ブレークスルーは必要ですが)も視野に入っているとか。いずれ嗅覚、味覚、触覚についても同じ進歩が達成されれば、部屋にいながら”海外旅行に行って、美しい景色を見て、素晴らしい音楽を聴いて、美味しい物を食べる”事がバーチャルに楽しめるようになるだろうとの事。ここまで来たら、映画「マトリックス」にあった、リアルな人間の人体は生理食塩水の様な液体の中で漂っているが、リアルな世界で生きているかのような世界を脳にインプットしているという世界観とほぼ同レベルですね。
現状のコンピューターの処理能力では無理であっても、その制約条件がなくなれば、「マトリックス」のような世界が十分に作り出せるというのには驚きを禁じえません。
障害を持つ方の社会参加であったり、地球環境への負荷を低減させたり(海外旅行をバーチャルでできてしまえば(それもリアルな体験との境目が分からないぐらいのレベルで)、もはや飛行機で移動する必要もなくなるし)と、社会に貢献できるインパクトは凄まじいという事は理解できます。
一方で、頭の中というのは究極のプライベート空間ですが、それさえもAIやコンピューターで読み取りが出来てしまうのならば、(心の中が明け透けになるわけですから)それをブロックするパスワードみたいなものも必要になるでしょう。この研究がもたらす果実の大きさは理解できるにしても、「そこまでやるかなぁ」と”ちょっとやり過ぎ感”を感じてしまったのは事実です。
本書の方向性としては、脳研究の最前線の可能性を広く伝えるということで、「こんなことも可能になります」という姿勢で一貫しているのですが、使い方を誤ると、こういう問題が出てくる、と言った部分にももう少し言及して欲しい気がしました。
投稿元:
レビューを見る
最近の動向がコンパクトに分かりやすく紹介されていることに加え、著者(紺野さん)の意見もすごく参考になります。
読んでて著者のワクワク感が感じ取れる一冊でした!
本文中に、「過去の偉人のデータを GPT‐ 3に学習させることで、あたかもその人が発言したかのような会話ができる」とありました。
人間の思考は学習によって変化しますが、圧倒的な速度で学習するGPT-3にも"思考の進化/変化"は見られるのか?という点が気になりました。
また、「脳のデータと人工知能を利用して精神疾患をこれまで以上に客観的に研究・診断・治療しよう」という点については、国内企業にも自然言語処理技術を活用した診断支援プログラムの開発を行なっている企業があり、基礎研究と産業の今後の発展が楽しみです。
投稿元:
レビューを見る
人間の脳の可能性について最新の脳科学とAI技術に基づきまとめられた本。
脳と人工知能の融合の過去、現在、未来のカテゴリーで分けられており、説明されている。
現在の状況だけでもとても驚いた内容であるのに、今後の未来は今まで想像した事の無い内容が盛りだくさんであり、非常に面白かった。
マトリックスの世界を思い出してしまったが、AIに乗っ取られる世界ではなく、人間の脳も進化(制限が取り除かれ)し、AIと協調できる世界になる事を切に望む。
投稿元:
レビューを見る
脳科学や人工知能、それらを掛け合わせた最新研究が豊富に紹介されている。
本文の執筆は基本的に紺野氏、共著の池谷氏はその師匠格だそう。
この紺野氏の書かれる文章の読みやすさが格別。「神経科学のファンを増やすことがライフワークのひとつ」とプロフィールで仰る通り、全く素人の自分でもするすると読むことができた。その氏が脳科学に興味を持つ切っ掛けになったという池谷氏の他書も、実に面白そうなタイトルばかりで、ぜひ読んでみたいと思った。
個人的に面白かったのは、本来は地磁気のセンサーを持たない動物でも電気信号を脳に送ると、脳がちゃんと新しい知覚を処理できるように対応するという研究結果。これは筆者らのラボにおけるネズミでの実験だそうだけど、極度の方向音痴である自分にとっては、真っ先に実用化されないかと心待ちにしている技術だ。(頭蓋骨パカッはまだちょっと怖いけど、首の皮を切ってセンサー埋め込むくらいなら全然やってもいい。)
読んで考えていたのは、タイトルである「人間の能力がどこまで拡張できるのか」について。上記の地磁気のような知覚の他にも、紫外線を見えるようになるとか、念じるだけで文章が書けるようになるとかの可能性が示唆されている。それらによって、今はまだ想像も出来ないことが、人間の身体で可能になるのかもしれない。
しかし現代の時点で既に、情報過多によるSNS疲れ、倍速視聴、ファスト動画、デジタルデトックスなどが話題になっている。「脳」がさらに情報量を増やしても対応できる高いポテンシャルを持っていたとしても、それとは別の?人間の心か何かが、追いつかないのではないかという考えも湧いた。それで、例えば逆に白黒しか見えないようにする技術とか、そういう知覚をデチューンするための技術発展もしそうな気がした。ゲームは1日1時間まで!とガミガミしてたオカンが、フルカラーで視るのは1日何時間まで!になるとか、ね。
モノで溢れた消費社会に反動が起きたように、情報量も増えるばかりが贅沢という考えに反動が起きるのではないだろうか。
投稿元:
レビューを見る
とても良い。タイトルに「人工知能」の入った一般書は基本的に読まない派だが、そういう人達にもぜひ読んでみてほしい。
平易で情報の伝わってくる文章で面白い研究や取り組みをたくさん紹介している。Neuralinkやノーベルチューリングチャレンジの動向を今後も追っていきたい。
最新情報や最新の研究が多く含まれており、神経科学とメタバースの融合について意見を述べる際FacebookがMetaに社名変更したことにまで言及されていることには驚いた。出版直前まで文章を推敲していたに違いない。
個人的に人間の認知とこれからの科学のあり方について考えされられた点が一番良かった。
「意識を持つとはどういう状態なのか」「意味を理解するとはどういうことなのか」の問いに紹介されたトノーニ先生の統合情報理論や北沢先生の主張は面白かった。なおここでこの理論が正しいかどうかは誰にも分からないよ、と一言添えている点に誠実さを感じた。
従来の科学は仮説検証と人間による理解を重んじており、自身も重んじて生きてきたけれど、潤沢な計算資源を用いて仮説を立てずして正解を導くことや人間には理解できない万物の方程式が生み出されることが現実的になってきた今、科学に対する姿勢や取り組み方は大きく変わっていくのだろうと未来に想いを馳せた。
投稿元:
レビューを見る
池谷裕二さん主導の研究テーマなので読んでみました。
脳とAI融合とは「脳と人工知能を接続する」ということですが、まだ初期段階で成果も乏しいし、法的・倫理的な問題もあります。
本書は人工知能開発状況の現状認識に役立ちました。
「人工知能」は「ヒトの脳」と優劣を競う時代から、「ヒトの脳」といかに共存するかという時代に突入しています。
最近は「AI家電」とか「AIで苦手を分析する教育」など、お気軽にAIを付けた商品が世間に溢れています。
ごく単純なプログラムをAIと言ってるようなものもあるので、AIが付くものは怪しいと思ってしまうようになりました。
「人工知能(AI)」とは何か。
松尾豊先生も「人工知能の定義は専門家の間でも定まっていない」と述べています。
世間では暗黙の了解として、
「人間が普段行うような活動や振る舞い、知的活動を人工的に再現する技術」
であれば、AIと呼んでもよいみたいです。
どのような技術をもってAIだと言っているのか、AIと接する時にはそこを確認しておく必要があると思います。
本書では「脳AI融合」の研究を紹介するのに先立ち、最先端の人工知能の具体例が示されています。
チェス、将棋、囲碁でAIが人間を超えたのは、既に何年も前のことです。
ここ数年では、自然言語処理分野について飛躍的な進歩があることを知ることができました。
Google翻訳も精度が向上しましたが、DeepL翻訳というさらに凄いレベルの人工知能ができており、誰もが使えるようになっています。
私も早速DeepL翻訳でCNNなどの海外の記事を読んでみましたが、かなりこなれた日本語に翻訳されました。(これは使えます。お試しあれ。)
GPT-3という文章作成の人工知能も衝撃的で、テーマを与えると専門家が書いたような記事が出来上がります。
DALL・Eは、テーマを与えると画像を作り出す人工知能ですが、これも有名画家が描いたような作品を作り上げます。
DALL・Eは固有名詞の認識には、GPT-3を使っているそうです。
「言語と画像と音声」の「認識と生成」技術の進歩はすさまじいので、人工知能が作ったフェイクニュースに騙されないよう注意が必要です。
脳と人工知能の融合研究では、
・考えていることを文書化する。
・夢を読み取る。
・目が見えなくなった人の視力を取り戻す。
などの実験で、希望が持てそうな成果が出始めていました。
現在、人工知能研究のツートップは米国と中国だそうです。
優秀な研究者を多く確保していることが大きいですが、大規模で超巨額な高性能コンピュータが必要です。
十分な予算を投入できない国や企業は取り残されるのが、人工知能研究の世界です。
発展著しい人工知能ですが、課題があります。
それは、「意味を理解していない」「人工知能に意識は宿るか」ということ。
人工知能は結局はコンピュータ上のプログラムに過ぎません。
このあたりの話題については他に面白そうな本があれば読んでみようかと思います。
本書で述べられていた内容ではないですが、最近AIの恩恵を大いに受けたものとしてコロナワクチンがあります。
通常10年かかるものが、短期間で開発できたのもAIの活用によるところが大きいそうです。
モデルナなどは、2010年設立の(市場で販売する製品は1つもなかった)ベンチャー企業だと知って、AIの有効活用がいかに重要であるかを感じました。
投稿元:
レビューを見る
オススメの一冊。
まず表題がすごい。脳と人工知能がつながる?
SFや空想の話ではない。東大教授と東大病院の医師の共著による冷静で現実的な本である。
医学や情報科学の指数関数的な進展でヒトはどうなるのか、シンギュラリティを迎えるのか。断片的なニュースに戸惑うばかりの私にとって、格好のガイドブックが見つかった。
脳と人工知能(AI)の融合について、過去、現在、未来の3つの章に分け、これまでの成果と現在の最先端の状況をわかりやすく整理し、未来予想図をビビットに示してくれる。
どのページの内容も濃密。敢えて要約すれば、爆発的に進化している脳研究の世界のことを、紺野先生の「纏括力と執筆力」で鮮やかに切りさばいてくれる格好のテキストとでも言えようか。
脳と人工知能の融合により実現しつつあるワクワクするような革新が簡潔にスピーディに語られつつも、専門家としての抑制の効いた誠実さを感じさせる文章なので安心して読み進むことができる。
落ち着いた筆致でありながら、情熱と躍動感に溢れていて、未知なる「知」に戯れる喜びがひしひしと伝わってくる。イラストや写真により多くのエピソードがわかりやすく紹介されているのもうれしい。
読後、神経科学や人工知能についての視界が一気に広がった。ニュースをフォローしていくための自分なりの視点、軸ができた気がする。よく耳にするメタバース(多次元の世界)やイーロン・マスクのNeuralink が、何だか身近な存在に思えてきた。
「進化しすぎた脳」の池谷先生が率いる、脳AI融合(!?)というすごい名称のプロジェクトがあるという。その研究室に東大病院医師の紺野先生が参画し、この共著が実現した。今後、このプロジェクトがどんな成果を上げるのか、楽しみだ。
紺野先生は、note やTwitterで最新のテーマを扱った情報発信をしている。podcast の「研エンの仲」では、「#35 老いというヒトの限界は克服できるは克服できるのか?」にゲスト出演していて生の声を聴くこともできる。
紺野先生は、数年後、いや数ヶ月後には、ものすごい有名人になっているような気がする。そんな予感を抱いた一冊だった。
投稿元:
レビューを見る
脳と人工知能をつないだら人間の能力はどこまで拡張できるのか
著作者:紺野大地
発行者:講談社
タイムライン
http://booklog.jp/timeline/users/collabo39698
脳AI融合の最前線
投稿元:
レビューを見る
脳科学・生物学と、人工知能が融合した本であり、小説調に「あと数年後にはこんな未来が待っている…」という、令和版2001年宇宙の旅のような本。
現在の最新研究から、もう少し先はこんな新技術が広まるだろうが過激に描かれており、楽しむどんどん読み進められる。
本屋・図書館によっては、医学書の棚に並べられており、非常にもったいないと言いたいくらい、皆にオススメする1冊。
投稿元:
レビューを見る
SFアニメなどで、視野の中にみているものの情報が直接表示されたりというようなアイデアがあったり、「ソードアートオンライン」に代表される脳に直接働きかけて疑似世界のなかに生きているようなゲームが描かれたりする。また「攻殻機動隊」ではネットワークの世界に意識をダイブさせたり、タチコマのように人工知能搭載した戦車が互いに通信して自分の得た情報を共有したり互いの情報をもとに議論する。挙げ句の果てはネットワークの中で生きる人格がでたりする。
本書では、そういった世界がサイエンスフィクションでなく、ノンフィクションになりつつある事が描かれている。先ずは脳とAI融合技術の過去・現在の事例が紹介され、そこから著者たちが取り組んでいる池谷脳AI融合プロジェクトの紹介を中心に「未来」がえがかれる。
〇脳情報の読み取りと情報の脳への直接的な書き込み
〇神経・精神疾患治療への応用
〇赤外線、紫外線、放射線、磁気などの画像情報による新しい知覚の獲得
さらに人工知能研究の進歩が描かれている。
ビックデータと人工知能を用いることで複雑な現象を直接モデル化することができる。しかしながらそこから導かれる知見の有効性は検証可能であるが、そこにいたるプロセスは人間には理解する事ができない可能性が高い。ディープラーニングによるブラックボックス問題といわれているものであろう。
本書で一番面白いと思ったテーマは、囲碁や将棋といったゲームで人工知能が人間を打ち負かす時代になってきているが、今話題の藤井聡太四冠が人工知能ソフトで自分の気づかなかった手や判断を示されることがあり、将棋の新しい可能性を拡げてくれるという主旨のことのいっている。人類と人工知能とが互いの強みを活かして、どちらか一方ではたどり着けないところまで行くことができる可能性があると言うこと。
『脳が人工知能とともに進化できれば、人間が持つ「脳の限界」自体がどんどんアップデートされていくかもしれません』単純に便利な人工知能をつくるのではなく、それによって自分たちの脳も限界をどんどん拡張させていく。脳科学恐るべしである。
投稿元:
レビューを見る
人は未知の技術開発に対しては「バラ色の未来」を夢想するものである。想定外の結末をもたらした原子力エネルギーの推進も、かつてはそのように捉えられていた。しかし、人間の生命や知性といった、私たちの根源的な存在に対する研究開発は、万人の人生を左右する絶大な影響を及ぼすものである。司法の場面で、裁判員制度が導入されているように、専門家だけでなく一般人も議論に参加できるようなしくみが必要ではないだろうか。
人工知能(AI)は私たちの知性を助けるものであるが、それ自体は人間の支配下にあるべきである。AIを論じるなかで決定的に欠けているのは、私たちが「こころをもっている」という視点である。AIは便利な道具であるが、私たちの大切なこころがAIに支配されるようなことがあってはならない。また、AIにこころを与えてはならない。制御不能となって暴走するからである。
AIという道具が役立つものとなるか凶器になるかは、それを操る人間次第である。いつの世も新しい発明や知見は、その利点や長所に目を奪われがちであるが、その使い方を誤ると取り返しのつかないこととなる。しかし多くの人は、それがもたらす想定外の事故や事件、犯罪被害や習慣的依存による中毒症などのような恐ろしいことがらに対しては、目を背けようとする。
脳がAIに接続された場合、最も恐ろしいのはハッカーによるウイルス攻撃によって脳が破壊されることである。ほかにも、悪意のある人物が意図的に人々の思考回路を操作したり、特定の思想に洗脳したりする恐れも十分に考えられる。
いっぽう、人々の能力はAIの接続の有無によってどのように区分けされるのだろうか。教育機関の入学試験や資格試験、各種検定などにおいては、知識や情報、処理能力が問われるが、AIへの接続によって本人の努力とは無関係に資質を判定されるのだろうか。
人間は、想定外のできごとに出会いながら成長を続けていくものであるが、教育のあり方も大きく変化してしまうかもしれない。知識や技術の習得がAIへのアクセスによって手っ取り早くできるとすれば、あらゆる人間的な努力が無駄なことと一笑されることになるのだろう。SFの世界だけであった「機械人間」が誕生するのだろうか。
AIの接続によって優位に立った人たちが、自分たち以外の人を蔑視したり支配しようとすることはありうる。社会に新たな偏見と分断がそびえたち、ますます世知辛く生きづらい世の中になるであろう。
技術の急激な進歩には、必ず危険がつきまとう。AIの暴走によって私たち人間が支配されることがないように、想定外の危険を常に意識しながら開発されることをただ祈るのみである。
投稿元:
レビューを見る
なんと長いタイトル。もちろん、池谷先生の名前があったから買って読んだ。本書の最初の方に出てくる「未来予想図」をツイッターで読んだときは、これは「トンデモ本」ではないかと思った。でも、池谷先生がそんなものに名前を連ねるはずはない、そう思って、目次とか「はじめに」とかを確かめて注文し、次の日から読み始めた。なんとまあ、この30歳の著者は楽天的なのか。著者自身が「おわりに」でもそう書いているから、まあ良しとしておこう。で、まあおもしろい。そんなことができるようになってきているのか、の連続。僕の記憶では、安部公房が「第四間氷期」で1人の人間の脳をすべてコンピュータにコピーしたのだったと思う。60年以上前のことだ。それから、筒井康隆が「パプリカ」で夢の中に入っていった。おもしろいこと考えるなあと思っていたけれど、それがいよいよ現実になる? しかし、それは何のため? 何らかの病気の治療のためならあり得るとは思う。ただ、単なる人間の欲望のためというなら、しっぺ返しがこわい。北野さんとかが取り組んでいるという人工知能にノーベル賞を取らせるという話、GPT―3の方が先に文学賞を取るのではないかという話、興味深い。AIが見つけてきた理論を人間が理解できないという話、四色問題がちゃんと証明になっていないとか言われるのと近いのだろうか。まあ、いずれにせよ、技術の進歩でできることは増えていく。そのときに、どこまで進めるのか、科学の倫理については同時並行で研究を進めて欲しいものだ。ところで、教え子の一人が大学入学前にたずねて来てくれたときに、池谷先生のブルーバックスを紹介していた。それから10年近くたって、FBを通してその生徒(もう大人の女性だったが)が東大の大学院でニューロサイエンスの研究をしているということを知った。連絡をしてみると、「あのとき紹介してもらった本があって今の自分がある」というようなことを言ってくれた。うれしい限りである。研究室は池谷先生のとなりっだたそうだけれど。
投稿元:
レビューを見る
脳研究、人工知能研究いずれも近年急速に進歩している分野であるが、両者を組み合わせたならばどれほどのことができるのか、最先端の興味深い事例が多数紹介される。
イーロン・マスク率いるNeuralinkの取組では、アカデミアとインダストリーの繋がりにより短期間で驚異的なブレイクスルーが実現されているが、豊富な資金力と高性能のコンピュータを擁する者の強みが実感される。(治療目的ではあるが、脳に電極を埋め込んだりと、SFに現実が近づいている感がした。)
著者は、東京大学「池谷脳AI融合プロジェクトに所属しているが、同プロジェクトでは、脳の未知なる能力をAIを用いて開拓することで、脳の潜在性の臨界点を探ることを目的として研究が行われている。
倫理的な問題には十分配慮して研究は行われているようだが、こうした取組の先にある"未来"はどのようなものとなるのか、各人の人間観、世界観を問われそうだ。
投稿元:
レビューを見る
科学の持つ可能性、明るい未来を描いた作品は久々なように思う。
題名の通りの内容。まさかここまでの可能性があるとは。AIが広がれば人間の仕事は取って代わられ無駄な存在になるようなある意味暗いイメージを持っていた。あくまで人間VS人工知能。
それが本書ではAIを人間の能力を拡張するために用いるという研究。しかも脳に電極、超音波などを用いて直接にやり取りするというまさに夢のような話。
技術の進歩を考えると本当に実現する日は案外近いのかもしれない。
科学そして人間の未来に久々に明るい作品に出会った。