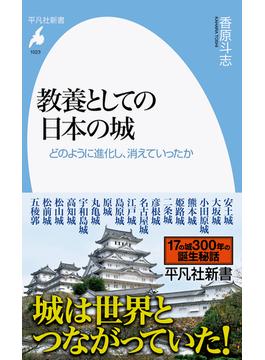「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
読割 50
紙の本
教養としての日本の城 どのように進化し、消えていったか (平凡社新書)
著者 香原 斗志 (著)
熊本城の石垣に見る鮮やかな技術の進歩、摩訶不思議な「つぎはぎ」の城・大坂城、京都に鎮座する「西洋風」の城郭・二条城の謎…。安土城から五稜郭まで、17の城の誕生秘話を世界史...
教養としての日本の城 どのように進化し、消えていったか (平凡社新書)
教養としての日本の城
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
熊本城の石垣に見る鮮やかな技術の進歩、摩訶不思議な「つぎはぎ」の城・大坂城、京都に鎮座する「西洋風」の城郭・二条城の謎…。安土城から五稜郭まで、17の城の誕生秘話を世界史の中で読み解き、新たな視座で捉え直す。【「TRC MARC」の商品解説】
高くそびえる天守、水をたたえた堀、堅固な石垣……。戦国時代に生まれた築城技術は、西洋の影響も受け、江戸時代初期までめざましく進歩し続けた。しかし一国一城令や鎖国により、状況は一変する。城郭様式は国内で独自の発展を遂げるようになるが、それは城という文化の衰退の始まりでもあった。世界とつながる城の魅力を写真多数で紹介。
《目次》
第1章 安土城
奇想天外な高層建築が突如誕生した理由
第2章 大坂城
秀吉の城を埋めて破格のスケールに 不思議な復興天守の理解のしかた
第3章 小田原城
北条時代はヨーロッパ流城塞都市 江戸時代は災害のデパート
第4章 熊本城
日本一美しく壮大な石垣には世界からの影響が
第5章 姫路城
世界が認めた屈指の名城がこれほど美しい隠された理由
第6章 二条城
天皇に徳川の権勢を示す城にこれだけ見つかる西洋の痕跡
第7章 彦根城
古城から建物を寄せ集める欧米では不可能な日本の早業
第8章 名古屋城
復元された本丸御殿の金碧障壁画に見えるもの
第9章 江戸城
焼けても同じプランで建てつづけた日本の特殊事情
第10章 島原城と原城
世界に開かれた窓を閉ざす契機となった島原の乱の舞台
第11章 丸亀城、宇和島城、高知城、松山城
鎖国下に建てられた進化が止まった天守たち
第12章 松前城と五稜郭
幕末に設計された最新の城が役に立たなかった理由
《著者プロフィール》
香原斗志(かはら とし)
歴史評論家、音楽評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。執筆対象は主として日本中世史、近世史。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』(平凡社新書)。ヨーロッパの音楽、美術、建築にも精通し、オペラをはじめとするクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリアを旅する会話』(三修社)、『イタリア・オペラを疑え!』(アルテスパブリッシング)など。
【商品解説】
姫路城、江戸城、熊本城……なぜ日本の城は豊かな発展を遂げ、消えたのか。16の城を世界史の中で読み解き、新たな視座でとらえ直す【本の内容】
目次
- 第1章 安土城
- 奇想天外な高層建築が突如誕生した理由
- 第2章 大坂城
- 秀吉の城を埋めて破格のスケールに 不思議な復興天守の理解のしかた
- 第3章 小田原城
- 北条時代はヨーロッパ流城塞都市 江戸時代は災害のデパート
- 第4章 熊本城
著者紹介
香原 斗志
- 略歴
- 〈香原斗志〉神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。歴史評論家、音楽評論家。著書に「イタリア・オペラを疑え!」など。
関連キーワード
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
城は日本の文化の縮図
2023/08/20 21:53
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:つばめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書はファッション&ライフスタイル誌『GQ Japan』に連載の「世界とつながっている日本の城」を大幅に修正・加筆した新書であり、安土城、大阪城など17の城について、その誕生から消滅までの歴史的背景や石垣、建造物の構造などについて写真と解説で、理解しやすい構成となっている。総石垣で築かれた日本初の城は信長の安土城、その後、大阪夏の陣あたりまで築城ラッシュ。城を築くための技術は短期間に飛躍的に進歩、海外まで包含する広い視野をもち、役立つものや魅力あるものは積極的に導入、進取の気性にあふれていた。だが、徳川時代の鎖国政策で、城の進化はぴたりと止まってしまった。城は日本の歴史や文化を理解するための鏡、城を軸に歴史や文化を広く俯瞰してほしいというのが、著者の執筆動機のようである。各章末には、その城に対する含蓄のある著者の考察があり、これが一般の案内書との違いを際立たせている。以下に、幕末の1854年に再建された松山城についての考察を一部抜粋する。<江戸初期の建築だといわれても違和感がない。それは二百数十年間にわたる、異次元の停滞を象徴している。…鎖国と開国は極端でバランスを失しているという点で紙一重である。松山城天守は美しい。だが、それは極限まで達した停滞が打ち破られようとする目前に開いた、洗練されたあだ花の美しさだといえよう。>本書でとりあげられた17の城以外にも松本城、犬山城、丸岡城など取り上げてほしい城はまだ、日本には数多くある。続編を期待したい。
一点、気になったのは、熊本城に関する次の解説である。「2016年の巨大地震でも築城当初の石垣は大きな被害がなかった。崩壊した石垣の大半は、少なくとも一度修理された箇所である」と、当初の石垣の頑丈さを強調している。築城当初の石垣が過去に変状(崩壊?)したから修理したのでは、なかろうか?