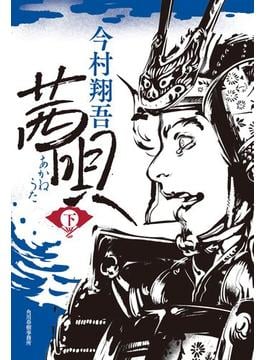紙の本
平家を語り継もの
2023/03/28 08:02
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:nekodanshaku - この投稿者のレビュー一覧を見る
平家滅亡の過程を語り、平家物語成立の謎を語り、「歴史とは勝者が紡ぐもの」という言説に逆らう語り物。平清盛最愛の子・知盛の生涯を通じて、感動的に感動的に描かれる。時代を動かし、次の時代を生み出したのは、多くの敗れ去りし者たちがおり、その隙間から生きのびたものがあり、それぞれの物語が残った。その幾筋もの物語が感動的に語られるべきものである。そしてその一つが、平家物語という語り物として口伝えされ残ったのだろう。最後の2章には鳥肌が立った。
電子書籍
今村版『平家物語』
2023/03/17 17:50
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:くみみ - この投稿者のレビュー一覧を見る
平清盛最愛の子・知盛視点で紡がれる、戦がもたらす景色が導く未来を示した、強くて脆い『平家物語』今村版、下巻。
穏やかなシーンも多かった上巻から激動の下巻。
人気武将・源義経との「源平合戦」がメインで、入り乱れてわかり難くなる斬り合いもリズミカルで、気象を使った緻密な作戦と、心情描写が加わり一層惹き付けられた。現代から見ると原始的に見えるけど、この時代では抜きん出ていて、ある種のハイブリッド戦争だったんだろうなと偶感した。
歴史は勝者が作る――『平家物語』が遺してくれた想いを受け取れていない今の世界へ、改めて突き付けられた生命の唄。
知章と敦盛のエピソードもあって、平家オタの方は必見です!
地図と系図があると尚わかり易くて良かったので、文庫化の際は宜しくお願いします。
今村先生が描くと、ここまで離れた歴史物語も、手が届きそうな親近感を錯覚する。
投稿元:
レビューを見る
歴史の授業では誰が何をして平家滅亡とかだったはずだが、この茜唄は平家の家族の物語で感動作です。
名前の読み方?が難しいかなと思いましたがそんな事もなく読みやすく面白かったです。
投稿元:
レビューを見る
久しぶりに読んでいて面白いと思った本。
1000年前が実際にどんな世の中で、平氏と源氏が何を思って戦ったのかなんて私たちには分からない。
今まで受け継がれてきている平家物語がどこまで事実なのかも分からない。
それでも、大切な人を守るがために戦った人たちがいたことは事実なのだろうな。
こんなストーリーが実際にあったらいいなと思った本。
1000年後の私たちにまで届いてるよと知盛に伝えたい気持ちが溢れた。
投稿元:
レビューを見る
平家物語がなぜ編まれたのかを、源平の戦いを追いながらドラマチックな物語に仕上げている。平家物語に描かれている戦いも、具体的な戦略にまで落とし込んで描いていて、強引に感じる部分はあるものの、物語としての合戦でなく、実際にあった戦いとして読めるのは新鮮だ。後半フィーチャーされる義経のキャラはあの大河の義経とかなり被るので、よりイメージしやすくなっていると思う。
投稿元:
レビューを見る
「祇園精舎の鐘の音・・・」
日本人なら誰もが知ってこのフレーズ。自分も多分に漏れず、学校で暗記した記憶がある。
またなんとなくの意味を知っている程度のものだった。
しかし「茜唄」を読了後、このフレーズが生き生きと色を帯び、そこに込められた多くの人間の思いが凝縮して、景色が見えるように変わった。
平家物語がこんなに面白い歴史物語だとは微塵にも思っていなかった。もっと深くこの歴史を知りたいと強く心を揺さぶられた。
著者の今村翔吾先生に感謝したい。
投稿元:
レビューを見る
文学書評
読書レベル 中級
ボリューム 366頁
ストーリー ★★★★★★!
読みやすさ ★★★
ハマリ度 ★★★★★★!
世界観 ★★★★★
知識・教養 ★★★★★
読後の余韻 ★★★★★★!
一言感想:歴史小説が好きな人、平家物語が好き(興味がある)人、『美しき平家』が知りたい人にオススメの作品です。
“この茜唄で詠まれた『平家物語』が一番好きになりました”
『今村翔吾氏』が描く『平家物語』のストーリー描写にはあらためて感服しました。特に【壇ノ浦の戦い】を舞台とした源義経と弁慶の描き方、平知盛と教経の描き方、源頼朝の描き方、そして大命題である『平家物語』誕生の解釈に心を惹きつけられました。
投稿元:
レビューを見る
屋島の戦、壇ノ浦の戦等々源平合戦の総てが目に浮かびそして知盛の心の内が心に沁みてくるそして最終章での希子の語らいそれに悔しがる頼朝、感動の連続だった。
投稿元:
レビューを見る
上下合わせての感想
面白い
さすがや
終わり方も良かったな
ひょっとしたら、こんな物語があったのかも
と思わせる今村節は健在
平家側の視点は新鮮で面白かったけど、
少年の心をもつ俺は
やっぱり
義経視点の痛快な英雄譚の方が好きなんだよな
ということで、
今回は今村作品に甘い俺も★5でなく★4
投稿元:
レビューを見る
後半のなんと切ないことか。
詠み人知れずの平家物語だが、まさに知盛が千年後の人々に伝えているようにしか思えなくなってしまう。
もし平家物語が編まれなかったならば、どのような史実が語り伝えられたのだろう。
一人の口伝が今なお残る平家の思いの強さが感じられる。
投稿元:
レビューを見る
楽しみにしていた今村さんの新刊。平家物語がなぜ編纂されたのか、最後の方で平知盛が平家物語を託した人物がわかったときに、感動した。壇之浦の戦いの真実も、悲しいけれど、清々しい気持ちにもなった。平家物語の時代に生きた人たちが、物語の中で生き生きとしていて、現代にまで語り継がれていることが、すごくかっこよく、おもしろかった!
投稿元:
レビューを見る
読書記録 2023.4
#茜唄 (下)
#今村翔吾
下巻では義経との戦いが苛烈を極める。
平家の男たちは次々と死出の旅へ。
哀しい結末だけど、美しく、爽やか。
源氏をも切り裂く夫婦の愛。
800年余りにわたって、平家物語が語り継がれる理由の一端を、教えてもらった気がしたよ。
#読書好きな人と繋がりたい
#読了
#平家物語
投稿元:
レビューを見る
昨年放送された アニメーション
平家物語でも とても魅力的に描かれた平知盛
彼を主人公に平家を語る
しかも 「じんかん」「塞王の楯」などの胸熱作品を世に送る今村翔吾さんが それを語る!
上巻は 助走といった感じ
溜めて 溜めて...
下巻では それらが 弾けていく
史実は既にあり 変えられないことを知っていても それでも 願いながら 祈りながら読み進める
何度も 涙を堪えられなくなりながら
何度も 溜め息をもらしながら 読み終えた
無常感に苛まれる
だけど この歴史が
この先人達の命が 今に繋がっている と胸に迫ってくる
濃密な時間を過ごさせて頂きました
投稿元:
レビューを見る
平家の滅亡を描く平家物語。公家化が進んだ平家が、清盛が亡くなることで、一気に滅亡へと突き進むのは当然のように思っていたのだが、読み終えた今、そうでないことを知る。
勿論、この小説の解釈も実際のところ、正しかったかどうかはわからないが、違う見方をすることで、歴史を何倍も面白く感じることができるのは間違いない。
こんな感想を千年後の現代に投稿させた作品についても、頼朝はさぞ悔しかろうか。今村翔吾さんの独特な解釈が溢れる次回作も期待したい。
投稿元:
レビューを見る
大河ドラマ「鎌倉殿...」のイメージがまだ記憶から薄れない状態で読む平家物語。
今村翔吾さんの描く人間ドラマは今回も小気味良いリズムで見せ場がやってきてゆっくりと物語の世界に引き込まれる。
上巻は比較的淡々と史実をほのままなぞるようなストーリー。
下巻は主人公知盛を最大限(いい意味で)美化してスッと納得いく気持ちよいエンディングにもっていく。
「驕れる平家も久しからず」のイメージをきれいさっぱり覆してくれる今村さんの技量に感銘を受けます。