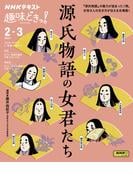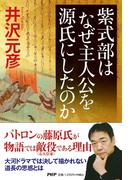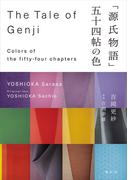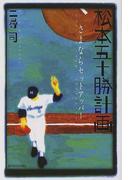目次
現代日本の小説 (ちくまプリマー新書)
- 尾崎 真理子(著)
- プロローグ
- 第1章 一九八七年、終わりの始まり
- 「ばなな伝説」の始まり
- 「サラダ記念日」と三島賞の創設
- 一九八○年代末、最後のはなやぎ
- 「純文学」のプリンス
- 春樹&ばなな、空前の快進撃
- 読者と文学のあいだ
- 「純文学」は消滅したのか
- 「キッチン」の世界性
- 大江へのノーベル賞が時代を画した
- 第2章 村上春樹のグローバリゼーション
- 『ねじまき鳥クロニクル』の文学的成功
- 小島信夫による村上作品の解読
- アメリカ人批評家の目撃したもの
- デビューした頃の村上春樹
- 私小説的な日本文学の風土との訣別
- 日本を客観視する視線
- アメリカ滞在の現実的なメリット
- 神戸の震災とオウム真理教事件
- アメリカ小説の翻訳と春樹の日本語
- 想像を超えた世界各国での反響
- 第3章 変容する創作のシステム
- 芥川賞の歴史上最大の“事件”
- 二十歳の金原ひとみ、綿矢りさの受賞
- 他ジャンルからの越境者を受け入れる
- 黒いミニスカート&白いワンピース
- しだいに過熱していく新人文学賞
- 応募数の増加と低年齢化
- 海燕新人文学賞が残した影響力
- 文学賞の女性選考委員と「文壇」
- 文学賞は日本独特の不思議な制度
- サブカルチャー化と対峙した江藤淳
- 地道に創作を続ける助けとなる賞を
- 第4章 パソコンから生まれる新感覚
- 昭和の終わりと平成の始まり
- 手書き原稿とファックスの登場
- 九〇年代の三つの文学的事件
- ワープロ化とジェンダーの消滅
- 小説という形に縛られない表現
- 『ノルウェイの森』と電話の役割
- ワープロ、パソコンと平成口語体
- キーボード入力と新しい表現
- 漢字文化と仮名文字思考
- 村上龍と『共生虫』の緊迫感
- 物語を破綻させる多重人格化
- 電脳空問と「顔」の消滅
- 視覚イメージの文学への取り込み
- ゲーム的リアリズムの時代
- エピローグ
- 若い読者のための参考文献
- 芥川龍之介賞1987〜2007
- 野間文芸新人賞1987〜2006
- 三島由紀夫賞1998〜2007
古典文学・文学史・作家論 ランキング
古典文学・文学史・作家論のランキングをご紹介します古典文学・文学史・作家論 ランキング一覧を見る
前へ戻る
-
1位

-
2位

-
3位

-
4位

-
5位

-
6位

-
7位

-
8位

次に進む