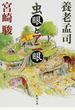ルーティーンさんのレビュー一覧
投稿者:ルーティーン
| 10 件中 1 件~ 10 件を表示 |
紙の本生きながら火に焼かれて
2008/01/11 21:44
殺される理由は『女だから。』 ノンフィクション、命を懸けた告白
11人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
衝撃的事実。有り得難い現実、有ってはならない現実。
知らなかった。
こんな空間が、地獄のような日々が、今現在この同じ地に存在しているなんて知らなかった。唖然とした。いくらこの世の中の富や貧、公平であること不公平であること、それに関連した様々な知識を頭に詰め込んでみても、私は無知であったことを知った。狭い狭い狭い井の中の蛙だ。
書評を書きながらの矛盾であるが正直、このショックをありのままに綴ることの出来る言葉が無い。無理だ。
この別世界の事実談は別世界には居ないのであって、幻想でも虚像でも何でもない。実在しているのだ。それがあまりにも刺激的過ぎた。本を何百冊読んできたがここまで心の奥底にずどーんと重いものを感じたのは初めてだ。
そう、同じ地球上に在る事実なのだ。今心臓を動かし息をしている全ての人が認めなくてはならない実際に有る事なのだ。地球という語を持ち出せば大規模に受け止めてしまうかもしれないが、これを読んだあとにその単位の本当の大きさを理解するだろう。地球に、こんなものが存在するのかと口から魂の抜かれた想いをするだろう。
本当に、こんな場所があるのだ。
家族から故意に火をつけられるようなそんな場所が。
あなたは何の権利も無い。怒鳴られようと、殴られようと、抵抗することさえ含め何をすることも許されない。生理であることも隠さなければ塵扱いされ殴られる。もちろん、恋をすることも許されない。
決められた結婚をし、貰い手がなければ殺されても文句は言えない。
一生奴隷のように生きて、死ぬだけ。
もし、あなたが女性であるなら。
あなたは理由も無く妹を殴っても構わない。あなたは理由も無く姉の首を絞めても構わない。あなたは理由も無く母親を刺しても構わない。そして決められる結婚よりも前に恋をした妹や姉や母を殺せば町中の英雄になれる。
家族の恥を殺し、そして英雄になれる。
もし、あなたが男性であるなら。
そんな信じ難い世界から、何度も殺されかけ逃げてきた著者スアド。彼女に幸運が味方し、この目を背けてはならないこの真実を世界に伝えるべく書いた命懸けの告白。
今もなお、進行しつづけているその残酷な女性差別。
これは、是非読んでほしい。
いや、世界中の人が読むべきであると思う。
何度も言うが、一匙の濁りもないノンフィクションである。
この本を開いた瞬間から異次元に飛んだような感覚が走り、
この本を閉じたその瞬間から世界観ががらりとかわるだろう。
一度でいいからどうしても読んでほしい。
そして広めたいと切実に願える一冊である。
紙の本デミアン
2011/02/10 10:30
心の中で、何かが解き放たれる。
10人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ヘルマン・ヘッセ
彼そのものは、好かない。
現にこの時代にも、才能や正確な眼を持っていようとも褒める気の失せる人間が居るだろう。彼は何もかもを持っていて、そして何も持ってはいなかった。根拠の無い自信家で、夢想家で、彼は陶酔するほど自身が大好きだった。彼の自殺願望は寧ろそれが原因の一部であり、それを証明していたと言ってもいい。
だが、それも本書のピストリウスが語りジンクレエルが最も感銘を受けたとする"ことば"に因果する。私自身をも見透かされている。本書は名言の宝庫であり、今回私に一番響いたのは彼同様その言葉だった。
何が言いたいのかというとヘルマン・ヘッセを好きだと思った人は、私のことを好いてくれる可能性が大いにあるということである。
一向に純粋で、美しく、だからこそ重苦しい。ピストリウスとの日々、そして最後の約30ページは心の奥底で何かが弾けるような、いやされるような、それでいて救いがないような、悲しみと愛しさに溺れるようだった。
この本は読み手の経験や性格、現状況、視点等によって響く箇所も違ければ、同じ箇所であっても感動の覚え方も違うと思う。様々な角度から違った色に見える、まるでプリズムのような本。
しかし、それら全ては同じところへ向かっている。本質は、変わらないのだ。
再びこの本を手にするのは、もう少し経ってからにしようと思う。その時、私はこの本の美しいことば一つ一つにどんな想いを寄せるのか、今回とはどのように違った発想を見出せるのか、そんな期待と不安を抱きながら、時期を待とうと思っている。
最後に、新潮社の翻訳がいいと言われているが…この岩波の実吉さんの翻訳の方が自然で、彼の言葉に近いと感じた。ただ単に私自身の好みだったのかもしれない。個人差があると思うので一度どちらにも目を通してみては。
紙の本100万回生きたねこ
2008/01/26 13:21
大人でも子供でもなく、「その人」に読ませたい。
6人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
これは大人の絵本じゃない。
よく『大人の絵本』として紹介されたり評されたりする本書だが、私はそう思う。
大人というのは、成長して行く過程で様々な物を纏い、子供が少しずつ肥大してきただけのものだ。大人は子供を含んでいる。大人も子供も、必要としているものや軸は変わらない。命という一本の芯は何も変わっていない。変わっていくべきものでもない。
この絵本は、そういう核に触れる絵本だと思う。だから人がこの本を読んで『大人の絵本だ』と口を揃えることに物凄く違和感を感じる。
私は幼い頃この本を読み、感銘を受け泣いた。理屈で理解しなくていい。何もこの世は理解出来るもので出来てはいない。全て言葉をもってした後付けだとさえ言える。
全てこと細かく説明出来る物なら絵や文章にする必要などない。
子供にこそ読ませたいし、大人になっていく過程の中で何度も何度も読んで欲しいと思う。自身も歳を重ねれば重ねるほど、大切に思う絵本である。
2011/02/06 11:40
これぞ傑作。
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
この短編集が森絵都の作品の中で一番好きかと言われたら迷いが生じるが、森絵都の傑作作品はと聞かれたら直ぐ様この作品を差し出すだろう。
全6編味の異なる作品で構成されている。音楽でいう所のアルバムが曲そのものだけでなくその組合せや順番が嵌って初めて一つの素晴らしい作品になる(と私は思っている)ように、小説達はそれぞれの人生を書き上げつつも作品として一本の筋を通している。
中でも『鐘の音』『風に舞いあがるビニールシート』、この二小説は群を抜いている。知性、鋭い洞察力、優れた感受性。そしてそれを纏め上げる冷静な分析力。彼女が兼ね備えている才能の豊富さに感嘆せざるを得ない。風に舞いあがるビニールシートでは、涙どころか嗚咽さえ我慢しきれなかった。
彼女の小説が齎す涙は、悲しく、せつなく、そして幸せで温かい。不思議な感情だとは思えど、それが人間なのではないかといつも一人で納得している。
彼女の潜在能力は留まり、尽きることを知らないのだろうかと改めて思った。彼女の作品を何冊か読んだ上でこの作品を手に取るとさらにのめり込めるかもしれない。
何度も繰り返し読みたい作品である。
紙の本虫眼とアニ眼
2011/07/27 08:42
みえないものをみる
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
初めて映画館へ行って観た作品が、もののけ姫だった。
たぶん親に連れられ家族で観にいったのだろう。当時幼かった私たちにとってその内容は少なからずショッキングなもので、弟に至っては映画の半分以上を目をつぶり耳を塞いでやり過ごしていた。私は十数年過ぎた今も、見過ごすまいと目を凝らして追った、あの祟り神の禍々しさを鮮明に覚えている。
本書は宮崎駿氏の絵『理想の幼稚園』から始まり、もののけ姫が公開された1997年から千と千尋の神隠しの公開後2001年10月までの対談が収録されている。
対談の相手は、養老孟司氏。ベストセラーとなった"バカの壁"でその名は大々的に世間に広まり、今や知らない人など居ないのではないだろうか。
同世代、戦後という同じ時代を歩んできた二人だが、そのアニメーション作家と解剖学者というまるで違う世界を生きているように思える。しかし本書の後方、『養老氏の宮崎アニメ私論』を読めば分かるように、これこそが方法論なのである。物の見方を別の分野で訓練してきた二人。このバランスが、読んでいてとても心地良い。
小さな発見をしたり、欠けていたものをもう一度見つめ直す大きなきっかけとなった。見えないものをジーッとみる、となりのトトロのメイのような『眼』をいつまでも持っていたい。
宮崎作品を軸に話が展開されていく。理屈から感性まで、人の対談にこれだけ心を躍らせたのは初めてかもしれない。
アニメーション。人の身体。
この二人は見える物に触れながら、見えないものを信じている、というよりも確信している二人なのだ、と思った。
今こそ、この時代に、この本を強く勧めたい。
紙の本ラスト・イニング
2008/02/03 14:07
器用すぎる彼の苦しみと、強く動いていく周りの変化 青春とはこういうものだと思う。
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
私は野球が好きじゃない。
というか、あまり関心が無い。
だからといってスポーツが嫌いな訳ではない。私は陸上競技を本気でやっていたし、バスケットボールにも熱烈な興味がある。
だが、野球というものの魅力を知る機会も無かったからか、甲子園のような一大イベントであっても興奮を覚えたことはなかったし(というかそれ以前に観てさえいなかったからなのだが)全くもって自分とはかけ離れた存在のように感じていた。
試合という一つの枠の中でグラウンドを降りてベンチに座ったり、ボールがくるのをベースで待っていたり、というような途切れる行動が、陸上のように、バスケットボールのように、開始の合図がなってからその瞬間が切れるまでの躍動感を感じ取ることが出来ない気がしていたからだ。
ある日、野球好きの友人が『バッテリー』という本の名を口にした。
本がかなり有名であることは知っていたし、その人気の高さから映画化されたこともずいぶん前に知っていたが野球というものには本当に(野球好きな方には申し訳ないのですが)意欲がわかなかったため、読む気は無かったし予定も無かった。それなのに貸してあげるからとその友人があまりに乗り気だったので断る手立ても無く、バッテリーを借りることになってしまった。
しかし、目を通した瞬間に、惹かれてしまったのだ。今までと、違う。
物語の多くは、周りの優しさに主人公が変わったり優しすぎるほどの主人公が周りを変えるというパターンでその中でさまざまな物事が少しずつ動いていくというのが基本になっている気がしていた。だから、ひとりの捻くれた天才自信家少年が出てきた瞬間にはああ、また、その流れなのだなと感じたのだ。 …鮮やかに欺かれた。もちろん、いい意味で。
自分への強い信念と、自負ではない確信。生意気で、絶対に折れない、本当に強い心。そんな一人の男の子に、皆が惹かれ、動かされ、変わっていく。
自然豊かな風景が目に浮かぶように綺麗な言葉と、一人一人の個性。 青々とした緑が広がり、やわらかな地元の人達の方言。 そして、本当に単なる言葉なのかという文章で、焦燥感や胸躍感や緊張感の染み入ったグラウンドを生々しく表現し、あんなにも遠かった野球というものを、まるでその場にいるかのように錯覚させ、こんなにも読み手を近づける。
知らぬ間に、私はたったひとりの少年に、のめり込んでしまった。
物語の中の人々と、同じように。
この『ラスト・イニング』では、そんな主人公の反対側に立つ、ライバル校のあるひとりの少年の目で捉えた、六巻の『その後』である。
その後、というよりそのままストーリーとして流れが継続されているので、決して+αというものではなく、『六巻の隠れた全てを引き出した第七巻』といった方がふさわしい。
器用すぎる新たな目である『彼』の心持ちや言葉は深く、とても新鮮である。
中学生から高校に上がる彼。全てをうまく、綺麗に受け流していて、野球からももう開放されたはずなのに、自由になれない、苦しい、何故か。精神年齢の長けすぎた彼が野球から逃れることの出来ない理由を、本当は彼が初めから一番、良く知っていたのかもしれない。
本当に爽やかで、衝撃的な本だった。読み心地がいい。
これでラストだなんて、本当に名残おしいくらいである。
紙の本円卓
2011/09/29 21:32
スピンの要らない本
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本を購入してから読むまでに、こんなにワクワクしたのは初めてだった。
ある日ふらりと立ち寄った本屋で、不思議な装丁を見つけた。方眼紙に朱い丸、それに被さるようにイビツな文字で『円卓』と書かれている。クレヨンの様なもので描かれたそれが一瞬日の丸に見えたのは、私の中で『円卓』と朱色がすぐに結びつかなかったからだ。そのデザインの所為だろうか、作品の存在そのものが異彩を放っているように感じられて私はこの本を手に取った。
朱い丸のハードカバーを開け、ギョッとするような赤をめくり、数行読んだところで私は後悔した。
どうして財布を忘れてきたのだろうか。
このまま一気に読んでしまいたいが、本当に面白い文章は自分の部屋でひとりきりで静かにじっくり落ち着いて読みたい。そんな葛藤を切り抜け、私は惜しみながらそれを元の場所へ戻した。本を閉じた時に見えた表紙裏の天狗がこっちを見ていて、相反する気持ちが増して縺れた。
何が言いたいのかというと、その数行にそれ程までの力があったということである。
私は焦ったように帰り、一番早く手に入るであろうネット購入を選んで直ぐさま注文した。その時既に巷では話題を呼んでいたらしい、探してみると沢山のレビューがあったがどれも星五つのものばかりであった。
届いたその日に読み終えた。結論からいうと、焦らしに焦らされて増幅した期待が裏切られることはなかった。
それどころか、読みはじめ、その物語の中へ入り、そして読み終えた後も、私は笑い、笑い、笑って、泣き、そして笑って泣き続けたのである。
本当の事を言うと、届いたその日に3度読んだ。
表紙の朱の様な個性の強さとその魅力でくらくらとする。
たった数行で引き込まれた世界。
私もこの作品と出会ったその始まりだけを紹介して、本の中身やその内容には触れずにこの書評を終えようと思う。
ただひとつ、こっそりお教えするなら、主人公・琴子の好きな言葉は、八歳にして「孤独」だ。
表紙に興味を持ち、幾つかの文字に惹かれ、見開き2ページ読んだところできっと貴方は琴子の虜である。
紙の本ラン
2009/01/23 20:15
【感情】を動かすのではなく、【心】を動かすのが目的だ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
タイトルに述べたように、この本は感動そのものを求めているわけではないと思う。
「感動を期待せずに、物語を書き綴る著者なんてあるか!」
と、誰かは言うかもしれない。
全くもってその通りである。感動を求めず何を求めるというのか。現に、私はこの本を読んで感動してしまったわけである。それは私の感情が自分勝手に動いたとは言い難い。なんせ、彼女の作った物語にのめり込み、きっと彼女の思惑通り(?)、感動してしまったわけである。
ただ、本を読み終わった後に残るものは、果たして「感動した」という、その事実だけだっただろうか?
小説やら映画やら…何のジャンルでもいいが
よくある涙、涙の大号泣ものだとか、悲劇のクライマックスだとか、そんなのを見て、感動したとする。そして、小説を読み終わり、もっと泣きたい気分だったらもう一回感動シーンを読み返してみたりして、また泣くなんてアホな事をやってみる。友人と映画館で観た映画であれば、感動したねー泣いたねーなんて言いながら映画館帰りの喫茶店なんかで泣き場を語ってみる。
そういう場合、印象深く残るのは何よりも先に"感動"なわけである。
「ラン」は違う。泣き所だけを綺麗に組み立て、そこだけを強調したいわけではない。
きっとこの本を読んだ方は、うんうん、確かに。と、理解してくれているであろうと思う。
今回ランを読み終わったあとに(読んでいる間は物語に没頭している)、森絵都さんが10年前までに書いてきた数々の物語と異なっていると感じた。
主人公の心中を上手く表しているのはもちろんだが、それぞれのキャラクター、つまり脇役と言われる人達の立場がカナリはっきりしていて、人生に対する批判だとか、やりきれない気持ちだとか、鮮明に書き表している。特に、本書に出てくるくそばばあ、強烈な主婦の真知さんには思い入れが強い気がする。
ちなみに、私はこの本を読み終わってすぐに母親に本書を貸し、育てていただいていた当初お母さんは大変だったよね、ごめんなさい、と侘びて礼を添えたほどである。笑
主人公に、たった一点のみに、視点を狭めなかったのは、どんな立場であろうと人生に立ち向かう姿勢は同じだと、本書を通じて"理解する"のではなく、"心で感じる"ことができるような伝え方になっているのだ。
泣く、笑う、怒る。そんな感情だけを動かす本ではない。自然と心ごとがっぽり動かす本である。一番大切なことを、がっぽりと。
経験、そして想い、それから、伝えるための手段の豊かさがなければできることではない。
死と触れ合い続けてきた主人公。彼女の立場からしたらそれはそれは暗い物語であるはずなのに、ページを捲るごとに賑やかさを増し、死の世界に彼女が何よりも近いはずであるのに、時間が経つほどに人間味に溢れた温かさに包まれていく。
自分の不幸さ、卑屈さに埋もれこんだ彼女を、無理矢理引っ張り出した素人ランナーズ、イージーランナー。
彼女だけじゃない。相互に引っ張り合い、ぶつかり合い、成長していく姿はあまりにも愉快で、美しく羨ましいものである。
大人の集まりとは思えない程笑えるあったかいやつら。最高だ。
そして、森絵都さん特有の、もうひとつの不思議な世界。あるはずがない…あるはずない、のに、何故ここまでリアルに描けるのだろうか。
そして、自分の不幸への卑屈さと、周りの存在に気付いたとき、彼女は決断をする。前向きに、なるために。
こんなに考えさせられて、納得して、共感して。それから愉快で、あったかくて。涙流して、もう一度、二度、三度笑って。
そしてこんなに前向きになれる贅沢な本は、この本くらいだろう。
やっぱり、これだから、私は森絵都さんの世界に入るのを、やめられないのである。
紙の本十二番目の天使
2008/03/03 12:07
不幸の意味
5人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
もうティモシーという野球少年が出てきた段階から、意外とオーソドックスな展開の物語だなあと先が読めてしまった。その後、んー、ワンパターンかなあ…と戸惑いを感じながらも読み進めたが、確かに涙は零れた。
その理由の一つとして、ティモシーの持っている魅力が、想いを引き込むほどのものだったことだと思う。私自身が感情移入しやすい性格だということも理由のひとつに含まれてしまうかもしれないが、この本はティモシーなくして、これほど多くの熱烈なファンに愛され得ない。
ただ、嗚咽をあげたくなるほど泣ける本ではないと思う。
このことを踏まえて、評価として良いか悪いか二択の選択肢から答えをいうと、読んでよかった。この本を手にし、読むことは間違いじゃない。
何故なら、この本の芯の趣旨は、感動の涙を流すか流さないか、つまり泣くか泣かないかということじゃないと思うからだ。
少なくとも私はそう感じた。
誤解しないで欲しい、感動し泣くことはとてもいいことだ。涙は一番、その人の「悲しい」だとか「切ない」だとか気持ちの高ぶりや感情を形にして現すことのできるものだし、なにより素直で、泣ける人は素敵だと思う。
だけど、書き手が読み手に届けようとしているものは涙ではなくて、もっと別の、何かだと思った。すべて失った不幸のどん底にいる主人公から話が始まり、ティモシーの登場へと繋がれていく。なぜ、ティモシーだったのか。
この本を読んだ後、考えてみた。
もし、もしも、主人公がティモシーであったとしたら、如何しただろうか。
主人公は立派なひとだと思う。同時に強いひとでもある。ただ、彼は不幸を不幸だと思い、その不幸にのめり込んでいく。いや彼の立場だったら、誰しもがそうなると思う。失うことは、何より痛くて、辛いことだ。
それでも、ティモシーは如何だろうか。
自分の才能や、自分の在る姿や、自分の居る場所を、不幸だとは言わない。前を向き進むことだけに一生懸命で、何よりその中で楽しむことを絶やさない。その小さな体のなかにいくつもの強さを抱えて、自分自身を支え、周りの人々さえ、いとも容易く支える。かけがえのない存在になっていく。
主人公がティモシーであったとしたら、こんなに強く前向きに、笑っていられただろうか。
たしかに、何かと比較したとき、不幸や幸せの大きさを測ることはできてしまうと思う。お金はあるほうがいいかもしれない。健康な体のほうがいいかもしれない。悲しみや苦痛は少ないほうがいいのかもしれない。それは、当たり前のことかもしれない。しかし、それは単なる一般論だ。勝手な判断に過ぎない。本当に周りの目がその人を不幸だと判断するのは、本人が自分をなんて不幸なんだと思っている時であり、笑顔が途絶えてしまった時なのではないかと思う。
話の展開のひねり具合としては、正直結果がわかりやすかったので評価をひとつだけ下げさせてもらった。
だけど、この本はいい本だ。
読んだあとに感じるのは、すごくすっきりとした感覚だった。心が洗われるってこのことか、と思った。大げさではなくて本当に涙と一緒に迷いも、汚いものも流れていったような、とても不思議な感覚。本を読んでこんなおだやかな気持ちになったのは、初めてだった。本を読んでというか、生きてきてこの感覚を感じたことがない。
心が温かくなるとか、引きちぎれそうなくらい切ないとか、そういった気持ちはきっと一度は感じることがあると思うが、何か違う。説明したいが言葉にするのが難しい…本当に、洗われた感覚。深い深い深い深呼吸をして、全て吐き出した後の一瞬のような、綺麗な気持ちになった。
なんだかんだ私も十二番目の天使に救われたひとりである。
好きなフレーズはと聞かれ、この本を読んだひとが声を揃え答えるであろう彼のあのふたつの言葉、毎朝毎晩読み返し、意を固めている。
この言葉は私が紹介するのではなくて、この本を読み、ティモシーの口から直接聞いていただきたい。
前に進まなければいけない時に、この言葉は本当に力になる。
一度、読んでみてはどうだろうか。
紙の本I love you
2011/04/23 16:11
本当に人間は、いろいろ
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
I LOVE YOU。
なんとも気恥ずかしいタイトルだ。
普段恋愛小説は好んで読まないが、日本人には馴染みの無い一種のきまりの悪さに興味を持ち、この本を手に取った。名の知れた6人の作家の短篇集らしい。しかも全員、男性作家である。
この言葉をこれらの男性が使った後、どんな照れた顔を見せるんだろう、とニヤニヤしながら覗くような、半分冷やかしの気持ちで読んだ。
男性というものは、女性よりもロマンチストだ。読み終え本を閉じながらそう思った。なんて純粋で、繊細なんだろう。女性からしてみれば、単純であるからして面倒なのであるが、だからこそいとおしい。
それぞれの作家の視点の違いがとても面白い。方向性が大分違うので合う合わないがあると思うが、どれも読みやすく、短い話なのでサラっと読めてしまう。気合を入れたディナーというよりは、軽口のランチ、もしくはちょっと贅沢な3時のおやつという感覚だった。
特に印象に残ったのは、伊坂幸太郎さんの『透明ポーラーベア』、中田永一さんの『百瀬、こっちを向いて』の二作。
伊坂さんはあの独自の文章とストーリーで読み手の背中を押す。何より目の付け所がさすが、と言ったところ。後者の作品は人物設定のせいかどうしてもアニメ風のイメージが沸いてしまうが、それはそれで魅力的で、ストーリーの運びや終わり方にもワクワクさせられる。
ひとつの作品の中で動くそれぞれのキャラクターと、それらが作り出す空気感や風景。そして、それを描きだすひとりひとりの著者。
それを読む私。
一言にI love youといっても何重に広がる色がある。
たまに甘い物を食べるのも、悪くないなと思えた一冊だった。
| 10 件中 1 件~ 10 件を表示 |