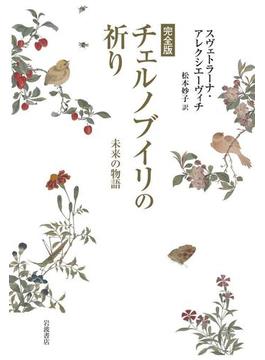0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
フクシマが起こる前は
原発事故というと、チェルノブイリ、でした。日本にも、影響したとか書いています。そのまま、今も核反応起こしながら、厚いコンクリート内部で……ともきいているので、あらためて、原発は、……
投稿元:
レビューを見る
完全版の前の版を読みました。
チェルノブイリ原発事故の事実は世界中誰でも耳にしたことはあると思う。
社会主義国家による情報統制下でこれまでの35年間、そして今後も何百万人ものベラルーシ国民が悲惨な状況下で、日常生活を送るさまになんとも言えない無力感を感じる。こんな世界が普通に存在するのかと。
政府だけでなく、医師、科学者、教育者誰ひとりとして真実を国民に伝える事が出来ず、ただ、ひとりひとりが目の前で起きたことを語る。それが国民が知る唯一の真実だから。
先の福島第一原発事故を国会事故調査委員会は人災と報告したが、チェルノブイリ原発事故もここまで被害が広域かつ長期的となり、多くの国民を苦しめる状況となったのは、まさに人災によるものではないかと思う。
投稿元:
レビューを見る
『アレクシエーヴィチとの対話』刊行記念公開オンライン研究会に参加するために読んだ。
『チェルノブイリの祈り』は既読だが、本書は旧版の1.7倍の増補改訂版だということで、どうしても読んでおきたかった。/
2021年6月23日、運転開始から40年を超えた福井県にある関西電力の美浜原発3号機が、再稼働した。
また、7月21日、経産省は、改定「エネルギー基本計画」の素案を発表した。
そこでは、原子力発電は、安定的なエネルギー供給源を確保する観点から、20~22%を維持することとされている。
「フクシマ」では足りないのか。
このうえ、まだ、「チェルノブイリ」が必要だというのか?/
《一九八六年四月二六日(略)ーー一連の爆発によってベラルーシ国境近くにあるチェルノブイリ原子力発電所四号機の原子炉と建屋が崩壊した。
(略)
チェルノブイリのあと、わが国(ベラルーシ)は四八五の村と町を失い、そのうち七〇はすでに永久に土中に埋葬された。
(略)
今日では五人に一人が汚染された国土に住んでいる。その数は二一〇万人で、そのうち七〇万人が子どもである。
(略)
チェルノブイリの惨事の被害がもっとも大きかったゴメリ州とモギリョフ州では、死亡率が出生率を二〇パーセント上まわっている。
事故の結果、大気中に五〇〇〇万キュリーの放射性物質が放出され、そのうち七〇パーセントがベラルーシに降った。国土の二三パーセントが放射性物質に汚染され、(以下略)》/
《チェルノブイリ事故以前‥‥腫瘍疾患はベラルーシ国民一〇万人あたり八二人であった。今日の統計では、一〇万人あたり六〇〇〇人。ほぼ七四倍に増えている。》/
《あの日‥‥。わたし、ベラルーシ科学アカデミー核エネルギー研究所実験室長は、職場に着きました。研究所はミンスクの郊外、森のなかにあります。すばらしい天気だ!春です。窓を開けた。
ー中略ー
このとき、研究所の原子炉ではパニックが起きていたのです。放射線モニタリング計器が放射能の上昇を示し、空気浄化装置のフィルター付近では二〇〇倍にはねあがっていました。(略)いったいなにが起きたのか。
ー中略ー
昼ちかく、あきらかになった。ミンスクの上空一帯に放射能雲がある。(略)
どこかの原子炉で事故が起きたのです‥‥。
まっさきに考えたのは、自宅に電話して妻に注意しなくては、ということ。しかし研究所の電話はすべて盗聴されている。
(略)
それでもやはりがまんできず、受話器をとる。
「いいか、よく聞いてくれ」
「なんなの」。妻が大声で聞きかえした。
「大声をだすな。換気窓を閉めろ。食料品はぜんぶポリ袋に入れろ。ゴム手袋をして、濡れぞうきんでふけるものをぜんぶふけ。ぞうきんもポリ袋にいれて、はなれたところにしまっておけ。ベランダに干した洗濯ものは洗いなおせ。パンは買うな。(略)」
「そっちでなにがあったの」
「大声をだすな。コップいっぱいの水にヨードを二滴たらして溶かせ。頭を洗え‥‥」》/
ここに引用��たのは、僕が特に感動した箇所という訳ではありません。
引用したい部分があまりに多かったため、本書の副題である「未来の物語」という観点から上記の部分のみを選び、他の部分については、泣く泣く割愛しました。
旧版『チェルノブイリの祈り』の感想
https://bookmeter.com/reviews/55222016
https://www.honzuki.jp/book/188552/review/247495/
でも二〜三引用していますので、よろしかったらそちらもご覧下さい。
投稿元:
レビューを見る
ウクライナに生まれベラルーシで弾圧を受けながらも、国家の影に隠された人々に取材し、その生の声を届けるジャーナリスト スヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチ。
ウクライナにあり、1986年4月26日に事故を起こし、隣国のベラルーシに深刻な放射能被害を及ぼしたチェルノブイリ原発事故。このチェルノブイリ原発事故の事故処理にあたった人々はソビエトにおいては国家の英雄として扱われたが、その事故の被害の真実は長く隠匿され、ベラルーシにおいてもそれは同じだった。
アレクシエーヴィッチはこのチェルノブイリの事故の処理にあたった人々、その事故処理による被曝で亡くなった人々の遺族、この事故のために住む村を追われた人々、事故後に重い障害や病を得て苦しむ子どもたちなど、様々な人々に取材し、国家が隠していた人々の苦しみ、悲しみをその人たちの言葉によって語らせる。
本を買ってからなかなか手がつかず、やっと読み始めたら、ロシアがウクライナに侵攻し、ベラルーシはロシア側に協力している。
チェルノブイリほかの原発についてもロシア軍が制圧していると聞く。戦争の中で、戦火による被害だけでなく、チェルノブイリの原子炉を覆うドームが破壊されて、放射能の被害が再度起きることがないように祈るばかりだ。
アレクシエーヴィッチはこの事態をどのように見ているのだろうか。
投稿元:
レビューを見る
“ここでは私たちみんながチェルノブイリの被災者です。庭の畑のりんごやキュウリをごちそうされてもお互いに驚いたりしません。もらって食べます。あとですてようと、きまり悪そうにバックやポケットにいれたりしない。私たちは記憶をともにし、運命をともにしています。ところが、よそではどこでも私たちはのけ者にされる。〈チェルノブイリの人々〉〈チェルノブイリの子どもたち〉〈チェルノブイリの移住者〉。もうすっかりおなじみのことばです。”
投稿元:
レビューを見る
チェルノブイリのドキュメンタリー。体験者の話をそのまま聞くような気持ちになる。
とくに、子供達との会話はすさまじい
「あちこちでネズミの死骸に出くわして、彼らは笑っていたのです。ほらね、ネズミや甲虫やミミズが絶滅しちゃったら、こんどはウサギやオオカミが死にはじめて、そのつぎはわたしたちよ。人間は最後に死ぬんだよ、と。」
投稿元:
レビューを見る
核はこわい
核の情報操作、放射能障害で沢山の方がなくなる
一方でチェルノブイリツアーの人気
怖いもの見たさなのでしょうか
まだ終わっていない、これからも原発がある限りリスクは続いている
投稿元:
レビューを見る
読み始めると、辺りが静かになる。
一人一人の物語を、己の少ない脳の記憶容量に刻みつけるように。文字を読むのではなく文字を聴くように読む。じっと。
アレクシエーヴィチの著作を読んだのは「戦争は女の顔をしていない」を含めこれで二冊目(未読だが手元にボタン穴から見た戦争がある)。
戦争は女の顔をしていないを読んだ時は、初めてアレクシエーヴィチの著作を読んだ時は、衝撃といろいろな感情がないまぜになって、これは今、ものすごく大変なものを読んでいるとわかって、恐れ多くて、畏ろしくて、感想が書けなかった。ただ心に刻みつけるしか。今回もそうだ。
著者は、「スターリンの強制収容所、オシフィエンチム(アウシュビッツ)…チェルノブイリ…そして、ニューヨークの九月」と人間の理解を越えた大惨事を述べる。そして解説で梨木香歩さんが「今ならきっと、3.11、そしてこの新型コロナウイルスによるパンデミックもあげることだろう。」と述べる。
さらに付け加えると、先月ロシアがウクライナに侵攻し戦争が始まり、よりによってロシアがチェルノブイリを軍事拠点としていることだろうか……
そしてその戦争にロシア側にベラルーシが加担していることだろうか…チェルノブイリ事故で多大な犠牲を出したベラルーシが…
本書で証言した様々な人たちがまだ生きていたら、このことについてどう思うだろう…そもそも正しい情報を知っているのだろうか…と読みながら考えてしまった。そしてソ連という今はなきはずの国は、その時代を生きた人の中にはまだまだ根ざしている…そう思わされる。
本書のタイトルにある「祈り」について、梨木さんは「今まで使ってきた言葉が、直面する現実に追いつかないーそういう事態を表す「記号」でもあったのだ」という。「この本は、「チェルノブイリの祈り」以外の何ものでもない」と。
祈り…記号以外の祈りを考えるならば、私は何を祈ればいいのだろう…人知を越えたものに捧げる…何を…祈ることが多すぎる…
本書には衝撃を受けっぱなしだったが、特に印象に残ったのは、チェルノブイリ人という単語。
事故後に生まれた子どもが「ぼくはチェルノブイリ人だ!」と叫ぶ。
子どもたちが死を身近に感じていて、自分もすぐに死ぬのだと悟る…
…本書ではいろいろな人が語る。事故処理に派遣された若い男たち、その妻たち、その子どもたち、避難してきた人たち、避難区域に住み続ける人たち、チェルノブイリにきたジャーナリストたち、戦争からチェルノブイリに逃げてきて原子よりも人間の方が怖いという人たち、避難区域の学校の教師たち、元書記官、核物理学者、心理学者……
本書は訳者あとがきや解説を含めて約410ページ。
全部読むのはなかなか抵抗がある、という人は、最初の、消防士、故ワシーリイ・イグナチェンコの妻・リュドミーラ・イグナチェンコの証言「孤独な人間の声」だけでも読んでほしい。
前知識なんてなくてもいいから…私もそうだったので…。
「チェルノブイリの祈り」の中でも本書を選んで読んだのは、完全版であることと、梨木さんの解説があることが大きいが、表紙の美��さに惹かれたのもあった。
読み終わってから改めて表紙を見ると、やはり美しい。小鳥たちが枝木に止まり、蝶が舞い、花は咲く。
美しくて涙がにじむ。チェルノブイリ周辺は放射線量を除けば、とても美しく、作物もよく採れたそうだ。食べられない作物が………美しいからにじむのだ。
ちゃんと感想になってるかわからない。書けた気がしない、でも私の心には残っている。
投稿元:
レビューを見る
「もう一つの戦争を体験、そしてそれはまだ終わっていない」「失ったのは町じゃない、人生丸ごと」「住民は人間ブラックボックス」「誰も何も理解していなかった。これが一番恐ろしい」……原発事故後、旧ソ連政権下で封殺された、或いは黙して語られることのなかった「チェルノブイリ人」の証言の数々。著者の地道な取材で拾い上げられ 、10 年という時を経て届けられた市井の人々の声なき声、拭い去ることのできない“心の傷跡”が痛過ぎる。特に冒頭の消防士の妻の証言には言葉を失う。ノーベル文学賞も宜なるかな、と思える衝撃の記録文学です。著者はロシアのウクライナ侵攻に際してもいち早く声明を発表。「市民に真実を伝えて」と訴え、ロシア国営メディアの嘘を追及されています。かの国の隠蔽体質、秘密主義は本当に根深い……。
投稿元:
レビューを見る
audibleで読了
内容が重たいだけに
読み切るまでにだいぶ時間がかかってしまったけど
読めてよかった
ソ連という国が、原発事故が、どんなものであったか
少しでも知ることができてよかった
描かれる内容があまりにつらい
とくに一番目の消防士の妻と最後の事故処理作業員の妻の話は愛の強さと夫の死にゆく姿の痛ましさが克明に描かれていて言葉にならない
放射能が人を殺してゆく姿が恐ろしい
また、ソビエト連邦の共産主義がどんなものだったのかさまざまな人の声から明らかになるけれど
信じられない気持ちだった
ロボットが高放射能下で、壊れてしまう中
人々をしっかりした防御なしに働かせたり
必要な情報を与えなかったり
偉い人間だけが情報や必要なものを持ち、家族だけを守ろうとしたり
一方で、放射能よりも人、戦争の方が怖いとチェルノブイリに移る人や、土地を離れがたく住み続ける人
真偽不明な噂話のようなものも含めて綴られていたのも印象的だった
3.11の福島原発事故の時
放射線被曝量を抑えるため動いた医師たちのドキュメンタリーをNHKで見た記憶がある。
そうやって動いてくれる人たちがいることはすごいことなんだと思う
不都合なこと、目を逸らしたい事象は知ろうとしなければ、簡単に見えなくなる
知ろうとすることを怠らずにいたい
一部の人の保身のためだけの社会には絶対にしちゃいけない
みんなにとってより良い社会であるよう
有事じゃない間こそ意識しなきゃいけないのかもしれない
投稿元:
レビューを見る
2022.5.8 市立図書館
コミックを入り口にして原作に進んだ「戦争は女の顔をしていない」が最初で、次に手にとったアレクシエーヴィチのノンフィクション。ウクライナ関連で今こそ読むべきかと思い借りた。
冒頭の、消火作業にあたって半月後に亡くなった消防士の妻の証言、続く著者の自己インタビューだけでも非常に重く深く、読んでいるだけでお腹のあたりが重たくなり咀嚼消化するのに時間がかかるが、コロナ禍の2年で感じていることの先触れのようなものもあり、20年をかけて「完全版」と銘打ってはいてもこれは終わりのない旅なのだと理解する。著者の話を引き出す力はやはりすごい。生涯胸にしまったまま終えたかもしれない、いまだから、あなただから話せる、というような内容の言葉を引き出す取材、こうした記録が残ることにはただ敬服する他ない。これは急いで読んですぐに忘れるのではなく、ゆっくりでいいから、きちんと読んでそれを土台にして自分で考え続けなければいけない話だと思った。
それにしても、著者も関係者も、2021年の訳者あとがきと梨木香歩による解説のついた完全版ができたちょうど1年後にこのようなことになってチェルノブイリも渦中となるとは想像もしていなかっただろう。しかし、今読めば、チェルノブイリの事故後まもなくソ連が消滅し、ロシア、ベラルーシ、ウクライナと別の国になり、その当事国のみならず、さまざまな土地でロシア人と○○人の間の対立が生まれ、居場所を失った少なからぬ人がさすらった末に住人を失ったチェルノブイリ周辺に住み着いているということを知ると、問題の複雑さにめまいがしそうになる。ロシア人でもウクライナ人でもベラルーシ人でもソ連人でもない「チェルノブイリ人」と自認する人がいまもウクライナとベラルーシの各地に大勢いて他の世界から少なからぬ断絶を感じていることも今の彼の地の問題を考えるとき欠かせない視点だろう。放射能の影響に国境はないのにもかかわらず、ロシア軍が原発を占拠するような愚挙がなぜ起こってしまったのかも、いずれ解明されてほしい。
チェルノブイリについてもウクライナについても、ロシア国内では今もさまざまな思いを抱きながら黙々と暮らしてる人がいるのだろうと思いやることはできるが、それ以上のことはなにもできないのが苦しい。
岡田利規の戯曲『未練の幽霊と怪物 挫波/敦賀』は能とともにこのような作品の影響も受けているのではないか、というのは考えすぎか?
投稿元:
レビューを見る
紹介くださった方
源明子さん
https://www.facebook.com/groups/snip4u/posts/759070578608324/
投稿元:
レビューを見る
ロシア・ウクライナ戦争がはじまって、いま起きていることを理解したくてスヴェトラーナ・アレクシエーヴィチの本を読みはじめた。
311が起きた時もこれからどうなるのかをチェルノブイリから学べるかと、本を読んだりドキュメンタリーを見たりしていた。
その結果としては何もわからないままで恐怖が残っただけだったけど。
新宿御苑で汚染土を使った実証実験が行われると聞いて、また少しずつ放射線に関する本を読みはじめている。
この本を読んだ印象では、福島の事故で出た放射線はチェルノブイリよりずっとマシだったみたいだ。
311の頃は「直ちに影響はありません」を聞くと一体何言ってるんだと混乱が深まるばかりだったけど、今考えると本当に不幸中の幸いで、チェルノブイリほどの深刻さに陥らずに済んだ。
ソ連の時代の人は、ソ連人というアイデンティティを持ってた人も多かったんだ。そのことに驚いた。この本に出てくるのはベラルーシ人がほとんどなので、すべての元ソ連の国々の人に当てはまるかはわからないけど。
投稿元:
レビューを見る
チェルノブイリの原発事故について、原発近隣の住民や被曝して亡くなった家族を看取った人たちのとにかくリアルな重さを持った言葉が綴られている。
最初の被曝した消防士の夫を看病した人の話は、近くで見ていた人だけが分かる現実が語られていて恐ろしかった
その他の人たちの話は、想像したこともない事象が自分の身に起こった時に、人間は何を思ってどんな行動をするのかが語られていると思った
理解できないことは存在しないことにしたり、理解するために哲学的な思索をしたり、現実を受け入れるために物語を創造しようとしているのだと感じた
とにかくミクロな視点から見たチェルノブイリの事故が語られていて、ニュースや歴史としてまとめられたものでは感じられない生々しさがあった
投稿元:
レビューを見る
伊藤 裕顕先生のおすすめ本
地域マネジメント学科
ーーーーーーーーーーー
宮代キャンパス
配架場所コード:2F:受付カウンター前
分類記号:543.5
著者記号:A
ーーーーーーーーーーー