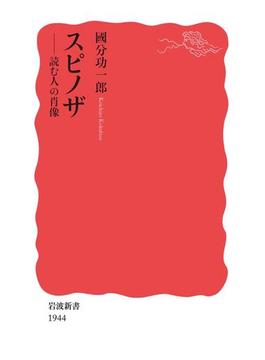0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なつめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
スピノザについて、わかりやすく解説されていて、よかったです。スピノザ哲学の全貌が俯瞰できて、素晴らしかったです。
投稿元:
レビューを見る
一歩ずつ立ち止まって、ターンイングポイントだよと言ってくれたり、後回しにしましょうと提案してくれたりと、懇切丁寧な解説をしながら伴走してくれます。
が、理解できない。何度も読むしかない。難しい。
投稿元:
レビューを見る
スピノザに興味があったわけではない。國分さんの本ならということで読んだ。「あこがれの連鎖」ということで、好きな人が好きなものだからどんなものか見てみようというわけ。これがいつもうまくいくというわけではなく、好きな人の好きなものを好きになれるとは限らないのだ。さて、正月休み1週間かけて読み切れずに、あと3日、通勤途中に読んだのだが、またしても頭に残っているのはほんのわずか。スピノザの生涯を読むという部分ではある程度意味はあったが、その思想を知るという部分はさっぱりであった。かろうじて神のとらえ方が頭に残っている。正しいかどうかは別として。物理学との類推で言って、神は空間、つまり宇宙すべてを占めている。そしてその外には何もない。この宇宙の中で何かが生成し消滅していく。総質量は保存している。これは完璧な神だ。神はすべてを知っている。一時にすべてを把握できる。未来永劫、宇宙が膨張しようとも、はたまた収縮に転じようとも、あまねくすべてを埋め尽くしている。僕なんかが想像する八百万の神とはほど遠い。そして意識。意識と良心はもともと同じことばだったという。conscientia 共通の知というようなところ。それが正しい知であれば良心と考えてよいということだろうか。間違った知を持つ人々は昔からいたとは思うけれど。ところで意識は人間に特有なものか。人も寝ているときには意識をなくしている。そういう意味では寝る生き物は意識を持っているということになる。これは養老先生から聞いた話(YouTubeで)だが、そうするとAIには意識が生まれないということか。政治のこと国家のことなども論じられていたようだが、総体的にはところどころ頭に残っていながらも全体像はまったくつかめないまま読み終わったという感じだ。そして、コナトゥスの意味はやはりつかみ切れない。
投稿元:
レビューを見る
國分先生の説明力をもってしても「ぜんぜん文章として頭に入ってこね〜!!!」とパニクる部分も多々ありつつ、スピノザの知性のオーパーツぶりがなんとなくわかったかと思う。すべては相対、すべてはグラデーション、単純な二元論に逃げるやつはバカ。
投稿元:
レビューを見る
【オンライン読書会開催!】
読書会コミュニティ「猫町倶楽部」の課題作品です
■2022年12月4日(日)14:00 〜 17:30
https://nekomachi-club.com/events/bf496678af76
投稿元:
レビューを見る
既にある著者「はじめてのスピノザ」より何歩も踏み込んだ内容でありながら、はじめての読者にも寄り添ってくれる内容だと思う。
神の定義、
第一〜第三認識という概念、
受動と能動。
自由という概念がぼくの外にあるんじゃなくて、ぼくは自由になったときに、それが自由だと気づく。自由の定義づけじゃなく、あくまで個々がぐるぐると認識を更新していく中で実践的な自由の在り方を提示する。
ドゥルーズのも読んでみようかな
投稿元:
レビューを見る
スピノザの著作を想定される時系列でその人生でのできごととも関連させながら、紹介していく。そのため、「エチカ」の執筆を中断して、「神学・政治論」を書いたということを踏まえて、エチカの前半と後半の間に「神学・政治論」の解説がはいる。そして、「神学・政治論」の議論が「エチカ」の後半にどう影響を与えたかが検討される。
一応、スピノザの「人と作品」という体裁はとっていて、それなりに入門書的にわかりやすいわけだが、内容的には、新書のレベルではなく、新しい研究動向まで含めたところで、著者の最新のスピノザ解釈を示すものになっていると思う。
わたしは、そこまでスピノザを読み込んでいるわけではないのだが、これまで読んだなかで、一番、「わかった」気がした。
スピノザはなんだかいいことを言っていそうなんだけど、それがなんだかわからないというモヤモヤをかなりのレベルでクリアにしてくれた気がする。
たとえば、スピノザは自由意志の存在を否定しているのだが、それなのにどうして「エチカ」、「倫理」を語ることができるのか?みたいな基本的なところで、わからなかった。そして、これまで読んだいくつかのスピノザ入門書ではそこがなんだか腑に落ちない感じがあったのだ。
「エチカ」は、神の存在証明からスタートするわけだが、やはりスピノザが問題にしているのは倫理なのだな。
とある意味、当たり前のことを確認した。
にもかかわらず、それを自分の言葉でまとめることがまだできないというもどかしさは残る。
いずれにせよ、これがこれからのスピノザ入門の基本図書になるのではないかな?
投稿元:
レビューを見る
スピノザに惚れ込んでから、手当たり次第スピノザ本を読んできたが、この本は新書の体裁ながら、第一級のスピノザ研究である。現時点で日本語で読める最上のスピノザ解釈ではないかと思える。
著者が10年以上かけて書き上げたというのは、むべなるかな。
一切の外的なるもの=超越的なものを必要とせず、すなわち目的論を徹底排除し、内在的なるもので世界と人間を語り尽くすスピノザ。
この哲学の射程は驚くほど広大である。
投稿元:
レビューを見る
読み終えた僕らは、岩波新書らしからぬ煽りに煽った帯コピー「この思考は、人間のすべてを根底から覆す」が、全然大げさではないことを体感する。
スピノザという至高の読む人と、國分功一郎という気鋭の読む人との対話を通じて、読むこと、読み継ぐことの難しさと楽しさ、素晴らしさを体感できる一冊でもある。
難解なテキストを薄めることなく、がしかし読み外さないように丁寧に根気強く、時にユーモアに時に切実に、日本語で導ききった國分功一郎の仕事、狂気の沙汰レベルに凄まじい。
スピノザが示した道としての「方法」や第三種認識は、仏教徒の柳宗悦が民藝運動に込めてた「不ニ」や道元の悟りにも通じるのでは?と思った。だとしたら、民藝を経由して、’ものづくり”についても考えたい
投稿元:
レビューを見る
「エチカ」を中心とし、それ以外の著書も解説しつつ、スピノザの哲学を肌感覚でも理解できるように書かれています。単にその著書の中身の解説というだけではなく、それが書かれた時代背景や、スピノザの置かれた状況も考えを伸ばし、その著書が書かれた順番にもできるだけ忠実に合わせて読解するようにされています。それにより、スピノザが言いたかったこと、書くという限界を超えた部分で到達したかった部分にまで考えを伸ばしていくことができます。そこからスピノザの書物を単に読むだけではなく、そこから何を成したかったのか、その課題が現代における私達に投げかけるもの、そして私達がその哲学を継承することから目指すものが見えてきます。まさに生きる哲学を本書から感じることができるものとなっています。
スピノザの哲学の難解な部分が、なぜ難解なのか。それは現代の私達の認識を一度捨てなければ理解できない部分があるということ。しかしそれが為せると当然に出てくる明快な結論であること。ゆえに理解が進むと世界に対する新しい見え方が出来るようになること。そこから私達の生き方について、倫理についての考えを知ることができます。そのスピノザの考えを、現代の私達に伝える著者の努力が伝ってくる内容となっています。
投稿元:
レビューを見る
『たとえば、三平方の定理のような数学の定理を証明する時のことを考えてみればよい。その証明が真であることは、何かに照らして真であるというより、その証明自体によって示されている。証明を終えた時、証明を行った本人にはそれが真であることが分かる。確かに三平方の定理自体は公共的に共有されうる。しかし、それが真であることは自ら証明してみないと分からない。そして証明してみれば分かる。真であることは公共的に共有されるものではなくて、各自によって経験されることだと言ってもよい。スピノザがイメージしている方法としての道もまた、それ自体で真であることの明らかな観念から別の諸々の観念が導き出され、それらの真であることが次々に理解されていく、そのような経験の連鎖である』―『第ニ章 準備の問題/スピノザの方法』
共通一次世代の理系少年であった自分にとって社会科系の暗記を前提とする学科は敬遠の対象だった。数学や物理の公式や化学でも周期律表とかイオン化傾向とか暗記しなくてはいけないことが結構あるじゃないかと反論する文系の人々も多いだろうけれど、それはレゴのブロックの特徴を理解するような作業であって、肝心なことはそのブロックを使って何かが作り出せることに満足感が伴うということなのだ。ブロックを文字と言い換えてもよい。文字を覚えることが目的になるのは嫌だが覚えた文字で文章を読んだり書いたり出来ると面白い、ということ。そういう訳で(って、どういう訳だ?詳しくは池田央(1981)『得点の分布と科目間の調整―共通―次学力試験を例として―』[行動計量学8巻1号]を参照」)五教科七科目の内の社会科系二科目の選択はリンシャセイケイ(倫理・社会、政治・経済。後にこの二科目の同時選択は不可となる)だったのだが、高三の選択授業で受けたのも倫理・社会で、そこで覚えたスピノザといえば、神は至る所に存在する、という「汎神論」というやつだ。当時は「スピノザ=汎神論」という符合として覚えていたのだが、汎神論って結局八百万の神々みたいなこと言ってシャーマニズム的だなあなどと勝手に考えていても点数は取れたのだから、やはり当時の社会科系の試験には問題があったのだと妙な感じで思い返してみる。その反省という訳ではないのだが、歳を取ったせいか実際にスピノザは何を言っていたのかが気になって本書に手を伸ばす。著者の國分功一郎には「中動態の世界―意志と責任の考古学」や「暇と退屈の倫理学」で馴染みがあったこともきっかけの一つ。しかし、この探求の徒の主たる研究課題がスピノザだったとは知らなかった。
「中動態の世界」で、言語に残る先人達の思考の痕跡を考古学よろしく探ってみせた著者の思考はとても数学的だ。数学的という言葉で自分が意味したいのは、ユークリッドの示した思考方法に倣ったものということで、「点」や「線」などの「定義」を示した後、誰もが真理と考えることのできる「公理」を構築し、そこから「定理」を導き出し「証明」する、というもの。哲学といえば「デカルト」な訳だけれど、デカルトもまたそのような「公理系」に則した思考をした偉人だし、いわゆるXY座標系(Cartesian座標系などとも言われるが、DesCartes[ラテン語���Cartesius]が提唱したことに因んでの名称)で知られるように数学にも足跡を残している。哲学的な考察を重ねることとはすなわち普遍的な真理を求めることであり、その為には不動の一点(デカルトにとっての「Cogito ergo sum」のようなもの。実際にはフランス語で記した「方法序説」の中の「Je pense, donc je suis」らしいが、どうしても「コギト」と参照されるよね)から命題を証明していくという道筋は数学的になる訳だ。その國分が「読む人」と称するスピノザもまたデカルト的な(すなわち数学的な)思考を積み重ねた人であったことが本書からこれでもかと伝わってくる。
ただし、この一冊は(他の國分の著作同様、と言ったら言い過ぎかも知れないが)判り易い入門書ではない。よく理系の人々の書き物に対する警句として「数式を入れたら誰も読まなくなる」とか言われるけれど、差し詰めこの本もそんな一冊である。理系の癖として、判り易くする為に(そしてその意図は論理を丹念に追う者にとっては確かにその通り)数式の展開を記す訳だが、そこで拒絶反応が起きて論理展開を追わなくなってしまった読者には、その先の理屈が解らなくなるという状況を生み出す。さすがに本書に数式は現れないが、スピノザの論理を追う為に一つひとつの言葉の定義を見定め、解釈(証明)をしていく本書の構成は、すらすらとその流れを追えるものでもない。何度も同じところを読み返しては、ああそうか、と納得するという行為が求められる(そんな苦労をしなくても読み通せる読者も居るとは思うけれど)。
『ここからスピノザは、『エチカ』においてある意味で最も有名なテーゼを導き出す。自由意志の否定、あるいは意志の自由の否定である。論証は次のように進む。虚偽の観念は何かそれを虚偽たらしめる積極的なものをもっているわけではなく、観念の混乱や欠損のゆえに虚偽である(第二部定理三三、三五)。人間は自らの自由意志によって行為しているという「意見」こそ、そのような虚偽の一例に他ならない(第二部定理三五備考)。意志の自由という考えは原因についての認識の欠損にもとづいているからである。「そうした誤った意見は、彼らがただ彼らの行動は意識する [conscius]が彼らをそれへ決定する諸原因はこれを知らない[ignarus]ということにのみ存するのである」(第二部定理三五備考)(中略)同じことは第一部の付録でも指摘されている。「彼らは自分の意欲および衝動を意識しているが彼らを衝動ないし意欲に駆る原因は知らない」(第一部付録)』―『第四章 人間の本質としての意識/自由意思の否定』
最新の科学的事実に基づく解釈によれば、人間の行動の始まりに際して、左脳を中心とした意識が立ち上がるより先に意識下の脳の活動があり、それによって次の行動が決定されるという。意識は気付くだけなのだ。著者は、これを(現代科学の新常識とスピノザの論理展開から導き出されるものの奇妙な呼応を)指摘するのだが、それによってスピノザの見立てを現代科学で権威付けするかのようでもある。そしてそんな例が幾度か出てくる。それが少しばかり気になる。基本的に著者の読みが論理的に展開するのを追うことは気持ちの良いこと(そう言えば内田樹のレヴィナス論考も似たような読書感を与えてくれる)なのだけれど、もちろん、スピノザの慧眼は当時知り得なかった科学的事実を先取りしていた可能性もあるのかも知れないけれど、それが如何に優れた観察と推量から提唱されていたものだとしても、証明可能な事実の積み重ねが在った訳ではない。なのでそんな風にスピノザを持ち上げることは行き過ぎのようにも感じるところがある。
そんなことをしなくても、スピノザの徹底した原点の定義の明確化への志向と論理展開の凄みは十分に伝わってくる。特にそれがよく表れていると思ったのは「エチカ」の執筆を中断してまで記したという「神学・政治論」で示される、エデンの園のリンゴの実の逸話だ。スピノザは神を「完全なる存在」と規定し、もしリンゴの実を食べることが真に禁忌であったのなら神はアダムがそれを食べることを容易に阻止出来た筈だ、と結論する。だとすればアダムがリンゴの実を食べたこともまた神の意図の一つであったと解釈されなければならず、そうであるなら、その行為に託された意味(神の意図)とは人間が持つ特質の表れの一つである筈で、それが自由意志への希求(欲望)あるいは好奇心ということへ繋がるのだと展開する。そこからはパンドラの箱を開けたように権威主義的教会の一般的な聖書解釈・教条との摩擦が生じるのだが、それでもスピノザは完全なる存在の神という定義とその神からアダムに託された人間の自由な意思を求める精神という特質こそ信仰なのだと主張する。それは無神論者であると非難されることへの反証であった筈だが、スピノザの聖書解釈が権威主義とは相容れない解釈であることをいよいよ明白にもしてしまう。その展開を読み説く國分の文章を辿ることは非情にスリリングである。
もちろん、本書を読んだからと言ってスピノザの哲学を理解したとは到底言い切れないが、判り易い入門書ではなく、こんな解説書を読むことで開ける地平というのも確かにあると実感させてくれる一冊だと思う。因みに、本書で得た知識を基にいわゆる一つの生成AIとスピノザについて会話したら、驚くほど面白かった、ということを記録しておこうと思う。たとえAIが神の如く振る舞ったとしても、それを面白いと思えることこそ人間の特質に違いないのだから。(この文章は、一部あるいは全て、生成AIが作成したもの、ではありません)
投稿元:
レビューを見る
『暇と退屈の倫理学』がおもしろかったので買ってみました。哲学ということで当然に覚悟してはいたものの、新書だからなんとかなるだろうとも思っていました。が、何ともなりませんでした。『エチカ』はじめスピノザの著作の解説的な内容なので、ベースがないと難解です。お経をお経で解説されている感じでした。といってもこれは読者サイドの問題なので、評価は真ん中ということで。
投稿元:
レビューを見る
新書としては分厚い。
私はスピノザの『エチカ』を畠中訳で読んだことがある程度だった。
勇気が湧いてくる本だった。また、頭のいい人が書いた人の本だった。
投稿元:
レビューを見る
『はじめてのスピノザ―自由へのエチカ』(2020年、講談社現代新書)につづいて新書で刊行された、著者のスピノザ入門書です。
本書の前半では、『デカルトの哲学原理』や『知性改善論』などの検討を通して、スピノザの哲学研究の方法に焦点をあてた解説がおこなわれています。とくに、懐疑を哲学的思索の出発点としたデカルトが、みずからを説得するようなしかたで神の存在証明を展開しているのに対して、スピノザは神についての観念を正しく形成することさえできれば神の存在にまつわる問題は解決すると考えていたことに目を向け、デカルトの方法が「分析的方法」でありスピノザの方法が「総合的方法」であるという整理がなされています。
後半では、『エチカ』や『神学・政治論』、『国家論』などの著作がとりあげられています。著者は、ドゥルーズのスピノザ解釈を参照しつつ、スピノザによる自由意志の否定の議論について考察をおこない、意志よりも欲望を人間の本質とするスピノザの立場が、意識によって完全に見通すことのできない多様な原因によってわれわれの行為が決定されているという主張に通じていることを明らかにします。さらに著者は、こうしたスピノザの倫理学とそれにもとづく国家論が、同時代の社会契約論に対してどのような関係にあったのかということについて、立ち入った考察を展開しています。
前著『はじめてのスピノザ』が、スピノザの思想を現代において読む意義について明快に語った入門書であったのに対して、本書は前著の解釈を踏襲しながら、スピノザの思想の全体像にせまることをめざした本ということができるように思います。
投稿元:
レビューを見る
伝記的事項から書き始められているので、初めは優しいが、思想的事項に内容が変わると、ついていくのしんどくなります。