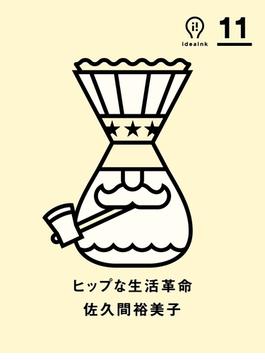0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:すたいる - この投稿者のレビュー一覧を見る
この本の冒頭で、以前読んだことがあった、ヒップ アメリカにおけるかっこよさの系譜学のことが書かれていて、興味を持ったので読んでみた。ヒップ アメリカ~はややこしくて、読んでる間もわかったようなわからないような、もやもやしながらなんとか最後まで読めた。もう読むこともないだろうなと思っていたけど、この本がなかなか興味深く読めれたので、ヒップ アメリカ~をまた読みたいなと思う。
投稿元:
レビューを見る
アメリカで起きている事、サブプライム問題が起きてそこから転換された動き出した人々の動きが新しい価値観や消費や流通の流れを生んでいる。自分でいろんなことができるようなテクノロジーが誰でも扱える時代とその流れはうまく連動している。アメリカで起きているこのヒップな生活活動は当然日本でも起きていて、でもその場所に根ざしたものだから場所ごとに発展したり起こるムーブメントだったり人々の関わりは違う。
アメリカの文化が数年遅れでやってくるという時代は過去のものだ。ここで書かれたことは同時多発的に日本でも起きている、ただ指向性やコミュニティは町や場所によって異なる。いろんな変化の兆しは大不況の煽りや今まで通りの消費社会への疑問から始まり、新しい消費が僕らの生活を変えていく。面白いことをしている人たちがいて僕らはいつでもそこに参加できる可能性がある。アメリカで起きていることは日本で参考になるし、逆もあるはずで、でもどういうコミュニティになって文化を根付いていくのかがより目に見えるのはこれからなんだろう。
生活が変われば社会は変わっていく。もっと面白いいい消費ができるようになれば今ある問題も少しは改善されていくはず。
投稿元:
レビューを見る
この本を読んで、最近無意味な消費に走り過ぎたなと少し反省したのですが、
アメリカではポートランド、ブルックリンの一部の人を中心に、食や文化が見直されているようです。
この本では、そういう人たちをヒップスターと表現しています。
身近なところで仕入れ販売することで、材料のソースが明確、作り手とのコミュニケーションが増しクオリティが向上、さらには環境にも良い。
中国で大量生産されたものを、みんなと同じように身にまとっても個性がない、そもそも愛着も湧かない。
だったら、確かなものを購入して、長い間愛着を持って使用したほうが良い。
最近、どうせ買うなら高くても良い物をと思ってはいるけど、ついつい大量生産されたものを買ってしまう自分もいる。
この本を読んで、やっぱり変わらなきゃと心から感じました。
人生のバイブル。そういったら大袈裟かもしれませんが、2-3ヶ月に一回は読み直してみようと思う本です。
http://konotokoro.com/2014/07/%E3%83%92%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AA%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9D%A9%E5%91%BD/
投稿元:
レビューを見る
最近よく聞く、ポートランド中心の西海岸の文化と、その背景について分かりやすく解説。米国ではサブプライム危機を背景に、価値観の変化が起きた。消費一辺倒の文化に抵抗し、現代のITなどもうまく取り入れつつ、自分らしく等身大の生き方を追求する「ヒップスター」文化。その最初の啓発メッセージを発信したのが、パタゴニア社のイヴォン社長だったというから納得。
いま、日本に起ころうとしていること、これからの社会作りで関わっていきたいことがまさに書かれていたから読めて良かった。アメリカの文化シフトが20年後に日本に訪れる、という説もあながち間違いじゃないのかもしれないな、と。
投稿元:
レビューを見る
DIY, オーガニック, ハンドメイド, ローカル, 若者, カルチャー, リベラル, ポートランド, LGBT
いい意味でも悪い意味でもやっぱりアメリカは先を行くのを感じた。
投稿元:
レビューを見る
PERISCOPEの人。アメリカから発せられる新しいインディペンデントなムーブメントが、どういう背景で起こっているのか取材した本。食・音楽・ファッション・クラフト・雑誌など様々なカルチャーで起こっている『ヒップ』な事象について紹介しつつ、なぜそこで起こりえたのか、どんな課題があってそれを解決していったのかを、社会背景やテクノロジーの進化の影響といった点から考察されていてよい。単純な模倣によるカルチャーの輸入はヒップじゃないのよなー。
投稿元:
レビューを見る
リーマンショック以降のアメリカで起きているという生活革命。コーヒーが美味しくなった、などの断片的な動きは知っていたけど、それが単発の動きではなく、他にも同じような変化があること、それらをまとめて「生活革命、それもヒップな生活革命」と名付けられるのだという。こうして紹介されると大きなうねりなのだと気付く。
ただし、この動きが起きているのは都会。手作り、顔の見えるつながり、効率最優先の否定、など、日本の「田舎暮らし」に通じる価値観がバックグラウンドにあるのに、その事例は都会の片隅または郊外。田舎ではない。
著者の取材の偏りという可能性は否定できないものの、都会にしかない文化が「ヒップな生活革命」を可能にしている、という側面が大きいのではないかと思う。
オープンなこと、自由なこと、価値観に基づいて集まり行動し発言できること、自分一人もしくは共働きのパートナーと二人が食べていけることだけ考えればいいこと(子供や親の養育なし)、など、田舎暮らしと都会暮らしのイイトコ取りができるのは、田舎ではなく都会なのだ。
昨年読んで消化不良になっていた『中身化する社会』がようやくつながった。
アメリカ人の生活を変えている「ヒップ」な革命とは? 佐久間裕美子さんに聞く・前編 | ライフハッカー[日本版] http://www.lifehacker.jp/2014/09/140928yumiko_sakuma.html
投稿元:
レビューを見る
自画自賛に終始する書きっぷりが鼻持ちならなくてあまりいい印象を持っていないこのシリーズだけれど、この本はその色合いがやや薄く(まったくないとは言えない)、興味深い内容だったのでそれなりにおもしろく読んだ。
現象としては、リーマンショックがもたらした経済的損失が価値観にまで影響を及ぼして、ウォール街の外で雨後の筍のごとく「小さい経済」が生じ始めている、ということらしい。
そういう流れが、食やファッションやいろんなところで起こっているよーという本。
一方で、そのムーブメントの流れの中で売られている割高な商品は、高額なファッションブランドの服を買うことや、高いレストランで食事をとることと本質的には変わっていないことにも気づかされる。
地産地消とか、無駄をなくすとか、理念はすばらしいのかもしれないけれど、ものを売る・買うという視点で考えると、実は何も進歩していない。「地産地消」「無駄をなくす」「自然に優しい」といった情報を付加価値にして割高でも買う理由を買い手に提供する。売り手は、原価コストや輸送費が低く抑えられるので利益率が向上する。
ビジネスとしては、リーマンショック前と何も変わっていない。
マーケティング手法が変わっただけのこと。
このシリーズには、物事を多面的に捉える視点が決定的に欠けている。
投稿元:
レビューを見る
ネットがこの世に登場して20年が経った。その時から大企業、大量生産の時代は終わり、草の根活動の時代になると言われていたが、なかなか実現しなかった。しかし、金融危機や大企業の海外移転等で、いわゆる従来型の仕事はなくなり、大企業が海外で低コストで製造した商品を大量に売りさばくということもできなくなってきた。そして、今従来なら時代遅れと言われていた物が再び脚光を浴びている。ネットも登場した時は、何だかんだ言いながらも大企業が牛耳っていたが、SNSやスマホの普及で、今度こそ草の根活動の時代となった。従来なら告知手段がなく、売り様のなかった商品も今なら宣伝コストもかけずに、自分のこだわり商品を、それを理解してくれる人だけに売ることができる。現状に、何か行き詰まり感を感じている時に、身近な所から、新しい事をやってみようと、勇気を与えてくれる本である。
投稿元:
レビューを見る
発行から結構たっているので、今更な話題もあったけど、まだまだ知らないネタもありつつ、、これからの生き方に参考になればと。
投稿元:
レビューを見る
現代のアメリカのライフスタイル(アメリカという括りがかなり乱暴ですが(笑))について書かれた本は、よく言うとポップで先行的な、悪く言うと軽薄で楽しければ良い、みたいな内容が多いように感じます。
『アメリカ人はバカだ。そう思っている人は少なくないかもしれません』で始まるこの本は、現代のアメリカカルチャーを牽引する人物を取り上げて、「軽薄で楽しければ良い」なんて言う僕のような人に対して、「もっと深淵な世界なのよ」とメッセージを発しています(と僕には感じられた)。
楽しい本でした。
投稿元:
レビューを見る
ヒップな人々、というネーミングが抜群。いるいるこういう人。特に、身につけるもの食べる物へのこだわりは持っていたい。
投稿元:
レビューを見る
アメリカもついに人口の中心値が40をこえてきた。すなわち中年化していく。次の世代にどうしようか?を考える人が大半をしめてくる。そして金融危機などをへて、新しい消費層が台頭。それについて整理した本。
金融危機をきっかけに「生きる」ということをあらためて考え直した人が増加。
かつてのパンクやヒッピーといったかつてのカウンターカルチャーの旗手たちとの違いは、主流と共存しながら、自分の商売や表現を通じて自己の価値観を主張していること。
こういう層をヒップ(hip)」「ヒップスター(hipster)」と命名。
無駄を出さない、責任ある食べ方」
たとえばうちでは、牛をまるごと1頭購入します。無駄がないように各店舗のシェフで肉を分け、残った皮で靴やバッグを作ります」 肉は食べる、しかしどうせ食べるのであれば、責任を持って無駄なくすべてを利用する。それがアンドリューの提唱する食べ物との付き合い方です。
ブルックリンの文化復興運動
ベンダー(売り手)の多くが少量生産の作り手で、出店希望者が跡を絶たないことからオーガニックの食材や調理の工程にこだわったベンダーが多数集まっています。
ブルックリンに食のアルティザン(職人)文化
locavore(ローカヴォア)」という言葉を耳にします。自分が暮らす地域(理想的には半径100マイル=
ニューヨーク市で急激に増えている屋上農園
CSAは「食の定期購買」とでも言えばいいのでしょうか。プログラムに参加して、毎週、毎月と決まった額を前払いすると、定期的に農家や牧場から新鮮な食材が届きます。農場から運ばれる食材は指定のピックアップ場所に届きますが、その場所は、コミュニティ精神の強いオーガニック系のカフェやグルメ食材店であることが多い
にいい食料を作ること、栄養を考えること、未来の世代のために土地を大切にすること、旬のものを食べること。こういった価値基準は、何も私のオリジナルでも、新しい考え方でもありません。ファストフード文化には、せいぜい60~80年くらいの歴史しかない。
我々が生きているこの経済は『充分ではない』という考え方に特徴づけられている」
パタゴニア」は感謝祭になると「Dont Buy This Jacket」の広告を出し続けてきまし
投稿元:
レビューを見る
ポートランドなど、アメリカの地方都市が元気な昨今、在米8年になる筆者が、現在のアメリカの動きをレポートする。オーガニック、サードウエーブコーヒーなど、注目すべき業態が増え続けている。薄い本だが、情報は多い。
投稿元:
レビューを見る
リーマン・ショック以降、アメリカに訪れた変化の波。ポートランドやブルックリンを中心に始まった、「ものに対して責任を持って向き合う」といった新しい文化。そして、それがインターネットによって加速していく様子が、沢山のキーワードや事例を通じて知ることができる一冊。