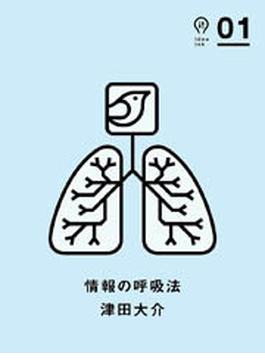- 販売開始日: 2012/11/01
- 出版社: 朝日出版社
- ISBN:9784255006215
情報の呼吸法
著者 津田大介 (著)
発信しなければ、得るものはない。ツイッターの第一人者であり、ジャーナリズムの最先端で注目を集めるメディア・アクティビスト津田大介による、超情報時代を楽しむための情報の「吸...
情報の呼吸法
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
商品説明
発信しなければ、得るものはない。
ツイッターの第一人者であり、ジャーナリズムの最先端で注目を集めるメディア・アクティビスト津田大介による、超情報時代を楽しむための情報の「吸い込み方と吐き出し方」。
フォロワーの増やし方から、信憑性のはかり方、アイデアを生む「連想ゲーム」術まで。
情報というガソリンを取り込んで、人を巻き込み、変化を引き起こすための行動型情報入門。
紙の書籍版では読めない電子版オリジナルコンテンツとして、東浩紀氏との特別対談「政治をアップデートする」を収録。
ツイッターやニコ生の先に見える政治と報道の未来、民主主義の理想=原点を語り合う。
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
書店員レビュー

私の心の奥底に、いつ...
MARUZEN&ジュンク堂書店札幌店さん
私の心の奥底に、いつも存在し続けていた知人の言葉。
「情報は自分一人で抱えていても意味がない。情報を提供することは、決して損することではない。
質の良い情報を発信すれば、質の良い読者が集まる。情報は外に出すことで、それは何倍にも大きくなり、自分の元に戻ってくる。」
それでも行動しきれずにいたのは、何かが怖かったから。見知らぬ人の批判が怖いから?
それとも、伝えたいことを的確に表現できる自信がないから・・?
『情報は発信しなければ、得るものはない』表紙の言葉に釘付けになり、本書を手にとった。
・・遅ればせながらツイッター、始めました。
PC担当

情報の選択が必要とさ...
ジュンク堂書店仙台本店さん
情報の選択が必要とされている中でツイッターの伝道師と呼ばれている著者が、莫大な情報量とのうまい付き合い方を書いている1冊。ほんの数年前までは「情報選び=媒体選び」で何を使って情報を得るのか、その媒体選択によって得られる情報は限られていた。しかしソーシャルメディアの時代となった今は「人選び」になったと著者は言います。人をどう選ぶかによって入手できる情報に違いが出てきます。原発報道もそのひとつでした。情報を発信する人を選ぶことで自分の欲しい情報により近いものを入手することができるのです。発信しなければ情報は得られない。著者のこの言葉からタイトル「情報の呼吸法」の意味が分かります。また、ソーシャルメディアを通じて人とつながり情報を得ることは、もはやひと付き合いではないでしょうか。著者自身がツイッターを介して情報を得る側と発信する側からソーシャルメディアとは何かを書いています。ソーシャルメディアをインターネットの中の一つというジャンル分けはできない、今後のメディア環境が変わっていくのだと強く認識させられる書籍です。
仙台本店 社会三塚
情報を行動につなげる方法を考える
2012/02/07 23:59
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:むらら - この投稿者のレビュー一覧を見る
情報大洪水のこの世の中、
私はTwitterもFacebookまったくやったことがないにもかかわらず、
雑誌やらネットやらテレビやらの媒体の情報で
すでに右往左往させられていたので、
いかに情報と向き合っていくべきかを考え直したくて手に取った一冊。
恥ずかしながら、著者のことは本書で初めて知ったのだが、
著者の体験談をベースにここ十数年の情報社会の変遷も知ることができ、
とても読みやすく、かつ、読みごたえがあった。
著者の情報の追い方、捨て方、信憑性の得方、自分を正しく保つ方法
など、とても参考になる。
まとめると、インプットとアウトプットのバランスを取ること、
「情報」を「行動」へ繋げること、が重要であるとのこと。
(「情報」は「行動」のためのガソリンとある。)
情報は発信しなければ、得るものはない、と言い切ってあり、
非常に考えさせられた箇所である。
提案されているソーシャルメディアによる新しい繋がりは
温かみを感じることができ、非常に共感できるものがある。
最後に、我々は情報とソーシャルメディアという新しい武器で、
未来を発明できる立場になった、自分たちの手で未来をつくろう
と綴られている。
一度読んでとても面白かった。
さらに再読して自分自身に落とし込もうと思う。
「ソーシャルキャピタル」の構築が、今後ますます重要になる!『情報の呼吸法』(津田大介著)
2012/02/03 00:34
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:まなたけ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書の内容の感想の前に、まず、本の感想を書きたいと思います。
まず、本を手にとって驚いたのが「装丁」です。私が立ち寄った書店では、アイデアインク・シリーズの2冊『情報の呼吸法 (アイデアインク)』と『ソーシャルデザイン (アイデアインク)』が並べられて置かれておりました。薄い水色と薄い黄緑の本のコントラストは、なんとも美しいものがあります。
今回読んだ『情報の呼吸法 (アイデアインク)』は、本編も薄い水色の紙に文章が書かれておりますが、見づらいということもなく、心地よい感覚で読めたので、「これはなかなか面白い装丁の本だな!」と思いました。
まだリアル書店では、渋谷や新宿など、限られた地域でしか出回っておりませんが、ツイッターなどの評判やアマゾンのランキングなどを見ると、今後の展開が楽しみなシリーズです。
2012年3月以降、続編が登場する後続の本にも期待したいと思います。
さて、本書の感想に入ります。
本書は、著者である津田大介さんの「素直な気持ちを言葉に表した本だな!」と思いました。
津田さんと言えば「tsudaる」という言葉が一世を風靡したように「ツイッターの伝道師」というイメージが強いです。
『情報の呼吸法』というタイトルが付いていたので、「ツイッターを使っての情報収集や発信について書かれた本かな?」と思いましたが、その期待は良い意味で裏切られました。
本書の内容を大きく分けると「津田さんが今までどのように考え、行動してきたのか?(音楽との関わり、ジャーナリスト生活、ツイッターとの出会い、震災後の思い、なぜメルマガでの発信など)」、「これからの情報社会を生き抜くために必要なことは何なのか(ソーシャルキャピタルの構築・棚卸・マネタイズなど))に大別できると思います。
しかしながら、そこで述べられている言葉はいたって自然。いわゆるビジネス書にありがちな「固い論調」というものではなく、平易な言葉で、津田さんの思いを自然に読者に語りかけるような感覚で書かれているため、本を通じて津田さんの思いを共有しやすいのではないかと感じます。
本書を読む中で注目したのは「人への着目」そして「ソーシャルキャピタル」という言葉でした。
「人に着目する」について、まずは私がツイッターやfacebookなどでどのように情報に接するのかを振り返ってみたので、まずはそれについて述べたいと思います。
私がツイッターやfacebookで情報に接するとき、大きくは以下の2つで行います。
1)タイムラインを眺めて、ピンと来た情報を拾い集める
2)特定の人の発言に注目し、ピンと来た情報を拾い集める
そして、上記2つのやり方は、多くの方がツイッターやSNSなどで情報を参照したいときに行っているのではないでしょうか。
ここで注目したいのは「2)特定の人の発言に注目し、ピンと来た情報を拾い集める」というやり方です。
「特定の人の発言に注目する」時、たとえ著名人でなくとも、常時「いい情報を発信しているな!」と思うと、自然に注目してしまいます。そして、これらの行動は、情報過多の現代において、「必然的な流れ」になってきております。いわゆる「インフルエンサー」と呼ばれる方は、良質な情報を発信し続けることで信頼を集め、「ソーシャルキャピタル」を構築してきたと思います。
私は本書を通じて「“ソーシャルキャピタル”という言葉は『7つの習慣』で言っている「信頼残高」と同義ではないか?」と思いました。
『7つの習慣』では「信頼残高」について以下のように述べております。
「銀行口座がどういうものであるかは、誰もが知っているだろう。口座にお金を預け入れることで貯えができ、必要に応じてそこから引き出すことができる。それと同じように、信頼口座つまり信頼残高とは、ある関係において築かれた信頼のレベルを表す比喩表現であり、言い換えれば、その人に接する安心感ともいえるだろう。」
(スティーブン・R・コヴィー著『7つの習慣』より)
本書を読んで、「ソーシャルキャピタル」を構築する上で重要なことは「エンゲージメント」ではないかと思います。それは先日読んだ、佐々木俊尚さんの著書『キュレーションの時代 「つながり」の情報革命が始まる (ちくま新書)』と相通ずるものがあります。
「エンゲージメントという関係の中では、「企業か個人か」といった「だれが主体なのか」という枠組みは融解していきます。言い換えれば、企業も個人もひとつの独立したキャラクターとして人格を持って語らなければ、エンゲージメントをだれかと生み出すことができない。自分自身の言葉で語っている存在だけが、お互いにエンゲージメントによってつながることができるのです。
(中略)
企業か個人か、という問題ではないのです。そこに人間らしさがあるか、自分の言葉で語っているかということが、エンゲージメントを形成してお互いにリスペクトを感じるためには絶対に必要だということなのです。」
(佐々木俊尚著『キュレーションの時代 「つながり」の情報革命が始まる (ちくま新書)』より)
「情報は、我々にとって空気のごとく不可欠な存在となった」と思っております。しかし、現代は「情報過多の時代」です。そのような中、「我々は、どのように情報と接していけばよいのか?」ということが課題となってまいります。『情報の呼吸法』というタイトルには、「情報とどのように接したらよいのか?改めて考えてみよう」という意味も込められて付けられたような気がしております。
「ソーシャルキャピタルの構築の重要性」をはじめ、本書は情報過多の現代を呼吸していくための大きなヒントを与えてくれる本です。
情報のインプットとアウトプット...もはや、それを呼吸するかのように成す時代。
2020/11/30 13:42
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:タオミチル - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書はすごく薄い本で、総ページも165ページ。あっという間に読めちゃうなと思って手にとったが、内容は示唆に富む。最後まで楽しく読めて、新しいメディアの水先案内人をやってもらったような読後感があります。