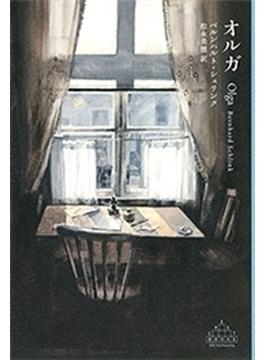現代史への一視点
2020/10/29 15:48
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:執事のひつじ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書「あとがき」によると、主人公オルガの恋人ヘルベルト・シュレーダーには同名のモデルがいるという。すると、(作中ではオルガの死後になって)、ヘルベルトの足跡を求めて北極圏に遠征隊が赴いたというのも史実なのだろう。作者はこれをきっかけにヘルベルトに関心を持ち、彼への愛と拒否を抱き続けるオルガという人物を創造して対置したのかもしれない。
ヘルベルトもオルガも独立不羈の人物であって、与えられた境遇に甘んじることなく、自己を超えていこうとするが、貧しいオルガが苦学して教員となり、地に足のついた生活を営み、公正な社会を求めるのに対し、大農場主の息子ヘルベルトは遥かなものへの憧憬をドイツ国家拡大の野望と同致させ、広大な砂漠や極地への探検行に明け暮れるようになる。神は存在しない、では無限は?永遠は?と問うヘルベルトのうちに、オルガは「彼自身がまだ知らない絶望」を感じ取る。第1次世界大戦を前にヘルベルトが北極圏で消息を絶ったのち、彼女はヘルベルトが虚無の中に自己を消したがっていたのだと考えるようになる。
(日本人にとって無との合一はむしろ安らぎであるが、もちろんそれとは違い、自己と世界の有限性を超克しようとするロマン主義的情熱の行きつく果ての光景である。だがどちらも、若者たちを戦死に突き進ませる原動力の一部となったのかもしれない。)
オルガは「偉大なドイツ」という夢想の空疎さや誇大さを非難し、長い間祖国(統一国家)を持たなかったドイツの歴史にその原因を帰しているが、当時の先進諸国はどこも広大な植民地を持ったり求めたりしていたわけで、もちろん日本も例外ではない。(現代においても、主に経済分野に領域を移しているとはいえ、状況はあまり変わっていないとも言える。)うろ覚えなのだが、昭和10年ころの子供たちへの「将来なりたいもの」を問うアンケートに、女子を含め多くの子供が「偉人」と答えていた・・・という記述を、30年ほど前の『中央公論』誌上の論文で読んだことがある。「偉大さ」に憑かれていた点で日本人も同じであった。オルガの批判には普遍性があると言えるだろう。
オルガは返す刀で孫世代の学生運動をも批判し、「自分たちの問題を解決する代わりに、世界を救おうとしている」「守られていて、道徳的であるために犠牲を払う必要もないのに、自分たちを勇敢だと思って威張りくさっている」として、「大きすぎる目標」を掲げている点で同様だと断じる。グローバル化が進み、絶えず「情報」を送受信しイメージによって思考してしまう我々にもこの批判は痛い。
重いテーマを扱っているが、読後感が明るいのは、逆境を乗り越えていくオルガの強さによるところが大きいが、風景描写の美しさも一因だろう。オルガが最後にとった行動とその結末については、見方が分かれるかもしれないが、私はアイロニカルなユーモアを感じ取った。
近代ドイツの運命と共に生きたある女性の物語
2020/07/15 17:45
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Takeshita - この投稿者のレビュー一覧を見る
名編「朗読者」の作家ベルンハルト、シュリンクの最新作。19世紀末東プロシァの農民の娘に生まれたオルガは貧苦の中苦学して師範学校を出て教師となるが、身分の違いから結婚が許されなかった恋人と、その後可愛がった友人の息子は冒険とナチズムと戦争のため悲惨な生涯を送る。オルガの生涯もまた悲しみに満ちたものとなるが、最後に主人公の「ぼく」がその秘密を解き明かす。ストーリーの展開は巧みで一気に読ませるが、なにぶんテーマが広く、かつドイツの運命と言う重いものであるためもっと長編小説にするきだった。シュリンクはやや軽めに描きすぎたと思う。「朗読者」ほどの読後の感動はない。
投稿元:
レビューを見る
個人の葛藤と世代的トラウマが折り重なる。
苦痛と困難の時代。
世界大戦、戦間期、再びの大戦、戦後。
近代から現代へ急速な変貌、それはオルガにとっても、彼女の世代にとっても苦痛と喪失を伴うものだった。
この物語に言うべき言葉はあまり見つからない。
喪失を乗り越えるために必死に生き、届くはずのない手紙を送るオルガ。
歴史は語られるものであって、読み解かれるものになる。
翻訳あとがき(松永美穂氏)の引用『「シュリンクは不愉快な問いを投げかけることを忘れない」』
まさしく、葛藤とは直面化したくないものだ。
しかし、その葛藤から洞察を得たいと思うのも健全な人間の文化だとも思う。
物語の構成はゲーテの『若きウェルテルの悩み』のように、語り部が変化する。
そして、オルガの人生の全容が明らかになる。
葛藤への苦しい直面化のために、こうした物語が作られ、それを読む事ができることに感謝。
投稿元:
レビューを見る
偉大なるドイツの幻影を追い求め、若くして北の果てに消えた恋人。彼を想い続けながら、激動の時代を力強く生き抜いた一人の女性。残された手紙が明らかにする彼女の秘められた激情、秘密、死の真相。ささやかな幸福を追い求めながらも男の従属物となることを拒み続けた彼女の心の叫びが静かに胸を打つ逸品。
投稿元:
レビューを見る
格調高い文学の香りに包まれました。一生ヘルベルトへの愛を貫いたオルガは幸せですね。手紙一通一通から熱い思いが伝わります。腹を立て喧嘩するからこそパートナー、、オルガに教えられました。夫とはしっかりパートナーだったんだな。戦争を絡めて人の強い意志をあぶり出す、朗読者でも感じたことです。久しぶりにシュリンク氏の著作を読み、久しぶりにその魅力に浸れました。しばらく強く生きられそうです。
投稿元:
レビューを見る
両親の死で祖母に愛なく育てられたオルガと金持ちの農場主の息子ヘルベルト.二人の友情が愛に育つ純愛と大きな物への果てしない欲望,探検,侵略,戦争.困難な時代を逞しく愛しながら生き抜いたオルガの記録.オルガの時代や流行にとらわれない真実を見つめて揺るがない生き方は素晴らしい.オルガから届くことのなかった手紙で構成された第3部によって露わになる真実に驚かされ,二人の間に流れていた珠玉の情愛に感動した.
投稿元:
レビューを見る
遠く離れて時折にしか会えない人を、どうやって思い続け心を通い合わせることが出来るのだろう。そして会うことも叶わなくなった亡き人を。
静かで強い。既読がつかなかったり返信がないだけで一喜一憂するような現代からは遠い強さ。多分、相手や相手との関係というより、自分自身の強さなのだろうな。
オルガにも不安や悲しみや眠れない夜はたくさんあったはずで、そしてそれはその時代の女性たちには珍しいことではなかったはず、とも思う。
我が身を問われる思い。
投稿元:
レビューを見る
19世期から20世紀の激動のドイツを生きたひとりの女性オルガ。
身分や性別、戦争によって翻弄されながらも常に姿勢を正して毅然と生きる彼女の半生が淡々と語られる第一部。
中年になった彼女が裁縫師として雇われた牧師一家の末息子「ぼく」によって、晩年のオルガについて語られる第二部。
そして第三部は書簡小説。1913年から1971年までにオルガが書き残した手紙によって全てが明かされて行く。
私のうすっぺらな言語能力ではこの物語の素晴らしさは到底伝えきれないから、ひとつだけ。
気丈で、賢く、自分を貫いて生きた強いオルガが望んでいた幸せのささやかさを知って胸が苦しかった。
堪えきれず嗚咽した箇所を、外出先で読んでいる時でなくて幸いでした。
投稿元:
レビューを見る
楽しみにしていた本作。
他作にも通ずる、一人で生きざるを得なかった女性が身につけた強さ、裏にある葛藤が描かれていた。
私のペラペラな感想なんてどうでもよいので、人類全員に読んでもらいたいと読後の余韻の中で思う。
訳も良い。
投稿元:
レビューを見る
オルガというポーランド系ドイツ人女性の人生を、第一部では主人公にして物語られ、次に彼女と親しくなった「ぼく」がその後のオルガとのかかわりを描き、第三部で、オルガ自身の書簡によって彼女の心の声を聴くことができます。戻ってはこない恋人にあてた手紙を、オルガの本当の人生を垣間見るよう気持ちで、主人公と共に次々と封を切って読みました。貧しい農村の生まれでありながら、誰にも頼らず一人で生き、第二次世界大戦を得ても自分の信念を曲げずに強く生きた女性。なんて強い人なんでしょう。最後の書簡ですべての謎が解ける仕組みに引き込まれて、飽きることなく読めました。心に残る作品です。
投稿元:
レビューを見る
とても読みやすかった。程よいところでパラグラフが区切られ、描写が端的。心地よいリズムで読み進められる。これがシュリンクか。内容は、20世紀前半の怒涛のドイツ史に主人公女性の人生が翻弄される、というもの。ある意味でドイツ版朝ドラだ。いや、違うんだけど。でも、私にとってこの主人公女性は、朝ドラヒロインくらいの重みしか感じられなかった。作りものっぽさが拭えないというか。でも、裏テーマであるドイツ論については、考えさせられることが多かった。ドイツ自体が持つ悲劇性。ある意味で主人公はドイツだったのかも。
投稿元:
レビューを見る
第一章、淡白で短い文章が続き感情移入できず読み難くて、『朗読者』の著者と訳者なのにおかしいなと思ってたら、章の最後に転換が仕掛けられてて、第二・三章に入るとオルガとヘルベルトのことが第一章とは違った角度から見られるのが面白く、先が楽しみで一気読み。オルガの人生は徹頭徹尾ヘルベルトへの愛の為にあった。最後の行動は、思想信条も背景にあるだろうが、それ以上にヘルベルトへの愛ゆえだったのだろう。家族に恵まれなくても、近くに寄り添う人々がずっといたのに、それでも彼女の人生にはヘルベルトしかいなかったのだろう。
古い手紙のコレクターの話が出てきて、ここでも『その姿の消し方』を思い出した。
投稿元:
レビューを見る
"墓地を歩くのが好きな理由は、ここではすべての人が対等だから、とのことだった。強者も弱者も、貧者も富者も、愛された者も心にかけてもらえなかった者も、成功した者も、破滅した者も。霊廟や天使の像や大きな墓石も関係ない。みんな同じように死んでいて、もはや偉大であることもできないし、偉大すぎることなんてぜんぜんない。"(p.102)
"沈黙は学べるのだ――沈黙に含まれる、待機の姿勢によって。"(p.119)
"要求は出さず、期待もせず、一番いいのは、言葉では何も言わないことです。"(p.170)
"雪や氷、武器や戦争――あなたたち男は、そういったものなら扱えると思っているけれど、一人の女の質問には耐えられないのです。"(p.213)
投稿元:
レビューを見る
『オルガは一九五〇年代の初めにあちこち走り回って、失われた書類や破壊された記録を見つ出し、プロイセンでかつて勤めた国民学校教師として、自分に権利のあったちょっとした年金をもらえるようになった。それからは、ぼくたちの家でだけ、縫い物をするようになった』―『第一部』
ドイツの起こした戦争を背景に物語を描くベルンハルト・シュリンクは多くを語らないことで善悪の色彩を物語に鮮明に付さないままに描く。戦争の悲惨さを敢えて正面から描写しないことは、市井の人々にとっての戦争が如何なるものであったかを深く語り得る大きな力なのだが、時として戦争そのものを直視するのを避けるように描かれるのには何か良からぬ思想を肯定している意図があるかのようにも見え、例えばハンナ・アーレントのような批評の目には責任を回避しているとも捉えられかねないと思ってみたりもする。そして、その不穏さに気圧される感じが新作を手にすることを、時に躊躇わせることもある。
「オルガ」でも、戦争そのものは描かれないままに、第一次世界大戦前から第二次世界大戦後までの時間の流れの中を生きた一人の女性(オルガ)と、三人の世代の異なる男性(ヘルベルト、アイク、フェルディナント)との交流が描かれる。特に幼い少年と主人公オルガの交流は「朗読者」の構図を思い出させるが、その構図の導入は見事な仕掛けによって為され、効果的に記される一人称の代名詞によってそれまで描かれていた二十五の断章の意味はがらりと変化するのを目の当たりにする。その変化を認識して初めて、短く素っ気なく細切れに描写されたオルガの六十余年の人生譚が、伝え聞いた話を繋げたものから成っていたのだと判り、はっと胸を突かれたような感慨に浸ることになるのだ。
そこから始まる第二部は、一人称のフェルディナント自身の思い出の中のオルガの生き生きとそた描写。しかし、主人公にとってオルガとの思い出が如何に何ものにも代え難いものであるのかが訥々と語られても、不幸な事故によってオルガの人生に終止符が打たれたことが告げられた後は、急に物語の重力の中心が失われてしまったかのような印象が(それもまた作家の張り巡らせた伏線の一つなのだが)生まれる。不幸な環境に生まれ育ち自分自身の力で困難な時を生き抜いた女性ではあることは確かに伝わってくるが、そこからはむしろフェルディナント自身の不幸な身の上話に話が移っていくかのような展開。オルガのことは何処へ?と思わず問うてしまう仕組みがそこにはある。しかしその先に「朗読者」と同じように過去の歴史への探索と埋もれていた謎についての再認識、という展開が待ち受けている。
訳者あとがきでも述べられているように、最終章である第三部で待っているのは、物語の中心にありながら多くを語らない女性というシュリンクの小説の定番を覆して、自らの心情を書き連ねた言葉の洪水。その中で明かされる幾つもの真実。時間と共に変化することとしないこと。読む者は、それを既に語られた時間の経過と照らし合わせて読むことで、物語の流れを再び辿り、幾つもの伏線を(もしかしたらそれは、過剰に、と言うべきかも知れない)紐解いていくことになる���
例えば木内昇の時代小説が決して歴史の因果関係を語らないと感じるように、ベルンハルト・シュリンクもまた決まり切った歴史観に批評されるような物語を描かない。一人ひとりの人生の中に地政学的な歴史の必然という法則の入り込む余地は無いこと、その抗し難い時代の律動を背景にした個人の生活だけがどこまでも現実として存在すること、そんなことにこの作家は拘っているのかも知れない。
投稿元:
レビューを見る
第一次大戦前のドイツ、祖母に引き取られたオルガは、農園主の息子ヘルベルトと仲良くなるが、農園主に反対される。ヘルベルトは英雄を夢見て北極圏の冒険に出かけるが、音信不通になってしまう。オルガは、祖母の反対を押し切り師範学校へ行き教師になる。行方のわからないヘルベルトに局留めの手紙を書きながら、オルガは第二次世界大戦を迎える。
第一部は、オルガとヘルベルトの若い日々と、ヘルベルトがいなくなったあとのオルガの日々をオルガが語る。
第二部は、大戦後オルガが親しくし家で裁縫をしていた家庭の息子フェルディナンドが、年老いたオルガを語る。
第三部は、オルガの死後フェルディナンドが手に入れたオルガのヘルベルトへの手紙により、オルガだけが知る真実が明かされる。
苦難の時代を果敢に生き抜いたオルガ。ドイツという国がたどった時代の中でのオルガの決断にあ然としてしまう。