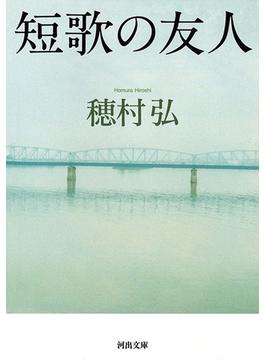歌人・穂村弘氏による初めての歌論集です!
2020/06/27 10:48
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、『シンジケート』や『手紙魔まみ、夏の引越し(ウサギ連れ)』などの歌集を発表しておられる歌人の穂村弘氏の初の歌論集です。同書では、長年、歌人として、歌を作り、歌を読み続けてきた作者が、今一度、歌について考えた一冊です。同書には、様々な歌人たちによって謳われた短歌の背後にある世界の面白さを味わえるためのヒントが述べられています。同書の内容構成は、「第1章 短歌の感触」、「第2章 口語短歌の現在」、「第3章 リアルの構造」、「第4章 リアリティの変容」、「第5章 前衛短歌から現代短歌へ」、「第6章 短歌と私」、「第7章 歌人論」となっており、短歌の深い奥底が垣間見られます!
短歌の世界に補助線を引く
2023/07/23 15:56
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぷー - この投稿者のレビュー一覧を見る
穂村弘の「読み」は、うっかり取りこぼしてしまいそうな短歌の輪郭を明確にし、図形問題に補助線を引くように、読者の理解を深めるように感じられます。このことは『短歌ください』の評でもどなたかが言われていたことなので私のオリジナルな感想ではありませんが、穂村弘の短歌評論を端的に表現していると思います。
斬新さを求めてはいけない。
2021/06/03 10:40
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:鶴 - この投稿者のレビュー一覧を見る
穂村弘さんが好きで、現代短歌について知りたいと思い、購入したが、やや緩慢な印象を受ける。章ごとに同じような話が繰り返され、内容も論文のように理路整然とはしていない。そのためか、なかなか頭に入らず、結局はわずかな情報しか残らない。現代短歌を語るのであれば、章を年代順にしたり、より多様性のあるトピックで紹介したりしてほしかった。
投稿元:
レビューを見る
短歌って面白い、と素直に思わせてくれる。引用している歌も素敵だし、各章で重複しているのがむしろいろいろな視点からの楽しみ方に気付かせてくれてよかった。
投稿元:
レビューを見る
難しい部分もあるが全体的には面白かった。いかに自分が短歌の世界に疎いかを痛感。引用されている歌人のほとんどが知らない名前。まあ「サラダ記念日」(俵万智)から一気に「渡辺のわたし」(斉藤斎藤)に跳んだ空白の20年間は如何ともしがたいか。
投稿元:
レビューを見る
ダ・ヴィンチの「短歌をください」がだいすきなのに
穂村さんがいままで歌人の仕事ちゃんとしてる本はじめて読んだ
おもしろいおじさんだと思ったらむずかしいことばつかってなんてなんだかへんなかんじ~ってのが第一印象(←超失礼´▽`;)
短歌はみてるのはすきだけど自分じゃあ詠めないな~
なんか作曲とかと似てる気がする ちなみにわたしは作曲が全くできません というどうでもいい情報
センスというか短歌のための回路が一部のひとにしかないんだろうなって感じちゃう
57577のあいだにいかに濃縮したことばをつめこむかとか
そのことばにしたって原稿用紙に意味全部書いてもおんなじ意味になるかっていうとそうでもないし
やっぱりセンスだよねー
音がぽんぽんなるのも楽しい!
なかの難しい言葉はひとつもおぼえられなかったけど
もう1回ゆっくり読めばわかるかな~
投稿元:
レビューを見る
穂村さんの短歌論。超日常感覚による日常の切り取り、リアリティを歌うということ、酸欠状態。面白く読めた。与謝野晶子と斎藤茂吉を読んで見たくなった。(2012/1/22)
投稿元:
レビューを見る
歌論というものを初めて読む。この人にとって、あるいは歌人にとって、歌というものはそうゆうものなのか。「ひとつのものがかたちをかえてるだけ」。個人的に色々示唆されるものが多い。引用されてる歌集を読んでみたくなった。
投稿元:
レビューを見る
エッセイしか読んでなかった人が読むと衝撃。
穂村さんのすごさが分かる。
短歌ってこんなに面白い。
投稿元:
レビューを見る
あまりにもいろいろ考えて、ウンウン唸ったあげく、感想がまとまらなかったので、ずっと放置してきた。読み返してもうまく言葉にならないので、しばらくこのままにしよう。未レビューが1件という表示が何となく気になるので、とりあえずこれを感想ということに。
投稿元:
レビューを見る
堅い歌論集というよりエッセイに近い軽さと短い文章を集めた本。その性質から引用されている短歌や趣旨がダブるものがおおい。選んだ短歌の説明や技術を分かりやすく説明してくれる。また文芸評論の入門書だと思う。各論考が短く参照する作品そのもの(短歌だから可能なこと)が全文引用されていて、作品をつかって自分の言いたいことを表現されていくのはスリリングだ。作品だけではなくて作品が生み出される時代性と変化を語る。ハッと思うところがいくつもあった。あまり馴染みがない現代短歌の名作?が収められていてまとめて読めるのはいい。
投稿元:
レビューを見る
穂村さんの短歌の評論をまとめたもの。つまりは短歌の評論集なのであるが、現代における「創作」の表現評論として読んでもとても面白かった。
「一人称の文芸」である短歌の特異さ、およびその<詠み>と<読み>について、穂村さんはじっくりと、しかし鋭く評論を重ねていく。
特に、現代の若い世代=現時点で30代以下? くらいの歌人の歌への評論は、その身体感覚……というか、世界認識感覚、を見事に言い表していると感じた。
私は現在24歳である。つまりはこの本で言われる現代の若い世代と同年代だ。しかし、この評論集に引用された「棒立ちの感情」の歌たちを読むと、そのあまりの絶望感に、私もぞっとしてしまった。
あの青い電車にもしもぶつかればはね飛ばされたりするんだろうな 永井祐
たすけて枝毛姉さんたすけて西川毛布のタグたすけて夜中になで回す顔 飯田有子
牛乳のパックの口を開けたもう死んでもいいというくらい完璧に 中澤系
どうしてこんなにさびしいのだろう。それに増して、どうしてこれらの歌をこんなにも「怖い」と思うのだろう。
これらの歌に共通する感覚を、穂村さんは
「「うた」としての過剰な棒立ち感」
「自己意識そのもののフラット化」
「「今」を生き延びるための武装解除」
などと言った言葉で読み解いていく。ああ、そうなのかぁ、というよりは、ああ、そうなんですそうなんです、と思ったあたり、私も「彼ら」と同じなのかなぁ、とも思う。
そしてこの評論集を読んでもう一つ強く感じたことは、短歌という文芸における「戦後」というものの大きさ、である。
短歌を読む際、私はいわゆる戦争(あるいは「戦後」)を読んだ「戦争短歌」について全く感想が書けず、むしろ書きたくないとさえ思ってしまうことにひどい戸惑いを覚えていた。それはさらに短歌や短歌の評論集を読むうちに、短歌が持つ文芸としての特異性(「一人称の文芸」というのはとてもしっくりきた)に関係があるからなのか、な? という考えがけっこう納得できたので、ちょっと落ち着いたのだが、それだけではないみたいだな、と穂村さんの評を読んで思った。
それは<背景>なのかな、と私は思っていたのだ。つまり、短歌とそれを読む歌人にとって、戦争(あるいは戦後)というのは、その人のバックボーンになっているものなのかな、と。
しかしどうも、違ったようだ、と私は思ったのである。どうやら戦争というのは、そして戦後というのは、<時間>のことらしいのである。
その時代を生きた、のではなく、その<時間>を生きた、ということが、私にはわからない。それが個人にとって、その時のその人そのものであったということが、わからない。その重さが、真実味が、わからない。
だから私はこれからも、戦争および戦後短歌に、戸惑い続けるんだろうなぁ、と思う。
投稿元:
レビューを見る
穂村弘の短歌評論。
目からウロコがボロボロ落ちる、そして理由はわからないけどぐっとくるのである。
後半は少々小難しい印象だったが、内容として抜群。
最初から最後まで短歌の話だけれど、表現すること、伝えること、感じること、生きること、あらゆる要素が詰まっている。
心を豊かにしてくれる一冊である。
生の一回性というのがこの本に限らず、貫くキーワードな気がした。
やっぱりほむほむ天才。
投稿元:
レビューを見る
平成の歌人をとりあげ、紹介している。
今橋愛と俵万智と与謝野晶子の比較も興味深い。
短歌は庶民のもので、詩は宇宙人のものらしい。
ことばを軽くにぎること、小さな些細なことが創作物に現実感をあたえること。表現の参考になった。
投稿元:
レビューを見る
短歌論。与謝野晶子、斎藤茂吉の時代から現代に至るまで、様々な時代の短歌が取り上げられている。これまで短歌に触れた経験がなかったので、一つ一つの作品が新鮮で面白かった。短歌は言葉遊びやパズルの印象が強かったけど、作者の世界を見る視点、観察眼を垣間見る楽しみもあることを知った。