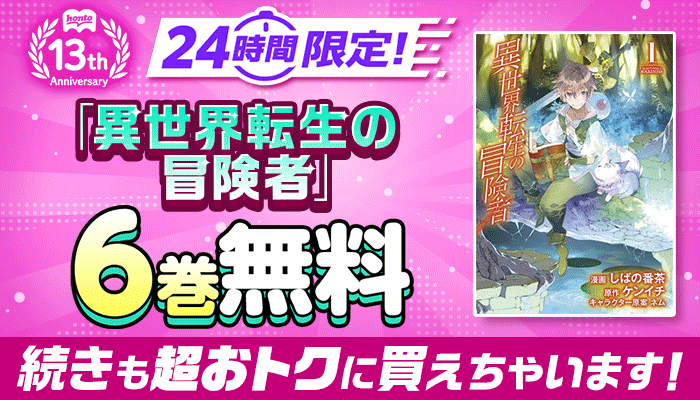- みんなの評価
 2件
2件
創造の方法学
著者 著:高根正昭
西欧文化の輸入に頼り、「いかに知るか」ではなく、「何を知るか」だけが重んじられてきた日本では、問題解決のための論理はいつも背後に退けられてきた。本書は、「なぜ」という問いかけから始まり、仮説を経験的事実の裏づけで、いかに検証していくかの道筋を提示していく。情報洪水のなかで、知的創造はいかにしたら可能なのだろうか。著者みずからの体験をとおして語る画期的な理論構築法が誕生した。(講談社現代新書)
創造の方法学
05/22まで通常869円
税込 608 円 5ptワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
創造の方法学
2009/03/28 00:27
新書のロングセラーにはずれなし
9人中、9人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:拾得 - この投稿者のレビュー一覧を見る
手元にあるものは、2004年29刷。1979年刊行なので、ほぼ毎年増刷していることになる。タイトルから推測して、新書に多い「知的生産」系列の本かと思い、ちょっと手をのばしてみた。
よく知られていることだとは思うのだが、梅棹『知的生産の技術』以来、新書には類書が多く、ロングセラーも多い。川喜田『発想法』、板坂『考える技術・書く技術』、野口『超整理法』など。先頃亡くなった加藤周一氏にも『読書術』という若い頃の名作ハウツー本があるが、これも最初はカッパの本である。いずれも、ハウツーの体裁をとりながらも、自身の考え方をきちんと書き込んでいるせいか、読むだけでも面白い。
本書もその系譜に属すようなものかと思ったら、著者の専門である社会学をベースに、「研究方法」についてまとめたものであった。また、冒頭から著者の研究歴以上に、運動遍歴も語られ、正直、思い入れたっぷりの話でも読まされるのかとつい感じてしまった。
しかし、そのはじまりを覆す面白さであった。日本での運動・研究者生活から、アメリカでの研究生活まで、その個人研究史にそって話は進められるものの、因果関係、理論と資料、デュルケームの「自殺論」、数量アプローチ、質的方法、ウェーバー、さらにはベラーやジャーナリズムまで、社会学徒に必要な方法論(もしくは考え方)のエッセンスを手際よくまとめてくれている。基本は社会学ではあるものの、社会学に関心はなくとも、この明快さは他の多くの分野の人にも役立つことだろう。
とりわけ感心したのは、二変量解析、多変量解析を説明する際に、パンチカードを使って説明していることである。本書刊行時にもすでにパンチカードは時代遅れのものになっていたようだが、「考え方」を解説するには視覚的でわかりやすくなっていることに驚いた。近年のPCとプログラムの普及とで多変量解析は劇的に広がっているが、その考え方が十分に理解されているかどうかはまた別の問題である。数式になじみのない文系学生には有り難い味方だろう。
当初の見込みとはずいぶんと異なる本ではあったのだが、新書のロングセラーにはずれなし、という感想はゆるぎのないものでもあった。ちなみに略歴をみると著者は81年に50歳で亡くなられている。本書がロングセラーとなることを見ることなく急逝されたのだろうか。合掌。
創造の方法学
2017/07/31 20:46
素晴らしい
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なえ - この投稿者のレビュー一覧を見る
研究の方法を学びたい方にとっては必読と言える本。
方法論に関してきれいにまとまって解説してあります。
方法論における1番の名著だと思います。素晴らしい古典。