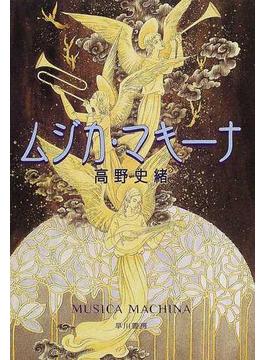紙の本
音楽と歴史とSFとをまとめて小説にしたら
2002/05/22 17:27
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ざきこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
最上の音楽とはいかなるものであろうか?
生まれる前に聞いていたであろう調べ、天上の音楽とはいかなるものであろうか?
それを、人の手によってこの世界に現すことはできないのであろうか……?
時は1870年。ベルンシュタイン公爵は、一人の少女を預かっていた。マリアと名付けたその少女は、彼にとって、最上の音楽を奏でる者を見つけだすための判断基準だった。
その公爵は訪問先のウィーンで、麻薬<魔笛>の流行を知った。それは聴覚から入ってくる音の刺激を快楽に変える麻薬。しかし、それはかつて自身が戦争時に命じて作らせ、副作用のあまりのひどさに完全破棄させた、とある薬と薬効が酷似していた。密かに彼は調査を開始する。
一方で、最上の音楽のために有能な音楽家を捜し求めている公爵は、ウィーン・フィルを振る若き音楽家フランツをマリアに引き合わせた。フランツは彼女とともにいることで天啓とも言うべき直感を得るが、彼の指揮にオーケストラは従わず、理想と現実の狭間で悶々とする。
公爵の庇護を得る約束も留保され、落ち込んだフランツの前に現れたのは、ウィーンで絶大な人気を誇る舞踏場の支配人。彼らが体感させた「理想の」音楽にのめり込み、フランツは彼らと共に英国へ姿を消す。そこで彼が体験したものは……
復刊ドットコムで得票を得て、復刊された作品。高野史緒のデビュー作でもある。日本ファンタジーノベル大賞最終候補作。
その筆致の勢いと内容の濃さで一気に読ませ、魅せる。
19世紀後半のあの時期に、どれだけ大脳生理学やらなんやらが発達していたかという学問的時代考証はよくわからないからおいておくとして、この話の発想に驚かされる。
その意味で、歴史SF小説と言えるかもしれない。
音楽と歴史とSFを一緒に小説にしたらこうなった、という感じ(良い意味で)。
とにかく、一読といわず何度でも再読する価値がある作品。
とくに音楽好きなら。
あの大音楽家ブルックナー教授も、重要な役回りを与えられて活躍しています。
紙の本
架空歴史舞台に展開する切ない音楽SF
2002/10/18 07:03
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Okawa@風の十二方位 - この投稿者のレビュー一覧を見る
「19世紀のウィーン、音楽シーンが古典派・ロマン派の時代を経て、今のポップスともどこか相通じる、ダンスのためのミュージックが流行していく時代。そんなウィーンで、ある黒い噂が流れる。音楽を絶対的な快楽に変えるという魔笛という名の麻薬。そしてその震源地は不可思議な技術を売りにした舞踏場プレジャードームだという。その麻薬を追い、プロイセンから赴いたベルシュタイン公爵は調査を開始する」。
あなたは何か一つでも楽器を演奏されたことがありますか?
もしそうであれば、自分の内なるメロディーと楽器が奏でるメロディーがぴったり一致した時の快感を体験されているはず。我々の内なるメロディー、理想の音楽はそれだけで我々を至福へと導く存在なのです。作品にも次々と登場する音楽家達が求めてやまなかった理想の音楽。その天上の音楽への切ないほどの憧れが、常に物語の背景に響いています。そんな詩的物語世界に、SFのみならず架空歴史的な要素が上手くリミックスされて、ラストに到るまでに次々と驚くような舞台が展開されていきます。お読みになれば、私が、なぜクラシックをこんな風な書き方で紹介しているかお分かりなるでしょう。
そしてラストシーン、理想の音楽への憧れは結実するのです、深い余韻を残して。
プロットは探偵冒険ものの要素があって実にスピーディーな展開、渋い探偵役の美形貴族・ベルンシュタイン公爵もかっこいいですし(なぜか某少佐のイメージが浮かびましたが(笑))、エンターテイメント性も高いです。
音楽好きの方であれば、特にお勧めの一冊!
投稿元:
レビューを見る
中世×クラシック×テクノ! プロットや世界観が非常におもしろいだけに、もちっと色気がほしいなと欲張りなことを思っちゃう。
投稿元:
レビューを見る
1870年、ナポレオン帝国が力を失ったヨーロッパ。
ウィーン音楽家達の間で密かに流行している麻薬『魔笛』。
ベルンシュタイン公爵は魔笛の特徴が、戦時中に開発させたものの
精神に重大な後遺症を残し、やがて廃人になることがわかり
すべてを廃棄したはずだった『イズラフェル』に酷似していると気付く。
魔笛の流行と重なるように出現した舞踏場:プレジャー・ドーム
プレジャー・ドームの常連客に多い中毒患者。
ベルンシュタインに預けられた音楽にしか反応しない
ミューズ(舞踏と合唱叙情詩の女神):マリア。
才能がありながら認められないウィーンフィルの若き指揮者フランツ。
相次ぐ音楽家の失踪と怪死。
『機械の音楽(ムジカ・マキーナ)』とは?
廃棄されたはずの魔笛(イズラフェル)の出所は?
巧みに仕組まれ、細部にわたって計算され
綿密に施された精巧なカラクリ・・・
音楽に憑かれた人達が、究極の音楽を求めた結果、
それぞれが導き出した結果は・・・
途中、説明がくどいところが結構あるんだけど
音楽を体感してる状態を活字にするにはしかたがないのでしょう。
478Pの長編ですけど、苦にはならないです。
途中、グロイ描写がちょっとあります。
苦手な人の為に一応・・・
最初は文章に慣れるのにちょっと手こずったけど
一気に加速しますから大丈夫です♪
投稿元:
レビューを見る
緻密な音楽SF、ファンタジー、ミステリー?
ある程度の音楽知識がないと読み進めるのが難しいかもしれないが、知らなくても十分に楽しめるストーリー性はある。
ブルックナー存命中のヨーロッパ、フランスはナポレオン3世が失脚した第三共和制時代なのに、音楽機械とかメモリとかの言葉が頻出する不思議な世界観。
無賞のデビュー作。このクオリティを持続させるのは難しいのではないかと思うが、次作も読んでみたい。期待大。
投稿元:
レビューを見る
図書館で借りた。
1870年あたりのヨーロッパを舞台にして、麻薬、音楽機械、理想の音楽が絡む話。
舞台の設定や時代に不釣り合いな技術の設定を見て、トリニティブラッドを思い出した。あそこまでの人外は登場しないけれど。
ルイ・ナポレオンの台詞で意外なものがあり、そこで危うく吹き出しそうになった。
投稿元:
レビューを見る
書籍が商業である故の弊害か、或いは流されやすい自身の性格由来か、売る側の位置づけと、実際に読んで得る位置づけとが大きくずれていて腑に落ちない結果に終わるというパターンが最近多いように思う。音楽「SF」と呼ぶには少しお粗末で、ただ此処には、過去も現代も混ぜた「音楽」とそれに取り憑かれた人々が在る。
ラストに至るまでの緊張感も、最終的な展開も、Jコレクションで刊行されているものと比べしっかりしていて、もしかこの人の作品の中では一番好きかもしれない。キャラクターとしてはエオンが不動の一番だけど。
映画化するなら、ジュノリアクターかアヴェンズ希望。というか、今作をテーマとしたコンピレーション希望。オーケストラあり、パイプオルガンもあり、テクノもあり、アシッドトランスもノイズロックもピアノも何でもありの。大沢さんとかジオーブがさりげなく居たりして。
投稿元:
レビューを見る
音楽×スチームパンク×歴史改変、な小説。SFというかファンタジィというか。とにかく面白いのは確かです。神保町の古本屋で買って長いこと積んでおりました。ごめんなさい。ベルンシュタインとブルックナーがかっこよすぎるなー! あとダニエルかわいいな。
ラスト、時がたつにつれて細部の記憶は薄れても、感動は残るっていうの、これが大事なんじゃないかなあ。完璧な録音がすべてではない。
投稿元:
レビューを見る
音楽SFと呼べる作品は他に飛浩隆「デュオ」しか読んでいないが、それもこれも面白かった。「デュオ」同様、本作はイデア論的な理想追求を基に展開する。音楽小説とはいえ、音を言葉で表すことは本来できない。だからこそ、現実にない理想の音楽を扱うことが、小説にはできる。音の連なりからではなく、奏でる者の言葉を通して、〈音楽の理想〉は知られる。〈理想の音楽〉なるものも、聴く者の言葉を通してのみ、存在が保証される。登場するガジェット以上に、語られる音楽の非存在性がSF的と言える。音楽とSFとの相性の良さを感じられた。
投稿元:
レビューを見る
ブルックナー教授大活躍ですよ。おまけに近代ヨーロッパのおいしいとこ取り。クラシック音楽+スチームパンク、最高ですね。
音楽SFという素敵なジャンルがあるとは知らなかった。これは「分かる」どころではなく、最初から自分の中に広がっていた世界だったりする。
投稿元:
レビューを見る
この手の歴史改変小説は合わないことに気がついた。
「クリムゾン大王」亭、「真紅のツェッペリン伯爵」亭、「薔薇と拳銃」亭、「巨万の死」亭、曲名「アナーキー・イン・ザ・大英帝国」だとかそそられる固有名詞が出てくるけど。