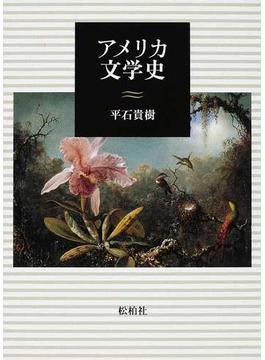「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
伝統の形成からアメリカン・ルネッサンスの隆盛、近代小説の展開、モダニズムの文学、戦後文学まで、「近代的自我」の変遷をたどりながらアメリカ文学の見取り図を描き、「文学史とは何か」「小説の評価とは何か」を問う。【「TRC MARC」の商品解説】
著者紹介
平石 貴樹
- 略歴
- 〈平石貴樹〉1948年函館生まれ。東京大学教授。著書に「メランコリックデザイン」「小説における作者のふるまい」など。
関連キーワード
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
著者(平石貴樹)が若者向けミステリーを書いているとは知らなかったが、読まずに言うのは失礼ながら、この本の凄さを前に、そうしたフィクションが余計なものに思えた
2011/09/10 09:58
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:本を読むひと - この投稿者のレビュー一覧を見る
以前、橋本治の『「三島由紀夫」とはなにものだったのか』を読んだとき、その内容とともにひどく感心したことがある。手元にないが覚えていることを言えば、その本には、いわゆる注がない。参考文献リストもない。そして他の三島論などの引用が一切ない。三島由紀夫自身の言葉からは引用があったと思うが、ともかく「いでたち」がすっきりしているという強い印象があった。
本書にも、そうしたすっきりした「いでたち」がある。一切「注」がない。一切「文献紹介」がない。橋本治の三島論と違って、さすがにいくらかの先行研究からの引用はあるが、そうしたものもまた各作品自体の引用も、すべて自身による訳なのであろう既存の翻訳への注や言及が一切ない。また本書には、本書を書くにあたっての著者の構えというか実情を示唆する「あとがき」がない(最終部分に村上春樹を置いているが、この春樹論が卓抜で、見事なあとがきとして読める、ということはある)。
そうした、通常の研究書にそなわっているものをすべて取っ払いながら、本書はその発生から現在に至るアメリカ文学の歴史を、各作家の代表作を分かりやすい言葉により分析することでダイナミックに描いている。
たとえばロシア・東欧文学者の沼野充義は例年の『みすず』読書アンケートのなかで、自分ならロシア文学史をこれほど見事に書けるだろうかといった言葉を(手元にないため曖昧な記憶でご容赦)、この本に対して投げかけている。
もちろん私はどこの国やどのジャンルの文学の専門家でもないので、そのような種類の判断をもつ資格がない。だが一読書家として、一アメリカ文学愛好家として、これは凄いと思わざるをえなかった。このレベルのロシア文学史、イギリス文学史、フランス文学史があったら読んでみたい。
基本的なことをいうと、個々の作家・小説の分析と文学史的な全体の構築が、かぎられた分量のなかで(といっても600ページ)、融合しているように思えた。
たとえば個々の小説家とその作品の紹介・分析にかまけるあまり、アメリカ文学史という全体へのヴィジョンがおろそかになるケース、また逆に一つの世界の構築に専念するために小説そのものが生きたかたちで読みこまれていないケース、本書はそのどちらとも異なっている。
私が読んでいる(ほとんど翻訳でだが)小説であろうと、未読のものであろうと、個々の小説作品に対して著者がほどこしている分析は、分かりやすい、行き届いた言葉によってなされているが、ほぼ例外なくそれらは、個別の分析であると同時に全体のなかの個の分析でありえている。
これにくらべれば、個々の小説への直接的な感想は容易(たやす)いし、また個々の小説が一種の「コマ」でしかない文学史も容易い、そんな感じを覚えつつ読み続けた。
文学史を書くというのは、もともと「文学的なもの」と矛盾した作業だと思う。というのは誰にとっても好みや個々の作家・作品への偏愛があるはずだが、文学史はそうした気持ちに蓋をし、全体に対して妥当な目配りをしなければならないからだ。そうした偏愛が一切ないという人もいるかもしれないが、私としてはそうした著者の文学史を読みたいとは思わない。奥付にある紹介によれば、著者にはフォークナーについての研究書や翻訳がある。だがこの文学史においては、特にフォークナーに偏向した書き方はみられない。
私には好みのアメリカ作家がいるが、それらの作家がどう扱われているか興味深かった。たとえばスティーヴン・キングは「第一八章 大衆の時代としての一九三〇年代」の最後の部分「8 ラヴクラフト、キング、作者の伝記」のなかに数行で語られているだけである。《二〇世紀後半の最大のゴシック小説家》と書かれているが、戦後アメリカ的なキングをこの部分に押し込めているのは疑問である。
だがパトリシア・ハイスミス、またフィリップ・K・ディックについても一行もふれられていないこの本の構想からすれば、キングにわずかにでも言及するために、どの場所にその名を入れるかは、著者にとって苦心なところだったのかもしれない。
どちらにしても網羅的な文学史ではないところが、この本の良さである。たまたま網羅的な映画史を読んでいるところだが(『イタリア映画史入門』)、名前だけが長々と列挙されるところが多く、そうしたところはとても真剣に読めない。
何を選び、何を捨てるかを考えるべきなのだ。思い切ってカットすることを真剣に考慮し、集中すべき部分に狙いを定める。そこから羅列的にしかならない網羅的な書き方の弊害を知ることができるような気がする。