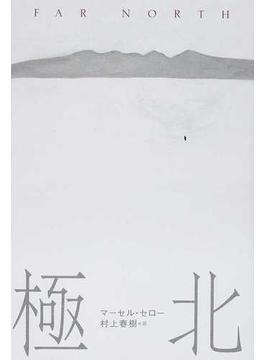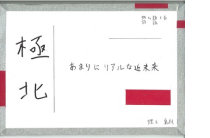紙の本
シンプルで、力強い。
2012/04/26 09:01
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:アヴォカド - この投稿者のレビュー一覧を見る
この作品の紹介を書くことは大変に難しい。
(まあ何の作品でもそうであるが)とりわけ、何の先入観もなしに、何の推測もなしに読むのが最もいいと思われる作品だから。
性別も時代もジャンルの思い込みも。何一つ持たないまままっさらで読むのが、最も、作者の描きたい世界に導かれる、と思う。
シンプルなタイトルからは、先の想像がつかない。
展開は意外と言っていいと思う。今まで読んだ中で、似た感じのものはちょっと思いつかない。
ロードノベル、と言うことは出来ると思う。
主人公は移動し、移動する中でいろいろなことが起こる。
種を蒔いて育つ、それを収穫して食べる。
獲物を自分でしとめて、それを自分で捌いて食べる。
妊娠して産んで、子どもを育てる。
そういう生き物としての人類の、シンプルさを思い出す。
そういえば、今ほど文明やテクノロジーが発達し、そのことになんの疑問も抱かずに多くの人々が享受している時代は、これまでの人類の歴史の中でもごく短く、ここ何十年だけのことでしかない、ということを思い出させられる。
電気も電話もインターネットもなかった時期のほうが、それがある時期より遥かに長かったはずなのに、人類はさっさと適応し、いとも簡単にそのことを忘れる。
悲惨とか苦労とか、そういうマイナスの言葉がどこかへすっ飛んでいく。ただ目の前の食糧、目の前の寒さ、目の前の危機。
主人公の自己憐憫のなさが眩しく、そして力強い。
紙の本
文明を支える科学技術、進歩や革新を求める精神、文明の災禍をどう考えればいいのか。村上春樹訳。暴力に転化した「文明」「システム」の行く末を透視する険しい小説。
2012/05/28 18:39
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:中村びわ - この投稿者のレビュー一覧を見る
物語は、語り手が銃を手に巡視に出かけるところから始まる。ほどなくその名が「メイクピース」という、何やら象徴的なものだと知らされる。何があったか街は廃墟と化した場所らしく、人の気配がほとんどない。明日を生きるにも容易でない環境に置かれたメイクピースは、巡視先で、同じように孤立して生きる少年と出会う。
この世界でも同じだが、出会いは孤独な心に火を灯す。メイクピースの心に灯った火は、読書という孤独な取り組みを覚悟する者の心に、暖かみをもたらす。
一つの出会いを得たことで、メイクピースは旅立つ。冒険と違い、北の放牧民のところへ食料を求めておもむく旅、命を永らえさせるための旅。テントに寝袋を持参、馬で移動、しかも行く手には厳しい自然が立ちはだかり、途中で賊でも出てきそうだ。
読み手もまた、安全や安心が保障されない別世界へ連れ出される。行く先は知らされない。何が起こるか分からない勇気と忍耐のいる旅だ。
文明から離れた過酷な環境で、人としての「誇り」「理念」といった社会性を内在させながらも弧絶する。生物としてのそういう限界を突きつけられたら、どう行動するのか――小説の前半には、このような冒険めいた課題が待ち受ける。
30ページ、34ページ、50ページ、99ページと、物語が突きつける罠のような展開に驚く。そこに至るまで、丁寧な語りにガイドされてきたのに、挿し絵や映像が与えられず言葉だけの世界を進んできたからなのか、かんじんの情報から遠ざけられていたと思い知らされる。
訳者の村上春樹氏は、罠のような展開を、小説に必要な「意外感」だと評価する。本当だ。その意外感が小説を読む潜在的願望だったのだ。
意外感ある物語の運びそのものに、物語が扱う重要な要素の一つがなぞらえられている気もする。それは、人類が作り出した社会機構や巨大技術といったシステムが単に大きいだけではなく、運用されるに従い、目的と手段が転倒し、予期できない影響を及ぼし、その結果、人の手に余り、人の手を離れ、全容が見えなくなっていくという事実だ。
ひとり歩きを始めるシステムに対する恐怖が、『極北』という物語の底を流れる。その恐怖を人々が常に意識に置いておけば、現実世界で生じる悲劇は、もっと軽減できるに違いない。
手さぐりのように、メイクピースという人物の属性や過去を知っていくと、これが文明の災禍につながる物語だと分かっていく。メイクピースの旅は食料を求めるものだけではなく繰り返され、監禁という危機もあり、さらなる旅で、物語の旅立ちからは想像もつかない場所へ至る。
ところどころに現れる哲学的な文章は、はじめ控え目なほのめかしで物語に深みを加える。だが、半ば過ぎから遠慮がなくなり、人類が切り拓いてきた文明、それを支える科学技術、進歩や革新を求める精神等に対する問いがむき出しで提示される。「私たちはこれで良かったのか」……と。
コーマック・マッカーシー『ザ・ロード』、ジム・クレイス『隔離小屋』、そしてストルガツキー兄弟が脚本に携わった映画「ストーカー」……そうした作品に通じるものがある。どれも圧倒的虚構世界を脳内に構築してくれた。卓抜した文明観、世界観、歴史観に触れる喜びがあった。
『極北』もスケールの大きな小説だが、肌身に触れてくる親しさがあった。昨年来、かつてSFが近未来カタストロフィとして表現してきたものを現実として経験したせいなのか。それもあろうが、おそらく、
メイクピースという主人公がさんざんに傷つき、苦悩を経てきたことに、ぐっと心を寄せられるからなのだろう。
投稿元:
レビューを見る
★あらすじ
近未来の世界は、温暖化(だけじゃないんだけど)に伴う砂漠化・食糧難により、紛争が起こり、人口が激減してしまった。
わずかに残された人間が居住可能な極北の地、シベリアへと大量の避難民が流れ込んでくるが、人口の急増にやはり争いがおき、どの町も壊滅状態になってしまう。
平和で穏やかなクエーカー教徒のコミューンで育ったメイクピースは、そんな争いの中を生き延びた貴重なひとりだ。
故郷の町で自給自足の生活を営んでいたメイクピースは、ある出来事がきっかけになり、文明的に人々が居住している可能性が残る他の町を
探すため、長い旅をはじめる。
★感想
マーセル・セローは、ポール・セローの息子だそーで、×村上春樹ってことで、著者と訳者への興味から手にとってみました。
面白かったッス! すごい力強い物語です。ストーリーがどんどん意外な方に転がっていきます。ハルキさんは「ドライブ」していくとあとがきでおっしゃってます。なるほど。
んで、最後のオチがこれまた泣けるし。
近未来ものなんでSFに入れたけど、むしろSF大丈夫な純文学ファンの方にお勧めかなあ。ハードボイルドファンにもいいかも。
文体は、ハルキさん訳にしてはちょっとごつごつした感じなんだけど、きっとこれは原作がそーなんだからなんだろうね。メイクピースの手記という体裁だからね。イイ感じです。
投稿元:
レビューを見る
近未来の物語で描かれるのは戦争や核などによって文明を失ったあとの世界。コーマック・マッカーシーの「ザ・ロード」が描く世界も同じような設定だったけど、震災以降の現実があるだけにただのフィクションとかたづけられない怖さを感じる。
投稿元:
レビューを見る
★百でも足りないくらいの小説に久々に出会いました。ほぼ一気読み。本当に村上春樹さんの言うとおり、あらすじとかを全く知らずにまっさらの状態で読めてよかった…。
投稿元:
レビューを見る
「僕は、一人の小説家として、この小説から我々が何を感じ取り、何を学び取るべきか、というようなことはあまり積極的に論じたくない。これはあくまでもフィクションであり、よくできたタフな物語である。[・・・]しかしそれでも、この小説の中に登場するいくつかのリアルな描写は、多くの読者に思わず鳥肌を立たせることになるだろう。そして我々はそこに描かれている事象が、ただのフィクションの装置ではなく、目の逸らしようもないひとつの現実、あるいは現実に付属するもの、現実を照射するものであることを既に知ってしまっている。我々が物語というシステムをくぐり抜けることによって、そこに見出すのはおそらく、痛々しいまでの共感だ。具体的に言うなら、そこに浮かび上がるのはチェルノブイリと福嶋との間を結ぶ、太く熱く脈打つ、悲痛な物語の動脈である。」(訳者あとがき p.376)
投稿元:
レビューを見る
シンプルなタイトルから、先の想像がつかない。
何の先入観もなしに、何の推測もなしに読むのが、最もいいと思う。
展開のいろんなことが意外で、今まで読んだ中で、似た感じのものはちょっと思いつかない。
ロードノベル、と言うことは出来ると思うけれど。
そういえば、こんなにも文明やテクノロジーが発達し、そのことになんの疑問も抱かずに多くの人々が享受している時代は、今までの人類の歴史の中でもごく短く、ここ何十年だけのことでしかない、ということを思い出させられる。
電気も電話もインターネットもなかった時期のほうが、それがある時期より遥かに長いはずだ。
種を蒔いて育つ、それを収穫して食べる。
獲物を自分でしとめて、それを自分で捌いて食べる。
妊娠して産んで、子どもを育てる。
そういう生き物としての人類のシンプルさを、思い出す。
悲惨とか苦労とか、そういうマイナスの言葉がどこかへすっ飛んでいく。ただ目の前の食糧、目の前の寒さ、目の前の危機。
主人公の自己憐憫のなさが、眩しい。
投稿元:
レビューを見る
怖い夢を見たあとのような読後感。正夢?予知夢?2011年3月の大震災後、いやな予感が現実になっていったあの頃の、不安だった気持ちを思い出す。それがまだ続いてるという事も。
投稿元:
レビューを見る
2011年3月11日のおかげでこの本は間違いなく重さを増したけれど、その前であっても重かったに違いない。訳者村上春樹自身はその日付をまたぐようにこの本に関わっていたのだから、それを深く感じていたのだろうと思う。
舞台は近未来のシベリア。放射能による汚染が蔓延する世界で生き延びる人々の姿を主人公の意外性に富みつつも、説得力のある行動を通して見つめていく。
個人的な感想だけれど、ドン・デリーロの「アンダーワールド」以来のショック。実に重たい。
投稿元:
レビューを見る
いわゆる「近未来小説」。何らかの理由で人類が滅亡しかけた後に生き残った人々の悲惨な生活を描いた「ディストピア」ものである。しかし、この紹介ぶりから、よくあるSF小説を想像されると困る。たしかに、設定はSF的かもしれないが、内容はきわめてリアル。時代は現在より何年後か、その舞台は極北の地シベリア、視点は主人公に限定されている。
科学技術が発展を遂げ、人類に不可能などないと思われていた時代はとうに過ぎ去り、核戦争か、地球の温暖化による大規模自然災害か、何らかの理由で、文明社会は崩壊し、人々は生存できる土地を求め、極北の地に逃げ延びてきていた。しかし、そこには過度の科学技術信奉を嫌い、人間本来の生活がしたいと考えた人々が先に入植を果たし、キリスト教信仰に基づいた平和な生活を営んでいた。
主人公メイクピースの父は、入植者たちが作った街エヴァンジェリンのリーダーであった。かつての都会から流れ込んでくる難民を受け入れようとする主人公の父の一派と、拒絶もやむなしとする一派が対立し、入植地は崩壊する。家族を亡くし、ひとりぼっちになった主人公は町の警察官を自称し、無人の町をパトロールすることを日課にすることで、かろうじて日常性を維持している。
そんなとき、逃亡奴隷をかくまった主人公は、仲間との新生活に未来を見るのだったが、その死により絶望し、入水自殺を図る。溺れかけた主人公が死に際に目にしたものが空を飛ぶ飛行機だった。文明の存在を知った主人公は再び生きることを誓う。飛行機を飛ばせる力があるということはそこに行けば未来があるということだ。
果てしない雪原を徒歩で、あるときは馬で、無法者と化した人々との遭遇を警戒しながらもメイクピースは探索をやめない。そう、馬に乗り腰にピストルを携えた主人公を持つこの小説は、ある意味フロンティアを舞台とした西部劇小説であり、ハードボイルド小説なのだ。
しかし、それだけではない。訳者である村上春樹があとがきで書いているように、この小説には「意外性」がある。それも、一つや二つではない。だから、むやみに面白いのだが、あらすじを紹介することがむずかしい「しかけ」に満ちた小説である。
根幹に流れるのは、「アンプラグド」の精神。つまり、プラグをコンセントから抜いたら、何もできない文明社会に対するアンチテーゼだ。メイクピースは、銃弾も自分の手で作る。まあ、店もないのでそうするしかないのだが、食糧を得たり、自分の命を守ったり、という我々文明社会に生きるものが自明とする一つ一つのことが、あらためて切実な意味を持って立ち現れる。
それと、もう一つは、このどうしょうもない世界で生きることの意味の問い直しであろうか。3.11以来、さまざまな論説が飛び交っている。真摯なものも多いが、時流に乗った発言も少なくない。やわな口舌の徒でしかない評者のようなものは、なかばこの世界のあり方に絶望しかけている。完膚なきまでに破壊された原発の姿を目の当たりにしながら、その検証もいまだしというのに、再稼動を言いつのる勢力と、それを政争の具としようと計る勢力のあいも変わらぬ争いに、うんざりするばかりだ。
しかし、最��の状況に陥った主人公が、持ち前の強靭な肉体と精神力をバネにして何度でも立ち上がる姿に、ありきたりの言い方で申し訳ないが、読者は勇気をもらう。どんな時代、どのような状況下においても、人は生きねばならぬし、生きることには意味がある。放射能や炭疽菌に冒された人類滅亡の地で生き抜く主人公に比べたら、今の世界は、まだまだ可能性が残されているじゃないか。そんな気になってくる。
テーマは、それぞれ読者が見つければいい。一つ言えるのは、そんなものを抜きにしても、この小説は面白いということだ。一気に読み通すことを約束できる。翻訳は、大事なしかけを十分に意識したていねいな仕上がりになっている。一読をお勧めする。
投稿元:
レビューを見る
村上春樹訳だったので読んだ。一気に読んでしまった。主人公の女性がタフでカッコよくてドキドキした。すぐに亡くなってしまったピングとピングのお腹の赤ちゃんの存在が大きかった。解説で村上春樹が書いてるように読了後とても重量感がある。後にひきずってしまう。
投稿元:
レビューを見る
2月に入ったばかりだけれども、今年最高におもしろかった小説になるかもしれない。
意外性の連続とスピード感、極北が産み出す重しのようなものが絡み合って、心に残る物語だった。
いやー、おもしろかった!
投稿元:
レビューを見る
モノトーンで近未来的な物語。
しかし、あり得ないお話かというと、
妙に現実感もあるし、
そもそも話の筋立てが大変面白く、
深く深く惹きつけられた。
翻訳して下さった村上春樹氏に感謝。
投稿元:
レビューを見る
小説でできる表現を存分に活かしたストーリーテリングに圧倒される。あらすじを書いてしまうと、これから取り組む人の楽しみを半減するので表現が難しい。だけどできる限りで読後感を記してみたい。
冒頭描写される風景は、必要最低限の生活を営む1人の人間。いっさいの無駄がなく、故に読む側のクエストを誘う仕掛けになっている。ある事象をきっかけに主人公が道行きを始めるのだが、その行程が面白い。人物が知っていることしか描写されないため、読む側も一緒に真実を見つける旅にでているような気分になる。
終盤の静謐な描写は飽きさせない展開を孕みながら、静かに「ただしく」描かれる。読ませるスピードをあらかじめ計算しているのかもしれない。主人公が「動く」とき、私の目も同時に速度を増す。主人公がじっと立ち止まるとき、私の目は何度もその描写を繰り返しなぞらえる。
荒涼とした大地を往く小説で思い浮かべるのは、コーマック・マッカーシーの「ロード」とポール・オースターの「最後の物たちの国で」。どちらも世界を揺るがす事象が起こった後の、人々のものがたり。だけどこの小説は、それ以上に訴えかけるものがある。
「必要以上のものは必要ない」
これ以上のシンプルは無い、という程の明解さであらゆる章にひた隠されるこのコンセプトが心に襞をつくるようだ。
ディザスターものというにはあまりに印象的すぎるし、人類への警鐘というのとは違った手触りが読後に残る。その読後感を読んだ人と分かち合えれば、世界はもっと幸せになるのだろうな、と今はそれだけを感じている。
スバラシイ小説です!
投稿元:
レビューを見る
とても面白く最後まで飽きずに、さらりと読めました。淡々とした空気感があるので、重すぎず軽すぎず、読み手が心地よいペースで読み進めることが出来ます。本の装丁のイメージがぴったりです。
もし同じような題材のSF小説を日本人が書くとしたら、主題が変わってしまいそうです。作者もまた「極北」に向かう思考であり、それを自覚しているからこそこの主人公でこのテーマで書けたのだと思います。日本人はよくも悪くも、無自覚にも楽観的なのだろうということに気づきました。内容の面白さ以上に深い部分もある、素晴らしい小説でした。