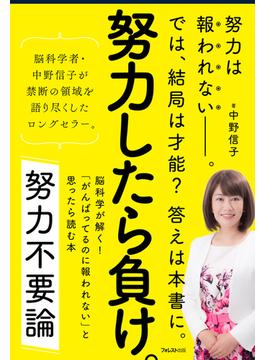紙の本
がんばりゃ良いってもんじゃない。
2015/03/01 21:24
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:thanatos - この投稿者のレビュー一覧を見る
頑張ってはいるけど、結果が出ない。周りの期待に答えられていない。
そんな時、その頑張りは、自身で決めたことか、周りから刷り込まれて、あたかも自身で決めたことのように思い込んでいないか?今一度考え直す必要性を著者は強調していると思います。
「結果はどうあれ、努力することはすばらしい」という考えは、
一神教でいうところの、「無条件で神を信じなさい」というものと同等、
洗脳の前提条件の一つです。
しかし、努力が不要ということではなく、
・誰が決めた目標に対する努力か?
・努力した結果だれが一番得をするか?
など穿った考えを踏まえたうえで、自身で納得した上で、楽しく実行できるか?
自身が努力をしていると意識しなくてすむようにお膳立てできればベストですが、
なかなかそうはいきませんよね。
著者の考えを理解することにより、理不尽な努力の強要でも割り切って対応できるような気がします。文中にもあるように、「生き辛い世の中です」。少しでも明るく楽しく過ごせるように読んでおいても損はない本だと思います。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:本好き - この投稿者のレビュー一覧を見る
本音で生きていれば努力などしなくても知らず知らずのうちに自分の思うような人生になる。本音ではないことをしようとすれば努力が必要になる。努力してできることはたかがしれている。この本に書かれていることには共感しました。
電子書籍
面白い
2023/04/08 16:00
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:本好き - この投稿者のレビュー一覧を見る
ビジネス書のベストセラー作家である千田さんが勧めるお金に困らない厳選された本が気になったので読んでみた
紙の本
読む機会があってよかったです。
2017/09/27 20:27
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:eri - この投稿者のレビュー一覧を見る
日本で努力が重視されるようになった背景についての指摘にとても説得力がありました。その危うさについても、無意識にそういうものだと思っているものもあり、はっとさせられました。
投稿元:
レビューを見る
「努力は報われる」と自身も思っていましたが、こちらの本を読み努力をした時、自身の破滅が待っているとも感じました。ブラック企業にあたる”努力”が”洗脳”とい事の内容は実感しました。身の丈にあった生き方をも必要だという認識をした一冊です。
投稿元:
レビューを見る
●努力が報われると思われる人はダメですね。努力を努力だと思ってる人は大体間違い。好きだからやってるだけよ、で終わっといた方がええね。これが報われるんだと思うと良くない。こんだけ努力してるのに何でってなると腹が立つやろ。人は見返りを求めるとろくなことないからね。見返りなしでできる人が一番素敵な人やね。by明石家さんま
●「努力は報われる」は半分本当である。
負荷がかからないと、どんどん機能が錆び付いていってしまう。そういう性質が人体にはあります。あるレベルのパフォーマンスを実現したいと思ったときには相応の負荷(=努力)をかけなければなりません。だから努力をしないと発揮できるパフォーマンスはどんどん落ちていきます。それが「努力は報われる」という言葉で表現される、ウソではない部分です。
一方、確かに努力すれば、その人の持つ可能性の最大値まではスピードアップできます。けれども、限界を突破してウサイン・ボルトのように優れた記録を残せるほど走れるか、というとまず不可能です。そのような意味では、才能は遺伝的に決まっています。つまり、「努力は報われる」はウソということになります。
●エジソンの「1%のひらめきと99%の努力」という言葉ほど誤解されている言葉も珍しい。エジソンの真意は99%努力しても1%のひらめきがなければ無駄、ということを言いたかったのだと言われています。
●努力の成功体験は「サンプル1」にすぎない。
偶然の要因についても、努力を重視した成功譚をつくろうとするあまりに、軽視されて語られないことのほうが多いようです。
●2大無駄な努力
1)努力をしていると自分では思っていても、単に努力していると思い込んでいるだけだった、つまり実際に努力をしているわけではなかった。
2)努力の方向が間違っていた、無駄な努力をしていたということ。
●本当の努力とは。
真の努力というのは本来、成果を出すために必要な1)目的を設定する、2)戦略を立てる、3)実行する、という3段階のプロセスを踏むことです。どれが間違っていても結果は出ません。
●ただがむしゃらに頑張る努力=「狭義の努力」といい、3段階のプロセスを経た努力を「広義の努力」という。
●人は我慢できる量は決まっている。つまり、我慢の限界を超えると、我慢しなければならないことでも我慢できずにハメを外してしまうのです。「自分はこれだけ正しいことをしたんだから、許される」という言い訳を、なんと無意識のうちに脳がやってしまっているのです。つまり、努力は人間をスポイルすることがあるということです。「がんばる」というのは、自分を冷静に見つめる目を失わせるものであり、努力そのものが楽しくなくなってしまうと、ほかのことが考えられなくなってしまう傾向があります。
●努力という言葉は人を縛り、無料、あるいは安価な労働力として使いたい人が用いるブラックなレトリックなのです。真の努力とは、本当に目的を達成したいのであれば、広義の努力、適切に目的を設定し、戦略を立て、実���することです。
●江戸時代、努力は粋ではなかった
江戸時代は「遊ぶ」ということを尊びました。遊びというのはプラスの概念であって、教養のある人や余裕のある人にしかできない、高尚で粋なものだったわけです。
明治維新を経て、それが変わってしまった。努力は一定の成功を収めたが、その過程で失われてしまった「遊び」の豊かさや、日本人らしい感性のふくよかさのような部分が、努力を重視し過ぎたあまり貧困になってしまったことは否めません。
努力以外の遊びの部分というのは、脳にとってのエサともいえるもの。ヒトは、努力よりずっと、遊びが必要な生き物なのです。
●究極的に言ってしまえば、私は「できるだけ努力をしないで生きよう」という考え方が、最も大事なことではないかと思っています。
●努力をしない努力
私は真の努力とは「努力をしない努力」のことだと思っています。
●才能がある人を使う
僕を見ていてくれた、見抜いてくれたからこの人のためになんかしよう、自分1人では小さな人生しか生きられないけれど、「この人について行ったら自分の才能を生かせるかもしれない」と思わせる力が、優れたリーダーには必要です。
●人生最後の時を過ごす患者たちの緩和ケアに携わった、あるオーストラリアの女性によれば、人間は死の間際になると自分の人生を振り返って後悔を口にするのだそうです。その後悔の中でも最も多かったものの上位が、「あんなに一生懸命働かなくてもよかった」「もっと自分の気持ちを表す勇気をもてばよかった」「自分をもっと幸せにしてあげればおかった」でした。これでも、自分の気持ちに反した努力を続けようと思うでしょうか?
投稿元:
レビューを見る
若い方とか小さなお子さんがいらっしゃる方は読んでみるといいと思います。
努力は報われるのは半分はホントで半分はウソ!
受験の合否はエピソード記憶が決める?
受験に勝つためには、思春期に無理なダイエットをして、脳の成長を妨げることは避けたほうがいい。脳の神経の配線の部分はほとんど脂肪でできているので、無理なダイエットをすると脳も痩せてしまう。
人間は多少の負荷をかけるぐらいの努力をすると能力が上がるけれど、自分を痛めつけるような努力はダメ。
私にとってこの本が一番刺さったのは、第6章の意志力は夢を叶える原動力。
”子供のころは愛情をたっぷり与えてあげないといけないというのは、愛情が脳にとっての栄養のようなものだからです”
”子供のころに虐待を受けて、前頭前皮質が肥厚するのが妨げられてしまうと、大人が交通事故などで脳に損傷を受けたぐらいのダメージがあると言われています”
若い頃の私は、この本に書いてあるような無駄な努力をたくさんしていたように思います。
近頃の私は、年とともに自然と無駄な努力をすることが少なくなってきたような気がします。
若い時にこのような本を読んで、無駄な努力をしなければ、今とは違う人生もあったんでしょうか・・・。
投稿元:
レビューを見る
成功者が語るとこは、結果を出したことに理由付けしているだけ
努力中毒にならない
努力の努には、奴隷の奴がある
日々の生活を楽しむという遊びの部分を失うな
人生を楽しくするために努力する
意志力
できるだけ努力をしないで生きよう
投稿元:
レビューを見る
「やればできると言うがそれは成功者の言い分。」
う〜ん、それを言っちゃ〜お終いよと思うが、心の何処かでそう思っていたんで、ある意味しっくりきた。
本論とは違うが、
「可塑性」とは、変化の起きやすさ。
努力は二つ
1 狭義の努力
ただがむしゃらに頑張る努力
2 広義の努力
①目的の設定、②戦略の立案、③実行の三段階
のプロセスを経た努力
投稿元:
レビューを見る
手っ取り早く自分を変えたいと思ったら、理想とする人物の振る舞いを、徹底的に細部に至るまで真似していくと言うのが一番の近道。
人間の脳には、ミラーニューロンがあると言われていて、まさに他者の思考や感覚、つまり認知をコピーすることができるから。
投稿元:
レビューを見る
努力とは、目的を設定し、それにたどり着くためのタスクを消化することを言う。
目的も設定せず思いついたタスクを根性で消化するのは戦略性のない努力である。
また、自分にできること、できないことを見分ける力も必要。
将来どうなりたいのか、しっかりと考えてそこにたどり着くための行動をとりたいと思った。
また、日本人と欧米人の考え方の違いも参考になる。
日本人は戦争でも無理な努力を洗脳を使って強要し、敗れた。アメリカは効率性、物資などの現状を鑑みて戦略的に戦った。欧米人は人間性も楽観的で、常にリスクや他人の目を気にする、日本人よりも0→1をつくるのが得意。日本人は既存のものの弱点を見つけるのが得意で1→100にする力を持つ。
心配性にならずに楽観的に。
自分らしく生きたいと思えました。
投稿元:
レビューを見る
前半は読むのが苦痛なほど、購入したことを後悔するほどだったが、後半は示唆に富む内容だった。真面目にがんばっているのに報われない、と強く感じてしまう誠実な人間というのはまさに自分のこと、どんぴしゃ、だと思った。万人受けするように平易な文章であまり深堀りせずにすっきりとまとめたのだと思うけれど、もっと突っ込んだ議論を知りたい。著者の言う知恵とか発想とは具体的にどんなことを指すのか、とか。
投稿元:
レビューを見る
著者は、「努力は報われる」というのは「半分は本当で半分は美しい虚構である」と指摘しています。半分が「虚構」である理由は、才能は遺伝的に決まっているからです。
『うまくいかないのは、自分の「努力」が足りないから』
そう考えるのは「洗脳マジック」に引っ掛かっているのだと主張します。
詳細なレビューはこちらです↓
http://maemuki-blog.com/?p=3323
投稿元:
レビューを見る
期待していた内容とほぼ同じ。
要は、
『(目的が不明確でも)ただガムシャラに努力をして疲弊するのではなく、(明確な目的の為に)ガムシャラに努力をするのが正しい努力である』
ということかな。
普段から努力とかけ離れた生活をしてる(と思ってる)自分としては、
読んだ後に特にスッキリする訳でもなく、なるほど、と思う所もあんまりない。
そもそも努力ってなんじゃらほい?
以上。
投稿元:
レビューを見る
タイトルだけ見ると、効率的な戦略を立てることで、努力しなくても目標に達することができる、と説くか、または、努力を努力と思わないように工夫するか、のどちらかと創造した。
おそらく本書は、後者に近い。
考えてみると、「努力」の定義も曖昧だし、個人差があるのも当たり前。
でも日本では、がんばってる、歯を食いしばってる、もがいている、苦しんでいる、ことに美しさを感じるような風潮があるのも事実。だから、そういうアピールをする人さえ現れる。
笑って、陰で頑張って成果を出しちゃう人の方は、全力を尽くしていないのでは、とか思われる。
本質を見抜くのは難しい。
しかし、努力でないようにもっていってあげると、成果は、努力しなければならない人にくらべ、桁違いになるんじゃないかな〜。