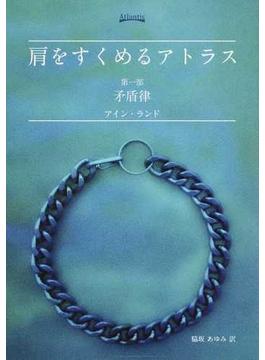紙の本
読み返しました
2017/01/31 12:39
3人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:K - この投稿者のレビュー一覧を見る
回りくどいとかロマンスシーンが必要なのかとか思いましたが、ランドさんは主人公に自己を投影されているのでしょうから仕方ないかもしれません・・・
紙の本
アメリカで聖書の次に読まれている
2021/12/05 14:07
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:カニ叔父さん - この投稿者のレビュー一覧を見る
と、帯に明記されています。聖書の次に読まれている、と言う箇所に興味が湧き購入しました。原作は、約60年強以前に書かれた書籍です。文庫本3部作で且つ1部あたりの頁数が500頁を超えているかなりの長編です。が、ついついのめり込んで時間を費やしています。アップテンポな内容展開で、目が離せなくなるとは、まさにこの事かと。単純に面白いと感じます。3部作、読了するまでにはまだまだ時間が必要ですが・・・
投稿元:
レビューを見る
■サマリー
舞台は、生産する能力がある者たちが、生産する能力が無く他人に自己犠牲を求めるたかりやたちに、たかりやたちの道徳主張のもとに能力や自由を搾取されている社会。
何世紀もたかりやに搾取を許した自分たち生産者が、たかりやを生きる目的の無い無能のままでいさせた原因の一つだという答えにたどり着いた思想家ジョン・ゴールドが中心となって、生産者はストを起こす。
たかりやに価値あるものを全く与えないよう、ストを起こした生産者たちは外部から隔離した理想郷で暮らして再建の時が来るのを待つ。
アメリカが、生産者がいなくなったことで輸送手段やエネルギー源を失った馬車の時代に逆戻りし、
自分に能力がないことを理由にして、能力のある者に「あなたは私を助ける義務がある。どうやってかは私の問題じゃない、私には思いつかない、それは能力あるあなたの問題だ!」と言うたかりやたちが消えたときを見計らってアメリカ再建をはかる。
■感想
実際だと馬車の時代に逆戻りする前に生産者の自由を奪う政策が機能しないことに人々は気づいて政策の修正が行われると思うが、この小説では極端を描くことで多くの示唆を伝えている。大人が子どもの思考能力を破壊する理由など、子育てに通じる話もあり面白かった。
自分の頭で考えることの重要性を伝えている。
■第1部メモ
フランシスコ、最も堕落した人間ってどんな人間のこと?
目的のない人間のことだ
■第3部メモ
能力の略奪が自己犠牲を説くあらゆる協議の目的です。
かれらの計画というのはー過去のたかり屋の王侯全ての計画と同じくー自分が生きている間略奪を続けることだけです。以前は常にそれが続いてきた。というのも一世代で犠牲者が尽きることは無かったからです。
生存術を子どもに教えこむ様々な生き物のことを彼はおもった。子猫に借りを教える猫、無情なまでの過酷さで雛に飛び方を教える親鳥。にもかかわらず、生存の道具が頭脳である人間は、子どもに思考を教える義務を果たさないばかりではなく、子どもが考え始める前に、頭脳を破壊し、思考が無益で悪だと教え込むのに適した教育に子どもをゆだねるのだ。
「あれこれ質問するものじゃありません。子どもは姿だけ見せて黙っているものよ!」「子どもに何が考えられるというの?私がそう言ったらそうなの!」「口答えしないで言うことを聞きなさい!」「角を立てないで人に合わせなさい!」「目立ってはいけません、所属しなさい!」「戦わないで妥協しなさい!」「心は頭よりもずっと重要なの!」「あなたに何がわかるというの?親が一番わかっているのよ!」「きみに何がわかる?官僚が一番よくわかっている!」
母鳥が子の羽をもいでから戦って生き延びよと巣から押し出すのを見たならば、人はぞっとすることだろう。だがそれが、人が子どもたちにしたことだった。
(自分で考えない人間は支配しやすい。支配したくて親・教師・大人は子どもの頭脳を破壊する、という見方)
神秘家とは他人の知性との最初の遭遇において知性を放棄した人間のことだ。幼少時代の遠い昔に、彼自身の現実の理解が、独断的な命令や矛盾する要求をともなう他人の主張と衝突し、彼は自立を恐れるあまりおのれの合理的な機能を放棄してしまったのだ。「私は知っている」と「人が言っている」を選択する岐路にあって、彼は他人の威信を選び、理解することではなく服従することを、考えることではなく信じることを選んだ。超自然的な存在への信仰は他人の優越への信仰としてはじまる。
〜〜神秘家は苦悩、貧困、追従、恐怖を見て楽しむ。それらは合理的な現実が敗北した証拠を呈し、彼は勝利感を味わうことが出来るからだ。
投稿元:
レビューを見る
アメリカでは聖書の次に読まれているというアインランドですが、なぜか日本での知名度は今ひとつ。私もつい最近知りました。さっそく読んでみようと思い書店に行き、書棚に見つけた本のなんと分厚いこと!! 弁当箱のような大きさに引いてしまい、興味はありつつも読み出せずにいました。そんな折、文庫での再出版。電車の中でも読めるようになったのを機に読み始めました。
読みやすくなったとはいえ全三巻、それぞれ550ページ、594ページ、768ページという大著、文字のポイントも通常の文庫本より小さめで、読み切るには相当の時間が必要です。また、アインランドの哲学を主人公のセリフとして話させているため、文章も難解で理解するためには相当の集中力と忍耐力も必要です。特に、第三部の第七章は相当腰を据えて読む必要があります。私はすべて読み終わるのに三週間を要しました。
読み切った感想ですが・・・この本は必読の書であり、まさに今こそ読むべき本であると思います。
彼女の思想はいわゆるリバタリアンや新自由主義の精神的支柱になったと言われています。事実、そういう陣営の主要人物の多くが、アインランドからの影響を語っています。ただ、彼女は明確にリバタリアンを否定していますし、無政府主義も否定しています。彼女のメッセージはいわゆるレッセフェールではなく、『出る杭を打つな』であり、すぐれた才能を持った人物たちの創造性を最大限活かすことが人類全体の幸福につながるのだということを訴えているように私には思えます。それにしても、その度合いが極端すぎる印象を受けるのは、彼女の故郷であるロシアが共産主義化していく過程を見届けた影響もあるのではないでしょうか。
ただ、この小説が書かれていた頃は、まだまだ世界全体が発展途上であり、能力や志を持っていた人たちの多くがその才能を発揮したのは、社会のインフラ整備など、社会全体が大きな恩恵を被る分野においてでした。たとえ、『実業家』や『産業資本家』が利己的にしか行動しなかったとしても、彼らの目的と社会全体の利益が一致する時代でした。
さて、現代はどうでしょう。能力、才覚を持った人間たちの多くが向かうのはマネー資本主義。実物の紙幣や硬貨すら動かない、電脳空間のみでのやり取り。物質的なものは何も生み出さず、いわゆるトリクルダウンも生まない、勝者のみが潤う、まさに1%-99%の世界。この現状を見て、アインランドはどう思うのか、非常に興味があります。
何にしても、賛否が大きく分かれる書籍であることは間違いありません。日本での知名度が低いのは、いわゆる『日本的』な感覚からは受け入れることが難しい思想なのでしょう。ですが、この機会にぜひ一読されることをおすすめします。
投稿元:
レビューを見る
(一)を読んだ段階での感想。すごい小説だと思う。この小説の背景や影響を考えると日本での知名度に反比例して結構重要な作品だと思う。
投稿元:
レビューを見る
面白い小説かどうかというと、面白くない。読むべきかどうかというと、仮にもリバタリアンなら読むべきだろう。現代のタカ派と比べても著者はラディカルな思想の持ち主だとは思う。しかし、私の個人の考えでは、人生の相当程度を経済活動に捧げることに肯定的である以上、やはり読んでおくべき必読書なのではないか。
投稿元:
レビューを見る
”友人の紹介で読み始めたところ。頻繁に登場する「ジョン・ゴールトって誰?」が意味深で気になる。
<キーフレーズ>
<きっかけ>
コミュニティマネージャー必読の書、と聴いて…。
聖書の次に読まれている本、というのも心ゆさぶるフレーズ。
単行本はあまりに分厚くて重そうだったけど、文庫本はサイズ的にいい感じ。お値段的にはずいぶんしますが… (^^;)
”
投稿元:
レビューを見る
リバタリアンに大きな影響を与え、書評では米国で聖書の次に読まれている、と言われる本書。著者のアイン・ランドは、共産主義化のソビエトで生まれ、後に渡米。その思想は、母国ソビエト共産主義への嫌悪に発しているようにも思われます。 全体主義、利他主義が徹底的に否定され、仕事を通して自己実現を果たす実存主義的な生き方を希求するダグニー・タッガートや、ヘンリー・リアーデン。
冒頭に語られる楢の巨木のエピソードに強い印象を受けました。巨大国家や組織に対するランドの不信感が感じられます。
「能力による秩序が金本位制に基づくたったひとつの道徳秩序だ」
「最高の能力を破壊することが道徳的なわけがない」
といった、メリトクラシー的な言葉が主人公たちによって語られますが、個人の成功は神の恩寵という、プロテスタント、カルヴァン主義の考え方がアメリカ資本主義の思想的支柱をなしていることを思わずにいられませんでした。
投稿元:
レビューを見る
そもそも読み進めが大変だった。急に場面や登場人物がガラリと変わり、少しでも気を抜くと理解出来なくなる。
登場人物同士の受け答えでハッとさせられる物が多く、自己啓発本を読んでいるかのような感覚。
巻末ラスト1ページで急展開。続巻が気になる内容なので、『二者択一』も読む。
以下より例。うる覚えだけれど。
「堕落した人間とは?」
→「生きる目的を無くした者のこと。」
「普段から正直な者は、信頼を得るための行動を改めてする必要がない。」
「人間は知性を持った高尚な生物とは言えない。大半は動物的本能のままに動く。」
投稿元:
レビューを見る
リバタリアンの主人公のお話。
利己主義と全体主義が争いあいながら、ストーリーが展開していく。優秀な人が富を搾取していくべきか、それともみんなで分け合い全体の幸福度を上げていくべきか。答えのない問である。
投稿元:
レビューを見る
本作の記載された背景は1950年代であり資本主義と社会主義の思想的対立が浮き彫りになった時代である。
著者であるアインランドはソ連からの移民であり、社会主義のある種の欺瞞を日常レベルで感じた方であり、だからこそ本作で核心に迫るような名セリフの数々を登場人物に語らせるのである。
本作が米国保守の思想的バックボーンにあると謳われるようだが、読み進めると、なるほどなと思うことも多い。
今この本を読む意味としては、米中対立の中で、米国の保守の核心に触れつつ、イノベーションを起こす際の、核心的要素は何かに思いを馳せながら読み進めると、学びは多い。
読み応えがある分、長い人生に沁みてくる気配がある名著だと感じているのが、一部を読み終えた感想
投稿元:
レビューを見る
小説は書かれた時代背景を反映する。現実の1950年代の米国社会がここまで暗鬱な状況には無かったわけだが、この物語が今でも米国エリート必読書となっているということが興味深い。とにかく長い。
ーーー
この本を教えてくれたのは波乗り友達のカワグチさん。波待ちしながらの読書談義にて。
投稿元:
レビューを見る
ビジネス系、自己啓発と読めば良いのか、単なる小説の顔はしているが、あふれかえる野心は行間からにじみ出ている。
要は、メッセージが強いのである。
しかし、女性の著者で、女性の主人公。
ちょっとだけイヤな予感がしました、個人的に。
女性性というモノの描き方が鼻につくケースが多いのでね、メルヘンちっくか、感傷的か、フェミ臭がキツいか。
それはさておき、単純、純粋なビジネスのみのお話なら良かったし、だいぶのめり込めましたが、
なんと後半になるに従いまして、
恋愛、それも性的なアレになってしまうのです。
しかも、あからさまなソフトSMプレイ風。
なんやねん、と鼻白む事はなはだしく。
もったいない、実にもったいない。
3部作を一気に読むつもりでしたが、ストーリーだけ知れたら良いかな、と思ってしまう感じに。
本来、そういう本ではなくて、
会話だったり、描写だったりでいちいち胸を打ったりする文章がいくつもあるので、頑張りたい気持ちも半分。
そして、一番の評価ポイントはしっかりブンガクしているところ。
色々な角度から楽しめるのは、
やはり名著だな。
目指せ、100de名著ご出演。
岡田斗司夫先生に指南役をお願いしたい。
追記:読後すぐにアウトプットする機会がありまして、
言葉になっていない感覚を言語化していきましたら、ムクムクと湧き起こる、終盤に放った主人公ダグニーの心の叫びが、私の胸を打ち、奮い立つような気持ちに。
やはり、これは万人が読むべき。
歩けるヒトは歩かねばならないし、
走れるヒトは走らねばならないと、
あえて、べき、と思いましたね。