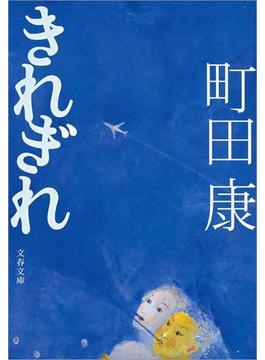きれぎれ
著者 町田康 (著)
絵描きの「俺」の趣味はランパブ通い。高校を中途で廃し、浪費家で夢見がちな性格のうえ、労働が大嫌い。当然ながら金に困っている。自分より劣るとしか思えない絵を描く知人の吉原は...
きれぎれ
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
商品説明
絵描きの「俺」の趣味はランパブ通い。高校を中途で廃し、浪費家で夢見がちな性格のうえ、労働が大嫌い。当然ながら金に困っている。自分より劣るとしか思えない絵を描く知人の吉原は、認められ成功し、自分が好きな女と結婚している。そんな吉原に金を借りにいく俺なのだが……。現実と想像が交錯し、時空間を超える世界を描いた芥川賞受賞の表題作と短篇「人生の聖」を収録。町田康ならではの、息もつかせぬ音楽的な文体。読むことがめくるめく快感、そんな作品です。
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
しょーもないこといい男の系譜
2010/10/24 07:53
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:analog純 - この投稿者のレビュー一覧を見る
えー、この小説は、なんやね。
この小説は、普通の関西人の男なら必ずみんな一日に一度は言うやろう(人によってはもっとしょっちゅう言うやろう)こんなせりふと一緒やね。これです。
「さぁ、仕事も済んだし、家帰って屁ぇこいて寝よ。」
一寸下品ですか。すんません。
このフレーズを、標準語に直すと、こんな風になります。
「さ、仕事も終わったことだし、家に帰って眠るとするか。」
こんな感じですかね。え? どっか抜けてますか? 「屁ぇこいて」がないって?
よぉわかりましたね。そやけど、これでええんですわ。
ご指摘の部分は、いわば言葉の調子を整えるためのフレーズなんです。そやから、意味なんて初めっからあらへんのです。
そんなら何のために喋ってんねんといえば、それが関西弁やから、としか言いようがあらへんですね。
関西弁には、こんな風な、誰に言うわけでもない、そやけど言わずにはおられへんようなフレーズが、しょっちゅう顔出してくるんですわ。
実はこの小説が、これと一緒やねと、まず思いました。
つまり、これは関西地域に昔から広く生息してる「しょーもないこといい」の男の系譜ですわ。
「しゃべくりの話芸」いうたらちょっと上品すぎるような気もしますが、それを芸というねんやったら、間違いなくこの「しょーもないこといい」は、関西弁芸のコアの部分に位置するもんですね。
そういうたら、筆者の最近作に浪曲講談をモチーフとした作品があるっちゅのは、もっともなことやと思いますなー。
ただ、以前この筆者の小説を読んだ時の感覚と較べると、なんやちょっと違う感じがするんですわ。
以前は確かこんな風に感じてたんですね。
「しょーもないこといい」と「不条理」を足して、さらにそれを「スラップスティック」に雪崩れ込ましたらこんな小説になりよる、と。
そやけど今回は、ちょっと違うなーという気が、かなりしてるんですわ。
何か、ちょっと、違う。スラップになりきってぇへん。
最初の方のタクシー待ちの場面とかランパブの場面なんかは、まさにその通りになってますね。
そもそも不条理っちゅもんは、サミュエル・ベケットの例を持ち出すまでもなく、ユーモアと、そしてその先に存在の悲しみがあるもんやと思うんですね。この辺にはそんなどたばたが、不条理な登場人物の言動と共に描かれています。
ところがその先の、母親の死のあたりになると俄然リアリズム、素直な落伍者(わりとええとこのぼんぼんの出来の悪いやつ、つまり「へらへらぼっちゃん」やね)のモノローグになってしもたように感じました。
それは、自らの心情に対して悲しいくらいに素直に描かれとって、なんや読んでるこっちまで心洗われるような気ぃがしてくるんですわ。
せやけどこの筆者は、いっつもこんなに哀愁を漂わせてたんやろか。
ところが、作品はもう一転します。
その先からまた、話がわけわからないようなっていくんですわ。
幻想描写と現実描写の接点が紙一重で、くっついたり離れたりしながら捻れ捻れて進んでいきます。そやけど悪夢というほど悪夢じみてもいません。狂気と言うほどその突き詰めも感じられません。
近いところで考えると、これはいわば、不条理にしばしば見られる「被害妄想」、なんやろか。
そして作品が唐突に終わっていくその時に、ああこれやこれや、この終わり方や。町田康独特の「情緒エンド」や。
『くっすん大黒』も『夫婦茶碗』も、なるほどこの「情緒エンド」でした。
とすると、やはり本作も、町田康小説の本道なんやろかねー。
「スラップ」と「情緒エンド」のさじ加減。
ついでに「しょーもないこと」を付け加えときますと、この作品は芥川賞受賞作です。
(そやからさじ加減がいつもより少しウェット、と考えるんはゲスの勘ぐり?)
しかし最後に一つ、上に書いた二つをつなぐ言語表現・しゃべくりオーバードライブ文体の強烈に独創的なイメージの噴出については、これはやっぱり、誰が何というても、抜群の力業や、町田康の吃驚するような才能やと、感心しきりではあるんですけどね。
読んでいくうちに、この文体にはまってゆく
2019/02/24 22:28
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふみちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
前に読んだ「くっすん大黒」が1997年の作品で、この「きれぎれ」が2000年の作品で芥川賞を受賞している。町田氏の作品を読むときに私は書いていることの内容を理解しないように心掛けている、といっても読み飛ばしているのではなくて吉本新喜劇を見ているような感覚で読んでいる。たとえて言うと帯谷たかしがいくら「あほんだら、あほんだら、あほんだら」と絶叫しようとも本筋には全く関係ないわけで、文章にぶら下がっている修飾語が他の作者の作品とは異質であることを理解して読み進んでいくと、その独特な文体も気にならなくなるというか読むことが快感にかわる。「権威を否定する者が公募展に応募するか」という、権威主義を否定するスタンスをとる旧友にむけての感想が今回のはまりどころだった
なぜかよくわかんなかった
2017/06/13 21:50
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ポージー - この投稿者のレビュー一覧を見る
きれぎれはなんだかあんまりわからなかった。夫婦茶碗はおもしろかったのに。たぶん僕の体調が悪かったんだろうと思う。