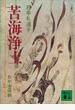ふみちゃんさんのレビュー一覧
投稿者:ふみちゃん

それでも、日本人は「戦争」を選んだ
2019/09/23 21:58
戦前の日本のことがよくわかる
7人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
作者が中高校生の前で講義した内容をまとめたものだが、かしこの学校の歴史研究部の生徒が相手とあって内容はしっかりしたものになっている。胡適の日本切腹中国介錯論(これは面白い論で、胡適という人は相当に頭がいい)、戦争に負けるということは戦勝国に自国の憲法を書き換えられてしまうということ、日露戦争では中国人が結構加担してくれたこと、松岡だって「堂々と退場す」だけの人ではなかったということ、日本の統治が悪いから三・一独立運動がおこったと言っているまっとうな軍人もいたということ、満洲侵攻にはまっとうな理屈がないと思っていた人も結構いたこと、逃げた関東軍ももちろん悪いが満洲に彼らを送り出した自治体はもっと酷いということ、などとってためになることがつまっている

対岸の彼女
2019/08/17 22:51
そうなんだよなと何度も頷いてしまった
7人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
中学時代、高校時代、いろんなことを語り合ってきた「こいつとは一生の友になるんだろうな」と思っていた友達も生活環境が変わって、大学生になり社会人になってしまうと疎遠になって日ごろ思いだすこともなくってしまう。それって寂しいことだけど仕方がないことかもしれない。いつも私が思っていることを小説にしてくれたのがこの作品のような気がする。同じ方向を向いていると思っていた友達が実は全然違う方向を向いていたということは今では当たり前に思えることをあの頃は全く考えもしなかった。この作品を読んでそんな友人の何人かに連絡を取ってみようかと一瞬思ったが、すぐにやめた。私たちは全然違う世界に生きているのだから。今は。

朝鮮紀行 英国婦人の見た李朝末期
2019/01/30 17:27
それにしても19世紀にこれだけ行動力をもった旅人がいたなんて何という驚きだろう
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
作者は「朝鮮にいた時、わたしは朝鮮人というのはくずのような民族でその状態は望みなしと考えていた。(中略)真摯な行政と収入の保護さえあれば、人々は徐々にまっとうな人間となりうるのではないかという望みを私にいだかせる」と、沿岸州の朝鮮人の暮らしぶりををみて考えが変わったことを辛辣ではありながも語っている。当時の朝鮮の両班や貴族の横柄な態度は平民のやる気を根こそぎ剃ってしまっていたのだろう。働けば働くほど金になる社会がそこにはなかったのだから。それにしても19世紀にこれだけ行動力をもった旅人がいたなんて何という驚きだろう。

52ヘルツのクジラたち
2023/12/04 10:01
タイトルの意味が切ない
5人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本屋大賞を受賞した作品、私はこの賞を受賞した作品はみんな読むことにしている(一部、どうしても読みたくない嫌いな作家のものは除く)、タイトルの52ヘルツってどういう意味があるのだろう、どうしてクジラではなくてクジラたちなのだろうと、疑問をもちながら読み始める、そうか、そういうことだったのか、他のクジラが聞き取れない高い周波数で鳴くクジラ、それは主人公のことだと思っていたら、「ムシ」と呼ばれて母に虐待されている少年や、「魂の番(つがい)」だったアンさんも52ヘルツのクジラだった、アンさんのことを思うとたまらなく切なくなってくる、主人公の小学校時代の担任教師、こういう人は結構いると思う、マニュアルどおりに行動するだけ、それで傷つくこどもがいるとは決して思わない人、こういった大人が子供に大人に対する不信感を植え付けていく
2019/01/28 12:31
読まなくてはいけない話
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
この作品は作者の取材に基づいたノンフィクション作品と思われがちなのだが、実は水俣病を題材として書き上げた私小説なのだ。何度も何度も被害者宅を訪問したうえで生の声を筆に起こしたというこtではなく、この人ならこんなことを言いそうだという発想で書き上げている。といって、生の声でないからこの作品に価値がないかというと、全然にそのようなわけはなく水俣病患者の気持ちをこれでもかというくらいに代弁しつくしている。その人の生の声をそのまま書いてしまうと、おそらくは本人の強い伝えたい気持ちが空回りして逆にこちらに伝わってこない可能性もあるのだ。それにしてもチッソという会社が貧しい水俣の住民を患者と非患者に引き裂き平然としているという醜悪者にはたまげた

恩讐の彼方に・忠直卿行状記 他八編 改版
2019/01/16 22:16
さすがの短編集
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
文芸春秋社の創設者という実業家としての肩書ばかりが私の頭の中にあったのだが、この短編集に収録されている10篇を読んでわかるのは、作家としてもとんでもなく才能がある人だということが認識できる(とても大作家には失礼な表現だが)。表題の「忠直卿行状記」「恩讐の彼方に」や「藤十郎の恋」と言った代表作と言われている作品はもちろんなのだが、死にたくないのに首をくくらなければならなくなった「頸縊り上人」や腕や足を切られても「命だけはご勘弁を」と恥ずかしげもなく叫び続けるなさけない武士を描いた「三浦右衛門の最後」などの恥ずかしながら今まで知らなかった作品も面白く読ませていただいた

韓国併合 大韓帝国の成立から崩壊まで
2023/02/02 10:16
韓国から見た日韓併合
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
私たちは「日韓併合」までの軌跡をいつも当然のことながら日本視点でみてきた、この本の興味深いところは韓国支店で見ていこうというところだ、私がなるほどと思ったところは、「属国」という言葉について、私は朝鮮というのは長期間、中国に従属していたとしか習ってこなかったが、「属国」というのは保護国や植民地を意味しない、内政外交の自主が保たれていたということ、これは確かに大韓帝国と日本の関係とは違う、また、この本にたびたび登場する日韓協約や日韓併合は日本側による強要・強迫で締結されたものだから無効だとする韓国では主流になっているということ、それを考えると日本側がいくら「あのころは、朝鮮人も日本人だったんだから」と納得させようとしても韓国側に通用しないのは当たり前のことだ

世界の果てのこどもたち
2022/02/01 09:53
この辛い話が本屋大賞3位、日本も捨てたもんじゃない
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
抑留されたシベリアで死んだ祖父は、、満州に派兵されていた。その祖父から祖母宛にこんな葉書が届いたという「〇〇(祖母の名前)元気でやっているか、△△、□□(母と叔母の名前)も元気か、満州は冬はとても寒いところだが、食い物もうまく、土地も広い、戦争が終わったら、こちらで暮らさないか」、祖父は日本が負けて、満州がロシアにずたずたにされて、日本人は中国人に報復されるなんて夢にも思っていなかったらしい。祖父が天国のような国と思っていた満州は、主人公の珠子にとって、親友だった八重子にとって戦後、地獄になる悲しい話、読んでいて辛くなる、でも、読み続ける。珠子、茉莉、美子、主人公三人は辛酸な思いをしながら最後は幸せを掴むが、右翼政治家が威勢よく気勢をあげているのを聞いていると胸糞が悪くなる今日この頃だ、戦争だけは絶対だめだ

清少納言を求めて、フィンランドから京都へ
2022/01/18 21:55
彼女の鋭すぎる考察
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
平安時代の女官・セイ(清少納言)とフィンランド人の私(ミア)、二人の物語。ミアは清少納言についての本を出版したいと、日本にやってくる、そして吉田神社の近くのゲストハウスに下宿することとなる、その間に東北大震災が起こって、一時、タイへ避難するなどの紆余曲折をへて、無事、本は出版されることとなった。フィンランドの、しかも日本語も片言しか話せない人が清少納言なんか理解できるのかと侮りながら読み進んだのだが、それは大間違い。彼女の紫式部が清少納言を芳しく彼女の日記に書かなかったことも、清少納言が道隆の死や定子の晩年の苦境を枕草子に描かず、宮廷の華やかな様子の描写に終始したので、すべて依頼者からの要望があったからという指摘は鋭すぎる、これが正解のような気がしてきた

どこから行っても遠い町
2021/02/14 21:25
どんな人にもドラマはある
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
東京近郊の町に住んでいる人たちの物語、魚屋さん、八百屋さん、予備校講師、料理屋さん、たこ焼きさん、占い師、いろんな人にはそれぞれのドラマがある、普段スポットライトなんか浴びたことがない人たちも掘り下げてゆくといろいろな人生が浮き彫りになってくる。ふと立ち寄ったたこ焼き屋で会話をしている男女や、おやじたち、この人たちはいいなあ、何も悩みがなさそうで、なんて思っていていたら実は・・・。でも、私のこれまでの人生にスポットライトを浴びせてもなにも浮かび上がってこないと思うよ、平凡だから。でも、川上弘美氏にかかれば私の人生も物語になるのか。登場人物の中では私はロマンのあけみさんに会ってみたい、あまりかかわるのは嫌だけど

私の名前はルーシー・バートン
2019/12/11 22:27
この作者の作品は、こころに染みます
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
この作者の作品を読むのは「オリーブ・キタリッジの生活」についで2作目。前の作品で感じた、何の変哲もなく感じられた生活の中にも確実に歪みはあり、その歪みは人々を苦しめているという感想は田舎町が舞台だった前作と同じように今回のニューヨークを舞台にした作品でも同じだった。いつごろまでは私は私小説的な作品というのは日本にしかない特殊な文学と思っていた、でもこのエリザベス・ストラウトや「シカゴ育ち」のスチュアート・ダイベック、「イラクサ」のアリス・マンローを読んでいるうちにクジラや拳銃は登場しないが読み応えのある小説はいくらでもあるということに気づかされる。当然のことなのだけど

日本文学全集 08 日本霊異記
2019/11/13 22:48
説話って、面白いものだったのですね
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
この全集に収められているのは、「日本霊異記」(伊藤比呂美訳)「今昔物語」(福永武彦訳)「宇治拾遺物語」(町田康訳)「発心集」(伊藤比呂美訳)で、いずれも説話集なのだが、説話というのは「伝説に類似するが、伝説は時代・人物が限定されないのに対して、説話は時代・人物が固有名詞で語られるのが特徴」と辞書には書かれているらしいのであるが、どうも説教臭い話だとずっと思っていた。仏教が隆盛を極めていた時代の話であるから仏教を土台とした話が多いのは当然であるのだが、みすぼらしい姿をした僧が実は尊い人だったりするから身なりで判断せずにやさしく接しろという説話があるかと思うと、ほいほい人を信用するから騙されることになるという話もある、どっちやねんと言いたくなる。でも、説話に対しての否定的な考え方が改めさせられおもしろく読むことができた。
2019/02/05 09:20
永遠のバイブル
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
この小説で龍馬が人気者になってから「実は坂本龍馬なんて、すごい人じゃなかったんですよ」的な本がたくさん出版されたと思いますが、そんなことは関係ありません。私が尊敬するのはいつまでも、司馬氏の本に出てくる龍馬なのですから

パプリカ
2019/01/31 12:50
筒井氏らしい作品
4人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
精神医学研究所の千葉敦子と時田浩作が無意識の世界である夢の世界に入り込んで、夢を見ている本人と一緒に、その夢に潜んでいる”意味”について探っていきます。こういう話は、筒井氏の真骨頂ですよね

ふがいない僕は空を見た
2019/01/28 23:05
どんどんはまっていく
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
2013年の「この文庫がすごい!」、また山本周五郎賞も受賞している。はじめの作品「ミクマリ」は正直にいうと、性表現がストレートで読むのがしんどかった。ところが連作を読んでいくうちに、登場人物ひとりひとりに愛情をわいてきてすらすらと読み進むことができてくる。なかでも私は良太とあくつの将来を応援したくなった。親友と周りからは認められている人を裏切る行為をしてしまう、それは嫉妬からくるもの。わかるわかるその気持ち。良太はおそらくこのだめ高校の中の優等生としていい大学に進学できるであろう、応援したい。またどの登場人物もダメ人間であっても愛すべき人に思えてくる(たとえば男のことしか頭にない良太の母とか)作者の技量に感心