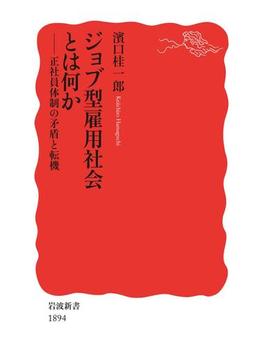ジョブ型雇用社会とは何か
著者 濱口桂一郎
前著『新しい労働社会』から12年.同書が提示した「ジョブ型」という概念は広く使われるに至ったが,今や似ても似つかぬジョブ型論がはびこっている.ジョブ型とは何であるかを基礎...
ジョブ型雇用社会とは何か
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
商品説明
前著『新しい労働社会』から12年.同書が提示した「ジョブ型」という概念は広く使われるに至ったが,今や似ても似つかぬジョブ型論がはびこっている.ジョブ型とは何であるかを基礎の基礎から解説した上で,ジョブ型とメンバーシップ型の対比を用いて日本の労働問題の各論を考察.隠された真実を明らかにして,この分析枠組の切れ味を示す.
目次
- はじめに
- 序章 間違いだらけのジョブ型論
- 1 氾濫するおかしなジョブ型論
- 2 ジョブ型の毀誉褒貶
- 3 メンバーシップ型の矛盾
- 第1章 ジョブ型とメンバーシップ型の基礎の基礎
- 1 ジョブ型契約とメンバーシップ型契約
- 2 入口と出口とその間
- 3 賃金制度と「能力」
- 4 対照的な労使関係
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
ジョブ型雇用に対照させて見えるもの
2021/12/19 16:00
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:第一楽章 - この投稿者のレビュー一覧を見る
雇用契約に労働者が遂行すべき職務(ジョブ)が明確に規定されている「ジョブ型」(日本以外ではこれが普通)と、雇用契約の中身はその都度遂行すべき職務が書き込まれる空白の石板で、むしろ雇用の本質が成員(メンバーシップ)になることという日本独自の「メンバーシップ型」を対比させ、それぞれの特徴と、日本の労働が抱える固有の問題をその歴史と合わせて簡潔に解説してくれています。「ジョブ型雇用」についての解説というよりも、むしろそれを鏡として、日本の「メンバーシップ型雇用」の持つ課題と矛盾を描き出しているところが、本書のポイントと言えます。
筆者がこの本を執筆するモチベーションとなったのが、マスコミも含めて、あまりに「ジョブ型雇用」の本質を外した言説がはびこっている現状で、それを軌道修正したいという思いからだそうです。「ジョブ型雇用とは何か」については本書をお読みいただきたいのですが、「ジョブ型雇用とは何ではないのか(どう誤解されているのか)」を挙げてみますと以下のようにいえます。
・職務遂行”能力”はジョブ型では関係ない
・ジョブ型が成果主義ではない
・ジョブ型は解雇しやすいわけでもない
・ジョブ型は新しくない
え?と思われたら是非本書を読みいただければと思います。
コンパクトながら内容の充実した良書
2022/04/10 00:58
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:アンカー - この投稿者のレビュー一覧を見る
コンパクトな新書サイズながら、ジョブ型雇用やメンバーシップ型雇用に関して詳細に論じている良書だと思います。認識を改められ、またとても考えさせられました。日本独特のメンバーシップ型雇用が成立していく経緯や事情はあまり論じられることがないので、興味深く読ませてもらいました。ただ、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用は、中身も社会的背景もあまりにもかけ離れているようで、転換とか移行がそもそも可能なのかどうか、不安しかありません。
ジョブ型とメンバーシップ型の理解の誤りと日本の雇用の問題を問う
2021/12/05 19:48
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:雑多な本読み - この投稿者のレビュー一覧を見る
今や雇用者の4割近くは非正規と言われ、統計的に見ても間違いないように思える。高度成長期や1990年頃のバブル崩壊までの低成長期は、正規社員、正規公務員が普通であったが、ここ約30年は国内での経済成長はなく、世界に大きく遅れ、非正規が増えるばかりであった。
また、労働組合の組織率もこの状況を反映するように低下していき、50%以上が10数パーセントまでに落ちっていっている。当然、非正規職員に組織に対する忠誠心はほぼない。日本企業の強みと言われる長期雇用、企業内組合、労使協調も崩壊していきつつある。
これをどう解釈するかというのは、企業サイド、労働サイドから諸説あるが、筆者はメンバーシップ型が後退し、ジョブ型雇用社会を構想する。
しかし、これに対して社会的に誤解が多いと説く。これまで、企業で長期雇用の下で、徐々ではあるが、確実に上がる賃金、社宅等の福利厚生で、不況期には解雇を避け、残業の削減等で対応される。最後は退職金、企業年金を含めて、日本の社会保障は企業が一定担ってきた。それが崩壊しつつある。しかし、これは大企業社員や公務員等に限られ、中小企業では別の世界があることも指摘する。法的に解雇規制が強いという俗説も排除する。
つまり、大企業社員や公務員はメンバーシップ型で、基本的に男性社員(一部で総合職の女性)に適用されており、他はジョブ型に近い実態があるとも指摘する。
筆者の論によると、ジョブ型が多数派になり、これに合わせた枠組みの必要性を説く。これまで言われている産業別や職業別とも違う枠組みでもある。
企業や労働組合自身が対応できていない中で、筆者は従業員代表制等の検討も行いながら問題提起を行っている。
比較労働法制史だな
2024/06/15 21:27
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:りら - この投稿者のレビュー一覧を見る
主に欧米の労働者との違いを比較しながらの日本労働法制史。
日本の労働者問題の経緯と法制度、判例のねじれ状態を解説している。
タイトルにある「ジョブ型雇用」の解説というよりは、欧米でのジョブ型雇用と日本でいうところのジョブ型雇用の意味は違うということをさまざまな観点から述べている感じ。
日本での経済界、労組側からの労働者の扱いの変遷が詳しく語られている。
これを読む限り、労組はwhoですな。
既得権益を守りたいがために、自分達の労働者としての価値まで下げておるようにすら感じられた。
それらを踏まえて今後の提言までを描きたかったよう。
文章が独特(大阪出身だから?)で、主語が何なのかわからないところがあるなど、やや読みづらいところもあった。
また、本や章のタイトルと文章の内容が合わないようにも感じた。
この問題に多少なりとも知識がないと、読みづらいところはあるかも。
しかし、膨大な資料をもとにまとめたものであることは伝わってくる。
ジョブ型雇用とかメンバーシップ型雇用とかだけでなく、非常に貴重な本。
「ジョブ型」を 日本は誤解し 受け入れぬ
2023/10/20 21:47
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:清高 - この投稿者のレビュー一覧を見る
1.内容
「日本的なメンバーシップ型と対になるジョブ型という言葉を作った」(はじめに1ページ)濱口桂一郎の見るところ、本書刊行当時の2021年5月時点において「ジョブ型」が注目されているが、濱口の言うものとは全然違うものである。そこで著者は「ジョブ型」と「メンバーシップ型」を対比して、それぞれの(筆者が見る限り、大部分が「メンバーシップ型」の問題点を指摘している内容であるが、一部「ジョブ型」の問題点も指摘している。例えばpp.92-96)問題点を記したものである。
2.評価
(1)日本が、外圧などを経て労働法規を改正するが、「メンバーシップ型」を前提としている日本において、本来の「ジョブ型」の規定が歪むさまが書かれており、興味深い。加えて、「メンバーシップ型」の問題点が多めで、日本社会に生きる者にとって啓発される内容であった。
(2)全体としては(1)の通りなので5点としたいが、濱口が強調する日本の「アカデミズムの幻想」(p.80)と、対比されるヨーロッパのことが詳しく書かれていないのでよく分からなかった。p.293にある文献、ブログを見ろ、ということなのだろうが、一読の限りでは本書の弱点のように見えるので、4点とする。
(3)なお、2点特記。
(ア)本書を読んで問題意識を持つのはいいが、とりあえずは日本の「メンバーシップ型」を理解し、それに適応するように努力した方がいい。学校卒業時に就職した方が楽である。
(イ)p.245「在日韓国・朝鮮人の雇用への悪影響」のところについての評価がまずい。在日韓国・朝鮮人は、大日本帝国が植民地にしたことを由来とするものであり、一般の「外国人労働者問題」(p.244)とは別の話である。
ジョブ型
2024/01/15 04:51
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
ジョブ型と、メンバーシップ型という雇用形態があること、初めて知りました。公務員とかは、昔ながらのメンバーシップ型みたいですね。ただ、今は、大学出ても、非正規の人も多いし…どうなんでしょうか