清高さんのレビュー一覧
投稿者:清高
2024/12/07 22:08
眠ってりゃ 休養になる わけじゃない
5人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1.内容
「健康づくりの三大要素は『栄養・運動・休養』」(p.4)だが、休養だけが体系化されていない印象である。そこで、日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹が、あるべき休養を探求した本。休養はたくさん寝れば取れるものではなく(睡眠は必要だが)、「『活力』」(p.104)を加えないといい休養にはならず、従って充電されない。休息タイプのような休養もあるが(睡眠も含まれる)、それ以外の6つの「休養モデル」(p.115)も組み合わせて充電を目指すべきである。
2.評価
(1)レビュー筆者は、休養といえば寝ることがメインだと思っていたので、本書の着眼点は気が付かず、いい着眼点だと思った。もちろん、積極的休養として軽い運動をすればいいというのは知っていたが(「アクティブレスト」で検索)、それのみならず人と会ったり趣味を楽しむのも休養になるというのは考えなかった(気分転換にはなるが、休養になると思っていなかったので)。
(2)ハウツーも充実している。「先に休みを確保しておく」(p.190-191)だとか、「手帳を『土曜日』に開く」(p.194にある見出しの表現)だとか、筆者が考えなかった方法が多かった。
(3)以上、休養について興味深い内容の本だったので、5点。

台湾 四百年の歴史と展望
2023/05/01 20:02
歴史修正主義的な 本でない
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1.内容
タイトルの通り、台湾の歴史を叙述した本である。本書p.235によると、「台湾は、オランダ(スペイン)、鄭氏政権、清国、日本(大日本帝国含め。筆者補足)、そして国民党政権という、いずれも『外来政権』に支配されてきた」(p.235。もちろん、レビュー当時は民進党政権であるが、本書初版は1993年だから書かれていない)様を叙述したものである。明国は台湾に価値を認めなかったが、清国は認めた。日本の植民地支配は苛烈であったが、その下で台湾は近代化し、日本の植民地運営は中華民国も肯定的に評価した(pp.237-238参照)。日本の敗戦などで中華民国になったが、国民党は「疑似『レーニン式の政党』をめざし」(p.170)ており、強権政治であった。しかし、共産主義に対峙するアメリカから民主化を求められ、台湾は民主化に向かっている。
2.評価
(1)本書の場合、筆者は「あとがき」から読んだが、「それゆえ私は、日本の台湾統治における『植民地化の近代化』を強調するのである」(p.237)とあり、日本を善とする、いわゆる歴史修正主義的な本と勝手に思ったが、当然そうではなく、筆者の見立てが浅はかだったということである。
(2)台湾の歴史の複雑さが理解できる本である。台湾の原住民、本省人、外省人の対立がわかり、台湾独立の意味がわかる本である(だから、最近は民進党でも「独立」を主張しなくなった)。もちろん、李登輝以前の国民党の強権体制をも理解できる。
(3)取り留めなく書いたが、以上の通りであるから5点とする。
2024/10/29 22:17
無茶苦茶な うえに独立も 形式的
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1.内容
大東亜共栄圏がいかなるものかを記した本。欧米に比べてそもそも脆弱な経済状況の大日本帝国は、そもそも英米と協調しないと生きていけなかったはずだが、英米と対立して共栄圏に命運を託した。しかし、英米と貿易していた時より豊かになったわけではなく、経済的に苦境に陥った。大日本帝国は、形式的には独立を認めていたが、実際は大日本帝国が支配していた。現在は行政権は内閣の属するものとされるが(憲法第65条)、当時の実際においては内閣と軍部に分立しており、方針が定まらず、それが苦戦の原因にもなり、共栄圏の経営の苦しさにもつながった。
2.評価
途中のデータが豊富な部分は、通読の際に眠気を誘うものであるが(もちろん、データの信憑性を疑っているわけではないので、データも熟読すべきである)、全体としては、大東亜共栄圏は、一部の見解のような、アジア諸国の独立を促したものではなく(例えば、フィリピンはアメリカから、1946年に独立を約束されていた。その前に形式上フィリピンは独立したが、改めて1946年に独立した)、無茶苦茶なプロジェクトで、誇れるものではないことがわかるので、5点。
GHQは日本人の戦争観を変えたか~「ウォー・ギルト」をめぐる攻防~
2024/08/29 22:02
日本人の 受け取り方は 多様だよ
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1.内容
江藤淳によると、日本人は、GHQ民間情報教育局(CIE)のウォー・ギルト・プログラムにより「間接的に洗脳された」(p.15、p.27.注1の文献は未読
)のだという。そしてそれは「保守論壇で支持され続けた」(p.16)という。しかし、江藤の言説は、実際のウォー・ギルト・プログラムを検討したものではない。実際のウォー・ギルト・プログラムは、時代によって異なるし(旧日本軍の問題の理解から東京裁判が中心になる、など)、CIEが考えていたような浸透もない。日本人の戦争のとらえ方も時代によって変遷し、1980年代から90年代は旧日本軍・旧日本の加害行為をクローズアップするものもあったが、その後は被害者としての側面が強い情報の流通が主流になった。このように本書はウォー・ギルト・プログラムの実際の検討を取っ掛かりに、日本における第2次世界大戦のとらえ方の変遷をたどったものである。
2.評価
筆者も保守論壇の、いわばウォー・ギルト・プログラム洗脳説に興味を持って本書を手に取ったので、ウォー・ギルト・プログラムの実際を見て、感心した次第である。興味のある人は江藤淳.閉ざされた言論空間:占領軍の検閲と戦後日本.文藝春秋,1994,(文春文庫).も併せて読むといいと思った。
また、ウォー・ギルト・プログラムを、日本人は素直に受け取るだけでなく、多様に受け取ったことや、その後現在までの第2次世界大戦のとらえ方の変遷も書いており、特定の情報を流したからといって一筋縄ではいかない状況が書かれており、参考になるだろう。
以上の通りであるから、5点。

客観性の落とし穴
2024/03/17 22:53
客観性で 生きにくくなり 経験もっと 重視しよう
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1.内容
科学の進化などによって、「自然も社会も心も客観化され」(p.149)るようになった。数値が力を持ち「人々が競争に追いやられる」(同)ようになった。一方で、「個別の経験の生々しさが忘れられがちになった」(p.150)。その結果、人は生きづらくなった(村上靖彦の見解)。もちろん客観性を全否定するわけではないが、生きづらくなっては行き過ぎである。そこで本書は、「個別の経験の生々しさ」を取り戻し、より生きやすい社会を作るために何をすべきかについて、「現象学」等のキーワードを用いて説明するものである。
2.評価
(1)参考文献に、小田中直樹.歴史学のトリセツ:歴史の見方が変わる時.がある(p.190)。思考の流れが、小田中の本の流れに似ており、面白かった。すなわち、小田中の本を読めばわかるが、歴史学は、客観性を重視したランケ派が今も主流であるが、オーラルヒストリーといった、「個別の経験の生々しさ」を取り上げた方法も用いられるようになった。本書のように、客観自体を否定はしないが、その問題点を克服するために「個別の経験の生々しさ」に焦点を当てるのは、大げさに言えば現代社会の流れに乗っている。
(2)内容面でも、客観性を全否定せず、「個別の経験の生々しさ」に焦点を当てようとする問題意識は、筆者はなるほどと思ったし、他の読者も読めばそう思うだろうと勝手に推測する。筆者は第8章の「アウトリーチ」をした・された経験がなく、読む限りではどちらもしんどそうに感じるが、筆者の経験不足が原因と思われるので点数は減らさない。
(3)以上の通りであるから、5点。

射精道
2023/12/12 21:49
射精につき 使える方法 満載だ
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1.内容
陰茎のある男性が、成長すれば行うであろう「射精」をきっかけとして、いかに性生活を営むべきかを記した本。思春期から中高年まで、射精障害が生じた時など、男性が経験するかもしれないことを、コンパクトな新書版でまとめている。
2.評価
(1)まず筆者が評価しないところ。
ア.武士道の強調。「『(ノーブレス・オブリージュ)』」(p.4)というのはわかるが。
イ.女性については第9章にさらっと書いてあるだけ。
しかし、本書にとって重大なところではないので、点数を減らさない。
(2)実践的な方法が満載なので、5点。以下、何点か。
ア.p.45「思春期における『射精道』」から面白かった。第9条は意識しなかったし、第14条や第15条も意識したことはなかった。恥ずかしながら「官能小説」(p.68)が使えるとは知らなかった。
イ.p.105「資料7」とp.112「資料9」は熟読が必要。筆者は、令和5年の刑法改正に不安を持っていた。「不同意」(ポケット六法令和6年版.有斐閣.の、刑法第176条、第177条の見出しにある)はどう判断するのだろうかと思ったが、「資料7」と「資料9」はいいヒントになると思った。
その他にも役に立つと思われる知識が満載なので、ぜひ。

基礎からわかる論文の書き方
2023/12/01 23:21
科学とは 何かについて 共感す
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1.内容
論文とは何か、というところから説く、論文の書き方の本といったところか。小熊英二は、東京大学農学部卒で、出版社勤務を経て、東京大学大学院総合文化研究科博士課程を修了している(プロフィール参照)ので、文系のみならず、理系の視点も取り入れ、豊富な例えを踏まえて説明している。
2.評価
(1)筆者は、現時点では、本書のような論文を書く予定はないので、書き方について特に見解はない。
(2)筆者が本書で感心したのは、第2章と、前述の「豊富な例え」である。豊富な例えの方は本書を読んでもらうとして、第2章の「科学と論文」について。科学は「お互いが共有する公理を前提にする」(p.65)ものであり、そのうえで「公開が原則で、誰でも疑っていいし、お互いに批判や対話をしながら進歩でき」(p.76)るものだという。科学に対する考えとして筆者の知る限りで一番わかりやすかった。理系の学部を卒業した賜物だろうか。
(3)特に(2)を長所とするので、5点。
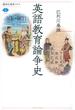
英語教育論争史
2023/10/28 23:28
大半の 論争過去の 蒸し返し
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1.内容
現在でも英語教育に関する論争はあるが(記憶に新しいところでは、大学入学共通テストにおける民間試験の活用。p.222参照)、それらの論争の大半は、過去にすでになされている。しかし、過去の論争に決着をつけなかったので、何度でも蒸し返される。そこで本書は、日本が近代化した明治時代から、英語教育についてどんな論争があったかを示すものである。
2.評価
(1)筆者は、大学受験を経験し、個人的に英語教育に関心を持っているので、本書の論争は全て興味深かった。大まかに書くが、とりわけ英語教育の目的が教養か実用かという論点が興味深かった(第3章や第5章が中心)。
(2)気になる点もある。本書でも示されているが、論争に決着がつかないのは、客観的なエビデンスに基づかないところが大きい側面があるから、調査を求めるか、蒸し返し自体を咎めないことのどちらかの方がよかったと思う。また、第5章の論争は評価しているのに、第6章の論争の評価が曖昧な理由がよく分からない。
(3)しかし、(2)に関わらず、英語教育のみならず語学全般について考えさせられた本なので、5点とする。
3.筆者のメモ(素人考え)
本書のニュアンスよりも、現在は英語のヘゲモニーが強いので、英語は全員が学ぶべきである。会話も大事だろうが、読めないと話にならないわけで(インターネットや学術論文を英語で読むことの重要性が増していると認識)、教養寄りの方法論、すなわち文法重視に意味があると考えている。ただ、アメリカの外交官が日本語を学ぶのに2200時間かかるのに(「『英語母語話者には極めて難しい言語』」(p.259)だから)、日本の中等教育の英語の授業は840時間しかなく(pp.259-260参照)、マスターするのは容易ではないから、工夫が必要だろう。

近代民主主義とその展望
2023/08/07 21:42
民主主義の 歴史と理念と 現状と
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1.内容
本書刊行時の1977年においては、世界中のあらゆる国で民主主義が制度化されているが(本書を読めばわかるが、当時のソ連流の共産主義も民主主義と無関係ではない)、それがどのように成り立ち、今後どうなるかを記した本。ギリシアのポリスや、イギリスの立憲主義は、元々民主主義的なものではなかったが(どちらも有権者になるには制限があったから)、それら古の制度や理念をも取り込んで近代民主主義が完成した。
2.評価
(1)近代の民主主義が、民主主義的なものではないものを用いて成り立っているという内容が興味深かった。日本国憲法第43条第1項には「全国民を代表する」とあるが、この表現が実は民主主義的でないことがわかり、目からうろこが落ちた。
(2)民主主義の歴史のみならず、民主主義の何たるかがわかるところがある。特に第2章2b「多数決の原理」のところ。多数決は擬制であり、「少数者の権利(略)の尊重と組み合わされてはじめて機能する」(p.142)ものであることは肝に銘じた方がいい。
(3)アメリカやヨーロッパの民主主義のみならず、共産主義や旧植民地における民主主義を検討していることが、とりわけ現在から見たら新鮮であった。
(4)以上の通りであるから5点とする。

人種主義の歴史
2023/05/15 21:39
西洋の 歴史から学ぶ 差別かな
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1.内容
「大航海時代から今日まで」の、主に西洋社会における人種主義(それは人種差別につながる)について概観したものである。いろいろな思想家が人種主義について述べており、その中には差別に反対の見解もあるが、その時代における主流の考えの影響を免れず、人種主義を肯定する記述も散見される。また、差別される側は、されている差別には抵抗しても、差別自体を悪としているわけでなない場合もある。このように、人種主義や差別にまつわる歴史は複雑なものである。
2.評価
著者の専門(プロフィールによると「フランス植民地史」が専攻)の範囲内で書かれていることは評価が分かれるかもしれない。すなわち、日本に関する記述が少ないと判断されるかもしれない。しかし、西洋社会における人種主義の歴史から翻って日本の歴史を思い返せばいいと思うので点数を減らさない。人種主義の歴史や歴史に複雑さを学べるいい本なので、5点とする。
3.追記
本書はジェンダー差別についても言及されている。重要と思われるのであえて特記した。

いつか死ぬ、それまで生きる わたしのお経
2023/03/12 22:19
現代語訳でいいし 気付きも もらえる本
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1.内容
お経の現代語訳、それに関連すると思われるエッセイ、そして、著者が朗読するお経の現代語訳がセットになっている。
2.評価
本書を読むまでは、(正直、お経を、現代の日本語に訳して何になるんだ?)と思った。しかし、「もともとサンスクリット語やパーリ語だったのが中国語に翻訳され、その中国語をそのまま、日本風のなまり切った発音で、意味のことなんか考えずに唱えている」(本書p.11)のであれば、現代の日本語に訳してそれを朗読するのもありだな、と思った。そしてCDの朗読がなかなか迫力があった。
また、お経や古典文学について気付きをもらえる本である。例えば、お経は語りであったり(p.12、p.27)、「日本古典文学は(『古事記』等は除いて)ことごとく皆な仏教文学である」(p.265)だったり。
以上の通りであるから、5点とする。
2025/05/16 21:47
論文とは違う 思考の実際
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1.内容
論文の基本構成はIMRAD(序論、方法、結果、考察の英語の頭文字。p.20)とされるが、実際の思考は行ったり来たりである(p.127.図3-2やp。147.図4-1「舞台裏」)。論文を構成する実際を、「リサーチ・クエスチョン」という言葉をキーワードにして明らかにする本である。
2.評価
書かれてみれば当たり前だと思われる読者も多いだろう。IMRADを意識して思考を進める人はまずいない。ただ、その「当たり前」とも思える方法を、「2W1H」だとか、豊富な図表だとかでわかりやすく説明できていると思われるので、筆者が本書で取り上げるレベルの論文を書いたことがないにもかかわらず、5点とする。
2025/05/02 22:00
「支配―被支配」の 関係重視かな
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1.内容
暦の上では、20世紀というのは、1901年から2000年の事であるが、歴史学の世界では自明の事ではない(らしい)。本書においては、1870年代から1990年初頭を「『長い20世紀』」(p.6。漢数字をアラビア数字に改めた)として概観する。1870年代においては「ヨーロッパ諸国によりアフリカ分割」(p.5)があり、そこから帝国主義に突入するが、1990年のナミビア独立、1991年の南アフリカにおけるアパルトヘイト終結宣言(p.5参照)をもって概ね植民地が旧宗主国から独立し、人種差別を否定する流れが出来たからである。なお、21世紀においても「帝国」や「帝国主義」(ともにp.4)という評価が用いられるが、本書はそれに賛成しない。また、ロシア革命からソ連崩壊までを20世紀とする「『短い20世紀』論」(p.7)は「ヨーロッパ世界を中心とした時代区分」(p.7)なのでこちらも採用しない。なお、「帝国世界の重層性をよく示した地域」(p.10)である、アイルランド、南アフリカ、沖縄について「定点観測」(p.9)もする。
2.評価
「支配―被支配関係」(第1章のタイトル)を重視した本書の歴史叙述は、たしかに「『短い20世紀論』」より、ヨーロッパ人ではないアジア人である日本語話者にとって有益である。
日本も支配の側に立っており、第2次世界大戦ではファシズム陣営であったのだから、本書のような否定的評価は当然だが、それにとどまらず、帝国を形成したイギリスやフランス、帝国を批判したが帝国の要素を持っているアメリカやソ連についても否定的な評価がされており、フェアな本である。
以上の通りであるから、5点。
2025/04/28 21:24
クィアの視点で K-POPなどが わかる本
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1.内容
現在のK-POPは概ね10代、20代を対象とした音楽だが、クィアの人は年齢に限らずK-POPを消費している。その消費から、シスジェンダーの異性愛を前提としたK-POPに新たな解釈を加えている論文を集めたのが本書である。
2.評価
(1)まず、K-POPに興味がある人でも、嫌いな人でも、楽しめる本である。興味のある人であれば、新たな視点で楽しめるし、嫌いな人であれば、K-POPが前提としているところを非難するくだりを読んで溜飲を下げればいいからである。
(2)少々K-POPとズレると思うが、BLやドラァグについても分かる。BLは実は日本初のようであること、ドラァグがパロディの側面があること、など。
(3)曲の紹介も結構ある。本書の解説を参考にして聞いてみるのもいいと思う。
(4)以上の通りであるから5点。
2025/04/25 23:09
箇条書き多用で 読みやすい本に
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1.内容
戦争が起きるのには5つの理由があり(p.31-33)、それを踏まえたうえで、平和をもたらす技術は4つあり(p.36.第7章から第10章に対応)、「脆弱な社会に住む人々」(p.405)「に手を貸したいと思っている外部の人間」(同)「に求められている」(同)のは、「『漸進的平和工学者』」(p.405)になることであり、それには「十戒」(p.411)がある。このように、本書は、戦争が起きる理由、平和をもたらす技術、平和を実現するために外部の人が持つべき心得、といったことが箇条書きになっているが、そのベースは、ゲーム理論だという。
2.評価
(1)学術書であるから、注釈も膨大で、筆者はそれをいちいち検討していない。従って、本書の主張が妥当かどうかはわからない。
(2)それにもかかわらず、箇条書きの形式もあってわかりやすく書かれており、戦争について考えやすい本になっているので、5点とする。









