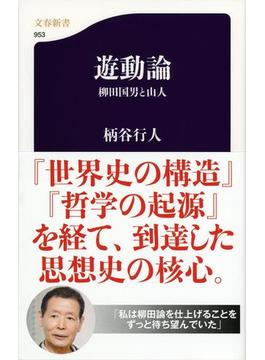難しいけど,おもしろい
2015/08/17 14:23
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:かずくん - この投稿者のレビュー一覧を見る
佐藤優氏の著書に取り上げられていたので興味を持ち,読んでみました。これまでの柳田国男についていわれていた言説が,根底から考え直してみるとそうではない,ということが示唆されており,なかなか難しかったものの,面白い本でした。特に「戦争で亡くなった英霊に養子縁組して,その御霊を祭ろう」という思想は新鮮でした。
世界史の構造における交換様式に遊動論を補助線として引くと…。
2014/03/10 20:09
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:やびー - この投稿者のレビュー一覧を見る
大著「世界史の構造」の著者が、柳田国雄の「遊動性」を概念に新たな思想を展開する待望の一冊。民俗学者、柳田国雄は「山人」を通して国家と資本を乗り越えるべき社会を追い求めたと、著者は説明する。
著者の作品を読んでいれば柳田国雄の思想を通して自らの思想を保管しうる、いわば「補助線」を引いて新たな側面からの視点を提供していると理解出来る。
初めて著者の作品をよんだと仮定すれば、著者の文章は柳田氏の文章を引用しながらも内容といては幽玄であり本質を理解できるか不安である。(…書く言う私も、理解者なのか不安であるが)特に第三章の実験の史学に関しては、腑に落ちないまま文章を読み進めてしまった。付論にて、遊動性を四つの交換様式に当て嵌めて持論を展開する。詳しくは作品を読んで欲しいが交換様式DにおけるXを明らかにしないまま論を終える。Xの説明をすると別著に触れればならないので割愛するが、飽くまで読まれる諸兄が著者の愛読者であると仮定したい。
日本における交換様式Dは既存のアソシエーションを越えるもの(信仰心やネット社会を代表する新たな共同帯)と仮定したいが、ふと日本人の底辺にある思想を考えてみた。祟りや怨霊、コトダマに顕す日本人を操る見えない力を考えた場合、古代から続く祭やハレとケガレ。行動に力点を加える作用を日本人は持っているのでは無いか?分配、贈与、返礼、交換、日常生活を遡及的に見れば氏の提案は人間を動かす原動となる力点である。
しかし、著者はあえて、様式Dを提示する事により多様性を持たせる。著者は遊動性を提示した。古代の日本人を読み解いていくと私は、祟りや言魂、怨霊や鎮魂の思想を軽くみたくない。
結論の部分が駆け足のような気がする
2016/09/08 23:10
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:まなしお - この投稿者のレビュー一覧を見る
柄谷行人にしては読みやすい文章である。でも何か物足りない感じがする。結論の部分が駆け足のような気がするからだ。約200ページという枚数では、柳田国男を論じきれないのか?それならもっと枚数を費やしてじっくり書いて欲しかった。今一度更に大部の本を望む。
投稿元:
レビューを見る
【柳田国男、その可能性の中心】柳田は「山人」を放棄などしていない。それを通じて、社会変革の方法を生涯、探求していた。画期的な転回をもたらす衝撃の論考。
投稿元:
レビューを見る
まず、柳田国男は純粋に民俗学の研究者だと思い込んでいた。それは完全に私の誤解であった。柳田は今の東大法学部で農政学を学び、卒業後は官庁で農業の政策にかかわる仕事をする。いろいろな地域で農民などから聞き取り調査をする中で、民俗学的な研究につながっていく。例によって、いろいろと心に響いた箇所はあるのだけれど、全体的には結局きちんと理解できないまま読み進んだ。そして、付論の最後の最後にこうある。「柳田がそこに見いだそうとしたものは、交換様式Dである。」次のページは見慣れた交換様式の4つの形態の表があり、そこで終わっている。交換様式D、いまだ名づけられていないX。何と魅力的であろうか。それを柳田も見つけていたという。もう一度読み直さなければならない。
投稿元:
レビューを見る
柳田邦男の「山人」という今は忘れられた人々のことをテーマに、その人々が持っていた概念を遊動性という言葉から解き明かそうとされています。国家などに所属をしないという点では、遊牧民もそうですが、彼らはそれに所属していなくても依存しています。そうではない、遊動性を持った過去の人はどういう人であったのか、その答えに一番迫ったと思われる柳田邦男の書からそれを知ろうとされています。
現在では、それに近く残っているのは世界宗教もしくは、この日本だけなのではとも思えました。
投稿元:
レビューを見る
去年読んだ大塚英志の http://www.amazon.co.jp/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%AE%E5%9B%BD%E3%81%8C%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%A7%E3%82%82%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%9F%B3%E7%94%B0%E5%9C%8B%E7%94%B7%E5%85%A5%E9%96%80-%E8%A7%92%E5%B7%9DEPUB%E9%81%B8%E6%9B%B8-%E5%A4%A7%E5%A1%9A-%E8%8B%B1%E5%BF%97/dp/4040800184/ref=tmm_hrd_title_0?ie=UTF8&qid=1454264566&sr=8-1 に続く柳田国男本です.
これまた前回同様端折って書けば「富の配分」をいかにするかってことが語られてるてます.
が,肝心の解答らしきものが書かれてません.大昔にあった(であろう)社会(システム)をバージョンアップして現代に持ち込めってことなんだろうけど,はてさてどうやったらよいのでしょうかね.
ま,考えてみます.
投稿元:
レビューを見る
柄谷行人は『世界史の構造』を書くにあたって、色々と調べ上げたということだが、柳田国男の遊動論もその中のひとつであったという。それでも、なぜ、今となって柳田国男なのか。
その答えは、彼の交換様式論にとって、柳田国男の遊動民(ノマド)の理論が重要な位置づけを占めていたからであった。二種類の遊動民(その一つが有名な山人)をあり、それが理解の鍵でもあるとする。遊動民と交換様式論の関係について引用すると次の通りである。
「各種のノマド(遊動民)が、交換様式C(商品交換)の発展を担ったのある」そして、「遊牧民は、交換様式Cとともに、交換様式Bの発展を担ったということができる」
さらに「定住以前の遊動性を高次元で回復するもの、したがって、国家と資本を超えるものを、私は交換様式Dと呼ぶ」
そう、『世界史の構造』における交換様式Dが、遊動性に関係しているのだ。
「交換様式Dにおいて、何が回帰するのか。定住によって失われた狩猟採集民の遊動性である。それは現に存在するものではない。が、それについて理論的に考えることはできる」
だが、その後の議論は具体的には進まない。
「彼がいう日本人の固有信仰は、稲作農民以前のものである。つまり、日本に限定されるものではない。また、それは最古の形態であるとともに、未来的なものである。すなわち、柳田がそこに見いだそうとしたのは、交換様式Dである」
と相変わらずの我田引水っぷりで本文を終える。
柳田国男を読んだことがなかったこともあり、ちょっとわからなかったな。
投稿元:
レビューを見る
(01)
柳田国男が用いた「実験」あるいは「実験の史学」をヒントに,1960年代以降,た評価が左右に揺らいでいる柳田の立場を擁護し,柳田テキストの新たな読みに挑んでいる.
柳田が一貫して「山人」の実在を手放さなかったこと,それが「一国民俗学」や「固有信仰」となって,当時の国際情況が国内事情(*02)に合わせ批評的に持ち出された概念であることが本書で主張されている.
民俗学や一国民俗学については誤解されることも多い柳田であるが,農政学や経済「経世済民」との関係により,柳田がその学をどのあたりに位置づけしようとしていたのかが分かる.著者は,柳田が「先祖の話」で説いた魂のゆくえの先を見極め,海と山の同位性や,平田国学や国家神道への批判性にも言及している.
タイトルにある「遊動」とは何か.柳田自身が使ったわけではないキーワードであるが,現代哲学のノマドや網野史学の成果も踏まえ,柳田のテキストにあった遊動の解明を試みている.しかし,著者が提唱する遊動や交換様式にもいくつかの内実や分類があって,この試論は批判的に継承されていく必要があるだろう.
(02)
家の延長に国家があるわけでないこと,オヤコ関係が遊動の双系制にあっては血縁関係に結ばれた親子に限らないことなども本書に指摘されている.おそらくそれは未来の社会に向けた著者の意見でもあるだろう.
投稿元:
レビューを見る
遊動論 柳田国男と山人 (文春新書)
(和書)2014年02月13日 22:52
柄谷 行人 文藝春秋 2014年1月20日
「思考実験=抽象化」ということと遊動性。
抑圧されたものは強迫的に回帰する。
柄谷さんの言いたいことを理解しようとそれぞれ考え思考実験(抽象化)してきた人たちにとっては柄谷さんがかなりわかり易い言葉と柳田国男という日本人にとってかなり具体的な例より解説されている。
今まで自分の中で疑問になっていた部分が氷解されています。
柄谷さんは人間が思考実験と遊動性をどのように実践していけばいいのか?抑圧された自然状態(遊動性)が強迫的に回帰するということが思考実験とどのように関係すればいいのか?を示している様に思う。
人間を弱者として体系化するのではなく弱者から格差の解消を目指すということ、それは人間の関係にある格差を止揚することを目指す姿勢であるのだろうと思う。それが思考実験としてありえるがスティグマされ不可触民のようにされているものであるが実践として非常に有効なものであると感じた。そういったものが強迫的に回帰するというのは僕のような人間にとって非常にオプティミスティックに感じるところである。
「小さきもの」の思想 (文春学藝ライブラリー)も楽しみにしています。
投稿元:
レビューを見る
「付論」が、たまたまいま読み始めた、同じ著者の『世界史の構造』の最初の章とほぼ同じことが書かれていて興味深い。この本のあとがきを読むと、最初に付論から読むとよいかも、みたいなことが書いてあって、それせめてはしがきみたいなところに書いておいてほしかった、と思った。ま、『世界史の構造』との重複を考えてそうなってるのかもしれない。『世界史の構造』では抽象化されてわかりにくくなっているものが、この本では具体的なものに仮託されているので、副読本的に有効なのではないか。