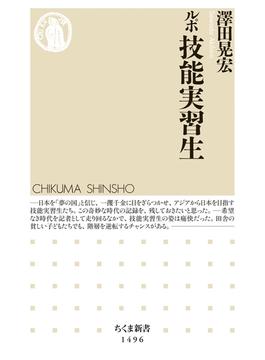技能実習生の実情を知れました
2020/07/28 13:41
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:広島の中日ファン - この投稿者のレビュー一覧を見る
「技能実習生」として今、日本に多くのベトナム人がやってきています。彼らはどうやって日本に来るのか、そのシステムを著者が現場まで体当たり取材した1冊です。
文章のほとんどは、技能実習生のシステムを考えるものになっています。実体験レポートの文章は、読む価値ありと思います。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:七無齋 - この投稿者のレビュー一覧を見る
どちらかと言えば好意的視点で見ている外国人労働者の在り様だが、現状を把握することが大事だといえる。ベトナム、フィリピン、韓国の事情を踏まえた論じ方だが無論すべてを物がっているわけではない。どのような制度が望ましいのか議論のきっかけにはなる。
投稿元:
レビューを見る
主にベトナムからの技能実習生を対象に、実習生本人や送り出し機関、監理団体や受け入れ企業を取材し、技能実習制度の実態を記載したルポ。こういった外国人労働者問題を扱った図書では、著者が自分の信念を強く訴えるような書き方になることが多いように思いますが、本書はあくまで、この制度の実態はこうですよ、というある意味で中立的な描き方に専念しているように思われて、読み応えのある1冊でした。
本書を読む限りでは、ベトナムからの技能実習生は日本での労働が"劣悪な環境ではあるが、期間限定の一獲千金の場"であることを予め知ったうえで来ているので、そういった意味ではこの制度は実習生にとっても受け入れ企業にとってもWinWinである制度なのかしらと思いました。
ただ、やはり以下のような点で、これが国として行っている公的な制度の実体か?と思わずにはいられませんでした。
〇「技能実習」制度の趣旨である「前職要件」はほぼ偽造
日本サイドの実習実施企業が求めるのは「単純作業に就く労働力」であり、実習生が求めるのは知識や技術ではなくお金(p.79)なので、公然の秘密として偽造が行われている。
〇送り出し機関から監理団体や受け入れ企業への接待費用が実習生の自己負担として重くのしかかっている
ベトナム側の送り出し機関が求人票を得たり、契約を得たりするために、日本の監理団体や企業を接待したり、裏金を渡したり、付加的なサービスを提供したりすることが常態化している。これらの費用が最終的には実習生自身から徴収されており、実習生の借金額を大きく増やしている。
このことが詳細に記載されている第2章「なぜ、派遣費用に一〇〇円もかかるのか」は圧倒される内容でした。実習制度に関わっている日本人たち(もちろん全員ではないわけですが)のひどさに、本当に胸糞悪くなりました。
結局のところ、実習生を助ける立場であるはずの監理団体は受け入れ企業とずぶずぶで、「監理団体」という役割を到底果たしていなさそうに思われました。これがこの制度の一番の欠陥のように思われました。
実習生が本当に困った立場になったときに、助けてくれるところがない、という意味で、結局は「現代の奴隷制度」のそしりをまぬかれないだろうなと思いました。
そしてこういう実態を知りつつ、日本という国はこの制度をそのまま続行しているわけで、とても国際社会に誇れたものではないなと改めて思ってしまいました。
投稿元:
レビューを見る
約3年間技能実習生の入国後講習に携わり、それ以前からボランティア教室で数多くの技能実習生に接してきた私は、テレビや新聞で技能実習制度の悪い面ばかりが報道されることに疑問を持ってきた。本書で特に興味深かったのは、ベトナムで元技能実習生の今を追跡していたこと。家だけでなく土地を買っていたり、元技能実習生同士で結婚したり再び日本に向かったり。
本書でも触れていたように、フィリピンは技能実習生に費用の負担をさせておらず、失踪も少ない。にもかかわらず相変わらずベトナム人ばかり多いのは実習生から搾取したお金で営業が行われているから。残念で仕方がない。
また、将来留学したいという実習生に、日本語を学ぶためなら技能実習で十分だと言ってきたが、技術、人文知識、国際業務のビザ取得には大卒が条件と知って納得した。
投稿元:
レビューを見る
著者はアダルト誌編集者や「SPA!」記者などの経歴のあるライター。あとがきにあるように、以前は大卒を経ずに著者のようにアルバイトやフリーのイラストレーターとして編集部に入り込み、その後才能が認められ世に出た有名人が結構いたが、著者はその最後の世代を自認する。まとまった著書としては本書が処女作となるようだ。制度の裏に隠された矛盾をつくというルポとしては伝統的なスタイルながら、問題提起がシンプルで構成にも無駄がなく、読みやすい。ストレートに著者の思いが伝わってくる良作だと思う。
日本の技術力の海外移転という国際貢献の美名のもと、単なる労働力受給の調整弁として扱われる外国人技能実習生。外国人側にも日本語習得と割の良い給料獲得以外のインセンティブもなく、結果として仲立ちする国内監理団体や外国人送り出し組織にチャリンチャリンとカネが落ちていくシステムが温存されている。一方、正面から国内労働力の補填を目的にした特定技能外国人制度は、人手不足に悩む国内中小企業と移民反対派の双方に気配りした結果、実質的に転職ができない、送り出し機関にメリットがないなど、外国人側にも雇う側にも使い勝手の悪い制度になってしまう。
新興国が発展し所得が増える中、経済成長力の衰えた日本は労働力を吸引するだけの魅力を保てるのか。「共生」といえば聞こえはいいが、所詮日本は外国人労働者を日本人がやりたがらない仕事の割り当て先としか考えていないのではないか。著者の提言は重い。
しかし、そもそも特定技能外国人は外食産業や宿泊業がターゲットだが、そこへこのコロナである。労働力の逼迫というそもそもの大前提すら崩れてしまったこの制度、これからどこへ向かうのだろう。
投稿元:
レビューを見る
技能実習生のルポといえば、NHKのドキュメンタリー番組「ノーナレ」にあるような外国人虐待に焦点を当てたものを思い浮かべますが、筆者は実習生へのいじめや性的強要といったさまざまな憎むべきハラスメントが存在することを認めながらも、同番組のワイドショー的な問題の取り上げ方と取材態度を疑問視しています。
本書では技能実習生のなかでも近年では日本への渡航が最も多いベトナム人実習生を対象として調査を行っています。問題をはらみつつも技能実習生が増加する理由は、日本の一部の実習先でそのような惨状があることを実習生希望者たちに知られていないためではなく、知ったうえで希望者である、周囲には山しかないようなベトナムの地方出身の高卒や中卒の若者たちにとっては日本での報酬に魅力があるからであり、実際に帰国後の多くの実習生たちは地元に家を建てたり商売を始めたりとその成功を証明しており、受け入れ先の日本だけではなく送り出し元にとっても「技能実習」は建て前に過ぎず、出稼ぎ目的であることが明らかになります。
そんな実習生から失踪者が現れる主な理由として、実習生として渡航するためには日本円で約100万円という彼らにとっての大金を送り出し機関に納める必要であり、多くの実習生が借金をして準備金を用意するために簡単には帰国できない事情があります。なぜ技能実習のためにそこまの金額を要求されるのか、筆者はベトナムの送り出し機関への調査を通して日本の技能実習生管理団体への性的なものも含めた過剰な接待を知るとともに、送り出し機関に対してキックバック(賄賂)を要求する日本の管理団体の腐敗に行き当たり、このような接待漬けのスタイルが、かつて日本に最も実習生を送り出していた中国の送り出し機関の関係者によって客とノウハウをそのままベトナムに持ち込まれたことに由来することを知ります。
筆者は日本以外の受け入れ国として韓国での調査において、外国人の受け入れを政府機関で実施することで中間搾取を取り除くことに成功していること、送り出し元としてフィリピンが海外労働者からいかなる費用も徴収しない方針を取ることで失踪者の低さが突出していることを探ったうえで、政府同士のやり方次第で管理団体にキックバックが求められる構造を排除し、受け入れ先企業の選定を厳しくすることで実習生への搾取やハラスメントを防いで、現状の大きな問題点は改善できることを提示しています。
筆者は技能実習生への虐待の存在を認めつつもそこを一面的に批判することを目的化する姿勢をけん制しつつ、ベトナム、日本、韓国での取材を通してこの制度の実情を立体的に描き出すことに成功しました。同時に、まえがきとあとがきなどで触れられる筆者の個人的な事情とともに今後成長が続くであろうベトナムと、停滞し先行きに不安を抱える日本を対照的に浮かび上がらせる結果にもなっています。
投稿元:
レビューを見る
技能実習制度の実像を理解するための良書。上っ面の行政資料のコピペではなく、送り出し機関や監理団体にも取材を敢行しており、冷静に実像を描こうという筆者の気迫が感じられる。
「一番の課題は受け入れ企業の選定ではないか」「技能実習生に関わる日本人は゛程度が低い゛んですよ(ある送り出し機関の社長)」の部分は、まさにその通りと思った。
受け入れ企業の6割は零細企業。遵法意識も薄く、生産性も低い。当然最賃労働。日本人労働者には見向きもされなくなった個人商店のような零細企業が、業界団体のロビー活動を通じて政治家に働きかけ、技能実習生という低賃金労働者を供給してもらう。技能実習生もそれを知って稼ぎにやってくる。
であれば、せめて一生懸命汗を流してもらい気持ち良く稼いでもらえばいいのだが。
そこで、゛程度の低さ゛を見せてしまう日本人の下層経営者たちには、失笑するしかないと感じた。
投稿元:
レビューを見る
技能実習制度の仕組みなどを詳しく解説してくれている。多くの人への取材を組み込んであり、読み応え抜群。
- 技能実習制度は技能を自分の国に持ち帰ることを前提としているが現実は労働力となっている
- ベトナムから来る人が最多
- 日本の最低賃金でも月収2・3万円のベトナムでは高い
- 前職要件に関わる偽装が多い
- 接待などのコストも技能実習生側の負担に回る
- 知らされていたよりも給料が低い場合もある
- 韓国も受け入れ先として競合する
投稿元:
レビューを見る
技能実習生という制度について知識をつけたく、手に取りました。
タイトルの通りで、様々な関係者に当たりながら丁寧に取材を重ねた結果が記されていました。技能実習生という複雑な制度を少し理解できたと思います。
都合のいいときだけの、使い捨ての労働力ではなく、同じ国で暮らし、多くの人の生活を支えてくれる実習生に敬意を表した世の中になればいいのにと考えます。
投稿元:
レビューを見る
https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480073075/
投稿元:
レビューを見る
技能実習生の実態を筆者が実際に現場に行き、リアルを書いた良書である。
よくある技能実習への単なる批判ではなく、実習生が醜悪な環境でもなぜ日本に働きに来るのか、正確に書かれていると感じた。
最初に描かれているベトナム人の300万円の自宅は写真の掲載があったが、
圧巻であった。なるほどこのような夢を求めてベトナム人は日本に来るのか。。
もちろん、メディアで騒がれているように明るい現実だけがあるのではない、
ベトナムの送り出し機関に登録するために、実習生は100万円程度用意が必要。
大抵は前借りをする。場合によっては実家の家や土地を担保にする。
やっと日本に来られても、残業が少なく給料が少ない場合、失踪し、他の場所で働くことになる。失踪者の斡旋人も数多くいる。
なぜ100万円も必要になるのか、それは技能実習制度で賄賂が多くまかり通っているからだ。送り出し機関が監理団体に賄賂を渡し、ベトナム人がきた際に監理団体を猛烈に歓迎するためにお金が必要となる。そのお金を実習生が払っている。
それだけお金をもらっている監理団体は、受け入れ企業の監理業務を怠り、ベトナム人が制等にお金を貰えていなかったりしている。
特定技能が新設されたが、まだ合格者は非常に少ないという現実がある。
とにかく非常に勉強になった。
投稿元:
レビューを見る
諸外国から奴隷制度と批判される我が国の技能実習制度とは、いったいどんな制度なのか外国人労働者は、どう感じてのか、実態を知りたかった。
ベトナム実習生の実情について、現地の状況など良く分かりました。特定技能制度が始まり、コロナの見通しが経ってくると、社会はどのように動いていくのだろうか?
ただ、裏金や接待のために技能実習生の借金を背負わせているような馬鹿な制度は認める訳にはいかない。呼称が変わって、出稼ぎではなく、日本に夢を持ってくる若者たちが明るい未来を描ける制度になって欲しいものだ。
投稿元:
レビューを見る
大学の授業での課題図書だったので必死で読んだ。なんか、ひどい労働環境なんだろうなあと思っていたが、想像以上だった。システムとか、機関の問題が大きいように思った。
投稿元:
レビューを見る
国際社会からは「奴隷労働」だと非難されている「技能実習生」についてのルポタージュだ。本書ではベトナム人に焦点が当てられて書かれている。最低賃金の手取りからさらに家賃なども差し引かれての収入で、3年間で300万貯め込んで本国に帰り家を建てるベトナム人もいることは確かだけれど、失踪しなければならないほど劣悪な条件で働かされている外国人もあとをたたない。これは本国の送り出し機関とそして日本の監理団体がクソだからだ。日本の監理団体は帳簿に形跡が残らない仕組みでキックバックを送り出し機関からもらっている。本国で飲めや歌えや抱けやの接待をベトナムで受けたり、または現金を実習生に運ばせたりしているらしい。結局そのお金のしわ寄せは、実習生が支払うことになる。70〜100万円が送り出し機関に支払っている。技能実習生は転職が許されない。仕事が嫌なら、辞めて本国へ帰るしかない。しかし、帰ったら送り出し機関に支払った借金が残っている。ベトナム人の平均年収は25万円だから、返す事も出来なくなる。だから失踪して、少しでも給与の高い仕事を探すのだけれど、入管に見つかれば強制収容そして強制帰国をさせられてしまう。技能実習生は以前は中国人が多かったらしい。しかし国力は逆転しているので、今や日本の労働力が中国に買われている状態。こんな制度も、アジアの国々がやがて日本を追い抜いて、見向きもされなくなるだろう。
投稿元:
レビューを見る
技能実習生に関わる人々を中心としたルポ。実態がよくわかる。
近年開始された特定技能制度への移行が望まれる中だが、それらも問題点が指摘される。
個人的には、
1.受入先企業の責任を強く求めること
2.送出機関、ブローカーの搾取排除
が肝要と考える