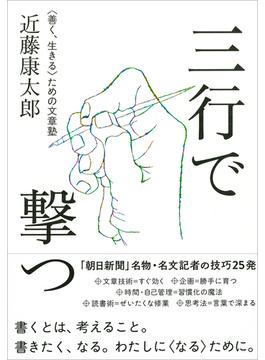5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なっとう - この投稿者のレビュー一覧を見る
ライターさん向けの、文章を書くことについてや向き合い方についての本ですが、「書くことだけでなく、描くことにも通ずるのではないか」と思って手に取りましたが、大正解でした。
勝手に自分の表現方法に当て嵌めながら、学ばせていただきました。
突然悪魔に襲われた時、必ず読み返すと思います。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ごーいち - この投稿者のレビュー一覧を見る
文章を書くことへの情熱が満ち満ちて、圧倒される。それでいて、説教くさくなく、ユーモアがある。 他人が考えた常套句ではなく、自分の五感で感じたものを書く。 「善く生きる人、おもしろい人が、いいライターだ。」これに尽きる。
話半分で十分な道楽教室
2024/06/16 21:24
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ブラウン - この投稿者のレビュー一覧を見る
役立てられそうな要素は全体の半分くらいか。成功者の語りになっていて、一般化するには怪しい項目やら、酒の席の与太話がお似合いな寄り道がどうにも目障りだ。後半に標榜される訓示ほど、著者の語りの凄みで誤魔化されて、中身を希釈されているように見えた。
特に科学の古典を読めという点はいただけない。老人が馴染みのある古い知識を見直して、最新の知見にアップデートするためには良いだろうが、遠回りが過ぎる。
投稿元:
レビューを見る
書くことに関して、新しい発見と実践してみようという意欲が湧く内容だった。言葉の選び方や冒頭のつかみのセンスは、経験を積む事しかないんだろう。
違った言い回しを辞書で探すは、下の下。同意語の選択から、さらにその言葉の意味を咀嚼した上で、使う事が重要である。そのプロセスが語彙力を高めるひとつの方法だという部分が妙に気に入った。今の自分は、下の下に位置する。残念だけど、現実を受け止める。
投稿元:
レビューを見る
書くことは生きること。ライターになりたいと言っているうちはライターにはなれず、ライターになるならば書けばいいのだ。
投稿元:
レビューを見る
好き嫌いが分かれそうだなと思った。
多くの学びや気づきを与えてくれる本であることは間違いないが、どこか違和感やひっかかりを感じる。
例えば、野球の例え。誰にでもわかる文章を書けと綴られている割には、野球用語の多用が見受けられる。野球を知らない僕にとってはよくわからない表現だった。(調べたらいいじゃない、という話だが)
あとは、塾生に対するエピソードの嫌悪感。若い塾生を非難して泣かせた、という内容で嫌な気持ちになりしばらく読む気が失せた。わざわざその内容を書く必要が、本当にあったのだろうか?
全体を通しては文章を書くことの意味、書くために必要なことを知れて良かった。けれど、上記のことがあって手放しに賞賛できるものではなかったのが残念。
投稿元:
レビューを見る
書くことに怖気付いたら、何度でも読み返すであろう本。「これを今すぐ綴って出さないと、これが世界に無かったことになってしまう」とよく思っていた、海外駐在時代を思い出した。
今だって出来ること、やりたいことはある。細くても長く、身を投じておきたいと改めて思った。
投稿元:
レビューを見る
ごめんなさい!なめてました。
文章術、テクニック本かと思ったが、レビューの良さに惹かれて購入。
久しぶりにアンダーラインをたくさんひいた。
文章を書くとは、場面で語るとは。
答えがない、けれども答えを教えてほしいことが筆者の生きた言葉で書かれていた。
この本はメルカリに出さない。本棚行き。
投稿元:
レビューを見る
文章を書くための手引書と思わせて、文章を書くことが自分を救い、生かすと教えてくれる本だった。私は私を救いたい。
黄色いダーマトグラフ(第21発)を実際に買った。本にはラインを引け、引くな、何色を使え、読む読書術本によって全く違うことが書かれている。この本を読み終わった今、私は黄色いダーマトグラフを使うことにした。今まで知らなかったけどこれすっごく使いやすいですね。
投稿元:
レビューを見る
文章そのものは書けるけれども、もう少し上手く言葉を選んで文章を書きたい。そう考えている方へお薦めする一冊。
そもそも文が書けない、という人も読んでマイナスに振れることはないかもしれないけれど、きっと自信をなくしてしまうだろう。それほどに強烈な内容。
TwitterなどのSNSを通じて、誰もが「物書き」になれる現代。AIが作成した文章の質はますます上がり、人間が書く文章の価値は下がる一方のような気がしてならない。
そもそも、アマチュアとプロの違いはどこにあるのだろう、なんて気持ちで読んでみたが、アマチュアがここまでやるのには、厳しそう。
読む側から読まれる側へのシフト。
誰が読むのか。通りすがりの人間を、惹きつけるための広告として書く場合と、小説の始まりに書く場合は、大きく異なる。
下手な鉄砲は当たらない、と著者は説く。
良い文章とは、経験の積み重ねだけでなく、テクニックも兼ね備えていなければならない。
投稿元:
レビューを見る
いかに美しい文章を書くか、という指南書ではない。言葉を使っていかにこの愚劣で生きるに値しない世界を生きるのか、という本だ。人生は生きるには退屈すぎる、だからこそ人は表現がなければ生きていけない。踊りも歌もなかった時代などない。それほどに世界は退屈だ。
文章とは何か。文章とはキャリアー。言葉を発する主体の、感情、判断、思想を載せて走るクロネコヤマト。
伝え方は9割とかともいうけど、それはちょっと嘘くさく思える。缶詰とか、3分でチンしたら食べられる簡単調理のトッポギか。
今まで出会った言葉とは〇〇である、構文の中で、クロネコヤマトに例えるものが一番的確に思う。というのも、速さ、温度、梱包の要素を送るべきシチュエーションにより誰しも変えているはずだ。
『法人契約』届けたい相手に正確に、速やかに届けるのが法人契約クロネコヤマト。むしろ速達バイク便。受け取り印は確実にいただく。緩衝材必須な場合あり。
『個人契約』お友達には、適切な間隔で、暇人だと思われないくらいの頻度で愉快なものを送りつける。時には可愛い梱包使う。
たまに物を裸で投げてくるやついるけど、宅配ボックス入れてくれ。
企画とは、結局、編集なのだ。すでに世に出ていることを、総覧して、何か新しい共通事項、切り口があるのではないか。共通するキーワード、「時代の気分」があるのではないか、そうした目で「切る」のが、企画なのだ。
自分の言葉は自分の過去の出会いや感覚、感情からしか出てこないと思っている。千鳥がやっているのもこれだ。みんなのあるある、が心地いいのだ。
創作の女神は、いる。時間はいつでもいい、都合のつく時間を、とにかく決めるんです〜 部屋に閉じこもり、たとえ一行も書けなくても、とにかく机に座って、何かを書こうとする。なぜか。女神に通知しているんです。
そしてここには悪魔がでるらしい。私は偽物だ、私が描くものには価値がないと。そこでうちなる悪魔と戦い切ったものだけに、女神が現れる。会社のできる先輩も言っていた。仕事は効率化し、長時間働けと。お前よりできるやつもお前より働いている。どっちが成長するか考えろ。できないなら働け。できるようになっても働けと。確かに彼はいつも同じ席に座って長時間働いている。彼は女神に通知していたのか。
投稿元:
レビューを見る
プロの物書きを目指す人に向けて書かれた、文章の書き方実用書。
タイトルは、物書きは最初の三行で読者の興味をひかなければプロではない、という意味。
この文章は良い、この文章は悪いと例文がたくさん出てきてわかりやすい。
その、良い文章の見本の作者の文章を読んで、読んだことがあるような文章だったのでひょっとして、と調べてみると、作者は朝日新聞の記者だった。
テクニックを指南しながら、物書きとはこういうものだ、こうでなければならない、と熱く説く。
だんだんヒートアップしてきて、最後の方は熱い文章ばかりで遊びが少なく少し読みにくかった。
投稿元:
レビューを見る
この筆者もまさしく「知の巨人」 だと思います。
単なる文章術の本の域をはるかに越えています。
学びの多い一冊で、この情報量で1500円+税はあり得ないでしょという感じ。
インスタなどで文章を人様の目にさらす人はもちろん、まったく文章を書かない、という人も読んだほうが良いです。
なぜなら悪文の見分け方もわかるから。
読みにくく思える文章の理由が、この本の説明を読み、納得できました。
素晴らしかったのが「起承転結」の「転」の五パターン。ほんとに教えちゃってもいいの!?と思うテクニックです。
とりわけ笑えた箇所は二ヶ所。
「どこが理想的な書き部屋でしょうか。そりゃもう台所に決まってます。」
「木を切り倒して、パルプ紙にして、紙にインクをにじませ …(略)…時代にまったく逆行した環境破壊的なメディアが、紙の本である。たった一人の著者の情熱だけでは、とてもできあがるものではないのだ。 」
この独自の考えを断言する感じが好きで、癖になります。
一気読み出来るくらい面白かったので、他の著作も読むつもりです。
投稿元:
レビューを見る
とても良かった。記者志望じゃなくても普段から使えるような考え方ばかりだった。早速上司に読ませたいと思った
投稿元:
レビューを見る
自分の書いた原稿を人に見てもらう立場のときは無責任だったなあ、と今になって思う。とりあえず球を丸めて投げる。球をもう少しきれいにしてくださいとか、もっとまっすぐ投げてくださいとか言われて、はいはいと言ってその通り直す。その通りにはなかなか直らない。それでもそれなりの形に仕上げて、最終的には受け取った側で整えてもらう。それでどうにかなっていた。
ところが人の書いた原稿を見る立場になったとたんものすごく不安になった。人が書いたものを直すというのはむずかしい。はたしてこの直し方で合っているんだろうか。責任を感じるにつれて自分の赤ペンにどんどん自信が持てなくなっていく。自分で書くほうがよっぽど楽だとすら思う。
いい文章とはなんだろう、と迷路に迷い込んだような気持ちになって、何かヒントが得られればと思いこの本を手に取った。ヒントどころじゃなかった。ページは真っ赤になったし、角を折りすぎてずいぶんぶ厚くなってしまった。文章を書くとは何か、書いて生きるとはどういうことか、なぜ私たちは書かないと生きていけないのか、自分がこれまで言語化できていなかったそういう感覚がどばどばと押し寄せてきて、頭のなかを一掃されたような気分になった。書くことは生きることだ。自分になることだ。
「三行で撃つ」は比喩かと思っていた。確かに比喩でもあるのだけど、著者は物理的に「撃つ」ことをしている人だった。だからこそ読んでいて「撃たれた」。しっかり狙われてしまった。書けなくなったとき、書き方がわからなくなったとき、書く力が伸び悩んでいるとき、折に触れて読み返したい。
【読んだ目的・理由】メルマガで見かけて
【入手経路】買った
【詳細評価】☆4.9
【一番好きな表現】言い換えるとは、考えることです。世界をよく観ることです。いままでと違う、他人の感覚ではない、自分自身の、ただひとつの世界の見方、切り取り方、考え方にたどり着く。(本文から引用)