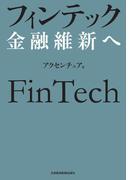FinTech関連本は次のフェーズへ! 入門書はもう終わり。
一歩踏み込んだ本が一度に登場
丸善とジュンク堂は、ビジネスパーソンや各界の専門家を主な利用者とする大手書店グループです。その購買データを分析すれば、ビジネスパーソンにとって「いま注目の本」が見つかるのではないか、というこの連載。今回は、7月の「経済」分野に絞り、売れ筋のランキングとトレンドを読み解いてみました。
経済分野の本は、他の分野と比べ、比較的毎月の順位が変動しやすい傾向にあります。購買層の関心がいくつかに大別されているのか、あるいは毎月、興味深い新刊が出るためなのかは分かりませんが、それにしてもこの7月の変動は大きいものでした。なんと、売れ筋のTOP 10のうち8冊も新刊がラインクイン。なかでも今回注目したのは、1位、6位、9位の書籍に共通するテーマ「FinTech」です。
2015年に火がつき、ややバズワードとなっていた「FinTech」。雑誌の特集、テレビの特集、概要を示した本の発売、と情報は広がってきていますが、約1年半もたった今、ただのバズワードではなく、しばらく続くトレンドへと変わりつつあるようです。今回登場した3冊も、今まで店頭に並んでいたような入門書・概要書のFinTech関連本とは趣が異なります。ではどんな内容が注目されてきているのか、その中身を見てみましょう。
その前にまず、7月の「経済」書TOP 10です。次の表をご参照ください。
丸善・ジュンク堂「経済」書籍ランキング2016年7月
2016年前半までは、入門書がほとんど
前述したように、FinTechにまつわる本はこれまでも発売されてきていましたが、概要書・入門書の傾向が強かったように思います。今年に入って売れていた本をみると、4月発売の『FinTech入門』(日経BP社)、5月発売の『決定版 FinTech』(東洋経済新報社)、3月発売の『FinTech 2.0』(中央経済社)などを挙げられますが、いずれも内容としては入門書に位置づけられるものでした。
そもそもFinTechとは何か、という疑問をもつ方々にとっては、これらの書籍はとても有益でしょう。例えば『FinTech入門』は、FinTechと呼ばれる世界を提供サービスごとに分類・整理したうえで、先行する具体的なサービス事例をいくつも紹介しており、分かりやすい本でした。
しかしそろそろ、感度の高いビジネパースンには、入門書では物足りなくなってきたことでしょう。そのような方を対象にしたのか、今月ランクインした書籍は、いずれも踏み込んだ内容になっています。
金融ビジネスの本質的変化へ切り込む『フィンテック 金融維新へ』
まず、初登場ながら「経済」分野で1位の販売数だったのが、『フィンテック 金融維新へ』(日本経済新聞出版社)です。テクノロジーに強いコンサルティングファームであるアクセンチュア株式会社が記した本書。数々のデータやフレームを示しながら、FinTechという「ビジネスの本質」に切り込んでいます。
- 予約購入について
-
- 「予約購入する」をクリックすると予約が完了します。
- ご予約いただいた商品は発売日にダウンロード可能となります。
- ご購入金額は、発売日にお客様のクレジットカードにご請求されます。
- 商品の発売日は変更となる可能性がございますので、予めご了承ください。
本書の第一の特徴は、そのスコープでしょう。今までのFinTech関連書においては、FinTech=新しい潮流という意識のためか、ベンチャー企業の手がける「新たなサービス」を紹介していたものが多くありました。また、ブロックチェーンや人工知能などの技術による金融への影響を描いていても、その概念的な説明にとどまっており、本質的なビジネスの変化まで踏み込めていなかった印象です。しかし本書はコンサルティングファームが記しているだけあり、また対象もベンチャー企業にとどまらず、従来の金融機関も含めてどのように変わるべきなのかという指針を記しているため、より本質的なFinTech(TechnologyによるFinance業界の変容)を語っている内容でした。
第二の特徴は、金融サービスの「周辺部」を手厚くし消費者の利便性を上げるサービス群と、従来の金融サービスの「本質」にまで影響しうるパラダイムシフトを起こしうるサービスとを、明確に分けて語っている点です。類書では、とにかく「新しい」サービスを同列にFinTechとして紹介していたものもありますが、本書はこれらを同列に語ってはいません。特に後者の、金融サービスの本質にまで影響しうるパラダイムシフトとして、ブロックチェーン、人工知能、APIの進展に注目し、これらの技術が金融サービスをどのように変容しうるのかを、仮説立てて紹介しています。
タイトルを見るだけでは、従来の書籍との違いが分かりづらいのが難点ですが、本書は、金融サービスおよび金融機関の未来を考える、特にビジネスの視点から考えるのであれば、入門書の次に押さえておきたい書といえるでしょう。
FinTech × 法律 の良書が、一気に登場!
FinTech関連書籍は、今月の6位と9位にもランクインしているのですが、いずれも「法律」の切り口からFinTechを語った書籍でした。本記事の冒頭に「バズワードからトレンドになりつつある」と書いたFinTechですが、より実務レベルでの切り口で語るべきテーマになってきたということでしょう。
とはいえ2つの本を比べてみると、そのスタンスは少し異なります。
6位の『FinTechの法律』(日経BP社)は、法律の専門家ではない実務家の方を主な対象としているため、FinTechに関わる法律について記しているとはいえ、概要や背景、課題や今後の方向というやさしい説明が中心です。さらには、金融庁や経済産業省、内閣官房など、行政がFinTechに対してどのような施策を推進しているかも解説しており、今後の方向性を自ら見極めるための材料にもなるでしょう。
- 予約購入について
-
- 「予約購入する」をクリックすると予約が完了します。
- ご予約いただいた商品は発売日にダウンロード可能となります。
- ご購入金額は、発売日にお客様のクレジットカードにご請求されます。
- 商品の発売日は変更となる可能性がございますので、予めご了承ください。
一方で、9位の『FinTechビジネスと法 25講』(商事法務)は、より専門的な内容です。西村あさひ法律事務所所属の弁護士が共同で記しているため、ビジネスモデルや事業評価の観点から、各FinTechサービスについて、法令に関する基礎知識と適用関係の考察を試みています。
FinTechビジネスと法25講 黎明期の今とこれから
-
税込3,300円(30pt) 発送可能日:購入できません
- 有吉 尚哉 (編著)
- 出版社:商事法務
- 予約購入について
-
- 「予約購入する」をクリックすると予約が完了します。
- ご予約いただいた商品は発売日にダウンロード可能となります。
- ご購入金額は、発売日にお客様のクレジットカードにご請求されます。
- 商品の発売日は変更となる可能性がございますので、予めご了承ください。
いずれにせよ、FinTechと法規制には密接な関連性があります。金融は規制業種であるため、イノベーションを起こすのであれば、法の範囲を把握しておく必要があるためです。
FinTechとはなにかを表面的に「知る」だけでなく、より踏み込んで「取り組む」のであれば、これら法律面からFinTechの世界を見通しておくことは必要でしょう。それゆえに、2冊とも大きく売上を伸ばしているのだと、納得しました。
さて、次回、8月の売れ筋ランキングでは、大きなランキングの変動があるのでしょうか。今月登場したFinTech本はひき続き売れている気もいたしますが、どんな本が登場するのか楽しみです。みなさまも、お楽しみに。
プロフィール
hontoビジネス書分析チーム
本と電子書籍のハイブリッド書店「honto」による、注目の書籍を見つけるための分析チーム。ビジネスパーソン向けの注目書籍を見つける本チームは、ビジネス書にとどまらず、社会課題、自然科学、人文科学、教養、スポーツ・芸術などの分野から、注目の書籍をご紹介します。
丸善・ジュンク堂も同グループであるため、この2書店の売れ筋(ランキング)から注目の書籍を見つけることも。小説などフィクションよりもノンフィクションを好むメンバーが揃っています。