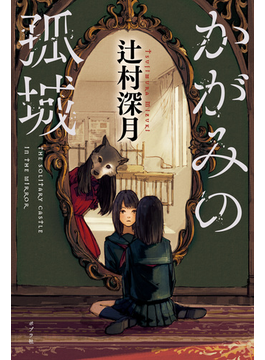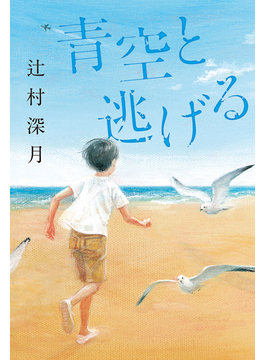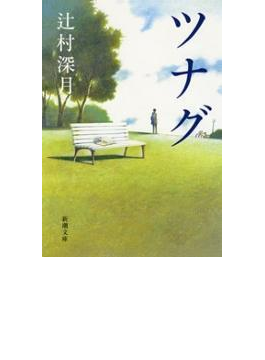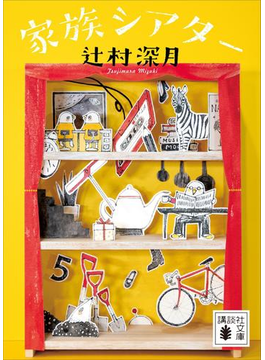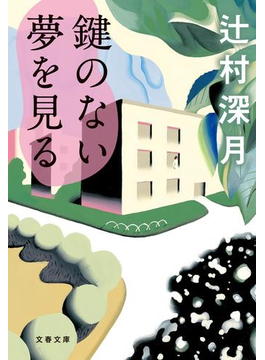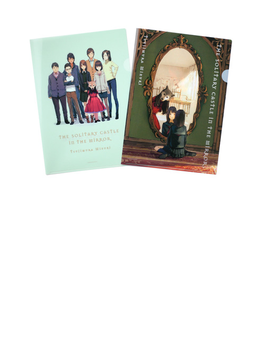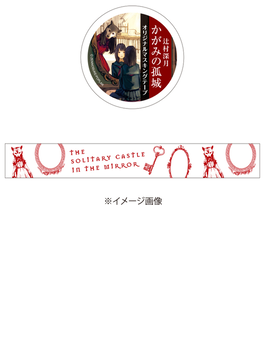注目作家や著名人に最新作やおすすめ本などを聞く『honto+インタビュー』。
今回は、『かがみの孤城』で2018年の「本屋大賞」を受賞した辻村深月さんが登場。
思春期の心を書き続ける理由はどこに?
「教室に残した大きな忘れ物を、こっそり覗きに行く感覚で、学校や教室でのことを書いています。」
「思い返せば私自身、学校という場所で『うまく過ごせた』という実感はないんです。いつもどこかしっくりこない、モヤモヤしたものを胸の内に抱えていた。あれはいったい何だったのか。教室に何か大きな忘れ物をしている気分がいまも残っています。どんな忘れ物だったか確認するためにこっそり覗きに行く感覚で、これまで学校や教室でのことを繰り返し書いてきましたね」
デビュー作の『冷たい校舎の時は止まる』(講談社)や今年の本屋大賞受賞作『かがみの孤城』(ポプラ社)、最新短編集『嚙みあわない会話と、ある過去について』(講談社)も。辻村深月さんのいくつもの作品では、学校や教室での出来事が鮮やかに描き出されていて、現役の生徒・学生はもとより、学校からすでに遠く離れた大人たちをも魅了してしまう。
なぜこれほど胸に迫る学校小説を生み出せるのだろう。10代のころの記憶を、人よりずっと豊富に持っているのか、または詳細な記録を残していたとか? 不思議に思ってお訊きしてみれば、先の言葉が返ってきた。とりわけ『かがみの孤城』では、「学校とどうもうまくいかない。そういう気持ちを最も強く持っているのが不登校の子たちかもしれないと思ったんです。学校に対する違和感みたいなものが、彼らを主人公にすることで見えてくるんじゃないかと考えました。
私には不登校の経験がないけれど、不登校の子が学校に行きたくないと思う気持ちはわかる気がして、すごく近しい存在に感じます。実際、不登校になる気持ちがまったくピンとこない人って、まずいないんじゃないでしょうか。私の中で不登校をしている子というのは、『休む勇気を持てた人たち』だというイメージが強いです」
作中には不登校の人たちの状況や心境がつぶさに書かれている。それで読む側としては、「これは作者の経験に基づく記述なんだろう。もしくは取材を重ねた賜物か」とも想像してしまうが、そうではないのだ。
「子どもや保護者に取材したということも、まったくないですね。私自身が中学生のときに大人に対して感じていたこと、教室の空気なんかを思い出しては書いていきました。ですからこれを読んで気づきが多いのは、中高生たちよりも大人のほうかもしれませんね。あのころ自分はどうしたかったのか、どうしてほしかったのかが見えてくるというか。
私も書いていて、そういうことを一つずつ確認しているところがありました。すっかり大人になったいまも、私が10代の人たちのことを書き継いでいる意味は、そのあたりにあるのかもしれません」
辻村さんの思春期小説には、大人が当時を振り返って語る視点も、どこかに織り込まれているということか。ただし、大人がついやってしまいそうな「わかった風な口の利き方」や、安易なレッテル貼りは決してしない。たとえば『かがみの孤城』では、不登校の理由を「いじめ」のひと言でくくったりはしない。
「そこで起こっていることに名前をつけて、理解したような気にさせるのは、小説の役目じゃないと思います。
どうにも名付けられないことや気持ちがあって、それをなんとか表そうと文字を連ねていくのが小説なんじゃないか。『かがみの孤城』は500ページを超える長さがありますけど、それだけのページを費やしてようやく言える何かがあるはず。そう信じて書いていったんですよ。」
新刊のご紹介
辻村深月(つじむら・みづき)
1980年山梨県生まれ。千葉大学教育学部卒業。2004年『冷たい校舎の時は止まる』でデビュー。『ツナグ』で第32回吉川英治文学新人賞を、『鍵のない夢を見る』で第147回直木賞を受賞。他の著書に『凍りのくじら』『ぼくのメジャースプーン』『スロウハイツの神様』『島はぼくらと』『ハケンアニメ!』など多数。
主な著作
バックナンバー
- 【vol.25】葵わかな『青夏 (講談社コミックス別冊フレンド) 』(講談社)
- 【vol.24】鳥居みゆき『やねの上の乳歯ちゃん』(文響社)
- 【vol.23】コシノヒロコ『だんじり母ちゃんとあかんたれヒロコ デザイナー三姉妹と母の物語』(マガジンハウス)
- 【vol.22】阿部和重&伊坂幸太郎『キャプテンサンダーボルト』(文藝春秋)
- 【vol.21】安藤忠雄『仕事をつくる(私の履歴書)』(日本経済新聞出版社)
- 【vol.20】栗山圭介『フリーランスぶるーす』(講談社)
- 【vol.19】伊坂幸太郎『ロングレンジ』(幻冬舎)
- 【vol.18】真梨幸子『祝言島(小学館)
- 【vol.17】阿部智里『弥栄の烏』(文藝春秋)
- 【vol.16】深水黎一郎『ストラディヴァリウスを上手に盗む方法』(河出書房新社)
- 【vol.15】小手鞠るい『たべもののおはなし パン ねこの町のリリアのパン』(講談社)
- 【vol.14】上田秀人『竜は動かず 奥羽越列藩同盟顛末』(講談社)
- 【vol.13】浅田次郎『天子蒙塵』(講談社)
- 【vol.12】けらえいこ『あたしンち』(KADOKAWA)
- 【vol.11】伊東潤『天下人の茶』(文藝春秋)
- 【vol.10】真保裕一『遊園地に行こう!』(講談社)
- 【vol.9】伊坂幸太郎『サブマリン』(講談社)
- 【vol.8】松岡圭祐『探偵の鑑定』(講談社)
- 【vol.7】堂場瞬一『誘爆 (刑事の挑戦・一之瀬拓真)』(中央公論新社)
- 【vol.6】山崎ナオコーラ『ボーイミーツガールの極端なもの』(イースト・プレス)
- 【vol.5】安藤哲也『崖っぷちで差がつく上司のイクボス式チーム戦略』(日経BPマーケティング)
- 【vol.4】藤原和博『たった一度の人生を変える勉強をしよう』(朝日新聞出版)
- 【vol.3】伊坂幸太郎『キャプテンサンダーボルト』(文藝春秋)
- 【vol.2】阿部和重『キャプテンサンダーボルト』(文藝春秋)
- 【vol.1】川上未映子『きみは赤ちゃん』(文藝春秋)